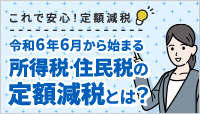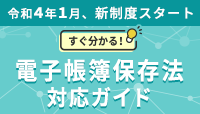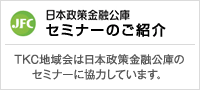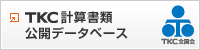「残業を減らせば利益が上がる」――この因果関係を認識できてない経営者は意外に多い。ただ漫然と作業するのではなく、個々人が時間管理の下に仕事を組み立てれば、生産性は劇的にアップし、減少した勤務時間を補って余りあるアウトプットが見込めるのだ。それが今、「残業しない強い中小企業」が増えている由縁なのである。
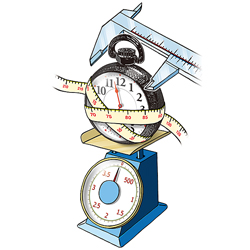
大切なのは仕事の「はじめ」と「おわり」
毎晩、遅くまで会社に残っている社員を見て、「いつも会社のために貢献してくれている。感心、感心」などと心の中で思っている経営者がいたら、ちょっと待ってほしい。その社員は本当に会社に貢献しているのだろうか。
まず仕事密度の問題から。通常であれば定時で仕上げられるボリュームの仕事を日中ダラダラとやっていた結果、残業しているだけかもしれない。次に、残業代の問題から。夜遅くまで残業代目当てに社内にいる可能性だってある。そのように社員個人に責任のある残業だけでなく、「モーレツ型の上司に従って仕方なく」といった理由も考えられる。そうした場合、その社員のモチベーションは極めて低いだろう。
多かれ少なかれ、「残業は当たり前」という意識がまだまだ根強く残っている日本の会社。しかし常態化した長時間労働が、日本のホワイトカラーの生産性を著しく低下させている可能性は高い。実は日本のホワイトカラーの生産性は国際比較した場合、驚くほど低い。先進7ヵ国中最下位で、OECD(経済協力開発機構)加盟国30ヵ国中20位という笑えない現実がある(社会経済生産性本部・2007年版「労働生産性の国際比較」)。
長時間労働が日本企業に浸透していったのは、昭和の高度経済成長期。滅私奉公の精神でみんなが頑張れば、それだけで成果が上がった時代である。長時間労働の弊害がすぐに現れれば方向転換を余儀なくされたに違いないが、そうならなかったところに日本企業の悲劇があった。「差別化」や「高付加価値」が事業拡大のキーワードになっている現在においても、過去の成功体験を引きずり、まだまだ“労働時間の長さ”が武器になるという幻想が残っているのだ。今の時代、必要なのは社員たちの知恵やアイデアをいかに結集させるか。朝から夜遅くまで会社という閉ざされた空間にいたのでは、斬新なアイデアが生まれるわけがないし、思考の「バネ」も伸びきってしまう。昨今の日本企業の不振は、こうした部分にも遠因があるのかもしれない。だが今からでも遅くはない。残業削減の取り組みによって社員の生産性を向上し、それによって会社の利益を高めるというのは決して無理な話ではないのだ。
では、残業削減を目指すうえで具体的にどうすればいいのか。そこで注目したいのが、限られた時間をいかに有効活用するかに視点を置いた経営手法「タイムマネジメント」である。時間というフレーム(柵)を用いて日常の仕事を見直すと、生産性を下げている不合理な間違いを発見しやすくなる。ダラダラと仕事をしている社員の存在が浮き彫りになるし、「気合い」や「根性」という言葉でブラックボックスに隠されていた組織内のまずい部分が見えてくる。残業削減の取り組みを進めようとすると、きまって社員の中から「残業なしでは仕事が回らない」と反論する者が1人や2人出てくるが、それが本当かどうかを見極めるうえでもタイムマネジメントの考え方は有効となる。
「4つの時間」という概念
タイムマネジメントを実践するうえで常に意識すべきなのは、「4つの時間」である。具体的には、(1)「自分一人の仕事のはじめ」(2)「自分一人の仕事のおわり」(3)「他人と共同の仕事のはじめ」(4)「他人と共同の仕事のおわり」の4つだ。この4つの時間をもとに、社員一人ひとりの仕事を「見える化」(可視化)していくことが、会社の生産性を高める第一歩となる。
4つの時間を意識して働いている日本のビジネスマンは現在本当に少ない。あるのは「他人と共同の仕事のはじめ」と「自分一人の仕事のおわり」の認識ぐらいだ。その証拠に、社内会議の開始時刻をグループウェアの予定表や各自の手帳に記している者が大多数を占めるはずだ。本来、時間を有効に使いたいのであれば、会議の「はじめ」と「おわり」の時間をきちんと決めておく必要がある。日本企業の会議が無駄に長引くのは、そもそも終了時刻が決まっていないから。「結論が出るまで延々と続く」という暗黙のルールのもとでは、活発な意見も出ないままダラダラと長引くのは当然といえる。終了時刻が決まっていれば、時間内に何とか終わらせようと参加者みんなが積極的に発言するだろうし、その後の予定も立てやすくなる。つまり、「他人と共同の仕事のおわり」を意識するようにするだけで、業務の効率化は進むのだ。
また、「自分一人の仕事のはじめ」を決めるのも大切。取引先に提出する見積もり書の作成や、プレゼンの資料づくりなど、自分一人で担当する仕事をはじめる開始時期を設定するのだ。それを蔑ろにしているから、期日が差し迫った段階でのバタバタとした仕事ぶりにつながり、残業を増やす結果となる。だとすれば、最も段取りよく仕事ができる日程の「はじめ」と「おわり」をスケジューリングしておき、その通りに実行するほうが何倍もよい。
日本のホワイトカラーの生産性は低いものの、その一方で日本の製造現場における生産性の高さは世界でもトップクラス。それは、カイゼン活動などを通じて、徹底的に無駄を排除した生産ラインに工員が張り付いているからといえる。ラインは、「いつからいつまではこの仕事をする」という計画にもとづき稼働している。言い換えれば、仕事の「はじめ」と「おわり」が決まっているということだ。結果、工員たちは特に意識せずとも生産性の高い作業が行えているのである。
仕事の「優先順位」を決める
ただ、ホワイトカラーの場合、製造現場と違い、毎日決まった仕事をしているわけではない。だから、その日優先的にやるべき仕事、つまり「大事」な仕事を見極め、それに重点的に時間を割く仕事のやり方をする必要がある。その優先順位を決めるうえで参考にしてほしいのが、「6つの仕事」の考え方だ。4つの時間に加え、この6つの仕事を意識することで、タイムマネジメントはより確かなものになる。
6つの仕事の考え方では、以下のような項目をベースに仕事の優先順位を決めていく。
(1)【仕事の種類】事前にわかるものか、突発・割り込みのものか
(2)【仕事の処理の仕方】今やるか、後でやるか
(3)【仕事をする主体】自分がやるか、他人でもよいか
優先順位が高いのは、「事前にわかっている仕事で、今または後で、自分がやらなければならないもの」や「突発・割り込みの仕事で、今、自分がやらなければならないもの」である。逆に、優先順位が低いのが、「事前にわかっていた仕事で、今、後関係なく、他人でもよいもの」だ。
こうした判断にもとづき仕事の優先順位を見極める習慣を身に付けると、仕事の「さばき方」は格段に上手くなる。従来よりも短い時間で同程度の仕事量がこなせるようになるだろう。残業ゼロでも仕事が回せる現実が見えてくるのだ。
いくらタイムマネジメントを通じて効率性を高めても、深夜残業抜きでは終わらないというのなら、それは明らかにその社員の能力を超えた仕事量を担当させてしまっているか、そもそも業務内容自体が社員のガンバリズムに頼ったものであるということになる。それについては、早急に見直しを図る必要がある。
ここで、私がコンサルタントしたのをきっかけに業務効率アップを実現したX社の事例を紹介しよう。X社は東北地方に本社があるIT機器関連のメーカーである。
X社の悩みは、生産部門はともかく、間接部門の生産性が上がらないことだった。ヒアリングを通じて見えてきたのは、従業員たちが仕事のさばき方さえ身に付ければ、生産性の大幅な向上が期待できるということだった。そこで、社員一人ひとりの仕事の「棚卸し」をすることと、1日のうちの「大事な仕事」を決めることの2つをデイリープランして定着させた。具体的には、「今日の一番大事管理表」を作り、それに毎朝記入してもらった。さらに、残業する必要があるときには、その理由や時間を書き込んでもらうようにした。それにより上司は、部下の仕事内容が今までよりも具体的に把握できるようになった。
この取り組みを始めるとすぐに効果が現れた。およそ1ヵ月で残業時間が1人平均5時間も減ったのだ。さらに、業務分担の仕方を全体最適でもう一度考え直したり、月・週の「大事」を考えることを追加で行うようにしたところ、月平均9時間の残業削減が達成できた。仕事の優先順位と投下時間がはっきりしたことで、その後の様々な改善策にもつながった。
社員の「自立」を高める効果
実はタイムマネジメントには、残業を減らすという効果のほかにも、社員たちの「自立」を促すというメリットがある。上司から言われたことしかやらない「指示待ち社員」をはじめ、今の日本企業に欠けているのは自分の意志で能動的に働ける社員の存在である。自立型の社員が増えれば会社の“経営力”は自ずと高まっていく。
こうした観点からすると、たとえば「1時から3時までの2時間は集中してデスクワーク」と会社側が決めてしまう「がんばるタイム」の導入はあまりお勧めできない。がんばるタイムとは、つまり社員から「自分一人の仕事」のはじめとおわりを考える権利を奪ってしまう制度である。優秀な社員ほど、自分独自の仕事のやり方を身に付けており、組織にコントロールされることを嫌う。何年か前に「がんばるタイム」を導入する企業が相次いだが、社員からの反発は強く、継続して実施しているところはほとんど見当たらない。
あまり知られていないが、実は日本は江戸時代、世界でも希なタイムマネジメント大国だった。たとえば17世紀の紀州藩の家訓には、その日やるべき仕事が終わった者については、定時前でも即刻下城することを許していた。「付き合い残業」という言葉さえある今では想像もできないが、こうした効率的な働き方が認められていたのだ。いずれにせよ、もはや長時間労働で勝ち抜ける世の中ではない。いかに効率的に社員に働いてもらえるか。企業経営者たちはこの課題にもっと目を向けるべきだろう。
(インタビュー・構成/本誌・吉田茂司)
掲載:『戦略経営者』2008年8月号