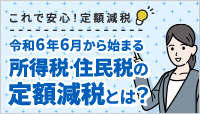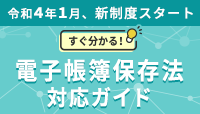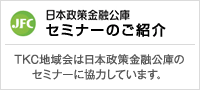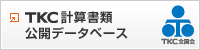日本には創業100年を超える老舗企業が2万数千社あるといわれる。それらの老舗が永く生き抜くことができたのは連続的なイノベーションを起こしてきたからだ。
創業後100年、200年を超える歴史をもつ老舗企業。様々な苦難を乗り越えながら“永続繁盛”している老舗には、長い時間軸のなかで連続的にイノベーションを成功させているという共通点がある。ここで言うイノベーションとは、「技術革新」(新製品の開発)という狭義の意味だけでなく、「新しい経営システム」や「新しい販売方法」までも含める。社会に対する新しい価値創造をすることが、企業にとってのイノベーションにほかならないからだ。
何世代にもわたる長期的な会社経営を続けていると、どこかで「節目」というものが生まれる。自然災害(地震など)、戦争、ライフスタイルの変化、交通インフラ(鉄道、道路)の変更などの「外的要因」によって、従来の経営スタイルでは立ち行かなくなるときがくるのだ。それをイノベーションを通じて乗り切ってきたのが老舗なわけである。
例えば、和菓子の老舗として有名なあの虎屋(創業16世紀末)だってそう。京都で皇室御用達の菓子司としてのポジションを確立していたが、明治維新で天皇陛下が東京に移られるという大きな変化に見舞われた。このとき後を追って東京に進出するという選択(当時の感覚で言えば海外に進出するようなもの)をし、新しい時代に即した商売のやり方に再構築したからこそ、今日の発展がある。
また、関西の奥座敷とも呼ばれる有馬温泉で最古の歴史をもつ温泉宿・御所坊(創業1191年)は、1995年の阪神淡路大震災によって観光客の数が半減するという事態に遭遇した。この危機を打開するために行ったのが、日帰り客を呼び込むために入浴とランチのセット販売や夕食なしの湯どまりという新サービスの提供だった。これがヒットし、周囲の旅館も追随したことが、有馬温泉に再び観光客を呼び寄せる大きな起爆剤となった。この一連の取り組みを通じて、御所坊のブランドはさらに輝きを増すようになった。
ピンチとチャンスはまさにコインの裏表。京都の尾池工業(創業1876年)は刺繍糸の製造販売からスタートしたが、外的環境の変化に合わせて加飾材料、蒸着フィルムの包装材料に進出し、現在はデジカメや携帯電話に使われる特殊な電子材料をメーンに好調な経営を続ける。このようにピンチをチャンスに変えた老舗は全国に数多く存在する。中小企業にとって今はまさに不況というピンチのときだが、世の中が大きく変化する時代だからこそビジネスチャンスがあることを忘れてはならない。そこに注目して新たなイノベーションを起こせば、不利な状況を一気にひっくり返すことも不可能ではないのだ。
「老舗のかたち」の連鎖
もちろん企業に襲いかかるピンチは、外的環境の変化ばかりではない。組織の内部にひそむ「内的要因」も、会社の継続を脅かす要素となる。経営者のマネジメント(意思決定)のまずさや、後継者不在、家業としてのガバナンスの弱さなどだ。これらがネックとなり、廃業を余儀なくされた会社はたくさんある。反対に、永続的に繁盛を続ける老舗はこれら内的な部分が非常にしっかりしている。親族への後継が困難だと判断すれば、婿取り、養子などの柔軟な対応を取るし、社長のマネジメント力が不足している場合には、ナンバー2である「番頭」がきちんと補佐する。そして、会社を存続させるために創業者一族を中心にチームワークがよくまとまっているというのも特徴だ。実は、今から数年前に同じく偽装問題で揺れた赤福(創業1707年)と不二家(創業1910年)の明暗を分けたのが、創業者一族のチームワークだった。赤福では創業者一族が一丸となって事態の収拾を図り、傷口を最小限に抑えた。他方、以前から組織のガバナンスの弱さを指摘されていた不二家にはそれができず、最終的に山崎パンの傘下に収まった。
つまり強い老舗というのは、長年受け継いできた家系・家訓・秘伝・強み・理念といったものを組織の根幹(DNA)としながらも、その時代によって異なる外的要因や内的要因を自分たちの味方にできるようなところだといえる。それを魚を模したイラストで表現したのが図1(〔『戦略経営者』2011年2月号33頁〕図1参照)の「老舗のかたち」だ。尾っぽに当たる部分が「起業・創業」で、時間を積み重ねるなかで背骨(家系・家訓・秘伝など)が形成されていく。そしてその背骨を通して、老舗の歴史は「現在の経営」に至るわけだが、それを肉付けして支えているのが外的要因と内的要因である。外的要因は、政治、経済、社会、自然環境といった「マクロ要因」と、地域資源、地元文化、交通インフラといった「地域要因」に細分化できる。内的要因についても、出身経験、生業家業の縁、代々の家系、社員団結などの「ファミリー要因」と、仕入先、取引先、顧客、業種業態、経営改善などの「マネジメント要因」の2つに分けられる。
この老舗のかたちは、長い時間のなかでいくつも形成されていく。老舗のかたちの繰り返しこそが、老舗の生成プロセス(〔『戦略経営者』2011年2月号34頁〕図2参照)なのだ。何十年あるいは何百年のスパンで老舗のかたちの頭の部分にピンチが襲いかかる。強い老舗はそれに見事対応して、次のかたちへと進む。ただし新しいかたちになっても、過去とは背骨でつながっていて組織としての一貫性は保たれる。そして、かたちとかたちの境目にはイノベーションの存在が必ずある。
ダーウィンの進化論に「生き残るのはいちばん強い種でも、いちばん優れた種でもない。環境の変化に最もうまく適応できた種である」という有名な言葉がある。これは何も生物に限ったことではなく、企業にも当てはまる。外的や内的な変化に対応しながら変貌を遂げていく会社こそが、強い老舗として名を馳せることができるのだ。老舗はまさしく進化論の優等生。むろん創業以来ずっと同じ業種業態、同じドメインで家業を継承していく道もあるが、それだけでは継続はしても老舗として永続繁盛するのは難しい。
「守成の戦略」が老舗の基本
たとえて言うなら、老舗経営はゴールのない駅伝競走のようなものである。山あり、谷ありの担当区間を走り切り、次の走者にバトンを引き継ぐ。そして、駅伝に参加するすべての走者が抱いているのは、「私の代で終えたくない」という強烈な意識。会社は「先祖から子孫への預かりもの」と考え、将来にわたって持続していくことを最大の責任使命と感じている。駅伝ではチーム全員が一致協力して、全体最適を目指す。一人の英雄の区間最高よりもチームの栄光に重きを置く。だから持続的な経営に支障を及ぼすような無理な成長や利益を追い求めたりせずに、安定成長が望める時代にはしっかりと守りを固める。だが、ひとたび会社存続の危機に見舞われれば、全力で革新的な行動を起こす。こうした「守成の戦略」が老舗の多くが基本としているところである。守成とは「創業の後を受けて、その成立した事業を固めて守ること」であり、単に継続することだけに努めるという消極的な意味ではない。
いずれにしても老舗の経営から多くのことが学べるのは確かである。閉塞感漂ういまの状況を打破するためのヒントが欲しいと願うなら、永続繁盛を続ける老舗の方途をよく知ることも大切だ。
- プロフィール
- まえかわ・よういちろう 1944(昭和19)年、大阪府生まれ。神戸大学経営学部卒業後、松下電器産業(現・パナソニック)に入社。経営企画室長、ネット事業本部長、取締役などを歴任。現在は、関西外国語大学や大阪商業大学大学院、流通科学大学などで教鞭を取る傍ら、老舗学研究会の代表を務める。
(インタビュー・構成/本誌・吉田茂司)