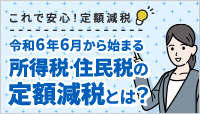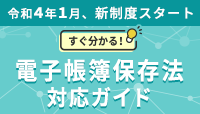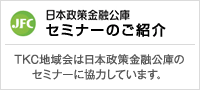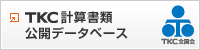──平成30年度税制改正大綱の印象は?
今仲 安倍政権の目標であるデフレ脱却、日本経済再生といった基本テーマは相変わらず続いています。そのテーマに沿う形で、昨年度は法人税の引き下げなどを目玉とした改正が行われました。そして、今年度は次の段階として、所得税の改革に取り組むという意図だったのでしょうが、私の印象では、「改革」というにはほど遠いように思われます。なぜなら、配偶者控除の抜本改革が先送りされたからです。フリーランスの増加などを鑑み、働き方改革の一部として、基礎控除を引き上げ、給与所得控除と公的年金控除を引き下げましたが、現状を大きく変えるには足りません。
抜本的な事業承継税制改革
──とすると、今回の大綱の目玉はやはり……。
今仲 そう。事業承継税制です。今回の改正は予想を超える抜本的なものとなっています。そのため、圧倒的に使い勝手が良くなったように思います。平成21年度に、経営承継の円滑化を目的に創設された事業承継税制ですが、これまでは、さまざまな意味でハードルが高く、適用を受ける企業は限られていました。なぜなら、経営者にとってリスクが大きく、そのリスクに見合うだけのメリットがなかったからです。
──どの部分が抜本的といえるのでしょうか。
今仲 中小企業が事業承継を行う際に、基本的には「贈与税と相続税が一切かからない」仕組みへと改正されたところです。図表を見てください。これまでの事業承継時の納税負担は、対象株式上限2/3×猶予割合80%なので実際の猶予割合は53%に過ぎませんでした。つまり、47%は納税が必要だったのです。ところが、今回の改正で、上限が撤廃、猶予割合も100%となり、自社株承継時の納税負担がなんとゼロになりました。これは画期的なことです。
──かなり思い切った改正ですね。
今仲 さらにもうひとつすごいのが、「雇用維持要件」の実質撤廃です。これが当税制を活用する際の「リスク」の大半を占めていました。というのも、現行では、生前贈与以降の5年間平均で当初の80%の雇用者数を維持できなかった場合は、全額納付しなければならなかったのです。これでは中小企業経営者にとっては厳しい。たとえば、リーマンショックのような大きな景気変動が起こった場合、一気に納税義務が発生し、元のもくあみになってしまいます。経営者が怖くて手が出せないのは当然でしょう。ところが、今回の改正で、この雇用維持要件は実質撤廃されました。5年で平均80%を下回っても、猶予税額を支払わなくてもよくなったのです。
──景気変動を怖がる必要がなくなったと。とはいえ、無条件に……ということはないでしょう。
今仲 その点についてですが、少し長くなりますが、大綱の原文を引用してみますね。
「現行の事業承継税制における雇用確保要件を満たさない場合であっても、納税猶予の期限は確定しない。ただし、この場合には、その満たせない理由を記載した書類(認定経営革新等支援機関(※)の意見が記載されているものに限る)を都道府県に提出しなければならない。なおその理由が、経営状態の悪化である場合又は正当なものと認められない場合には、特例認定承継会社は、認定経営革新等支援機関から指導及び助言を受けて、当該書類にその内容を記載しなければならない」
※認定経営革新等支援機関(認定支援機関)
中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるよう、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関。具体的には、税理士をはじめ、商工会や商工会議所など中小企業支援者、金融機関、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されている。
──つまり、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の指導・助言があれば、どんなに経営状態が悪くなり、人員を削減しても納税は猶予されるということですか。
今仲 その通りです。そこで認定支援機関(約2万6000件)の約4分の3を占めるわれわれ税理士の役割が大きくクローズアップされてきます。極言すれば、企業は認定支援機関としての資格を持つ顧問税理士のサポートを得ることができればほぼ例外なく、贈与・相続税がゼロになるということになります。
──この改正は、永続的な措置なのですか。
今仲 いいえ。今後5年以内に「承継計画」(仮称)を都道府県に提出し、平成39年3月31日までに承継を行う必要があります。つまり時限立法なのです。それだけにチャンスであり、これを使わない手はありません。承継計画はできるだけ早く出しておいた方がいい。計画を出せば平成39年3月31日まで贈与猶予期間として使えるわけですからね。経営者としては安心です。
将来の納税不安を大幅に軽減
──そのほかの改正点は?
今仲 現行の税制では、経営環境の変化によって納税が免除される特例は、後継者が死亡するか、会社が破産するかなど限定的です。そこで、今回の大綱では、経営状況の悪化にともない、譲渡や合併、解散を余儀なくされた会社において、承継時の株価の税額と、株式を売却した時点での株価での税額との差額を減免する制度(解散を除いて当初の評価額の半額が下限)が創設されました。これも心理的に少なからず影響を及ぼすでしょう。リスクが低減され、経営者にとって将来の納税不安が軽減されますから。
──計画を提出する前に先代が亡くなったとしたら?
今仲 その点も心配は無用です。平成30年1月1日から平成35年3月31日までに先代経営者が亡くなり、その時点で計画を提出してなかったとしても、この特例事業承継税制は全面的に有効性が確保される予定です。
──贈与する側、される側の要件も緩和されたようですね。
今仲 はい。現行では、贈与するのは先代経営者だけで、されるのは後継者ひとりでした。ところが、今回の改正案では、贈与する側については、先代以外の株主からの贈与にも特例が適用されます。さまざまな事情から株式が細分化し、いろいろなところに分散され、事業承継のハードルになっている会社は非常に多いのが現状です。しかし、この改正によって、後継者に株式を集中させやすくなり、結果として承継のハードルを低くできます。
また、贈与される側も、現行の1人から、代表権を持っていることが条件になりますが、3人まで可能になりました。たとえば、親族の3人が経営をしている会社で、社長1人だけに贈与するといろいろと問題があるので、他の2人にも15%ずつ株式を割り当てるといったケースがよくあります。現行では、この2人には税金がかかってしまうのですが、今回の大綱では、3人とも無税(1人10%以上が条件)になります。この改正も大きい。スムーズな承継の一助となるでしょう。
また、平成29年4月から事業承継税制に推定相続人または孫に対する相続時精算課税の適用が認められました。改正案では、これら以外の親族や第三者に対する非上場株式の贈与についても相続時精算課税の適用が可能となり納税猶予の特例を受ける場合のセーフティーネットが推定相続人以外のものにまで拡大されました。つまり、受贈者は先代の直系卑属(子、孫)でない場合でもOKとなり、さらに、前述の通り、複数への贈与がOKになったことで、非常に幅広く、納税猶予制度が使えるようになりました。
「認定支援機関」が鍵を握る
──ところで「承継計画」とはどのようなものなのですか。
今仲 A4紙2枚程度の簡単なものでいいとされています。なので、もはや「出さない」という選択肢はないと考えてください。しかし、それにともない、計画を提出したあとは「ほったらかし」といういい加減な事例が出てこないとも限りません。それでは、事業承継税制が目先の税金対策だけに利用され、中小企業の早期改善計画に基づく健全な発展と後継者の育成につながらない危険性があります。
──この制度自体の有効性が危惧されるということですね。では、どうすればよいのでしょう。
今仲 われわれ税理士などの認定支援機関が、次期経営者を育てるべくきちんとした計画を立て、行程表に落とし込んで、それを着実に実践することが大事になります。国もそれを期待しているのだと思います。ただ、認定支援機関にもさまざまあり、承継計画を作成はしても、一時的にしか関与しないコンサルタントなども存在します。それでは本当の効果は望めないわけで、やはり、税理士、とくにわれわれTKC会員のように、毎月の巡回監査を行いながら、月次決算や業績検討会、経営計画の策定などを恒常的に行っている認定支援機関が、継続的にサポートすることが必要でしょう。
──認定支援機関のなかにも優劣の差が出てきているということでしょうか。
今仲 もちろんです。事業承継は非常に難しい経営課題であり、一筋縄ではいきません。企業経営者は、認定支援機関の「質」を見極めてサポートを依頼する必要があります。
──ところで、国はどうして、このような「至れり尽くせり」の税制をつくったのでしょうか。
今仲 中小企業は日本経済をボトムから支えています。ここが底割れすると大変なことになる。中小企業庁のデータによると、1995年から2015年までの間に経営者の平均年齢は47歳から66歳へと20歳近くも跳ね上がっています。しかも、企業の廃業数は創業数を大きく上回っている。国としては、背に腹は代えられないと考えたのでしょう。このままではどんどん国力が落ちていくのは見えていますから。何としても既存の中小企業をできる限り存続させなければならない。そのような意図が、今回の事業承継税制の抜本改革に込められているのだと思います。
──平成30年度税制改正大綱には、「租税正義」という意味合いでの改正もいくつか見られます。
今仲 一般社団法人に対する課税回避行為が規制されました。現行では、企業の株を一般社団法人に移し、20%強の譲渡税を払ってしまえば、その後はオーナーの子供などへの贈与税、相続税は一切かかりませんでした。持分の定めがないという制度を利用しての課税回避行為が長らく問題視されており、今回の大綱ではこれが規制されました。小規模宅地の特例もそうです。現行、亡くなった方が住んでいた宅地を配偶者や同居親族(あるいは別居で賃貸に住んでいる子)が相続する場合、100坪までは評価額の80%まで減額してもらえます。しかし、非同居で自己またはその配偶者の所有している家屋に居住している場合は適用を受けることができないため、住んでいる家屋を子供や孫などに贈与し、自己または配偶者の所有する家屋に居住していないようにして課税回避をするケースが頻出していました。ここにも規制の網がかかりました。
税金とは、国民にもれなく能力に応じ、かつ租税法にのっとって均等に課税されるべきものです。つまり、正直者がばかをみないような世の中をつくるためにも、上記のような税法の改正は必要なことだと考えます。
「正規の簿記」がすべての基本
──冒頭に述べられた所得税の改正について、少し触れていただけますか。
今仲 まず、自営業者などフリーランスが増加している状況を踏まえ、給与所得控除・公的年金控除の額を10万円減額し、基礎控除を10万円引き上げています。その分、フリーランスに手厚い税体系にしたということです。さらに年収が850万円を超えたら給与所得控除が195万円(現行は1000万円超で上限220万円)となり、また、合計所得金額が2400万円を超えると、基礎控除が逓減、2500万円でゼロになります。高額所得者にとってはきびしい改正となりました。とくに850万円という線引きですが、この金額が高額所得に当たるのかどうかは、いまの日本の労働環境を見ると少し疑問だと思います。
──「青色申告特別控除」についても、注目すべき改正がありましたね。
今仲 正規の簿記、つまり複式簿記の原則のもとに記録している青色申告特別控除の額が65万円から55万円に引き下げられますが、重要なのはその際、「電子帳簿保存法」(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)の適用を受けているか、あるいは電子申告を行っている場合は、控除額が65万円のままとなり、基礎控除が上がる分、実質減税となることです。
──この改正が行われた意味は何なのでしょうか。
今仲 正規の簿記(複式簿記)には、網羅性、立証性、秩序性が求められます。なかでも立証性は極めて重要。この改正には、過去にさかのぼっての記録改ざんを防いで立証性のある簿記を推奨するという意味合いがあります。現在、ちまたで販売されている会計ソフトは、過去の記録を履歴を残さずに遡及(そきゆう)訂正できるものがほとんどです。一方、TKCの会計システムの場合、やむを得ず遡及的な訂正・加除を行った場合には履歴が残ります。ちなみに、電子帳簿保存法では過去の訂正履歴を残さなければならないとされています。つまり、青色申告事業者は、TKCのような履歴が残るシステムを使用し、電子申告を行えば、減税の恩恵を受けることができるということです。この改正は、正直者がばかを見ない税法への第一歩といえるかもしれません。今後は法人税にも、この条項を入れるよう、TKC全国会として働きかけていきたいと考えています。
※令和4年税制改正で、特例承継計画の提出期限が1年延長され、2024年(令和6年)3月31日となりました。
(インタビュー・構成/本誌・髙根文隆)