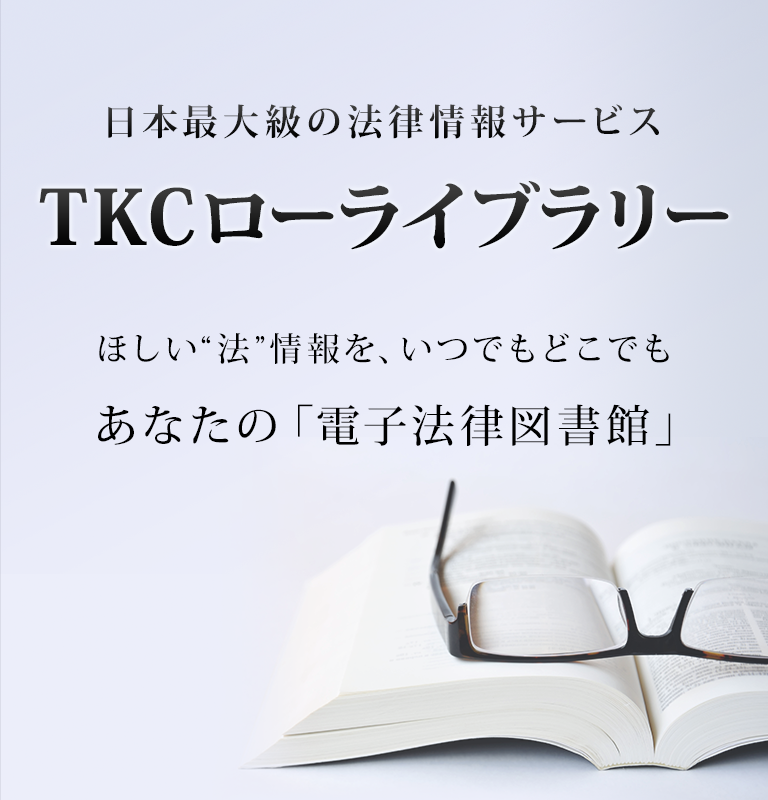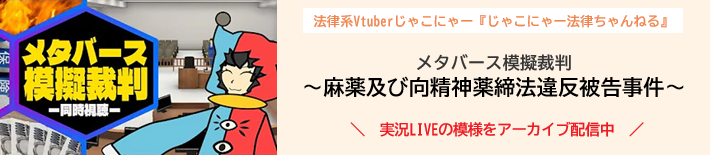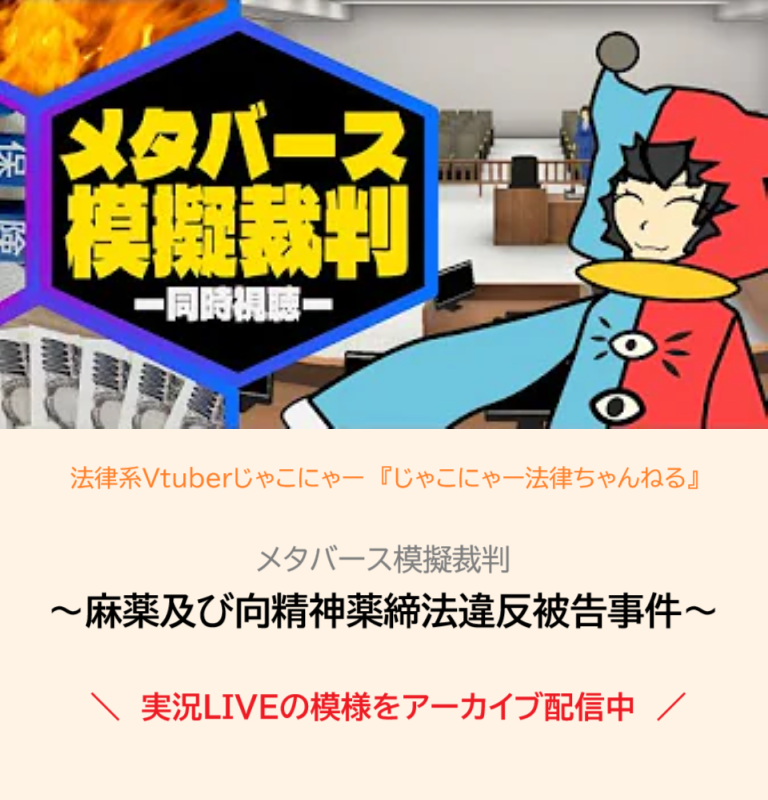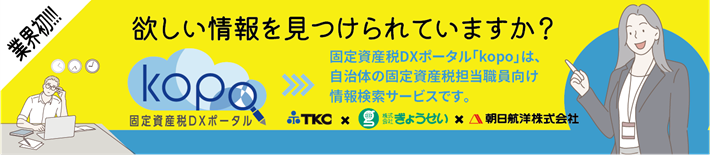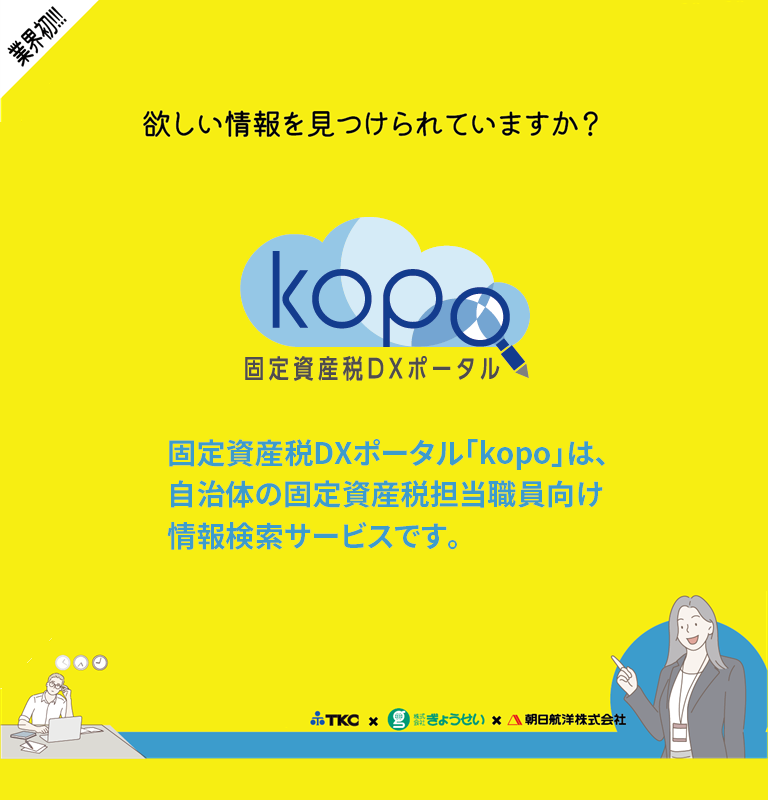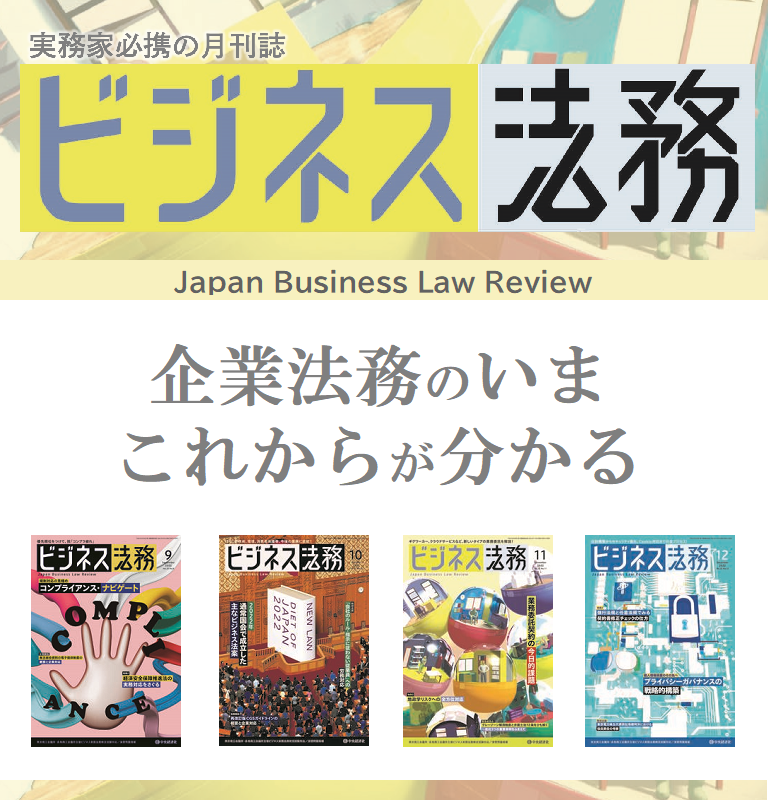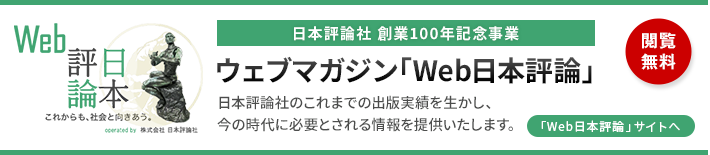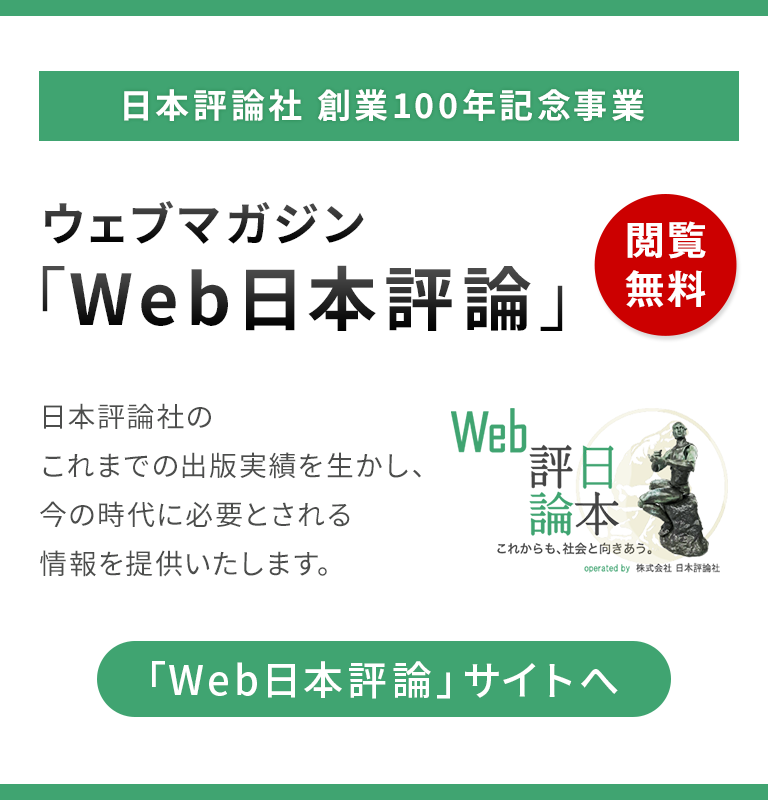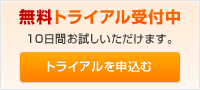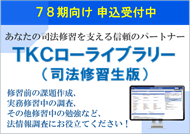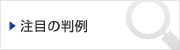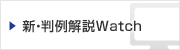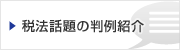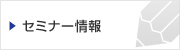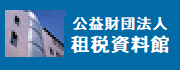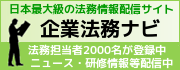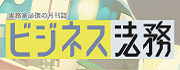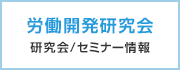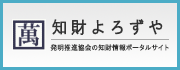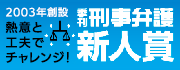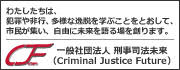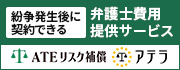2025.07.15
児童扶養手当支給停止処分取消請求事件
 ★
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年8月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
★LEX/DB25574366/最高裁判所第三小法廷 令和 7年 6月10日 判決(上告審)/令和6年(行ツ)第54号
配偶者のない母として4人の子を養育し、児童扶養手当を受給していた上告人が、平成29年4月20日、平成27年11月分に遡って障害基礎年金(障害等級1級)の給付決定を受け、同月分から平成29年3月分までの障害基礎年金として195万3158円の支払を受け、同年4月分以降も障害基礎年金の支給を受けることになったため、京都府知事から、児童扶養手当法(令和2年法律第40号による改正前)13条の2第2項の規定を受けた同法施行令(令和2年政令第318号による改正前)6条の4に基づき、同年2月分以降の児童扶養手当の支給を停止する旨の処分を受けたことから、児童扶養手当法施行令(同改正前)6条の4のうち、障害基礎年金の子加算部分だけでなく本体部分についても併給調整の対象として児童扶養手当の支給を停止する旨を定めた部分は、〔1〕児童扶養手当法(同改正前)13条の2第2項に基づく法律の委任の範囲を逸脱した違法、無効なものである、〔2〕憲法14条、25条及び国際人権規約等の条約に反した無効なものであると主張して、本件併給調整規定に基づいてされた本件各処分のうち、それぞれ障害基礎年金の子加算部分に相当する部分を除く部分の取消しを求め、第一審が請求をいずれも棄却したことから、上告人が控訴し、控訴審が、本件控訴を棄却したところ、上告人が上告した事案で、児童扶養手当法13条の2第2項1号の規定及び児童扶養手当法施行令6条の4の規定のうち同号所定の公的年金給付中の受給権者に子があることによって加算された部分以外の部分を対象として児童扶養手当の支給を制限する旨を定める部分が、障害基礎年金との併給調整において憲法25条、14条1項に違反するものとはいえないなどとして、本件上告を棄却した事例(反対意見あり)。
2025.07.15
損害賠償等請求事件(ジェットスター・ジャパン事件)

LEX/DB25622534/東京地方裁判所 令和 7年 4月22日 判決(第一審)/令和4年(ワ)第18366号
航空運送事業を営む被告との間で労働契約を締結し、客室乗務員として勤務していた原告らが、被告から労働基準法34条1項の定める休憩時間が付与されない勤務を命じられ、これに従事したことにより精神的苦痛を受けたと主張して、被告に対し、選択的に債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為に基づく損害賠償金(慰謝料及び弁護士費用)として、原告各自につき金員及び遅延損害金の支払を求めるとともに、現在客室乗務員として被告に勤務している原告らが、将来にわたって継続的に、被告から同法34条1項の定める休憩時間が付与されない勤務を命じられるおそれがあると主張して、人格権に基づき、上記勤務を命ずることの差止めを求めた事案で、被告が原告らに対して同条に違反する勤務を命じたことは、労働者の健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)に違反するというべきであるから、被告は、これにより原告らに生じた損害について賠償する責任を負うとし、また、現職原告らの差止請求は、被告が、現職原告らに対し、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を付与しない勤務(労基規則32条2項所定の時間の合計が上記休憩時間に相当する場合を除く)を命ずることの差止めを求める限度で理由があるとして、原告らの請求を一部認容した事例。
2025.07.08
警察庁保有個人情報管理簿一部不開示決定取消等請求事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和7年8月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25574338/最高裁判所第三小法廷 令和 7年 6月 3日 判決(上告審)/令和5年(行ヒ)第335号
上告人(控訴人・原告)が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、警察庁長官に対し、行政文書の開示を請求したところ、警察庁の保有する保有個人情報管理簿122通につき、それぞれの一部を開示し、その余の部分には、情報公開法5条3号又は4号所定の不開示情報が記録されているとして、これを不開示とする旨の決定を受けたため、被上告人(被控訴人・原告)・国を相手に、不開示部分の取消し等を求め、第一審が、本件処分のうち一部を取り消し、警察庁長官に対して同部分を開示する旨の決定をするよう命じ、本件処分のうちその余の取消請求については棄却し、またその余の義務付け請求に係る部分を不適法却下したため、上告人が控訴し、控訴審が、全10項目のうち3項目の記載欄についてはいずれも3号情報又は4号情報に該当すると認められ、7項目の記載欄については、そのうち分類A及び分類Bの情報については3号情報又は4号情報に該当すると認められる一方、分類Cの情報についてはこれらの該当性を認めることができないとし、7項目の記載欄のうち分類Cに係る部分は、情報公開法6条1項に基づき、開示しなければならないとして、第一審判決を変更したところ、上告人が上告した事案で、控訴審は、別件各決定によっても開示されていない「備考」欄である別紙目録記載2及び3の部分についても、被上告人に対し、文書ごとに、小項目が設けられているか否か、小項目が設けられている場合に、それでもなお当該「備考」欄について一体的に本件各号情報が記録されているといえるか否か等について明らかにするよう求めたうえで、合理的に区切られた範囲ごとに、本件各号情報該当性についての判断をすべきであったということができるが、しかるに、原審はそれぞれ一体的に本件各号情報該当性についての判断をしたものであり、判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとして、原判決中、一部を破棄し、当該破棄部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻し、上告人のその余の上告を棄却した事例(3名の裁判官各補足意見、裁判官1名の意見あり)。