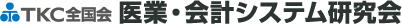病医院訪問・FX4クラウド活用事例 透析治療と予防医療で患者に貢献「100年続く医療法人」を目指す
訪問先 医療法人社団厚済会
理事長 大西 俊正(おおにし・としまさ)
会 長 花岡 加那子(はなおか・かなこ)
「医療法人社団厚済会」(神奈川県横浜市)は、1980年に大西俊正理事長(写真右)が開業して以降、横浜市・横須賀市に5つの病医院を展開。透析治療を中心として地域の患者を支えるほか、近年は生活習慣病の予防にも力を入れる。経営面では、FX4クラウドを導入し、部門別管理などを通じて経営状況の詳細な把握や打ち手の検討を行っている。主に経営面を担当する花岡加那子会長(写真左)に話をうかがった。
| DATA | 医療法人社団厚済会 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-10-1 TEL:045-844-5739 https://kousai.or.jp/ | |
| 運 営 医療機関 | 横浜じんせい病院 上大岡仁正クリニック 文庫じんクリニック 金沢クリニック 追浜仁正クリニック |
透析患者の需要に合わせ分院展開 患者のニーズに応じ在宅血液透析など実施
――まずは医療法人としての、これまでの歩みをお聞かせください。
花岡 1980年に私の父である大西俊正理事長が、横浜市の上大岡に透析特化のクリニックを開業したのが始まりです。当時は透析治療が保険適用となり、透析の患者数が増加する一方で、透析ベッドが主に大学や中核病院にしかなく、不足が問題になっていました。
そのため、横浜市立大学に勤務していた理事長は、「地域に透析患者の受け皿が必要である」と強く感じ、クリニックの開業を決意したのです。それ以降、地域の需要に応じるかたちで、京急沿線の主要駅を中心に透析に特化した医療機関を開設していきました。
また、以前は透析を受けている患者さんの合併症に対応できるよう、急性期病院を開設、運営していたのですが、地域のニーズの変化に合わせて閉院し、代わって療養病床を持つ病院を開設しました。現在は横浜市内と横須賀市内で4つのクリニックと1つの病院を運営しています。
――貴法人における透析治療はどういった特徴があるのでしょうか。
花岡 1つ目に、クリニック内で手術に対応していることが挙げられます。患者さんの高齢化が進むなか、手術のために馴染みのない病院へ移ることは大きな負担を伴います。シャント(透析に必要となる、動脈と静脈をつなげた血管)が詰まるなどして使えなくなったときも、普段から通い慣れたクリニックで手術を受けられるよう、上大岡仁正クリニックでは透析治療で必要となる手術を実施しています。
こちらのクリニックには毎週、慈恵医科大学の先生方に来ていただいて手術できる体制を整えています。クリニックの臨床検査技師や診療放射線技師らともチームを組んで患者さんの状態を管理することで、大学病院並みの医療を提供できていると考えています。
2つ目としては、透析患者さんの希望に合わせた透析治療法を提供しています。透析といっても、頻度や1回あたりの時間などが異なるさまざまな方法があるわけですが、特に患者さんの自宅で行える「在宅血液透析」は負担が少なくなる一方で、機器の設置作業や担当する医療機関からの遠隔での管理が必要になるため、実施できる医療機関はそう多くありません。上大岡仁正クリニックは、横浜市内のクリニックでは唯一実施しています。
――近年では透析治療だけではなく、透析を受けるような状態になることを防ぐ、予防の面にも注力されているそうですね。
また、できるだけ透析の導入を遅らせるような取り組みを行うなど、透析の導入期から患者さんと「伴走」することにも注力しています。あらかじめシャントを作っていつでも透析できるような準備をしつつ、患者さんの状態に合わせ、生活習慣の改善を促したり、薬の調整を行ったりすることで、できるだけ透析を受けずに済む期間を長くできています。もちろん、緊急時には迅速に対応できるよう、中核病院との連携も強化しています。
療養病床50床を有する「横浜じんせい病院」
――連携のお話がありましたが、ほかの医療機関とはどのようなかたちで地域連携に取り組まれているのですか。
花岡 近隣の病院など14の腎医療および関連医療機関と連携し、腎臓・高血圧疾患診療のネットワークを構築しています。また、クリニックや病院の外来では中核病院の先生方に担当いただくこともあり、まさに「顔が見える連携」が実現できています。スムーズな連携の背景としては、当法人で横浜市の透析患者のうち約1割を受け入れていることや、大学の先生方との共同研究に積極的であることも挙げられると思います。
持続的な経営を目指し人材育成 チーム活動で業務改善に取り組む
――貴法人では「研修センター」を設置するなど、人材育成に積極的なように見受けられます。人材育成の取り組みを行われたきっかけは何かあるのでしょうか。
花岡 「100年続く医療法人」を目指そうと思ったからです。私が入職したのは2007年だったのですが、当時は他の多くの病院や医療機関と同様に、理事長のカリスマ性やリーダーシップに従って職員が動く、というような組織でした。そのため、「職員の自発性や改善への意欲を高めよう」と思ったのです。
誰かの考え方に依存するのではなく、1人ひとりが学んで能力を伸ばして行けるようにしなければ、価値観が多様化するこれからの時代では、持続的な経営は難しくなります。そこで、職員の主体性を高められるよう、人材育成に注力してきました。
――具体的には、どのようなことに取り組まれているのですか。
花岡 取り組みの1つとして、全職員が参加する「チーム活動」での業務改善策の話し合いを行っています。
当法人では「10か年計画」をつくり、それに基づいた3か年計画や、年間事業計画を立てています。そのなかで、年間事業計画を達成するための、「患者さんのニーズにどうこたえるか」「職員満足度を向上させるためにはどうすべきか」といった課題を定め、それらについて、職員をそれぞれ割り当てたチームをつくり、チームごとに話し合ってもらいます。
現在は40以上のチームが活動しており、最小単位では10人程度です。メンバーは看護師や理学療法士など、多職種で構成しています。チームでの活動によって、職員の主体性が生まれるほか、さらに新しいプロジェクトの発足や業務改善策の提言につながることもあります。また、さまざまな職種の職員が、実際の診療の場を離れて話し合うなかで、課題解決以外の部分についても話が出て関係性が深まり、結果として多職種連携がスムーズになる効果もあると思っています。
そうしたなかで、2020年に「研修センター」を設置しました。センターで組織横断的な研修を行うとともに、職員に当法人の理念を理解してもらうよう取り組んでいます。センターには会議できるスペースがあり、そこでチーム活動の会議が行われることもあります。
88床の透析ベッドを備える「上大岡仁正クリニック」
――貴法人では「くるみん認定」や「えるぼし認定」を受けるなど、働き方の改善にも取り組まれておられます。
花岡 もともと療養病床や透析クリニックでは、夜間や救急の対応はそう多くないため、たとえば家庭の都合などで時短勤務を希望する職員の方や、働きたいけれども大学病院では働くのが難しいという医師の先生方の入職が比較的多くなっているように思います。そのため、そういった職員や先生方の要望に柔軟に対応してきたことで、結果的に体制が整備され、職員の待遇について手厚くなったという面があるかと思います。とはいえ、外部評価に気づける機会になりますので、各種認定は積極的に受けるようにしています。
法人事務局は上大岡駅直結の「ゆめおおおかオフィスタワー」にある
FX4クラウドで部門別・診療科別管理を実現 予防医療で地域の健康を支える存在に
――貴法人では経営管理ツールとして「FX4クラウド」を導入しているとうかがいました。
花岡 導入してから9年ほどになります。顧問税理士の押田吉真先生から、単に過去の計算をするだけではなく、将来の計画を組んで追いかける必要性を伺い、また部門別による管理機能が充実しているとお聞きしましたので導入を決めました。
導入以来、少しづつ整備を進めていて、現在は施設ごとに部門別予算を組んで管理しています。特に外来を設けている医療機関については、診療科別の管理を行っています。
――使用していくなかで、特に利便性を感じられているところはありますか。
花岡 やはりクラウドなので、いつでもどこでも、気になったときに数字を確認できるのが便利ですね。単に毎月の収支だけであれば、レセコンのデータを見ればある程度わかりますが、費用などを含めて全体および医療機関別の推移がどうなっているかがすぐにわかるのは、FX4クラウドがあるからこそだと思っています。細かく数字を見られるからこそ、状況を分析しやすくなり、何かあった際の計画変更もやりやすくなっていると思います。
私は経営の数字のなかでは、特に限界利益に注目しています。各年度のなかで目標数値を定めていますので、1年や10年後の目標値と達成状況をこのシステムから出力し、各部署の部門長とも共有できるようにしています。
毎月の経営状況を確認する会議では、MR(マネジメントレポート)設計ツールを使い、最新のデータを表計算ソフトに出力して作成したグラフを活用しています。たとえば過去3年分のデータから収益などの推移をグラフ化できるので、経営の打ち手を考えるときも一目でわかって便利です。
――それでは最後に、これからの運営の展望についてお聞かせください。
花岡 「顧客価値を生み出せる医療機関」を目指し、経営の品質を高めていきたいです。人材育成の面では、チームの活動において、職員の希望に応じてプロジェクトのコンテンツが増えすぎてしまった面があるので、選択と集中を行っていきたいです。
当法人はもともと透析患者への医療の提供というところから始まってはいますが、これからは予防段階での医療により一層力を入れていきたいと考えています。たとえば、これまでも地域の企業の健診を受け付けてきたのですが、今後は健診センターを開業し、より多くの健診を実施していく予定です。また、「求められる医療に対してはできる限りこたえる」というスタンスのもと、地域での需要があれば、さらなる分院の開業も検討したいと思っています。
生活習慣病の改善などを通じて、当法人が横浜や横須賀の患者さんの健康を支え、医療を守る存在になりたいですね。
左から順に、巡回監査士の小林正樹氏、花岡加那子会長、大西俊正理事長、押田吉真税理士、藤田倫子氏
税理士事務所からの一言
税理士法人押田会計事務所
代表税理士 押田 吉真
独自領域で医療の未来を切り開くクリニック
厚済会様に関わらせていただき15年以上になります。この間、事業承継についても取り組みました。現在、大西理事長のご子息達が病院を運営する次世代の体制が整いました。毎月の報告会では、部門別変動損益計算書で診療所別に経営状態をチェックし打ち手を考えています。今後、予防医療にも力を入れていく次世代の病院経営を全力でご支援していきます。
(2024年3月29日/TKC医業経営情報2024年5月号より)