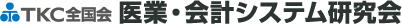病医院訪問・MX2クラウド活用事例 妊婦・スタッフの安全・安心を無痛分娩で支える
医療法人寿恵会船橋レディスクリニック
理事長 船橋 宏幸(ふなばし・ひろゆき))
1994年に茨城県古河市で承継開業した船橋宏幸理事長(医療法人寿恵会船橋レディスクリニック)。以来、30年にわたり地域の出産を支えてきた。また、ネックとなっていた出産における痛みを取り除くため、無痛分娩にも対応し、その質向上と妊婦の安心・安全に取り組んできた。運営面では「MX2クラウド」による業績検討会で、厳しい環境下の経営数値の把握に余念がない。船橋理事長と顧問の税理士法人報徳事務所の赤岩茂代表社員、羽鳥華純巡回監査士に話をうかがった。
| DATA | 医療法人寿恵会船橋レディスクリニック | |
|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県古河市諸川657-3 TEL:0280-76-0386 https://www.funabashi-lc.jp/ | |
| 診療科目 | 産婦人科・内科・小児科 | |
| 診療時間 | 9:00~11:30(月曜~土曜) 休診日 日曜、祝日、第2水曜日 第2土曜日・第4土曜日は1か月検診のみ |
昼の外来と夜の当直は不可欠 「使命感」がなければできない仕事
――まず開業の経緯からお聞かせください。
船橋 もともと父の代からの産婦人科診療所で、それを事業承継し古い診療所を建て替えて、1994年に開業したという流れになります。父は医局の近くということから横浜で1960年に1度開業していたのですが、敷地も狭く2床くらいのベッドでしたので、故郷であるこの地に1972年に移転して開業しています。昔は、診療所と自宅が隣接していて、夜遅くの出産などは生活の一部になっていました。そういう中で赤ちゃんが生まれるというのは感動的な仕事だと感じていましたので、小さいときからお医者さんになろうとずっと思っていました。
現在のクリニックは、産婦人科を核として一般内科、小児科、予防接種など、漢方医療を得意とする女性内科医師の応援を得ながら、女性医学の総合クリニックを目指しています。20年くらい前から自治医科大学の内科の医師を派遣してもらっているのです。先代からのクリニックなので更年期障害や内科的な病気などの患者さんも多く、また赤ちゃんが生まれるとその流れで子どもも来院する。娘も大学で産婦人科医をしていますが結局のところ、三世代ぐらいの年月が経過すると女性の一生を診ることとなり、総合的な診療が求められます。お産は減ってきているのですが、あくまで産婦人科がメインで、得意とする無痛分娩でお産を中心に広げていくことを考えています。
8床ある入院個室
――患者さんと接する際に心掛けていることやモットーについてお聞かせください。
船橋 実践していることとして、①診療は、誠意と献身をもって対応する、②患者さまの立場に立って考える共感、思いやり、愛情を忘れない、③患者さまには、自分にとって良好な状態で、微笑みを持って対応する、の3つに集約されます。それと患者満足度については入院がありますから意識していて、食事には気を遣っています。外注のレストランが入っているのですが、その食事を看護師さんらと一緒に食べながら相談してメニューを決めています。
――産婦人科診療所は各地で減ってきていますね。 船橋 そうですね。お産をしている開業医はだんだん減ってきて、古河市でも2件になりました。当クリニックでもピーク時は年間約280件のお産がありましたが、近年は150件くらいになっています。 ――年間280件といえば、いつもお産があるような状態だったと思いますが、先生の負担も大変だと思います。 船橋 週末だけ当直の医師を頼んでいましたが基本は私が当直しています。それは今も変わりませんが、全体の数が減ってきたのは、肉体的には助かっています。ただ、当然のことながら経営的には厳しくなってきているというのが正直なところです。 ――病床は8床ということですが、ピーク時も8床のままだったのですか。 船橋 正常分娩の場合の入院期間は5日程度なので、8床でもかなりのお産に対応できます。とはいえ、患者さんは均等に来るわけではなく、夜もある。リスクも伴いますのでその受け入れ体制をつくっておかなければならず、コストもかかります。夜間や深夜の分娩も私が対応しますが、1日30人~60人の外来の対応もある。そこが産婦人科診療所の難しいところです。私が昼も夜もなぜできているかといえば小さいときからの習慣もあってだと思いますが……。 赤岩 使命感だと思いますよ。それがなければできない仕事だと思います。
船橋 以前のようにお産が多かったときは、ほとんどの開業は成功していましたが、せっかく技術があるのですから数が減ったからやめるというのは残念です。
無痛分娩でお産の最大のネックだった「痛み」を取り除いてあげたい
――船橋先生は早くから無痛分娩に取り組んでいらっしゃるようですね。
船橋 開業してからですが、開業産婦人科医の勉強会があって、そこで無痛分娩のルーツともいえる田中ウイメンズクリニックの田中康弘先生のところに研修に行く機会がありました。田中先生は1973年の開業以来、麻酔科医の経験を生かし、局所麻酔(硬膜外麻酔)による無痛分娩とマタニティビクス(有酸素運動)によって、「出産は痛くて苦しい」から解放することに取り組んできた人で、無痛分娩の師匠です。私は小さいときからお産のときの痛がる声を聞いて育っていたので、何とか痛みを取ることはできないのかとずっと思っていました。ところが大学でも無痛分娩は行っていないし、麻酔科で勉強しようとも考えましたが、地元に戻らなければならずそれもできませんでした。そういう中で田中先生にお会いし、無痛分娩研究会に参加して習得できたのが1999年のことです。
当時は研究会への参加者はまだ少数でした。というのもまだお産の数も多かったので、正常分娩でよかったからです。しかし、「十数年経つと無痛分娩と3D超音波が一般的になる」と田中先生が言っていたように、現在は無痛分娩を行う医師も増えてきていますし、無痛分娩の希望者も増えてきています。そこでは、体制をしっかり整え、スタッフの教育を含めより安全性を高めていくことが重要となっています。
――どのようなことに取り組んでいるのでしょうか。
船橋 当クリニックのお産も、近年は硬膜外麻酔による無痛分娩の割合が高くなっています。昨年の実績で30%を超えました。そういう中でクリニックの院長が孤独に1人で取り組むのではなく、専門家の指導のもとで行うほうがさらに質を高められますし安心を得られます。そのため、無痛分娩の質と安全性向上、スタッフの人材育成を事業とする㈱LA Solutionsにコンサルテーションしてもらうようにしました。代表の入駒慎吾先生というのは産婦人科医を8年続け麻酔科医に転向して12年。聖隷浜松病院や国立成育医療センターでの無痛分娩を牽引した経験を持つ人です。
実際に技術や取り組み方のアドバイス、相談をしながら行うと質も向上するとともに安心できます。
――誰でも無痛分娩を適応できるのでしょうか。
船橋 基本的には誰でもできます。一般的には痛みに弱い人ですね。特に里帰り分娩の人に多い傾向です。
お産の最大のポイントは痛いということなんです。けれども、これからの時代は、痛いものは取り除いてあげなくてはいけません。かつ、結果として赤ちゃんも元気、お母さんも元気。無痛分娩はスタンダードになっていくと思います。
日本の無痛分娩は、2007年に2.8%でしたが、2020年には8.6%に増えています。諸外国を見ると無痛分娩のほうが一般的になっているケースが多く、たとえば、米国では約70%です。そういう波が日本に押し寄せていると思います。
――船橋先生にとっては無痛分娩と正常分娩とでは、どちらのほうが安心かというのはあるのでしょうか。
船橋 無痛のお産のほうがとても安心ですね。なぜかといえば、いろいろな人が血圧を測ったり、痛みの感覚をチェックしたり、より患者さんのところに行くことになるんです。患者さんも安心ですし、われわれも異常があればすぐに発見できます。
計画無痛分娩はスタッフの配置や負荷を小さくする
――リスクの大きい患者さんもいらっしゃると思いますが、病院等との連携も大事になりますね。
船橋 分娩に関してはローリスクの分娩を中心に行っていて、ハイリスク分娩の場合は自治医科大学病院、筑波大学病院へ紹介しています。その一方で無痛分娩を希望する患者さんがいらっしゃる場合は、逆に病院から当クリニックに紹介されたりします。
――経営管理のツールとしてはMX2クラウドを使われているとのことですね。今日もこの後、業績検討会を行うと聞いています。 羽鳥巡回監査士 毎月訪問させていただき、月々の業績については奥様(助産師)と一緒に変動損益計算書を見ながら確認しています。5か年の中期計画をもとに作成した単年度の計画と実績の数値とを比較し、ズレがあれば打ち手について検討いただいています。最近は医薬品の値上がりなどもあり、利益率の変動などを中心に説明しています。 「MX2クラウド」の画面
院長先生には3か月ごとの「業績検討会」に同席いただいています。本日は決算が近づいていますので、着地予測について検討いただく予定です。合わせて、次期の予測も検討しています。お産が減っている傾向にありますので、今後は資金繰りの対応や、自費診療の単価の再検討などがポイントになります。
※画面はサンプルです
――船橋先生は、クリニックの課題をどのように捉えていらっしゃいますか。
船橋 人口減少、出生数の減少により、全国的に従来の分娩中心の経営は厳しくなっていて、今後も大きな増加は期待できません。国や行政からの支援や補助がなければその存続は難しい。地域の重要な社会的インフラなのですから、その手当が必要になっています。当クリニックの場合は無痛分娩のニーズがあるので成り立っているといえるでしょう。さらに、計画無痛分娩が里帰り分娩や2人目以降の出産で増えていて、分娩の数だけでなくスタッフの配置や負荷なども小さくて済む。また、無痛分娩によって帝王切開率も下がっていて、経営面でも有効です。
地域の産婦人科クリニックの存続のため、今後も若い医師や看護師、スタッフなどに周産期医療やその未来像を伝えていきたいと考えています。
船橋院長を中心に、左が赤岩茂公認会計士・税理士、右が巡回監査士の羽鳥華純さん
会計事務所からの一言
税理士法人報徳事務所
巡回監査士 羽鳥 華純
タイムリーな業績報告と業績予測で経営をサポートします
寿恵会様とは設立当初からのお付き合いとなります。少子化で分娩数が年々減少するなか、産婦人科の経営は以前より厳しい状況ですが、MX2クラウドを利用したタイムリーな業績報告、継続MASを利用した業績予測を行うことで、診療所経営の一助となるよう尽力しています。地域のインフラとしても重要な寿恵会様の経営を今後も全力でご支援いたします。
(2024年4月10日/TKC医業経営情報2024年8月号より)