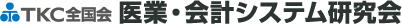クリニックの「税」のあれこれ 第4回 親族への給与は経費になる?
TKC全国会 医業・会計システム研究会 赤松 和弘
配偶者などの親族に、事務を手伝ってもらっている院長先生もおられるのではないでしょうか。今回は、こうした事業に従事した親族に支払う給与は必要経費に算入できるのか、そのためには何が必要になるのか、など、親族が事業に従事したことによる給与の扱いについて解説します。
Q 個人診療所を開業しましたが、看護師である妻にも管理面などで手伝ってもらっています。その給与は経費となるのでしょうか。
A 生計を一にしている配偶者その他の親族に対する給与は原則として必要経費になりません。しかし青色申告の場合、一定の要件のもとで「青色事業専従者給与」として必要経費に算入できます。
生計を一にする親族に支払う給与等の規定は?
個人事業において事業主の親族が事業に従事しているケースは多く見受けられます。しかし親族への労務の対価としての給与等の支払いが、経費性を有する労務の対価としての支払いなのか、扶養の立場からの家計的な支払いなのかを明確に区分することは極めて困難と考えられています。
そこで所得税法では、事業主と生計を一にする親族に支払った給料、賃借料、借入金利子等は、その事業主の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入しない旨を規定しています。また、その親族が他に支払う賃借料、保険料、公租公課等必要経費とされるものがある場合には、その金額は事業主の必要経費に算入することとされています。この場合の親族は収入金額も必要経費もないものとみなされます(所得税法第56条・図表1参照)。
たとえば、院長(事業主)が先代院長と生計を一にしている場合、先代院長へ支払う労務の対価は経費にはできません。しかし、先代院長が所有する医療機器を事業の用に供している場合、先代院長が他に支払う賃借料や保険料、減価償却費、償却資産税などが事業主の経費に計上できます。
「生計を一にする」とは、日常生活の資を共通にしていることをいい、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものではありません。
労務の対価が経費となる特例
ここまで、生計を一にしている親族への労務の対価は経費にできないと説明しました。しかし特例として生計を一にしていても労務の対価を経費とする方法があります。それが青色申告による青色事業専従者給与です。何気なく親族へ支払う給与を経費に計上しているかもしれませんが、これは特例です。ここで青色申告について確認しておきましょう。
わが国は申告納税制度を採用していますので、その制度が有効かつ円滑に実施されるため、納税者自らが正しい記帳に基づく適正な申告と納税を推進する必要があります。そこで真の申告納税制度の確保発展のため、シャウプ勧告に基づく1950年の税制改革によって青色申告制度が設けられました。これは、「正しい記帳を行うことで事業と家計とを明確に区分し、正しい納税額を算出して正しく納税する」ことに積極的に取り組む納税者には恩恵を与えるという制度です。その恩恵の1つが青色事業専従者給与であり、必要経費として算入できるようになりました。青色申告には次の要件が必要です。
(1)税務署で青色申告の承認申請書を提出して、あらかじめ承認を受けること
(2)一定の帳簿書類を備え付けて、これに事業所得等の金額に係る取引を記録し、かつ、これを保存すること
なお、TKCシステムを活用すれば上記(2)は完全に遂行されます。
なお、TKCシステムを活用すれば上記(2)は完全に遂行されます。
事業者自らが記帳する重要性
青色申告の承認は、次に掲げる事由に該当する事実がある場合、その事実があった年に遡って取り消され、その年分以後は青色申告以外の申告書とみなされます(所得税法第150条)。
(1)帳簿書類の備付け、記録又は保存が所定の規定に従って行われていないこと
(2)帳簿書類について税務署長の必要な指示に従わなかったこと
(3)帳簿書類に取引を隠ぺい又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についての真実性を疑うに足りる相当の理由があること
いまでは帳簿書類の作成も会計ソフトに取引を入力する(=取引を伝票起票する)だけになりました。しかし仮に、会計事務所においてよかれと思って取引内容を自己判断して入力し、後日税務調査で事実が異なっていた場合は、上述(3)ととられ、青色申告の承認を取り消されることになりかねません。われわれTKC会計人が、事業者自ら会計ソフトに取引を入力することを推奨する本質はここにあり、医療機関を守るためなのです。必ず納税者自らが取引の事実の意思表示を残してください。
また、TKC会計人が巡回監査を通して、第三者の目でその真実性を確認し、確定申告に加え、税理士法第33条の2第1項に規定する計算事項等を記載した書面を添付(書面添付制度)し、税務の専門家の立場から作成した申告書をどのように計算し、整理したかを明らかにし取引内容が真実である旨を記載するのは、貴院の申告が税務署からの信頼を得るためです。
なお、現在のTKCシステムは、入力に代えて証憑書類をスキャンすることで取引を取り込め、事務負担が大幅に軽減されます。ぜひご活用ください。
なお、現在のTKCシステムは、入力に代えて証憑書類をスキャンすることで取引を取り込め、事務負担が大幅に軽減されます。ぜひご活用ください。
青色事業専従者給与は年末の未払計上に注意
青色事業専従者給与は、図表2の要件をすべて満たす必要があり、また、労務の対価として認められる金額は、図表3の状況に照らして判断することになります。
青色事業専従者給与額の判断基準については、TKC医業経営指標(M-BAST)やTKC医業経営指標[医業賃金統計編](M-BAST賃金)も活用できます。詳細はTKC全国会医業・会計システム研究会会員にお尋ねください。
生計を一にする親族の場合は、夜間緊急対応など時間外に従事することも考えられます。仮にそのような勤務環境において人材を募集する場合、どのくらいの給与提示が必要になるのか、なども考慮するとよいでしょう。
なお、月末締めの翌月10日払いの給与体系を採用している病医院が、12月末に他の従業員と同じく青色事業専従者給与を未払計上した場合は、その給与はその年分の必要経費に算入できませんので注意が必要です。
これは、所得税法第57条第1項で「給与の支払いを受けた場合」と規定されており、必要経費とするためには、支払うことが要件と規定されているからです。その代わり、翌年1月10日に支給したとき翌年の必要経費となります(参考:TKC税研データベース「12月末における青色事業専従者給与の未払計上」)。次回は中退共などの共済制度について、掛金や受取りの税務上の取扱い等を解説します。
(TKC医業経営情報2024年11月号より)