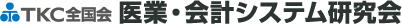予防活動と基礎知識の周知で山の遭難を減らしたい!
日本で初めての「国際山岳医」(Diploma in Mountain Medicine)として、「山岳遭難を減らしたい」という強い想いを胸に、遭難予防の活動などに力をいれる大城和恵医師。80歳でエベレストの最高齢登頂を果たした冒険家・三浦雄一郎氏の遠征隊のチームドクターとしても知られる大城医師に、山岳医としての活動やその役割について話をうかがった。
大城和恵
社会医療法人孝仁会
北海道大野記念病院
循環器内科・山岳登山外来
医師
Oshiro Kazue
長野県生まれ。日本大学医学部卒業。2010年、英国で日本人初「UIAA(国際山岳連盟)/ISMM(国際登山医学会)認定国際山岳医」を取得。2011年、北海道警察山岳遭難救助アドバイザーに就任。同年、札幌市の北海道大野病院(現・北海道大野記念病院)にて登山外来を新設。医学博士。日本循環器学会認定循環器専門医、日本内科学会認定内科専門医、日本プライマリ・ケア連合学会指導医・認定医、等。国立登山研修所専門調査委員、文部科学省南極地域観測統合推進本部委員、日本山岳協会医科学委員常任委員等も務める。主な山行歴として、2010年、北米最高峰マッキンリー(6,194m)山頂よりスキー滑降。2013年、三浦雄一郎氏エベレスト世界最高齢登頂遠征チームドクター。
ヒマラヤでの経験から
──日本で初めて、「国際山岳医」(Diploma in Mountain Medicine)を取得された大城先生ですが、もともとは内科医だったとお聞きしました。
大城 日本大学医学部を卒業後、同大学附属病院の第1内科に入局しました。特定の臓器ではなく、全身を診ることができる医師になりたいと考えたからです。
他方、勤務しながら、夏休みなどが取れると、カナダのロッキー山脈やタンザニアのキリマンジャロなどに登ったりしていました。長野県で生まれ育った自分にとって山は身近な存在だったのです。
北海道に移住したのは35歳のことです。博士号と内科専門医を取得したこともあり、環境を変えて自分の力で仕事がしたいと考えました。総合医を目指して呼吸器、血液、免疫と学んできた。次は生死に直結する循環器の勉強がしたい。そこで心疾患治療で実績を持つ北海道の「心臓血管センター北海道大野病院」(現・大野記念病院)で勤務することにしました。北海道を選んだのは、これまで何度も登山やスキーで訪れていた憧れの地だったからです。
──山岳医に転身されたきっかけは何だったのでしょうか。
大城 分岐点は、北海道に移住した後、ネパールのヒマラヤにトレッキングに行った時に、高山病の日本人に遭遇したことです。
できる限りの医療処置を行った結果、その日本人は無事に下山できたわけですが、その時は、自分の対応が正しかったのかどうか自信がなかった。それまで山の病気については、学んだことも診たこともなかったからです。
「山岳医療を勉強したい」。そんな思いが強くなるなか、海外の学会で「国際山岳医制度」の存在を知りました。これなら山岳医療を体系立てて勉強できると考え、病院を退職。約1年間、アルバイトをしながら、山登りのトレーニングを積みつつ、ヨーロッパで講義や実習を受けました。
その後、2010年に国際山岳医を取得すると、一度、辞めた大野病院からオファーをいただきました。山岳医として活動することを認めてもらい、さらには、「登山外来・登山者健診」を設置していただくことになりました。
現在は、月に1週間、予約制ではありますが、登山外来の医師として登山者のサポートを行いつつ、山岳医として活動しています。
多岐にわたる山岳医の活動
──これまで山岳医としてどのようなことを行ってきたのですか。
大城 北海道警察の「山岳遭難救助アドバイザー」を務めていて、救助隊と一緒に2011年から山岳パトロールをしています。遭難件数が多い8月に、救助隊と一緒に大雪山や旭岳を登りながら、登山者に声をかけたり、脱水予防の啓発をしたり、足首の捻挫予防のテーピングの仕方をレクチャーしたり、現場での遭難予防に取り組んでいます。
これまでの5年間の山岳遭難死者553人を調べたところ、救助隊が遭難者に接触した時に生きていた割合はわずか2.5%。つまり、医師が遭難に駆けつけたとしても何もできないわけです。遭難者を救助するのは救助隊の役割。だったら山岳医は何をするのか。遭難しないように予防することにこそ意味があると思っています。
──その他の取り組みとしてはいかがですか。
大城 7月から9月には、静岡県の富士山と富山県の剣岳に設置されている山の診療所で登山者等の診療を行っています。
富士山の診療所は8合目にあり、私は3週間ほど滞在するわけですが、体調を崩した登山者を待っても仕方がないので、ここでも登山道に出て、酸素量を測ったり、水分補給を意識させたりなど、遭難予防の活動をしています。
──山の診療所ではどのような疾患の患者さんが多いのですか。
大城 富士山は高山病と脱水症がほとんどです。剣岳は岩場が多いので怪我、骨折です。診療所で応急処置をして、1人で下山できる場合はよいですが、できない場合は、救助隊が背負うか、ヘリコプターで下山します。富士山ではヘリコプターが8合目まで上がれないので、7合目まで一旦、下してからヘリコプターを使います。
──主に遭難予防の取り組みに力を入れておられるわけですね。
大城 2012年から年4回、ファーストエイドの講習会を開催しています。登山者に自分の足で帰ることができるように最低限の知識と技術を学んでいただく場です。
「ファーストエイド=応急処置」と捉えるかもしれませんが、私はそのなかでも遭難予防を学んでいただくようにしています。このカリキュラムは、私が欧米で学んだことを基本に、日本の山の事情に合わせてつくりました。
登頂法を一緒に考えるのが
──他方、日本では珍しい「登山外来」ですが、具体的にどのような医療を提供しているのでしょうか。
大城 登山外来には、登山前の人と登山後の人が来院されます。
たとえば、登山前の人の診療の流れは、まず心電図と心臓の超音波検査、次に運動負荷心電図で不整脈や狭心症を診て、必要に応じて心臓CTで動脈硬化などがないかを確認します。そこで何かあった場合はまず治療です。
病気がなかった場合は、さらに心肺運動負荷試験で心臓と肺の機能を確認し、どういうペースで登れば心臓や肺に負担をかけないのかをアドバイスします。
三浦雄一郎さんも心肺運動負荷試験を行います。80歳の三浦さんがなぜエベレストを登頂できたのか。自分のペースを認識し、それを守ったからです。
身体の状態を確認した後は、山の地図を開いて、「あなたはこのルートを選んだ方がよい」など、一緒に登山計画などを考えます。
私のスタンスとして、病気があっても基本的にどうしたら登れるかを提案します。登山はチャレンジするスポーツでもあります。「自分の能力に合った山を選びましょう」と言われても、違う景色が見たいという人もいるし、憧れのあの山に登ってみたいという人もいます。私の役割は、その想いを諦めさせるのではなく、登頂できる体調に持っていき、その方法を提案することです。
平地の常識が通用しない世界
──冒険家の三浦雄一郎氏の海外遠征に、チームドクターとして同行しているともお聞きしましたが。
大城 三浦さんの海外遠征のコーディネーターの方から、「海外の山に登るので国際標準の山岳医療を知っている人に同行してほしい」ということで声をかけていただき、それからのご縁になります。また、その他でも、テレビの企画でタレントさんが海外の山を登るという時に登山隊に参加させてもらうこともあります。
三浦さんとは付き合いも長く、信頼関係もあり、継続的に体調管理をしてきたのでよいのですが、スポット的なテレビの登頂企画などは、登山隊の規模も大きく、個々のメンバーの体調の経過や、それぞれのパーソナリティなどを理解するのがなかなか難しい側面があります。そのことが取り返しのつかない事態を招く恐れもあるので、細心の注意を払っています。
話は逸れますが、三浦さんは毎回、私に敬意を持って接してくれます。それは私だけでなく、三浦さんを支えるすべての隊員に対してです。三浦さんは、自分がみんなに支えられていることを知っているのです。たとえば、10人のメンバーが2か月間、毎食、一緒に食事するわけですが、三浦さんはチーム全員が揃わないと絶対に食事をしません。「○○はまだ来ていないのか」と言って待っているのです。そのような行動の1つひとつが、「三浦さんのために頑張ろう」という気持ちにさせます。
──より過酷な環境の海外遠征となると、“教科書どおり”にいかないこともあると思います。
大城 そうですね。たとえば、ネパールのマナスルの登山隊に参加した時のことです。みんなが4リットルの酸素を吸入しながら登っていたのですが、渋滞してきたので、このままでは下山まで酸素が持たないと判断し、2リットルに変えたことがありました。
すると間もなく、カメラマンの体調が悪くなったのです。点滴や酸素吸入でリカバリーできたので結果的にはよかったのですが、限られた酸素のなかでの医療の難しさを痛感しました。
そのカメラマンは若く、心肺機能も高かったのですが、運動量も多く、何より体格が大きく、他の人より酸素量が必要だった。酸素2リットルの価値が他のメンバーとは違ったのです。
あと、これはこれまでの経験から学んだことですが、点滴は、温めてもマイナス20度の環境ですぐに冷えてしまう。そこで温めてから太い針で一気に落とすわけです。
平地の常識がどれほど通用しないのか。これには想像力が必要で、想像するためには経験と知識が必要なのです。それでも想像をはるかに超えた事態に遭遇することもあり、その場で判断しなければならない。その繰り返しです。
多くの登山者は山に対する
──昨今、日本は登山ブームとも言われていますが、その一方で、遭難者数の状況はどのようになっているのでしょうか。
大城 山岳遭難の発生件数や遭難者数の状況については、平成27年に過去最多となっています。翌年の平成28年こそ微減となりましたが、ここ十年の推移を見ると、右肩上がりで増えています(表)。
死者・行方不明者数について見ると、かつては遭難者の6人に1人が死亡していましたが、現在は9人に1人です。その理由として、救助体制の充実や携帯電話の通話エリアの拡大などが考えられます。
また、最近の傾向としては、仕事をリタイヤした中高年者が登山を始めるケースが増えています。それにともない遭難者の年齢層は、40歳以上が2,269人と全体の77.5%を占め、60歳以上でも1,482人と50.6%を占めます。
山岳遭難をケース別に見ると、「道迷い」が約40%と最も多く、「滑落」(約17%)、「転倒」(約16%)と続きます。登山道が比較的整備された富士山でも霧がかかったりして道迷いは起きます。
──そもそも人はどうして遭難してしまうのでしょうか。
大城 山に対するイメージが楽観的なのだと思います。多くの方は、良い天気のなか、整備された登山道を登り、自然を楽しみつつ登頂して帰りたいと思っています。でも自然のなかに入っていくのですから、平地より体の負担は大きくなりますし、霧や吹雪で道に迷うこともありますし、転んで怪我をすることもある。リスクを実感できないまま登山をしていることが問題です。
山を楽しむ気持ちは理解できます。ただ、どんな山でも危険があり、医療機関からも離れている。何かあった時は自分で何とかしないといけない場所であることを認識してほしいです。リスクを想像できれば、そのための事前準備ができ、万が一の時にも対応できるはずです。
多くの開業医に山岳医療の
──山岳遭難が増加するなか、山岳医の役割もますます重要になってくるのでしょうね。
大城 ただ山岳医といっても特別な資格ではありません。そのカリキュラムを受けなくても、山の診療所でずっと医療を提供している医師もいます。登山をしながら独自に山岳医療の勉強をしている医師もいます。私は山に携わるすべての医師と一緒にできることがたくさんあるのではないかと考えています。
時々、医師会主催の講演会で、患者さんが登山をする際に伝えていただきたいポイントや注意点などをお話させてもらうのですが、皆さん、非常に関心を寄せられます。多くの開業医の先生にその基礎知識を知っていただき、患者さんにお伝えすることで遭難件数は減っていくと思っています。
──開業医に知ってほしい山岳医療の基礎知識としてどのようなものがあげられますか。
大城 まず、高血圧、糖尿病などの持病が管理されていることです。そして、管理されていたとしても「平地の半分のスピードで登ってください」と伝えてほしい。登山1日目は血圧や脈が上がり心臓に負担がかかりやすいからです。
あとは最近、疲労遭難が増えていますが、そういう人は午前中の時点で脱水状態にあります。その際は、「登る前に500CC、途中は30分おきに150CC飲んでください」など具体的に数字で示すことが大切です。脱水症の遭難者に「水を飲みましたか」と聞くと決まって「飲んだ」というのですが、「どれぐらい飲みましたか」と聞くと、ペットボトル半分も飲んでないということが多々あります。
──その他はいかがですか。
大城 遭難は下山時に起きることが多いです。足の疲労で転んで怪我や骨折をしてしまう。初めて登山をする人、久しぶりに登山をする人には、標高が低い山を選んでもらう、もしくは緩やかな登山道を選択してもらう、さらにはストックを使うなどのアドバイスが遭難予防につながります。
あとは最近、血圧薬で利尿剤が入っているものがあり、それを飲んでいると脱水症になる可能性があります。どういう血圧薬が処方されているかを確認し、飲んでいる場合は、「この薬はたくさんおしっこが出るので、たくさん水分をとったほうがいいですよ」ときちんと伝えることが大事です。
──最後に、先生の今後の目標などについてお聞かせください。
大城 私の目標は「山岳遭難を減らすこと」です。そのために、これからも予防活動を続けていく。遭難を減らすには、山でのリスクを認識し、想像してもらうことが大切ですが、そこには知識が必要で、それは私たちが情報提供しなければなりません。しかも現場で役立つ情報です。その提供の仕方も工夫していきたいと思います。
もう1つは、救助隊が安全に活動できるように適切な知識や処置法を身につけていただくことです。これまでも救助隊に必要な医療的視点を提案してきました。その甲斐あってか、低体温症の遭難救助は進歩し、今まで助からないといわれていた人を助けることができるようになっています。遭難救助に医療が貢献できたと実感しているところですが、まだまだ社会に伝えきれていないことがあるので、今後、さらに力を入れる。山岳医としてのこれからの活動の中心になると考えています。(平成29年11月27日/本誌編集部 佐々木隆一)
大城和恵

社会医療法人孝仁会
北海道大野記念病院
循環器内科・山岳登山外来
医師
Oshiro Kazue
長野県生まれ。日本大学医学部卒業。2010年、英国で日本人初「UIAA(国際山岳連盟)/ISMM(国際登山医学会)認定国際山岳医」を取得。2011年、北海道警察山岳遭難救助アドバイザーに就任。同年、札幌市の北海道大野病院(現・北海道大野記念病院)にて登山外来を新設。医学博士。日本循環器学会認定循環器専門医、日本内科学会認定内科専門医、日本プライマリ・ケア連合学会指導医・認定医、等。国立登山研修所専門調査委員、文部科学省南極地域観測統合推進本部委員、日本山岳協会医科学委員常任委員等も務める。主な山行歴として、2010年、北米最高峰マッキンリー(6,194m)山頂よりスキー滑降。2013年、三浦雄一郎氏エベレスト世界最高齢登頂遠征チームドクター。
ヒマラヤでの経験から
山岳医への道を歩み出す
──日本で初めて、「国際山岳医」(Diploma in Mountain Medicine)を取得された大城先生ですが、もともとは内科医だったとお聞きしました。 大城 日本大学医学部を卒業後、同大学附属病院の第1内科に入局しました。特定の臓器ではなく、全身を診ることができる医師になりたいと考えたからです。
他方、勤務しながら、夏休みなどが取れると、カナダのロッキー山脈やタンザニアのキリマンジャロなどに登ったりしていました。長野県で生まれ育った自分にとって山は身近な存在だったのです。
北海道に移住したのは35歳のことです。博士号と内科専門医を取得したこともあり、環境を変えて自分の力で仕事がしたいと考えました。総合医を目指して呼吸器、血液、免疫と学んできた。次は生死に直結する循環器の勉強がしたい。そこで心疾患治療で実績を持つ北海道の「心臓血管センター北海道大野病院」(現・大野記念病院)で勤務することにしました。北海道を選んだのは、これまで何度も登山やスキーで訪れていた憧れの地だったからです。
──山岳医に転身されたきっかけは何だったのでしょうか。
大城 分岐点は、北海道に移住した後、ネパールのヒマラヤにトレッキングに行った時に、高山病の日本人に遭遇したことです。
できる限りの医療処置を行った結果、その日本人は無事に下山できたわけですが、その時は、自分の対応が正しかったのかどうか自信がなかった。それまで山の病気については、学んだことも診たこともなかったからです。
「山岳医療を勉強したい」。そんな思いが強くなるなか、海外の学会で「国際山岳医制度」の存在を知りました。これなら山岳医療を体系立てて勉強できると考え、病院を退職。約1年間、アルバイトをしながら、山登りのトレーニングを積みつつ、ヨーロッパで講義や実習を受けました。
その後、2010年に国際山岳医を取得すると、一度、辞めた大野病院からオファーをいただきました。山岳医として活動することを認めてもらい、さらには、「登山外来・登山者健診」を設置していただくことになりました。
現在は、月に1週間、予約制ではありますが、登山外来の医師として登山者のサポートを行いつつ、山岳医として活動しています。
多岐にわたる山岳医の活動
遭難予防に力を入れる
──これまで山岳医としてどのようなことを行ってきたのですか。 大城 北海道警察の「山岳遭難救助アドバイザー」を務めていて、救助隊と一緒に2011年から山岳パトロールをしています。遭難件数が多い8月に、救助隊と一緒に大雪山や旭岳を登りながら、登山者に声をかけたり、脱水予防の啓発をしたり、足首の捻挫予防のテーピングの仕方をレクチャーしたり、現場での遭難予防に取り組んでいます。
これまでの5年間の山岳遭難死者553人を調べたところ、救助隊が遭難者に接触した時に生きていた割合はわずか2.5%。つまり、医師が遭難に駆けつけたとしても何もできないわけです。遭難者を救助するのは救助隊の役割。だったら山岳医は何をするのか。遭難しないように予防することにこそ意味があると思っています。
──その他の取り組みとしてはいかがですか。
大城 7月から9月には、静岡県の富士山と富山県の剣岳に設置されている山の診療所で登山者等の診療を行っています。
富士山の診療所は8合目にあり、私は3週間ほど滞在するわけですが、体調を崩した登山者を待っても仕方がないので、ここでも登山道に出て、酸素量を測ったり、水分補給を意識させたりなど、遭難予防の活動をしています。
──山の診療所ではどのような疾患の患者さんが多いのですか。
大城 富士山は高山病と脱水症がほとんどです。剣岳は岩場が多いので怪我、骨折です。診療所で応急処置をして、1人で下山できる場合はよいですが、できない場合は、救助隊が背負うか、ヘリコプターで下山します。富士山ではヘリコプターが8合目まで上がれないので、7合目まで一旦、下してからヘリコプターを使います。
──主に遭難予防の取り組みに力を入れておられるわけですね。
大城 2012年から年4回、ファーストエイドの講習会を開催しています。登山者に自分の足で帰ることができるように最低限の知識と技術を学んでいただく場です。
「ファーストエイド=応急処置」と捉えるかもしれませんが、私はそのなかでも遭難予防を学んでいただくようにしています。このカリキュラムは、私が欧米で学んだことを基本に、日本の山の事情に合わせてつくりました。
登頂法を一緒に考えるのが
「登山外来」の大きな役割
──他方、日本では珍しい「登山外来」ですが、具体的にどのような医療を提供しているのでしょうか。 大城 登山外来には、登山前の人と登山後の人が来院されます。
たとえば、登山前の人の診療の流れは、まず心電図と心臓の超音波検査、次に運動負荷心電図で不整脈や狭心症を診て、必要に応じて心臓CTで動脈硬化などがないかを確認します。そこで何かあった場合はまず治療です。
病気がなかった場合は、さらに心肺運動負荷試験で心臓と肺の機能を確認し、どういうペースで登れば心臓や肺に負担をかけないのかをアドバイスします。
三浦雄一郎さんも心肺運動負荷試験を行います。80歳の三浦さんがなぜエベレストを登頂できたのか。自分のペースを認識し、それを守ったからです。
身体の状態を確認した後は、山の地図を開いて、「あなたはこのルートを選んだ方がよい」など、一緒に登山計画などを考えます。
私のスタンスとして、病気があっても基本的にどうしたら登れるかを提案します。登山はチャレンジするスポーツでもあります。「自分の能力に合った山を選びましょう」と言われても、違う景色が見たいという人もいるし、憧れのあの山に登ってみたいという人もいます。私の役割は、その想いを諦めさせるのではなく、登頂できる体調に持っていき、その方法を提案することです。
平地の常識が通用しない世界
想像力と経験が必要
──冒険家の三浦雄一郎氏の海外遠征に、チームドクターとして同行しているともお聞きしましたが。 大城 三浦さんの海外遠征のコーディネーターの方から、「海外の山に登るので国際標準の山岳医療を知っている人に同行してほしい」ということで声をかけていただき、それからのご縁になります。また、その他でも、テレビの企画でタレントさんが海外の山を登るという時に登山隊に参加させてもらうこともあります。
三浦さんとは付き合いも長く、信頼関係もあり、継続的に体調管理をしてきたのでよいのですが、スポット的なテレビの登頂企画などは、登山隊の規模も大きく、個々のメンバーの体調の経過や、それぞれのパーソナリティなどを理解するのがなかなか難しい側面があります。そのことが取り返しのつかない事態を招く恐れもあるので、細心の注意を払っています。
話は逸れますが、三浦さんは毎回、私に敬意を持って接してくれます。それは私だけでなく、三浦さんを支えるすべての隊員に対してです。三浦さんは、自分がみんなに支えられていることを知っているのです。たとえば、10人のメンバーが2か月間、毎食、一緒に食事するわけですが、三浦さんはチーム全員が揃わないと絶対に食事をしません。「○○はまだ来ていないのか」と言って待っているのです。そのような行動の1つひとつが、「三浦さんのために頑張ろう」という気持ちにさせます。
──より過酷な環境の海外遠征となると、“教科書どおり”にいかないこともあると思います。
大城 そうですね。たとえば、ネパールのマナスルの登山隊に参加した時のことです。みんなが4リットルの酸素を吸入しながら登っていたのですが、渋滞してきたので、このままでは下山まで酸素が持たないと判断し、2リットルに変えたことがありました。
すると間もなく、カメラマンの体調が悪くなったのです。点滴や酸素吸入でリカバリーできたので結果的にはよかったのですが、限られた酸素のなかでの医療の難しさを痛感しました。
そのカメラマンは若く、心肺機能も高かったのですが、運動量も多く、何より体格が大きく、他の人より酸素量が必要だった。酸素2リットルの価値が他のメンバーとは違ったのです。
あと、これはこれまでの経験から学んだことですが、点滴は、温めてもマイナス20度の環境ですぐに冷えてしまう。そこで温めてから太い針で一気に落とすわけです。
平地の常識がどれほど通用しないのか。これには想像力が必要で、想像するためには経験と知識が必要なのです。それでも想像をはるかに超えた事態に遭遇することもあり、その場で判断しなければならない。その繰り返しです。
多くの登山者は山に対する
イメージが楽観的
──昨今、日本は登山ブームとも言われていますが、その一方で、遭難者数の状況はどのようになっているのでしょうか。 大城 山岳遭難の発生件数や遭難者数の状況については、平成27年に過去最多となっています。翌年の平成28年こそ微減となりましたが、ここ十年の推移を見ると、右肩上がりで増えています(表)。
死者・行方不明者数について見ると、かつては遭難者の6人に1人が死亡していましたが、現在は9人に1人です。その理由として、救助体制の充実や携帯電話の通話エリアの拡大などが考えられます。
また、最近の傾向としては、仕事をリタイヤした中高年者が登山を始めるケースが増えています。それにともない遭難者の年齢層は、40歳以上が2,269人と全体の77.5%を占め、60歳以上でも1,482人と50.6%を占めます。
山岳遭難をケース別に見ると、「道迷い」が約40%と最も多く、「滑落」(約17%)、「転倒」(約16%)と続きます。登山道が比較的整備された富士山でも霧がかかったりして道迷いは起きます。
──そもそも人はどうして遭難してしまうのでしょうか。
大城 山に対するイメージが楽観的なのだと思います。多くの方は、良い天気のなか、整備された登山道を登り、自然を楽しみつつ登頂して帰りたいと思っています。でも自然のなかに入っていくのですから、平地より体の負担は大きくなりますし、霧や吹雪で道に迷うこともありますし、転んで怪我をすることもある。リスクを実感できないまま登山をしていることが問題です。
山を楽しむ気持ちは理解できます。ただ、どんな山でも危険があり、医療機関からも離れている。何かあった時は自分で何とかしないといけない場所であることを認識してほしいです。リスクを想像できれば、そのための事前準備ができ、万が一の時にも対応できるはずです。
多くの開業医に山岳医療の
基礎知識を知ってほしい
──山岳遭難が増加するなか、山岳医の役割もますます重要になってくるのでしょうね。 大城 ただ山岳医といっても特別な資格ではありません。そのカリキュラムを受けなくても、山の診療所でずっと医療を提供している医師もいます。登山をしながら独自に山岳医療の勉強をしている医師もいます。私は山に携わるすべての医師と一緒にできることがたくさんあるのではないかと考えています。
時々、医師会主催の講演会で、患者さんが登山をする際に伝えていただきたいポイントや注意点などをお話させてもらうのですが、皆さん、非常に関心を寄せられます。多くの開業医の先生にその基礎知識を知っていただき、患者さんにお伝えすることで遭難件数は減っていくと思っています。
──開業医に知ってほしい山岳医療の基礎知識としてどのようなものがあげられますか。
大城 まず、高血圧、糖尿病などの持病が管理されていることです。そして、管理されていたとしても「平地の半分のスピードで登ってください」と伝えてほしい。登山1日目は血圧や脈が上がり心臓に負担がかかりやすいからです。
あとは最近、疲労遭難が増えていますが、そういう人は午前中の時点で脱水状態にあります。その際は、「登る前に500CC、途中は30分おきに150CC飲んでください」など具体的に数字で示すことが大切です。脱水症の遭難者に「水を飲みましたか」と聞くと決まって「飲んだ」というのですが、「どれぐらい飲みましたか」と聞くと、ペットボトル半分も飲んでないということが多々あります。
──その他はいかがですか。
大城 遭難は下山時に起きることが多いです。足の疲労で転んで怪我や骨折をしてしまう。初めて登山をする人、久しぶりに登山をする人には、標高が低い山を選んでもらう、もしくは緩やかな登山道を選択してもらう、さらにはストックを使うなどのアドバイスが遭難予防につながります。
あとは最近、血圧薬で利尿剤が入っているものがあり、それを飲んでいると脱水症になる可能性があります。どういう血圧薬が処方されているかを確認し、飲んでいる場合は、「この薬はたくさんおしっこが出るので、たくさん水分をとったほうがいいですよ」ときちんと伝えることが大事です。
──最後に、先生の今後の目標などについてお聞かせください。
大城 私の目標は「山岳遭難を減らすこと」です。そのために、これからも予防活動を続けていく。遭難を減らすには、山でのリスクを認識し、想像してもらうことが大切ですが、そこには知識が必要で、それは私たちが情報提供しなければなりません。しかも現場で役立つ情報です。その提供の仕方も工夫していきたいと思います。
もう1つは、救助隊が安全に活動できるように適切な知識や処置法を身につけていただくことです。これまでも救助隊に必要な医療的視点を提案してきました。その甲斐あってか、低体温症の遭難救助は進歩し、今まで助からないといわれていた人を助けることができるようになっています。遭難救助に医療が貢献できたと実感しているところですが、まだまだ社会に伝えきれていないことがあるので、今後、さらに力を入れる。山岳医としてのこれからの活動の中心になると考えています。(平成29年11月27日/本誌編集部 佐々木隆一)