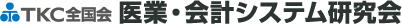バーチャル・リアリティの可能性 教育・手術計画・メンタル
現実には存在しない仮想空間をつくり出し、体験する「バーチャル・リアリティ」(以下、VR)。さまざまな産業において、その活用の可能性が期待されている。医療においては一部の大学病院等がすでに導入し、手術トレーニングなどに実際に活用しているという。そうしたなか2018年2月、東京大学では、あらゆる教育現場でのVRの活用の研究を進めるために「連携研究機構バーチャルリアリティ教育研究センター」を設置。その機構長を務める廣瀬通孝教授に、VRの進化の変遷や医療分野での活用への期待などについて話をうかがった。
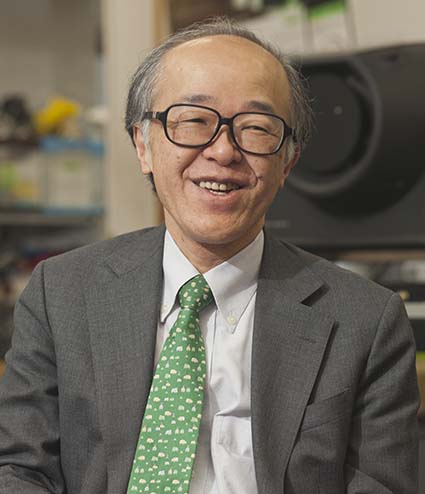 廣瀬通孝
廣瀬通孝
東京大学連携研究機構
バーチャルリアリティ
教育研究センター機構長
聞き手/
本誌編集委員
丹羽 篤
Hirose Michitaka
昭和29年5月7日生まれ、神奈川県鎌倉市出身。昭和57年3月、東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。工学博士。同年東京大学工学部講師、昭和58年東京大学工学部助教授、平成11年東京大学大学院工学系研究科教授、東京大学先端科学技術研究センター教授、平成18年東京大学大学院情報理工学系研究科教授、平成30年東京大学バーチャルリアリティ教育研究センター長(併任)、現在に至る。専門はシステム工学、ヒューマン・インタフェース、バーチャル・リアリティ。主な著書に「バーチャル・リアリティ」(産業図書)。総務省情報化月間推進会議議長表彰、東京テクノフォーラムゴールドメダル賞、大川出版賞、など受賞。日本バーチャルリアリティ学会会長、日本機械学会フェロー、産業技術総合研究所研究コーディネータ、情報通信研究機構プログラムコーディネータ等を歴任。
VRの登場は1989年にまで遡る「システムのなかに未来を見た」
──今、ゲームというエンターテインメント業界に留まらず、医療をはじめとしたあらゆる分野において「バーチャル・リアリティ」(以下、VR)の技術の応用が期待されています。まずは、VR技術の始まりからお聞かせください。
廣瀬 もともと「バーチャル・リアリティ」という言葉が登場したのは、1989年6月まで遡ります。アメリカ・サンフランシスコで開催された展覧会において、ある電話会社が「未来の電話」をテーマに、「バーチャル・リアリティ」という新たな電話システムを展示しました。
それはどのようなものだったのか。「ヘッドマウンテッドディスプレー」(以下、HMD)を被ると、360度見渡せる部屋の一室がCG空間に広がり、ドアから入ってきた人と会話をすることができるというものです。「これは面白いシステムだ」「システムのなかに未来を見た」など、多くの人から評価を受けました。HMDが商用化され、一般の方々にVRという存在を知ってもらったのはその頃です。
ただ、当時のVR技術は未熟であり、HMDも相当高価なものでした。そこに表示される映像は粗く、画素数は「100×150」ぐらいだったと記憶しています。ですから、実際はモヤのかかったようなCGで、文字が浮かんだとしても読むことはできないほどのものでした。
──そんなに前からVR技術は存在していたのですね。
廣瀬 我々は、この1989年からを「第1世代」と呼んでいて、そこが本当の“VR元年”といえるでしょう。
ただ、実はその前から研究開発は進められていました。いわば“紀元前”の話です。1980年代半ばには、アメリカ航空宇宙局(NASA)で、その前はアメリカ空軍で研究が進められていました。
そのなかで、「第0世代」とでもいわれているのが1968年です。アメリカ・ユタ大学の教授が、コンピュータで3Dの世界を描き、そこに入り込んでいろいろな疑似体験を可能にするシステムを開発したのです。線画で描かれた立方体のなかを見渡すことができるぐらいで、今から考えるとまったく原始的ですが、当時としては画期的なものでした。
──1989年の「第1世代」から昨今のVRが注目されるようになるまで、少し時間がかかっているような印象も受けますが。
廣瀬 技術の進化や注目度には波があります。最近、注目度が高いAIについても、1980年代前半に盛り上がり、80年代後半に衰退しました。当時、「AIで何でもできる」ということで期待されたわけですが、実際にはなかなか思うような開発が進まず、実用化もされない。実は、当時のAIへの失望にともなうアンチテーゼとして、VRやCGの技術に注目が集まったということがあります。
このVRも1989年から1990年代にかけて盛り上がり、2000年に入ってから静かになります。そして、2016年頃からVRが再び脚光を浴びることになった。これが現在です。我々は、この2016年からを「第2世代」と呼んでいます。
──「第2世代」が生まれた背景には、昨今の急激な技術革新が関係しているのでしょうね。
廣瀬 ご認識いただきたいのは、ニーズやブームに関係なく、研究者たちは地道に技術開発を重ねてきたということです。極論をいえば、今の最新技術は、すでに何年・何十年も前に開発されていて、実用化も可能であったということです。それが何かをきっかけに顕在化する。技術開発というのはその繰り返しなのです。
そのなかで、「第2世代」が生まれた背景としては、高性能のHMDを安価で提供できるようになったことがあげられます。先ほど申し上げたように、「第1世代」のHMDは低性能であるにもかかわらず300万円から400万円の値段でした。それが、今では当時とは比べ物にならないほどの性能を持ったHMDを数万円で購入できるようになっています。
フェイスブック社が2014年にHMDの開発会社を20億ドルで買収し大きな話題を集めたこともきっかけでしょう。これにより世界的にVR技術に脚光が集まりました。また、それまで文字情報が中心だったマイクロソフトやグーグルなどの大所がVRに目を向けはじめたことも関係するでしょう。もちろんインターネットやスマートフォンなどの普及もあります。いろいろな要素が大きなムーブメントを起こし、「第2世代」へとつながったと考えています。
リアルよりもVRの方が教育効果は高い
──医療におけるVRの活用の実際、または可能性についてお聞かせください。
廣瀬 いろいろな可能性があるでしょう。その代表的なものとして「手術シミュレーター」があげられます。経験が浅い外科医などの手技の訓練ツールとして、実際、当大学病院でも活用されています。
一人前の医師になるためには、座学も大事ですが、体験的なものも同じぐらい重要です。しかし、その体験を、実際の患者さんで身につけようと思ってもなかなか難しい。そういうなかで、手術体験を身につけることができるVRは非常に有効なツールです。また、それに関連して、VRで手術計画を立てるということも、「第1世代」から行われています。
──確かに、医師の教育ツールとして役立つものだと思います。
廣瀬 実は、実際の人体で学ぶより、VRの方が訓練効果は高いということもいわれています。
たとえば、訓練のなかで、A点での判断を誤り手術が上手くいかなかったとします。人体の場合、失敗につながったA点に戻ることはできません。環境等を含めて同じ状況をつくることはできないわけです。しかし、VRの場合は、A点の状況を再現できるのです。自分自身の苦手な状況を何度も再現して、クリアできるまで訓練することが可能なのです。
教育という意味では、VRの方がそのエッセンスが集約しているということがいえます。
これは医療に限ったことではありません。たとえば、動物園に行って実際の動物を見せることが子どもの教育にとってよいことだと考えている人がいます。でも、動物園の動物は、檻に入った飼いならされた家畜と同じなのです。それよりも、アフリカの野生の動物を映したテレビ番組というのは、本物ではありませんが動物の本質を表しているわけです。
その点、多くの医師はこの本質をしっかり理解されていると感じています。すべてVRでもいけない、でもすべてリアルでもいけないことを知っているのです。今、少なくとも当大学の医学部では、VRとリアルを融合させて、医師の教育に活用することが真剣に考えられはじめています。
メンタル的な部分を支えるツールとしてVRは活用できる
──手術トレーニングの他に、どのような活用が考えられるのでしょうか。
廣瀬 特に私が感銘を受けたのは、かつて国立小児病院で行われた、院内学級でのVRの活用です。
難病の小児患者は外出が禁止されています。でもそれでは社会性が身につきません。そこで、VRを使って山に遠足に行ったり、ゲームセンターやスキー場を体験してもらうという取り組みが行われたことがありました。実在する動物園をVRで再現した際、親御さんは「初めて自分の子どもを動物園に連れていけた」と喜んでおられました。
これは間接医療ということになりますが、私たち工学系の研究者にとっては、子どもたちやその親御さんの喜ぶ姿に、VRの大きな可能性と研究の意義を感じました。それまで我々が進めてきた工学系の研究というのは、人間の感情とは最も遠いところに存在すると思っていました。しかし、VRの研究はそうではない。VRは人間に近いテクノロジーでもあるので、メンタル的な部分を意識した研究も必要だと考えるようになりました。
──患者のメンタル面を支えるツールとしても可能性がありそうですね。
廣瀬 特に、超高齢社会でVRの可能性は広がるでしょう。たとえば、施設から出られない高齢者に対して、VRを使って思い出の地を回るなんてことも可能です。それによって高齢者の気持ちが穏やかになる、または充実した最期を迎えられる。そんなところにも活用できるのではないかと考えています。
また、最近、当研究室でVRを使った面白いシステムをつくりました。自分の顔が映る鏡なのですが、普通の表情で鏡に向かっても笑顔が映ってしまうというものです。これを見ると本人はどうなるか。無意識に自分の表情が変わり、メンタルが上がるのです。表情のような身体の状況と心の間には何かしらの相関関係があるのです。
服装などの外見も心に影響を与えるといわれています。VRでネクタイを締めた自分の姿を見てもらうと、多くの高齢者はしゃきっとした姿になるのです。外見に対する自分の認識によって人の行動は変わるのです。
──VRを使った外見と心、行動の関係についての研究は非常に興味深いものがありますね。
廣瀬 もう1つ、バスケが上手な学生に対して、VRでゴールにボールを入れてもらうという研究もしています。その際、少しでも腕の角度などがズレたりしたら、ゴールから大きく外れるようにプログラムしました。極限の学習状態をつくり出したわけです。このVRで十分に訓練をすれば、本番で高い結果が得られると考えました。しかし、結果は逆でした。少しぐらい方向や腕の角度がズレてもゴールできるようにプログラムした方が、本番でよい結果が出たのです。つまり、「自分はできる」と刷り込ませた方が、よいパフォーマンスにつながるのです。
メンタルとパフォーマンスの関係は、一般的にいわれてきたことですが、こうした細かい研究データをVRでは積み重ねることができるのです。
このように今、VRを活用した心理的な効果の研究が進められているわけですが、その研究結果は、医療において特に心療内科の領域などで有効に活用できる可能性があるのではないかと考えています。
本体の医療のあり方について再び議論を起こさせる技術
──今後、VRの浸透は医療にどのような影響を与えるとお考えですか。
廣瀬 手術トレーニングや診断、手術計画の支援などのツールとして使われ、医療の質の向上につながっていくということは想定できることですが、それ以外に、私は、今の医療のあり方を再認識する大きなきっかけになる技術でもあると思っています。
たとえば、今後、遠隔診療においてVRが使われるようになるとします。検査データなどが反映されたバーチャルの患者さんを相手にリアルタイムで診療を行っていく。「遠隔では患者を十分に診られないよ」という医師がおられるかもしれません。しかし、現在の診療でも医師が患者に触ってくれないという意見をよく聞きます。先ほどの動物園の話と同じく、何が何でも実物がよいというわけではないでしょう。VRは、本来の医療のあり方とはどういうものかについて再び議論を起こさせる技術なのではないかと思っています。
──VRがさらに進化するために乗り越えなければならない課題などについてはどのように見ておられますか。
廣瀬 今のVRはファッションショーの洋服のようなレベルではないでしょうか。いきなりファッションショーの服で街を歩いたら笑われます。本格的社会装着のためには、何らかの開発が必要だと思います。
価格の問題もあります。さまざまなビジネスで活用され、普及するためには、費用対効果が大きく関係します。この部分の改善です。
あとは、技術的には触覚の部分をどのように具現化していくか。医療においても触診は診療のなかで重要ものとして位置づけられています。これを将来的にどのように再現するかだと思います。現在、触覚に関する研究については、国際学会も組織され、相当の研究者たちがその実現のために研究を重ねているところです。
医療での積極的な活用を期待健康問題についても向き合う
──東京大学では「連携研究機構 バーチャルリアリティ教育研究センター」を設置し、廣瀬先生はその機構長に就任されましたが。
廣瀬 当センターは、VRをつくる技術を学ぶ場ではなく、VRを教育のなかでどのように生かすことができるのかを研究する機関として設置されました。
今、当センターに登録している教授や研究者、教員は70人ぐらいいるのですが、そのなかで驚いたのは医学部の先生が非常に多いことです。VRが今後、どのような使われ方をしていくのかは、それぞれのドメインによって違うと思いますが、医療においては、その“出口”の答えが出しやすいということもいえます。
当センターの設立記念式典を開催した際、ある脳外科の医師は、「医療は戦略が大事だから手術計画での活用を期待している」と話しておられました。ある耳鼻咽喉科の医師は「手術は手技が大事。その教育へ活用していきたい」と話していました。医師によってVRへの期待が異なるのが非常に興味深かったです。
──最後になりますが、VRの研究者として医療に期待することなどはございますか。
廣瀬 実は、技術イノベーションのうち、かなりの部分は医学から出てきているのです。たとえば、ハイビジョンテレビについても、今でこそ当たり前に普及していますが、当時、一般の方々はそこまでの高性能は求めていなかった。でも医療では、著名な医師の手技などを事細かに見るために、それだけの解像度がなければ伝わらないということで使われてきたのです。それが一般にまで普及していきました。
もしかしたら、VRは過剰品質といわれるかもしれません。しかし、同時に医療ではその活用の場があるわけです。そういう意味では、まずは医療分野での積極的な導入、活用を期待しています。
もう1点、VRは一部で身体に悪影響を及ぼす可能性があるといわれています。少なくとも「第1世代」以前から研究を続けてきた私たちの身体に問題は起きていません。ただ、我々技術者がいくら安全といっても世間は信じてくれません。
医師と連携を組んで、健康被害がないことを科学的に証明していただく、または健康被害が起きるとしたらそのメカニズムはどうなっているのかを解明いただく。そういう取り組みも今後、センターで行っていきたいと考えています。
(2018年12月6日/構成・本誌編集部 佐々木隆一)