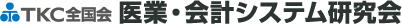人材確保に重点を置いた診療報酬改定 ~2024年度改定の特徴とこれから~
2024年度診療報酬改定に関する内容が3月5日に告示された。中央社会保険医療協議会の診療報酬調査専門組織(入院・外来医療等の調査・評価分科会)で分科会長を務める九州大学の尾形裕也名誉教授によると、今回の改定は従来と異なる特徴があるという。どのような内容となったのか、そしてこれからの医療機関の経営で意識すべきことは何か、話をうかがった。
尾形 裕也
九州大学 名誉教授
聞き手/本誌編集人 石川 誠
Ogata Hiroya
東京大学工学部、経済学部卒業。厚生省各局、OECD事務局、在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部一等書記官、千葉市環境衛生局長、国家公務員共済組合連合会病院部長、国立社会保障・人口問題研究所研究部長、九州大学大学院医学研究院教授、東京大学政策ビジョン研究センター特任教授等を経て、2013 年より現職。
本体のプラス改定分は賃上げに使い切る構図
──まずは、診療報酬改定の全体像に関して、どのように評価されていらっしゃるのか、お考えをお聞かせいただけますか。
尾形 今回は本体がプラス0.88%、薬価等がマイナス1%となりましたが、このように、本体がプラス改定、薬価がマイナス改定、トータルでマイナスになるのは、2年ごとの改定としては連続で5回目です。そういう意味では、基本的な構造は変わっていないのだろうと思います。
私は厳しい財政状況や経済環境を踏まえれば、やむを得ない結果なのではないかと考えています。
──何かの意図に基づいて、全体でマイナス改定が行われているということでしょうか。
尾形 診療報酬という価格の体系が全体としてマイナスだったとしても、医療費はいろいろな増大要因があるわけですから、必ずしも減るわけではありません。意図があるというよりは、医療費は増えていくというなかで、いろいろな財政上の制約などから、こうした結果になっていると思います。
──今回の改定では、人材確保が重点課題に位置付けられましたが、その意義についてお聞かせください。
尾形 昨年12月に示された「診療報酬改定の基本方針」で、4つの「基本的視点と具体的方向性」が打ち出されているわけですが、そのトップに「現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進」が据えられています。これは今回の改定の非常に大きな特色を表しているのだろうと思います。
いうまでもなく、岸田政権の基本的なスローガンである「新しい資本主義」の実現、あるいは成長と分配の好循環、そういった観点もあるのでしょうが、もともと医療従事者の人材確保、処遇改善は必須の課題だったということでしょう。
あわせて、2024年から医師の働き方改革が動き出すということも、当然その背景にあり、トップに位置づけられたのもある意味予想されたことでした。
──賃上げを目的として、具体的な点数に反映されることは珍しいのではないでしょうか。
尾形 診療報酬を賃上げに活用する例としては、前回改定の看護職員に関する処遇改善がありました。今回の改定は、基本的にはその方式をさらに拡大した位置づけだとみています。
本体改定の中身を見てみると、看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種のベースアップの実現のために0.61%、40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げに資する措置として0.28%程度ということになっています。
単純にこれを足し合わせますと、0.89%程度ということになります。本体改定率は0.88%ですから、今回のプラス改定分のすべて、あるいは少し足が出る部分を含めて、賃上げ実施のために使い切る、という構図です。
このうち0.61%については、看護職員の処遇改善の方式を基本に、ベースアップ評価料を新設し、規模や対象を前回より大幅に拡大するかたちでの改定となります。
一方で0.28%程度分については、基本診療料の入院基本料の引き上げ、あるいは初再診料の引き上げで対応することになったわけですが、これは消費税増税分への対応を除くと、2004年以来の初再診料の引き上げとなったわけで、注目すべきものでしょう。
所得分配にまで踏み込んだ“異例”の改定に
──初再診料の引き上げは20年ぶりとなるのですね。
尾形 しかし、こうしたかたちでの診療報酬の改定は異例と思われます。そもそも診療報酬とは何かというと、医療サービスへの対価について、公定価格で示しているものです。その公定価格である診療報酬を、いわば価格のシグナルとして、各医療機関は保険診療における資源配分を決めているわけです。
つまり、医療機関は診療報酬をにらみつつ、どれだけ人を雇い、施設・設備を整備し、あるいは医薬品をどれだけ購入するかという、経営上の意思決定を行っているのです。
そもそも、医療従事者の賃上げやベースアップというのは、資源配分ではなくて所得分配の話です。個別の診療報酬で診療行為を評価しているのであって、診療行為にかかわる医療従事者の賃金を評価するものではありません。どういう賃金水準を設定するかは、基本的には労使交渉を通じて、最終的には経営者の経営判断として決定されるべきものです。
医療機関と民間企業では、公定価格か自由な市場価格かという違いはありますが、所得をどう分配するかは全く同じ構図だろうと思います。そう考えると、本来は個々の診療行為に対する評価である診療報酬、つまり資源の配分は、医療従事者の所得分配とは次元の異なるものといえます。今までは全体の診療報酬を受け取って、そのなかでどう配分するかは医療機関の経営者の裁量でしたが、今回は使途まで決められているということです。
また、本当に診療報酬として使われたかどうかの報告を求めるとのことですが、これまでは、診療報酬として渡せばどこに使うかは裁量の範囲でしたから、この点でも従来とは異なった改定になっていると思われます。
──こういった内容の改定は、次も行われるのでしょうか。
尾形 次の改定時期も賃上げが問題になっているようであればまた行われる可能性はあるでしょう。
前回の改定で看護職員を対象にした際は、看護職に絞っていたのと、対象がコロナ禍で頑張っていた病院ということで限定的に行われました。今回の改定ではほとんど全部の医療機関が対象になるわけですから、診療報酬の性格を変えるものになると思っています。
加えて、改定率は予算編成のなかで、財務大臣と厚生労働大臣との間で決められますが、その改定率に関する文書を見ますと、直近の3回分の改定では、本体改定のところに注書きがつき、使途にまで踏み込んでいる。私はイヤマークと呼んでいますが、あらかじめ配分についても決められている部分がつくようになりました。
2020年では救急に関して、前回の2022年改定では看護職員の処遇改善に関して、使途が記載されています。それが今回はさらに拡大しています。
これは従来の診療報酬改定のやり方と変わってきているということです。診療報酬改定というのはいわば2段階あって、全体の改定率をどうするかというマクロの部分と、個別に何点などと技術的に配分するというミクロの部分があります。マクロについては政府が予算編成の中で決める、ミクロについては中医協が担うというかたちで“分業”していました。
ところが、使途が決まった部分、これは細かい点数についてまでは書かれていませんが、ミクロとマクロの間の部分が出てきているということです。これは近年の報酬改定における顕著な特色だと思います。
医療介護連携を意識した改定
ポスト2025は今後の議論
──今回の改定では、「特定疾患療養管理料」の算定要件が見直され、対象疾患から糖尿病をはじめとする生活習慣病が外されるなど、医療費の抑制による医療保険制度の持続可能性向上を意識した改定があったように思われます。
尾形 「基本的視点と具体的方向性」で4番目に示されている「効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上」の一部であろうと思います。
今回の改定では、特定疾患療養管理料の対象疾患から糖尿病、脂質異常症、高血圧が除外されて、ギランバレー症候群など、本来の特定疾患らしいと言えるものが追加されました。何か特定の意図を持っているというよりは、特定疾患療養管理料の本来あるべき姿を考えたということではないかと思います。
──地域包括医療病棟入院料の新設といった、入院医療のさらなる機能分化・連携を促し、地域包括ケアシステムの構築を進めるように思われる内容については、どう見ておられますか。
尾形 「基本的視点と具体的方向性」では、2番目の柱にあたる話です。ただ、そこでは「ポスト2025を見据えた」と書いてありますが、2025年が目標年次となっている地域医療構想について考えてみると、その後、まさにポスト2025はどうなるのか、というのは現時点では明らかではありません。今後、検討が進められていくことになると思います。
また、診療報酬と地域医療構想の関係については、「診療報酬は地域医療構想に寄り添う」という有名な答弁がありますが、まさにそういうものだと思うので、今回の改定では2025年以降を先取りして、「こちらの方向に持って行くんだ」というような明確なメッセージが取り入れられているとは思いません。
地域包括医療病棟入院料は、ポスト2025という見方もできるかもしれませんが、むしろ今の救急のあり方に関わるものです。特に三次救急など高次の救急医療病院の負担が非常に重いものになっている、そういったなかでの負担軽減を図るために、地域で特に高齢者の救急患者等を受け入れる病棟について、新たに評価したということでしょう。
実際、救急医療については中医協でもいろいろなデータが出されていましたが、二次救急の部分は病院によって非常にばらつきが大きい。熱心にやっているところもあれば、ほとんど実績がないところもあって、それがすべて二次救急というかたちになっています。そのため本当に機能する地域の救急体制を整備する必要があることから、この項目の新設が出てきたものかと思います。
これは3,000点を超えて、それなりに高い水準の入院料になっていますから、今後どのくらい手を挙げる病院があるかは注目すべきでしょう。
──それでは、ポスト2025の内容については次の改定で対応していくことになるのでしょうか。
尾形 次回の改定も2年後に来てしまいますから、どうなっていくか不明ですが、おそらく、次の地域医療構想を考えるということは、医療法の改正が必要になる。簡単なことではありませんから、タイミングとしてどうなるかは微妙なところです。
──今回は6年に1度の「トリプル改定」でしたが、その点についてはいかがですか。
尾形 2025年を前にした最後の同時改定ということもあるので、明らかに介護との連携に留意した内容になっていると思います。
個別改定項目のなかにある、「生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組」について見ると、「介護保険施設入所者の病状の急変時の適切な入院受入れの推進」「医療機関と介護保険施設の連携の推進」「介護保険施設及び障害者支援施設における医療保険で給付できる医療サービスの範囲の見直し」と、医療と介護の連携を意識したものが並んでいます。きめ細かく連携が進むような内容が入っていて、明らかに同時改定を意識した評価です。
──そのほかに、個別の項目で注目されたところはありますか。
尾形 1つ気がついたのは、療養病棟の患者の状態像についてです。今までは疾患状態についての医療区分3段階とADL区分3段階という、
9つのボックスを作って、そこに1日あたりの定額の報酬を入れていましたが、今回から「処置等にかかる医療区分」というものを設けて、
患者の状態像の見方が精緻化されてきたといえます。
これは急性期病棟におけるDPCにも言えることですが、やはり患者さんの状態をみるときに、3×3では粗いということで見直しがあった
というのが、技術的に注目した点ですね。
──次回の改定に向けた課題というのはありますか。
尾形 個人的な感想として、今回の改定で気になった議論がありましたので紹介します。急性期の病院の経営者の方からの話なのですが、入院患者の高齢化が非常に進んでいるなかで、かつては考えられなかったような、80~90代の患者さんに対しても手術を行い、成功している例が増えているそうです。
しかし手術は成功しても、患者さんのADLが入院中に低下し、入院期間が長くなってしまう。そのような場合、急性期の病棟でも療養病棟のように、介護の人手を配置して、患者のADL低下を防ぐような措置、評価をすべきではないか、という議論がありました。
これは難しい問題で、もっと議論が必要であり、推移を見守りたいところです。
大きな流れをとらえて医療機関こそ健康経営の実現を
──今回の改定と医業経営との関係はどうお考えですか。
尾形 1回ごとの診療報酬改定に一喜一憂する必要はないと思います。毎回の診療報酬改定と医療機関の基本的な経営戦略は次元が異なる問題ですから、分けて考える必要があると思っています。
まずは各医療機関の経営戦略があって、その上でどういう診療報酬を取るかという話だと思います。
もちろん、診療報酬のなかで一番有利なものを取っていく必要はありますが、診療報酬によって戦略を変えるというのは、私は本末転倒な話だと思います。
特に、今回の改定を通じて2025年までどのようになるかは、一応明確になったと思いますので、問題はその後のことです。地域医療構想の議論がこれから本格化していくと思うので、そういったなかで自院のポジショニングをどうするかについてぜひ考えていただきたいです。
次の構想がどういうかたちになるかはわかりませんが、たとえば病床機能報告も今言われているところでいえば、入院だけではなくて、外来、かかりつけ医機能といったところも含めて議論をしていくという話ですから、そういうなかでの自院の立ち位置がまた問われてくると思います。
おそらく今後1年くらいの間に、2040年に向けた大きな動きがあると思いますので、そちらに注目すべきだと思います。
──先を見据えて情報を知り、戦略を立てることが重要ですね。
尾形 大きな流れを踏まえる必要があります。そしてそれ以上に重要なのは、自院の置かれている地域の状況です。高齢化や人口減少は地域差のある話ですから、他の地域と単純に比べられません。それぞれの環境のなかでどう考えていくかが大事になります。
昨年3月に改正された「総合確保方針」では、二次医療圏単位で細かく医療需要の変化の推計が行われています。また、12月には地域別の新しい人口推計も出ています。この推計に基づいて新しく医療需要を検討していく必要があります。
もう1つ、強調したいのは、今回の改定では人材確保や働き方改革が前面に出ており、今後の医療機関の経営を考えるとき、いかに人材を確保するかが非常に重要な点になっています。
そうすると、賃上げはもちろん重要なのですが、それだけではなくて、いかに医療従事者のモチベーションを高めて、働きがいのある職場をどうつくるか、という観点でいろいろ考えていく必要があるでしょう。
健康経営ということも考えていただきたいと思っています。健康経営で使うデータは、医療費や健診のデータを使いますが、これは医療機関が作っているデータです。つまり、民間企業に比べて“土地勘”があるのです。なかには地域の健康増進のコアになることを目指している病院もあります。医療機関こそ健康経営に力を入れていただきたいと思います。
(024年2月19日/構成・本誌編集部 川村岳也)