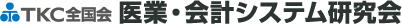病院が安心して暮らせるまちをつくる ~「何でもやってみる」病院の取り組み~
団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者になる2025年まで、残り1年を切った。各地では急ピッチで地域包括ケアシステムの構築が進められている。そうしたなか、群馬県沼田市にある大誠会グループでは、病院を核とした医療・介護・福祉の連携、さらには商業複合施設の運営等を通じて、誰もが安心して暮らせる“まちづくり”に取り組んできた。田中志子理事長に、想い描く“まち”の姿とその実践について話をうかがった。
田中 志子
医療法人大誠会 理事長
Tanaka Yukiko
1966年、群馬県沼田市出身。1991年帝京大学医学部を卒業後、群馬大学附属病院第一内科を経て、1995年医療法人大誠会・内田病院に就職、2011年に医療法人大誠会理事長に就任。
医療・介護・福祉の連携で 地域住民を支える
──病院からほど近い場所に位置する、温泉やレストランなどを備えた商業複合施設「ソナタリュー」は、貴グループが運営されているとお聞きしました。
田中 「ソナタリュー」は、福祉施設と商業施設が合わさった複合施設です。病気や障害の有無にかかわらず、また年齢や性別の違いにかかわらず、あらゆる方々が「ごちゃまぜ」に交流できることを目指してオープンしました。
施設内には天然温泉をはじめ、地元で獲れた野菜などを提供するレストラン、ウェルネスジムなどがあります。一般の商業施設との大きな違いは、ここが障害を持つ方の就労の場になっていることです。ここで働く障害者の方のケアができるように、施設内には障害者グループホームや放課後等デイサービスなども入っています。
実は、この複合施設をつくった発端は、障害を持つ子どものご家族からの要望でした。当グループでは以前から放課後等デイサービスを運営し、障害のあるお子さんを受け入れていたのですが、ご家族から「子どもが大人になったとき、働ける場所をつくってください」とお願いされたのがきっかけだったのです。
オープンしたのは2020年11月です。ちょうど新型コロナウイルスの感染拡大と重なってしまい、住民の方々の認知度も高めることができず、特に当初は経営的に厳しい状況でした。そうしたなかでも運営を続けて、今年で4周年になります。
さまざまな人たちがごちゃまぜの交流を目指す商業複合施設「ソナタリュー」
──貴グループでは医療、介護、福祉の連携を通じて、地域住民の支援ということに積極的に取り組まれているようですね。
田中 そもそも、当グループは1976年、私の父である内田好司初代理事長が、沼田市内に19床の有床診療所を開設したのが始まりです。
そのころ、高齢者が増加するなかで、いわゆる社会的入院が問題視されるようになっていました。父は「退院後に受け皿となる施設が必要ではないか」という問題意識を持つようになります。
そうしたなか、介護老人保健施設の制度が始まることを知った父は、「これからの時代は医療だけではなく介護やケアも必要になる」と考え、1988年、病院と介護老人保健施設が一体となった施設をつくりました。これをきっかけに、地域のニーズに合わせて順次、必要な機能を整備していき、現在のグループが形づくられました。
1992年には、特に介護が困難な方を受け入れる「認知症専門棟」の許可を得て、認知症の患者さんへの対応にも力を入れることになりました。
大誠会グループの核となっている内田病院
「まちづくり」を理念に 地域のニーズに応える
──地域ニーズに合わせ、必要な機能を1つずつ整備してきたわけですね。
田中 そうです。また、障害福祉の分野に進出したのも、私たちが今でいう企業内保育所を始めたことを聞いた、地域の方からの要望によるものです。障害のある子どもも含め、さまざまな子どもを預かる施設の運営を本格的にスタートさせたわけです。
2017年には共生型施設「いきいき未来のもり」を開業しました。この施設では、保育園や放課後等デイサービス、通所介護施設などが一体化しています。施設のなかでは、子どもと高齢者の交流や、障害の有無に関係ない子ども同士のつながりが生まれています。
──当初から地域の困り事に対応してきたわけですが、そこにはどのような想いがあったのでしょうか。
田中 父は「地域の方々のためにできることは何でもしてあげたい」という想いを持っていました。たとえ物理的に、金銭的に難しかったとしても、どうにかして実現するという強い意思があったのです。
今でこそ、理念のなかで「まちづくり」というフレーズを掲げていますが、最初からそうしたまちづくり、あるいは地域包括ケアシステムの実践を目指していたわけではありません。
この地域でグループを運営していくなかで、1つひとつ必要とされたものを作ってきました。これまでを振り返ってみると、結果的にまちづくりをしてきたことに気づきました。
利用者さんの要望に応えていくなかで、信頼関係が構築されて、それがよい評判につながり、結果的に経営によい影響を与えているようにも思います。
──貴グループの関連組織にはNPO法人もあります。
田中 これは最初、配食サービスなど医療法人ではできないことに取り組むために設立したものですが、現在では地域と一緒に何かを展開する組織として位置付けています。
特徴的な取り組みとしては、「認知症にやさしい地域づくりネットワーク」への参画があります。このネットワークは、認知症の患者さんが行方不明になった際、警察だけではなく、協力いただける地域の方々に情報を提供して、一緒になって捜索するというものです。これはもともと父が発案したことがきっかけで、運営協議会が設立されました。この取り組みによって早期発見につながっています。
身体拘束ゼロは根性論だけでは実現不可能
──他方、貴グループの中核を担う内田病院では、長年にわたり「身体拘束ゼロ」に取り組まれています。
田中 身体拘束ゼロを達成したのは2002年です。病院を開設したばかりのころ、病床は埋まってはいたものの、ケアのあり方が定まっておらず、人材も定着していませんでした。常勤医師もまだ多くはいませんでしたし、かといって父1人で全員を診るわけにもいきません。それで病棟のことは看護師たちに任せざるを得ず、日常的に身体拘束が行われていました。
1995年に、私が病院に入職した際、今までいた学校や職場では見ることのなかった、身体拘束の光景を見て思わず絶句しました。それで父から病床の管理を任された私は、患者さんの身体拘束を解いていくことにしました。
──実際に、現場でケアを行ってきた看護師からの反発は大きかったのではないでしょうか。
田中 看護師たちも「患者さんのため」と思って、患者さんの治療に支障をきたさないため、また事故を防ぐために拘束していたのが実情です。
最初は私が拘束を解いても、他の看護師が拘束することの繰り返しでした。仲間外れになりながらも続けていくなかで、理解してくれる職員もだんだん増えていきました。
1999年には厚生省令(当時)で「原則身体拘束ゼロ」が打ち出されました。私も改めて勉強し、身体拘束ゼロを実現した他の施設の運営者たちにお会いするなかで、「拘束廃止はケアの補助があってこそ」ということを学び、施設内での身体拘束ゼロを達成できました。
それから20年以上、拘束ゼロを続けています。拘束するための器具もありませんし、今働いている職員は見たこともないのではないでしょうか
──現在も「身体拘束をやめたいができない」という医療機関もあるかと思われます。拘束ゼロを達成・維持するためにはどのような取り組みが必要になるとお考えですか。
田中 まず、根性論だけでは維持できません。手法やノウハウがなくては難しいと思います。
グループでは20年以上にわたるノウハウがあるため、たとえば職員の声の掛け方から点滴を指す位置まで、詳細な内容をマニュアル化しています。
拘束されないことは人の尊厳を守るためには当たり前のことではあるのですが、実現させるためには、手法を日常的に考案して確立し、共有していく必要があるのです。
また、職員たちが利用者の幸せを考えられる環境をつくるためには、職員にとって働きやすい環境をつくることも重要です。
タテもヨコも機能する組織に収支管理の透明化も実現
──いま、職員の働く環境づくりというお話が出ましたが、特色ある取り組みを円滑に進めるためには、そうした職場環境の整備が重要になるかと存じます。
田中 当グループでは「地域といっしょに。あなたのために。」という理念を掲げていますが、この「あなた」というのは、利用者さんやそのご家族だけではなくて、職員を含めると定義しています。そのため、健康経営には特に力を入れていますし、子育て支援の「プラチナくるみん認定」を取得しています。また職員に対しても、まず自分自身を大切にしなければ仕事はうまくいかない、ということを伝えています。
──組織運営にあたって、特別に取り組まれていることはありますか。
田中 主に2つのことに取り組んでいます。まず1つ目は職種ごとに統括する組織体制の整備です。当グループでは、法人本部に「看護部長」や「介護部長」などの役職を設けて、働いている施設がどこかに関係なく、法人本部の部長が担当の職種を統括する仕組みにしています。こうした組織のなかで、救急患者に対応する職員から、特別養護老人ホームの職員まで、同じ職種であれば同じ教育を受けることになります。
2つ目は「プロジェクト」の実施です。部門や施設にかかわらず職員が参加して業務改善に関するプロジェクトを実施しています。参加人数は内容によってさまざまですが、現在は「病院のファンづくり」「掲示物などの美化」といったプロジェクトが同時に複数動いています。
プロジェクトの実施によって、施設を超えて多職種での連携が進みますし、プロジェクトリーダーになった職員は目標の立て方や進捗管理などを通じてマネジメント能力を伸ばし、私たちも役職の新しい適任者を見つけるきっかけになります。
組織は職種だけの縦割りではダメですし、かといってヨコの病棟だけで完結してもうまくいきません。タテとヨコを合わせてスムーズに機能させる必要があると思います
──病院をはじめとするグループの安定的な運営のためには、経営管理の面での取り組みが重要になりますが、どのような工夫をされていますか。
田中 まず、収支管理の透明化に取り組んできました。以前、組織が小規模だったころは特に支出について、各職員の給与までわかってしまうこともあり、あまり見せていなかったようです。
しかし、支出まで見せなければ収益がどう配分されているかわからず、かえって「これだけしかもらえないのか」と不信感を抱かせることになります。そのため、支出も含めた透明化を行いました。
また、部門ごと、病棟ごとの収支管理も始めました。以前は面積按分でざっくりとした管理だったのですが、私が理事長に就任した後はフロア別に収益と支出を見て、アンバランスなところはないか、月次ベースで確認しています。
こうした月次決算や部門別管理の考え方は、顧問税理士の秋葉仁先生(あおば税理士法人)から指導いただいて学びました。
現役世代への支援を増やし地域振興につなげたい
──今後のグループ運営について、どのような点が課題だとお考えですか。
田中 承継も含め、グループ運営の安定的な継続をどうするか、という点です。現在の理念やサービスの質を継続できるよう、次の3代目となる人を育てていかなければなりません。
この地域を見回すと、当グループのような役割を持つ施設はそう多くはありません。特に子どもの障害福祉については撤退しているところが大半です。そういった状況もあり、運営を継続できるよう、「100年続く病院」を考えていかなければならないと考えています。
継続していくためには、何かに追われて動くのではなく、自分たちから地域の声を拾えるかどうか。つまりニーズの洗い出しが重要であると考えています。
──それでは最後に、これからの展望についてお聞かせください。
田中 この地域への移住や定着を支援できないかと構想しています。たとえば都市部に引っ越さなくても十分に子どもを育てられる環境を提供できるように、教育の充実であるとか、暮らしやすさ向上を目指した活動ができないかと思っています。
私たちは高齢者への支援を中心にスタートしましたから、これまでそうした現役世代を支える活動はあまり行っていませんでした。私たちを含めて現役世代は「支える側」であって、「支えられる側」ではない、という意識があったかと思います。
しかし、これからますます高齢化や人口減少が進むなかでは、現役世代を支えることで、活躍できる期間の延長を目指さなければならないと考えています。
そうした活動のためには、医療や介護、福祉に興味・関心がない人をどう巻き込んでいくかが課題になると思います。もちろん、1つの医療法人、単体のグループがどこまでできるかというのは、ある意味チャレンジではありますが、それでもやらなければならないと考えています。
もしかすると、私たちは他の医療機関などから見れば“とがった”活動をしているように見えるかもしれませんが、私たちはそうは思っていません。
「病院だからやらない」「病院なのにやるのか」といった意識がなく、「何でもやってみよう」と思えるところが私たちの一番の強みではないかと思っています。
(2024年4月22日/本誌編集部 川村岳也/取材協力 あおば税理士法人/画像提供 医療法人大誠会)