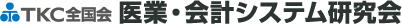人口減少時代の医療制度を問う ~持続可能な社会保障をつくるには~
医療制度をはじめとする日本の社会保障制度は、少子高齢化にともなう人口減少を背景として「曲がり角」にあるといわれる。持続可能な制度を構築する上で、考えるべきことは何か。これまで官僚として介護保険法の制度設計や「社会保障と税の一体改革」に携わった経験もある香取照幸氏に、将来あるべき日本の社会保障の方向性をうかがった。
香取 照幸
一般社団法人未来研究所臥龍 代表理事
兵庫県立大学大学院社会科学研究科
経営専門職専攻 特任教授
Katori Teruyuki
1980年東京大学法学部卒業後、厚生省入省。在フランス OECD 事務局研究員、埼玉県生活福祉部高齢者福祉課長、厚生省高齢者介護対策本部事務局次長、内閣官房内閣参事官、同審議官、厚生労働省政策統括官(社会保障担当)、年金局長、雇用均等・児童家庭局長、在アゼルバイジャン共和国日本国特命全権大使、上智大学総合人間科学部教授等を歴任。
2040年以降も医療需要は増加
治し支える医療が求められる
──日本の医療制度というのは、世界的にどのように評価されているのでしょうか。
香取 日本の医療制度は、フリーアクセスや国民皆保険の整備などの点がかなり高く評価されています。しかも、海外の医療費に比べて日本の医療費は安い。
そういうなかで、患者も医師も、今の制度を当たり前のものだと思ってきました。しかし今後は少子高齢化や人口減少を背景に今のままの制度を続けていくことが難しくなっていきます。
日本の医療は独自の発展過程をたどってきました。全国各地には中小病院が存在しますが、多くは開業医が自己資金で診療所から大きくしてできたものです。
海外の場合、病院は社会的な資本として公的に整備され、必要な医療ニーズに合わせてコントロールし配分していますが、日本の病院の多くは自由開業医制、自由標榜制の下で民間資本で整備されてきました。今は病床数に制限がかかりますが、これも昔はありませんでした。
そうした状況のなかで、患者が自由に医療機関を選ぶことを前提に医療機関の整備が展開されてきました。結果として、日本では津々浦々に診療所や中小病院ができ、日本の医療を支えてきました。しかしこの先、病院経営はやはり難しくなるでしょう。
──これからの医療をとりまく環境はどのような変化が予測されるのでしょうか。
香取 人口減少が進み高齢者人口がピークアウトすることで医療ニーズが減るという予測があります。たとえば、年金給付の総額は高齢者人口が最大になる2040年ごろでピークを迎えることになりますが、医療や介護はそうはいかない。高齢者の中の高齢化が進むことでサービスを必要とする人の割合は増え、医療・介護需要は増加していきます。地域によって状況が大きく異なりますが、全体として見れば2040年ではピークアウトせず2060年やその先まで伸び続けるでしょう。
医師数問題も、「日本全体で人口減が進むので医師数不足は解消されていずれ均衡する」という主張もありますが、そうはならないと思います。医療・介護需要の増大に見合って医師数を増やすことはできませんし、そもそも医師の開業する場所が自由である以上、人口減少地域で新規開業する医師は少なくなります。その上、いまの開業医も高齢化して廃業していくのですから人口の減少以上に医療機関が減ります。偏在問題は解消されません。
加えて医師の働き方改革があります。これまでは、医療従事者が長時間労働をすることで制度を維持できていたわけですが、医療現場にこれ以上の負担をかけるわけにはいきません。
患者の疾病構造も変化していきます。急性期の入院患者でも高齢者の割合が増えます。複数の基礎疾患、慢性疾患を持ち日常的に医療を受けている人が急性疾患で入院してくる。がんや感染症などの患者よりも、誤嚥性肺炎や転倒骨折、低栄養といった患者が増えていきます。患者の構成が変わる以上、医療機関は診療科の構成から考え直す必要があります。
──医療を持続させていくには、何が重要になるとお考えですか。
香取 まず、これからはタスクシフトは必須です。医師や看護師といった専門職は養成するのに時間も費用もかかります。少子化が進む中で今と同じペースで養成することは困難です。そもそも誰でもなれるような職種でもありません。
患者側にしても、たとえば外科の執刀医が同じ患者を術後までずっと担当することが当たり前とされていますが、これからはもう無理です。医師同士・医療機関同士の業務分担やタスクシフトを進めていかなければ現場は回らなくなります。
イギリスには、かかりつけ医の登録制度がありますが、医師ではなく医療機関の登録です。医療機関は医師1人だけではありませんから、医師と患者は1対1の関係とはなりません。それでもかかりつけ医制度は機能しています。患者も医師との関係のつくり方について意識を変える必要があると思います。
もう1つは医療DXを通じた医療の効率化です。在宅モニタリングやオンライン診療など、時間と空間を超越して診療を可能にするさまざまな機器・技術が実用化されています。そういった技術を使って医療を提供する仕組みを考えなければなりません。
──遠隔医療の普及によって、高齢で外来受診が難しくなった患者にも対応できるようになりますね。
香取 患者自身が出向いて受診することが難しくなると、遠方の専門医よりも、地元の医師を受診するケースが増えます。慢性疾患などの場合は比較的安定していますから、単に「治す医療」ではなく、多職種連携のもと、在宅などを含めて最後まで診てくれる「治し、支える医療」が求められます。
サブスペシャリティを持っている医師であっても、幅の広い診療にあたることが患者側から求められますし、経営上も必要になってくるでしょう。すでに過疎が進む地域では、そうした患者のニーズに応えられる中核病院が、自然と地域で中心的な役割を果たすようになってきています。
中小病院の効果的活用が問われている
──他方、中小病院には今後、どういう役割が期待されますか。
香取 開業医・かかりつけ医をバックアップする後方の入院機能を提供する役割があります。すでに、地域の慢性疾患の患者が急性増悪を起こした場合に、急性期病棟で受け入れている中小病院もあります。急性期病棟に急性期でない患者が入院する「なんちゃって急性期」には批判も多いのですが、重要なのは名称よりも実際にどういう機能を果たしているかです。「急性期」という名称に固執して、急性期病棟をつぶしてしまえば、患者を受け入れる場所がなくなります。
イギリスの医療体制は、基本的にかかりつけ医と1,000床規模の急性期病院の二本立てで成り立っていて、日本のような地域の中小病院はありません。もともと診療所と病院の間の空白が大きな問題でしたがコロナ禍でこの問題が顕在化しました。
日本の中小病院にもさまざまな課題はありますが、病院の7割が中小病院で、医療リソースの多くがそこに存在することを考えると、高齢化率が30%を超えるような国では、診療所と病院が別々の役割・機能を持つ急性期モデルは機能しなくなります。診療所と病院の機能連携、連続性が大事で、その意味では中小病院はむしろアセット(資産)であるといえます。
そうした中小病院を全体の医療提供体制の見直しの中でどう組み込み直すかを考えるのが、これから重要になると思います。
──病床機能の分化のあり方については、どのようにお考えですか。
香取 機能分化は効率化にあたってもちろん必要です。機能分化の議論はすでに一通り済んでいます。重要なのは、分化した病床機能を「地域のなかの病床」と捉えたときに、どういった機能を組み合わせて「病院」をつくるか、ということです。
近年は、急性期と回復期の間に、地域を支える病棟として地域包括ケア病棟がつくられ、6月の診療報酬改定で創設された地域包括医療病棟につながっています。小回りが利いて間口が広く、一定の二次救急を受け入れ、入院患者は速やかに在宅に帰す――という在宅支援の機能は地域に必須であり、同時にそれは地域包括ケアシステムを支える病院になるのです。
開業医も、日本はずっとソロ・プラクティスが中心で、これからもそうした状態が続いていくのでしょうが、一方でグループ・プラクティスのような規模の大きい診療所は、単独の開業医の先生方をバックアップする役割も果たすでしょう。
今後はそうした医療機関相互の機能連携・アライアンスで医療を提供する「面で支える医療」、ゾーンディフェンスが中心になっていくのではないでしょうか。
効率化のために必要なのは切れ目のない医療体制
──日本の医療の特徴の1つという、フリーアクセス制度の今後については、どのようにお考えですか。
香取 この議論をするには「フリーアクセス」の定義は何か、を考えなければなりません。
フリーアクセスというのは、「必要なとき、確実に医療が提供されることを権利として保障する」ことです。「いつでも好きなときに好きな医師にかかることができて、医師はそれに必ず対応することを保障する」ということとは少し違います。これまでの日本では、患者が医師を選んで受診することを最大限保障してきました。それが早期受診につながり国民の健康を支えてきたことは事実ですが、同じような体制をこれからも維持することは難しいでしょう。
しかし「フリーアクセスを制限する・しない」という乱暴な議論にしてしまっては、物事が前に進まなくなります。医療が提供される・医療が受けられる保障はしなければなりませんが、保障の方法をどうするか、を考えるべきです。
今の日本の制度は、実はひどい制度という見方もできます。何か体調が悪くなったとき、患者側でどの診療科のクリニックに行くかを考えて決めます。それはいわば素人に診断させている状態です。たとえば、腰の痛みで整形外科を受診したけれど、後になって実は腎臓疾患だったということがわかった、というケースはよくあります。または、忙しさなどを理由になかなか受診せず、いよいよ体調の悪化が深刻になってからようやく受診するケースもあります。どちらも適時適切な診療が行われなかったわけですが、基本的には受診するしないは患者の判断ですから患者側の責任ということになります。
こうした事態を防ぐため、保険者のお金を使って健康診断を実施しているわけですが、もし兆候が見つかった場合も、改めて医師の診察を受けて、一から説明し直さなければなりません。
そもそも、必要なのは「医師にかかる前に診てくれる医師」です。何でも診てくれて、必要に応じて専門医に紹介する医師、というのはそういうことで、それが家庭医やかかりつけ医になります。
また、必要なときに受診できるというのは、実際に受診できるかどうかという面のほか、何かあったときには診てもらえるという「安心感」を支える側面もあり、フリーアクセスはこの安心感を支えるという意味で大きな役割があります。コロナ禍では発熱外来を行っていない医療機関が患者を帰すケースがみられましたが、患者にとっては「自分が必要なときに断られた」こと自体が、その医療機関だけでなく、制度に対する大きな不信を生み出しました。「医師と患者の信頼関係が破壊されてしまうと医療制度も壊れる」という意見は正しいと思います。
──医療費抑制の観点から、かかりつけ医の登録制を求める意見もあります。
香取 「かかりつけ医制度は医療費抑制にはつながりません。そもそも無関係です。かかりつけ医は患者が選ぶものであって行政が決めるものではない。かかりつけ医とは制度を作れば機能するというものではありません。
患者は診療能力やコミュニケーション能力などから、信頼できるかどうかを考えて、かかりつけ医を選択します。もしかかりつけ医を登録制にして、医師の選択を制限しても、患者側がその医師を信用できなければ、結局はかかりつけ医を飛ばして救急車を呼ぶこととなって、制度が機能しなくなり、「無駄な医療」は削減できません。
本当に機能するかかりつけ医制度をつくるには、それを担う意思と資質のある医師を養成する必要がありますし、患者側にもかかりつけ医のかかり方の教育が必要になります。医療全体の効率化、費用対効果の最大化を考えるのであれば、切れ目のない医療体制をつくることです。医療提供側が、何かあったときに確実に他の医療機関につなぐネットワークをつくる。そういう意味でも、ゾーンディフェンスが求められます。
今のままだと、個々の患者や医療機関の行動の集積が全体でみればとても非効率な結果を生むという、壮大な「合成の誤謬」が起こってしまう。患者も医療機関も変わらなければならないと思います。
──持続可能な医療を検討する上で、患者負担についてはどのような方向性が考えられるのでしょうか。
香取 フリーアクセスを前提とする現行制度の下では、患者の受診行動を適正化するための政策手段としては一部負担の調整くらいしかありません。逆に言えば、医療提供の方法を変えることを考えれば、一部負担の取り方もいろいろ工夫することができるでしょう。
たとえば、かかりつけ医の仕事は何かあったときの診療だけでなく、普段から患者の管理をする役割ですから、まず基本報酬として患者1人当たりの報酬を支払い、具体的な診療行為があったときはそれに合わせて出来高で払う、というやり方もあります。イギリスのGPはこのやり方(定額報酬+出来高)です。その上で、定額部分と出来高部分の一部負担を変えることも可能でしょう。さらにいえば、診療行為の類型によって変える方法もあるでしょう。受診の仕方、かかり方とを組み合わせて考えればいろいろな案がありえます。
社会保障には経済をけん引する役割もある
──香取先生は「産業としての社会保障」という考え方を唱えておられるとうかがいました。
香取 たとえば年金について考えてみると、毎年の年金総額は50兆円以上あります。これは高齢者にとっては「収入=所得」ですから、50兆円以上の購買力を生み出しているわけです。
この50兆円がなければどうなるか。もちろん年金受給者の生活は成り立たなくなりますが、国内から50兆円分の消費が消えることでもあります。年金は立派に景気の底支えをしている。特に高齢化率の高い地方では、県民所得のうち年金が2割近くを占めているところすらあります。
同様に、医療は約45兆円、介護は10兆円の規模があって、医療・福祉分野は約850万人の雇用を生み出している産業といえます。高付加価値産業である製薬産業も医療保険制度が創薬力も安定供給も支えています。
社会保障の財源はもちろん保険料や税金ですが、産業として大きな経済効果を生んでいる上に、国民の命と健康を守り、労働力を保全し、次世代の子どもを支え、社会の安定を支えています。負担の反対側には給付があって、その給付が国民や社会に大きな付加価値を生んでいます。社会保障を負担として考えるのではなく、むしろ社会を支え経済成長をけん引する役割をもつものとして積極的に考え直すことが必要です。
最近では「グローバルヘルス」という考え方があります。日本では保険制度のもとで当然に普及している医療でも、発展途上国、特にアジア各国では普及していません。しかし、2040年には、世界の65歳以上の6~7割はアジアの住民という推計もあります。日本の医療・介護のサービスはレベルが高く、日本の知的資産といえ、これを使わない手はありません。
現代の日本の社会保障のような、国民から安定的に数十兆円を集めるような仕組みは、何もないところからいきなり構築できたわけではありません。そうした日本の資産を簡単に壊してはいけないと思います。
(2024年6月28日/本誌編集部 川村岳也)