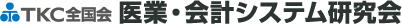データ統合で変わる「未来の医療」 ~遠隔医療の普及のカギ~
コロナ禍がきっかけとなり、オンライン診療をはじめとする遠隔医療に注目が集まった。海外では遠隔医療が積極的に活用されている一方、日本ではまだ普及が進んでいない。遠隔医療の普及のためには、どのような取り組みが必要になるのか。また今後、遠隔医療の広がりによって医療の姿はどのように変わっていくのか。日本遠隔医療学会の近藤博史会長に展望をうかがった。
近藤 博史
日本遠隔医療学会 会長
Kondoh Hiroshi
日本遠隔医療学会会長、鳥取大学名誉教授、協立記念病院院長。1981年大阪大学医学部医学科卒業後、大阪大学医学部附属病院助手、徳島大学医学部附属病院医療情報部副部長、鳥取大学医療情報部部長などを経て、2022年に協立記念病院院長に就任。また、2017年から日本遠隔医療学会会長。
聞き手/TKC全国会医業・会計システム研究会 兵庫県リーダ 尾上かおり
技術進展で「いつでもどこでも」診療できる世界はそう遠くない
──まずは、日本における遠隔医療のこれまでの流れについてお聞かせください。
近藤 もともと1990年代にIT技術が進歩するなかで、遠隔病理診断が導入されたのが始まりです。特に術中迅速病理診断(胃がんなどの手術の際、断端のがん細胞の有無を確認する)は専門医が地方では少なく、降雪などで行けない時にはがんの切除範囲をより広く手術する必要があった。そこでテレビ電話で顕微鏡をつないで判断しようという試みが行われました。
また、CTが普及するなかで、画像診断の専門医に見てもらう需要が高まっていたという背景もあります。2000年代に診療報酬で患者さんがいるほうの医療機関で算定できるようになりました。
2010年代からは、地域医療構想で慢性期と急性期の機能分化が進み、患者さんがその間を移動するようになったことで、診療情報の共有が求められ、地域医療再生基金のなかで地域医療連携システムを整備する動きが始まりました。
同じころ、離島や過疎地など、専門医がいない地域でのテレビ会議による遠隔の診療のニーズが出てきました。しかし当初は研究段階だったことや、テレビ会議システムが高額だったことなどからあまり広まりませんでした。
ところがスマートフォンが広まるにつれて、スマホの活用によるオンライン診療が始まり、診療報酬も算定できるようになりました。ただ、当時は点数が非常に低かった上、まだ電子処方箋もありませんでしたから、結局医療機関に行かないといけないということで、普及しませんでした。
それが新型コロナウイルスの感染拡大によって整備が進み、急速に広がって現在に至る、という流れがあります。
──先生はこれまで、勤務先の病院などでIT技術の導入に携わってこられたそうですね。
近藤 私はもともと放射線科の専門医ですが、大阪大学医学部附属病院では「インテリジェント・ホスピタル」の構想の実現に向けて、検査画像のデジタル化や会計のオンライン化も含む、放射線部門のIT化を担当し、業務効率化につなげました。
その後は約20年間、鳥取大学医学部附属病院で医療情報部長として、電子カルテの導入や、「おしどりネット」という鳥取県の医療情報システムの整備を担当してきました。
特に「おしどりネット」は、日本で初めてとなる、世界標準の規格に基づいたネットワークです。コスト削減やセキュリティ向上につながる「シンクライアント」という仕組みや、表示や処理を高速化できる大容量フラッシュメモリなどを導入しました。
──さまざまな技術の導入や活用を進めてこられた先生から見て、遠隔医療に関する技術はどれくらい進展してきているのでしょうか。
近藤 海外ではすでにさまざまな機器が実用化されています。たとえば電子カルテにデータを送れる耳鏡などです。自分で耳鏡を耳に当てて、遠隔の医師が鼓膜の様子を見て中耳炎かわかりますし、皮膚に当てて血糖値を測定する機器や自分で眼底写真を撮って遠隔でAI診断する研究もあります。顔面の動画で脈拍を読み取るソフトは日本でもフリーのソフトにあります。
モバイルヘルスの分野は、上記の遠隔モニタリングの他に遠隔治療、遠隔治験があり、遠隔治療はモニタリング情報からタイムリーな介入を行うもので、症状に対して投薬を促したり、食事制限、外来受診の指示などをします。遠隔治験は治験患者の参加勧誘から説明や検査指示をしますが、脱落者対策に効果的といわれています
──世界的に見ると、遠隔医療の技術は相当進化しているのですね。今後は日本においても普及していくのでしょうか。
近藤 遠隔医療は患者さんにとってメリットがありますから、普及の動きは避けられない話だろうと思います。
これまでの医療はロケーション・ディペンデント(場所への依存)で、病院や診療所に行かなければ医療を受けられませんでした。しかし、医療というのは情報ありきで動いている世界なので、極端な言い方をすれば、情報さえあれば医療の提供が可能になります。モバイルヘルスやスマホなどの技術が進展し、モバイルでいつでもアクセスできるようになりつつあるのが今の状況です。
特に、モバイル機器で常時データを取り続けることは非常に意義があります。特に高齢になると、いつどのような病気を発症するかわかりません。入院患者だけではなく、地域で普段通り暮らす人も含めて、モバイルでモニタリングすることにはメリットが大きいと思います。
そうしたモバイル系の機器においてはセンサー技術が使われているわけですが、実はセンサー機器の小型化については、日本が強みを持っているとされています。
センサー技術を使った機器には高額なものもあるため、誰でもどこでも使えるようにするためには、仕組みの構築が必要になります。しかし、AEDと同じように、拠点に置いて管理できるようにすればどんどん普及するでしょう。「いつでもどこでも診療ができる世界」というのは遠くないと思います。
──医療機関での診療のあり方も変わるのでしょうね。
近藤 今後は遠隔医療を通じて、診断が非常に難しい疾患や、診療した経験のある先生が少ない疾患にも対応できるようになると思います。たとえば循環器系の先天性の疾患では、緊急に検査、診断して投薬しなければならないような病気もありますが、専門医が遠隔で検査できれば素早い処置が可能になります。
また、健康診断の分野でも、採血用ロボットの開発も構想されており、各地の「採血センター」でロボットによる採血を受けて、検査結果は各医療機関に共有されるとともにスマホで通知される――という世界になるかもしれません。
健診センターはこれまでロケーションに依存したサービスを展開してきましたが、今後はセンターに行かなくても健診を受けられる時代になってもおかしくないと思います。
もちろん、CTやMRIなどの大型の検査機器は場所に制約されますが、予約の取り方については、空いている病院が事前にわかって、他の病院から急ぎの検査を受け入れるなど、ダイナミックに考えられるのではないでしょうか。
ちなみに、専門医に遠隔で診療してもらおうという発想は、専門医の技術をAIに学習させようとする発想と似ています。遠隔医療の研究の進み方はAIの進化の流れと非常に近いと思います。遠隔医療では選択された有用な情報をデジタル化して通信します。このデジタルデータはまさにAIの学習データとして最適なものです。遠隔医療と、AIを使った診療効率化・精度上昇の研究は非常に近いところにあるといえます
データの蓄積と統合が遠隔医療の普及には不可欠
──日本では、現実的にオンライン診療は普及しつつあるとはいえ、そのほかの遠隔医療はまだまだという印象があります。
近藤 日本の遠隔医療については、「オンライン診療さえできればよい」と思われているところもあり、世界とのズレが生じているのではないかと心配しています。
新型コロナウイルスの感染拡大後、日本では各学会に意見を求めましたが、遠隔でどのような疾患に適応してはいけないかと制限する方向へ進みました。一方、EUのIT関連基金Horizon2020ではモバイルヘルス機器の開発とデータ統合に利用されました。
たとえば「触診ができないので診断できない」という意見があります。しかしネットワークに接続できる超音波検査機器があれば相当カバーできるのではないかと思います。本人や家族が操作し、医師が遠隔で画像を見てを指示すれば、かなりのことがわかります。
疾患で制限してしまうのか、それとも診察する先生と患者さんの合意の上である程度許容し、技術発展を促すのかは考え方次第だと思います。拡大使用、危険排除に他の方法は考えられないものでしょうか。
確かに遠隔医療自体のリスクについては低下するかもしれませんが、たとえば離島などで緊急に医療が必要とされた場合にも、遠隔医療ができないので医療を提供できない、というリスクが考えられます。
制限するとしても新しい機器を開発できるような余地を残しつつ、社会で活用する方向性を打ち出すべきではないかと思います。
──遠隔医療の普及にあたり、どのようなことが必要になるのでしょうか。
近藤 カギとなるのはインテグレーション、つまりデータの統合だと思います。眼底鏡や耳鏡といったモバイルヘルスの技術も、診療情報と統合されて初めてデータの意義がわかります。たとえば気圧のデータと頭痛の発生を合わせて統計処理することで、気圧の変化で頭痛が起きることがわかったように、データを統合することに意義があると思います。単にモバイルのデータだけで何かできるわけではありません。
そうしたデータの統合のためには、個人の過去の情報がすべて1つに集まっていることが重要です。海外、特にフィンランドではデータを統合化しています。それによって個人の長期間のパーソナルヘルスレコード(PHR)が保存され、各国民のPHRが国のデータベースとして2次利用できる状況です。
また、これは私の考えですが、データを常に蓄積し続けることで、個人個人の正常値が見えてくると思います。それは統計的な処理をしている、一般的な正常値よりも非常に狭い範囲にあるので、異常の検出も早くなるのではないでしょうか。
日本の医療の状況がデータ統合を阻んでいる
──海外ではデータを1つに集め、統合しているとのことですが、日本での状況はどうなっていますか。
近藤 日本でもデータの標準化が進められてきましたが、統合が進んでおらず、結局は時系列で追えるデータがないという状態です。たとえばPHRの収集については、かつて政府は「企業の有料サービス」という考えでした。このため、国ではデータが集まっていません。
診療情報の研究利用のために次世代医療基盤法が制定されましたが、データを医療機関から収集する組織がいくつもできて、それぞれの間でデータが統合されることは許されていますが、1つに統合されるとはなっていません。セキュリティ上、セキュアな情報は数が増えるほど漏洩の危険性が上がるものです。また、日本の多くのモバイル機器のモニタリング情報は、外来で主治医がウェブで参照するだけで、病院の電子カルテに統合されません。
このため、個人に応じた医療の提供にあたっての障壁となっていますし、その上医療に関する研究においても、症例のデータを集めるのに限界がある状況です。
つまり研究データベースのインフラが劣っている状況です。臨床研究のアイデアがよくても、日本では症例数を大きくできない状況です。臨床研究のインフラがないことは、日本の臨床研究評価の低下にもつながりかねません。
──日本でデータの統合やシステムの標準化が進まない原因はどこにあるのでしょうか。
近藤 医療機関の多くが診療所と中小病院から構成されていることが影響していると思われます。
海外は大病院が中心で規模が大きいので、IT技術者を職員として直接雇用します。そこでは部門システムと電子カルテと画像管理システムをそれぞれ別に仕様書を作成し導入します。システム間のインターフェースは仕様書のなかで彼らが書きます。各病院の技術者はこのインターフェースを議論し標準化されていきます。病院間の接続も同様に標準化され、病院間接続も容易になります。
一方、日本の場合、中小病院やクリニックが技術者を雇うことは難しい。このため、ベンダーに丸投げになってしまいます。ベンダーは大きな電子カルテベンダーがインターフェースを決め部門は従います。本来システム間接続はソフトが稼働する利用者権限でよいのですし、必要最小限の設定にしますが、「閉じたネットワーク神話(閉域網神話)」のなかで利便性が優先され管理者権限のパスワードを共通化までしました。
これではシステム間接続の標準化は進みません。また、セキュリティ上のリスクも大きいものです。院外のサプライチェーンにも同じ対応をして大きな被害を受けた医療機関が出たわけです。
新しい知見が生まれてようやくDXの実現となる
──遠隔医療の普及のために、どのような課題を解決しなければならないのでしょうか。
近藤 遠隔医療の目的を明確にすることとそのために何をするべきかを試行錯誤することです。クラウドやFHIRなどは重要ですが、技術を目的化しないこと。これらは手段・方法です。
たとえば、「オンライン診療」ですが、日本では対面で会話するテレビ会議システムを使うことだけが目的のように見えます。欧米では電子カルテの情報、検査情報などがオンラインで開示されたのちに、コロナ禍で対面診療に代わってテレビ会議システムを導入しています。医師、患者間で診療情報を共有する基盤の上で擬似対面しています。
前述のデジタル聴診器もデジタル耳鏡もデジタル眼底鏡も電子カルテに連携した後のことです。対面診療に必要な情報を同時に利用できる仕組みになっています。
もちろん、この前にシステムアクセスの認証と認可のシステムも確立しています。日本ではテレビ動画のなかで証明書を見せたりしますが、フェイク動画、静止画の時代には危険です。
遠隔医療の病院間連携では診療情報が1箇所に集中することを漏洩の危険があるとして2010年の地域医療再生基金による地域連携ではデータの標準化をSS-MIXでするとしておきながら、データ統合がされていません。
また、標準形式のSS-MIXを必須としましたが、コード体系が広く普及している保険請求のコードとは別の普及していなかったものにしたので、データ統合が難しかったのです。
セキュリティの考え方も医療情報システムの安全管理ガイドラインが5.2版から6.0版に大きく変わりました。これまでの、素人に「まずこれをすること、可能であればこれを推奨する」といった形式から世界標準のISMSを原則に各医療機関が状況に合わせてリスク分析する考え方に変わりました。ベンダーも医療機関も慣れるまでには時間を要します。遠隔医療学会としては、研修制度や簡便な方法を提言していくつもりです。
──遠隔医療は医療DX推進の観点からも求められるかと思いますが、どのようにお考えですか。
近藤 私はDXというのは、たとえば音楽や書籍がデジタル化されてサブスクリプションの売り方が変わったように、コンテンツのデジタル化で社会経済の構造が大きく変わることだと考えています。
「医療機関に遠隔医療などのIT技術を導入すればそれで終わり」と考える人も多いかもしれませんが、デジタル化して何らかの新しい知見が生まれるところまで行って初めてDXが実現するのだと思っています。音楽、書籍の例からすると医療機関が少なくなることも考えられます。
その意味で、モバイルヘルスは、外来、入院以外の時間、医療機関に依存しない状況で医療データが収集され、新たなエビデンスが得られ、また、デジタル治療ではタイムリーな介入や日常生活の改善などこれまでの医療で対応できなかった治療をもたらします。治験でもこれまで以上の多くの参加者を集め、脱落者の少ない治験実施の可能性を持っています。
また、離れた医療機関の診療情報や医療機関外の情報との統合は新たな知見をもたらし、人工知能の利用も容易にするでしょう。
(2024年7月23日/構成・本誌編集部 川村岳也)