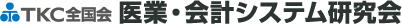「幸福」になるためにできることは何か ~医療現場におけるウェルビーイングの重要性~
右肩上がりに経済成長した時代が終わり、格差の拡大や少子高齢化など将来が見通せない社会にあって、幸福度の向上を目指す「ウェルビーイング」という考え方に注目が集まっている。日本のウェルビーイング研究の第一人者である前野隆司教授に、ウェルビーイング向上のためには何をすべきか、また医療現場では何を意識すべきか、話をうかがった。
前野 隆司
慶応義塾大学大学院
システムデザイン・マネジメント研究科 教授
武蔵野大学ウェルビーイング学部長
Maeno Takashi
東京工業大学理工学研究科機械工学専攻修士課程修了後、キヤノン株式会社、カリフォルニア大学バークレー校機械工学科、慶應義塾大学理工学部機械工学科教授などを経て現職。
聞き手/本誌編集人 石川 誠
ウェルビーイングとは、身体・こころ・社会のよい状態
──そもそも、「ウェルビーイング」とはどのように定義されているのでしょうか。
前野 WHOは健康の定義について、「単に疾病や病弱な状態でないということではなく、身体的、精神的そして社会的に完全に良好ですべてが満たされた状態」としています。この「良好な状態」を指す英語として、1946年に初めてwell-beingという単語が使われたといわれています。
近年ではウェルビーイングのことを「幸福」とか「善き人生」とか、いろいろな訳され方をされていますが、原点に立ち返って、身体とこころと社会のよい状態のことをウェルビーイングであると考えてよいと思います。
もっとも、医療系の学問では以前から、身体的な健康という意味で「ウェルビーイング」という言葉が使われていたように思います。最近になって、「広い意味での健康」という意味が普及してきた、ということですね。
ところがスマートフォンが広まるにつれて、スマホの活用によるオンライン診療が始まり、診療報酬も算定できるようになりました。ただ、当時は点数が非常に低かった上、まだ電子処方箋もありませんでしたから、結局医療機関に行かないといけないということで、普及しませんでした。
──前野先生はもともと工学に関する研究をしておられたとうかがっています。
前野 私は以前、精密機器メーカーのエンジニアとして勤務し、「人々に幸せになってほしい」と思ってカメラなどを設計していました。しかし、設計のパラメータにシャッタースピードや重量はあっても、「幸せ」というパラメータはない。それでは設計したとしても使う人が幸せになる保証がありません。私はこれを設計論の不備だと思い、補完する必要があると感じて、ウェルビーイングの研究を始めました。
設計論のなかには、ユーザーがどんな価値を求めるのかという考え方が含まれますが、それを追求していくと、結局、人々は幸せになりたいわけです。ですから大学に移ったときに、「幸せ」というパラメータを含んだ、究極の設計論をやりたいと思いました。「幸せ」のパラメータを入れなければ人々が幸福な社会をつくれない、と気づいたのです。
私自身としては、今でも工学の研究をしていると思っています。人々のウェルビーイングを向上させる製品やサービスは工学の研究対象です。たとえば、ウェルビーイングを向上させる職場をつくるには職場の「設計」が必要になります。
ただ、医学系からみると医学の研究にも見えるでしょうし、学問横断的な分野といえると思います。幸せに生きるというのは基本的人権の最初の部分、幸福追求権です。すべての学問は人々の幸せのためにあると考えれば、幅が広いのは当然といえます。
──近年のウェルビーイングへの注目度の高さは、前野先生も実感されていますか。
前野 私がウェルビーイングの研究を始めたころは「何か怪しい研究を始めたのか」と冗談を言われたものです。しかし今ではウェルビーイング経営を掲げる経営者が増えていますし、国の教育振興基本計画にウェルビーイングが明記され、首相の発言にも登場するなど、産官学どこでも注目されるようになったと実感しています。
ここまで注目されるようになった要因としては、2つあると思っています。1つは学問の進歩です。もともと、幸せに関する研究は心理学の分野で行われていましたが、研究がかなり充実してきたうえ、私の研究のように、心理学でわかったことを世の中に役立つサービスや製品に応用しようとする研究も発展してきました。学問の発展で使えるパッケージができあがったということです。
もう1つは、残念ながら不幸せな社会だからだと思います。戦争や貧困、パンデミック、環境破壊など、さまざまな不幸はありますが、多様な課題が世の中を覆っている不幸な時代で、幸せについて考えなければ幸せになれなくなってきた、という背景があると思っています。
幸福度を高めるためには利他性と強い自己が必要
──それでは、個々人がウェルビーイングを向上させるための考え方について教えてください。
前野 私がこころのウェルビーイングについて、因子分析という手法で分析したところ、「4つの因子」(下図表)をすべて満たしている人が幸せで、すべて満たせていなければ幸福度が低いという「幸せの条件」がわかりました。幸せになるには、いわば健康に気をつけるのと同じく、これらの因子を満たすように「幸せに気をつける」ことが必要です。
近年は予防医学の発展とともに、健康に気をつける、健康に気を配るという考え方は普及していますが、「幸せに気を配る」という概念はあまり広がっていません。幸福度が高い人は健康で長寿であることも研究でわかっていますから、医療従事者の方にも患者さんにも取り入れていただきたい考え方だと思っています。
──「ありがとう因子」があるということは、自分だけが幸せになろうとするだけでは幸福度が高まらないのですね。
前野 世界各地の研究では、「利己的な人は幸福度が低く、利他的な人は幸福度が高い」という相関関係が出ています。
ただしここで注意すべきなのは、利他的なだけでは自己犠牲に陥るリスクがあります。特に医療機関で働く方は利他的な想いを持つ方が多いかと思いますが、コロナ禍で自己犠牲を払い、つらくて辞めてしまった方も少なくなかったのではないでしょうか。
つまり、「ありがとう因子」だけが高くても幸せではないのです。利他的なのは素晴らしいことですが、それだけだとバーンアウトしてしまう。それではどうすればよいのかといえば、「やってみよう」という自己の強い意志、「なんとかなる」というチャレンジ精神、「ありのままに」という個性が重要になるのです。
利他にプラスして強い自己があると、幸せになるのです。医療従事者の方には特に、ありがとう因子だけではなく、ほかの3つの因子も満たしているか、チェックいただきたいと思います。
4つの因子のうち、「やってみよう」「何とかなる」「ありのままに」というのは利己的という意味ではありません。やりがいを持って、何とかなるとチャレンジして、ありのままの個性を持つ。自分をより良い人にするという強い自己です。利他だけでは自己犠牲、強い自己だけではわがままになりますが、両方があるから社会も丸く収まるのだと思います。
イェール大学のニコラス・クリスタキス博士の研究によると、幸福感も不幸な感情も他人に“伝染”するとされています。つまり自分を幸せにしていれば他人も幸せにできるのです。自分も他人も幸せで、みんなが円満な社会というのがウェルビーイングが向上した社会だと思います。
「幸福寿命」は超高齢社会の希望になりうる
──患者が自分自身のウェルビーイングを向上させるために、どのようなことを心がけるべきなのでしょうか。
前野 最初に申しました通り、健康とは身体的、精神的、社会的によい状態であって、単に病気または病弱ではないことを指すのではありません。つまり病気か健康かという問題ではないのです。
障害もそうですが、すべての人には病気も含めて多様性があります。すべての多様性を受け入れて、それとともに豊かに生きていくことは可能だと思います。
これからの超高齢社会においては、多くの高齢者がいろいろな病気を抱えながらも幸せに生きていける、「幸福寿命」を延ばすことが重要になるでしょう。
そういう意味では、もちろん医療者にとっては病気を診断して治すことが大事ですが、病気であろうとなかろうと、すべての人のこころのウェルビーイングを考慮する。病気でない人が健康に気をつけるように、病気かどうかで分けずに、幸せに気をつける発想が必要になってくるのではないかと思います。
病気になったからダメだと思って不幸を感じ、死にたいと思う人もいますが、たとえば「キャンサーギフト」という考え方のように、死を意識したことでいきいきと生きたいと思って、人生が鮮やかに見えるようになったという人もいます。
病気になったり障害を抱えていたりしても、生きている限りは幸せに生きることは可能なはずです。健康寿命とは別の概念として、幸福寿命という概念が広まってほしいと思います。「病気かそうでないかにかかわらず、すべての人がウェルビーイング向上を目指せる」という考え方が広まれば、超高齢社会の希望にもなると思います。
もちろん、きれいごとだという反論もあるかと思いますが、1日のうち5秒でも1秒でも幸せを見出すことができれば、幸せは残っているわけです。それをいかに楽しんで充実させていくかということを目指すべきだと思います。
──患者たちに日常的に接する医療従事者が、患者のウェルビーイングを向上させるために必要な心構えや姿勢はどういったことだと思われますか。
前野 医療従事者の方は自分自身の時間を削ってでも、患者さんの命を救う尊い仕事をされていますから、本当に頭が下がります。まずは無理をせず、自分自身のウェルビーイングを大事にしていただきたいと思います。その前提で、純粋な医療行為だけではなく、ちょっとした気遣いを足していくよう心がけていただくことが重要なのではないでしょうか。
医療従事者の方がウェルビーイングの考え方を認識いただくことで思いつく取り組みもあると思います。より一層人間らしく生きるための工夫が可能な時代になっていると思います。
また、そうした気遣いを周囲とシェアすることもよいでしょう。特に医療分野は安全管理が求められますから、どうしてもネガティブな方向に目が向きがちです。もちろん危険をなくすために極めて重要なことなのですが、同じくらいポジティブな内容の共有も行っていただきたいと思います。
そのためには職場内の関係性が重要です。異なる職種の間でも尊敬し合う風土をつくるよう、気をつけることだと思います。
特に院長先生などのトップの方は、まずは医療機関に勤めるすべての人の幸せを考えていただきたいと思います。幸せは“伝染”しますから、医療従事者が幸せなら患者さんも幸せになり、よい循環が生まれます。
現代の課題解決にはウェルビーイングが欠かせない
──近年はウェルビーイング経営にも注目が集まっています。
前野 一般企業の場合では、幸福感の高い社員は創造性が高いとか、生産性が3割向上するなどの研究結果があります。おそらく、幸福感が高い職場というのは人間関係も良好ですから、判断ミスや伝達ミスなどが起こりにくくなり、ミスへの対応時間が少なくなることで、生産性が上がっているのではないかと思われます。
医療機関の運営においても同様ではないでしょうか。生産性が高くなり、残業時間も減り、余裕をもって効率的に仕事ができるようになり、ひいては患者さんの満足度向上も期待できると思います。
──しかし経営者からすると、「ウェルビーイングを向上させるために福利厚生を増やすことで費用がかさむ」という意見もあるかと思います。
前野 もちろん福利厚生も重要なのですが、そもそも職場でのウェルビーイング向上のために必要なのは「働きやすさ」ではなく「働きがい」です。
早く帰れるようにするとか、保養施設を整備するとか、働きやすさのほうが成果が目に見えるのでやりやすいですよね。お金さえかければ働きやすさは向上できますから、ついつい快適なオフィスづくりにばかり集中する経営者もいます。
しかし、快適になったところで「不幸せでない職場」にはなりますが、働きがいのほうが高まらなければ仕事はつまらないままで、幸福感は高まりません。働きがいは向上しづらくて、成果も見えにくいですが、着手しなければ幸せな職場はつくれないのです。人間関係を改善して、仕事の意義を理解して、みんなで一致団結して大きな視野で大きな目標を持って取り組む。まさに幸せの4つの因子を満たして、人間らしく働くことを醸成していかなければならないのです。
──最近はどの業界も人手不足の問題が深刻ですが、採用の側面からもウェルビーイングに関心が高まっているようです。
前野 それは明らかです。私も幸福度が高いとされる企業へ視察に行くことがありますが、そういう企業は地方の小さな会社であっても、全国から応募が集まって採用倍率が高くなりますし、また辞める人はほとんどいません。人手不足とは無縁なのです。
つまり給料がいいだけではなくて、働きがいがあるとか、人間関係が整っているようなよい職場をつくり、ウェルビーイングを高めなければ、いい人材に来てもらえず、定着してもらえない。ウェルビーイングの向上を競い合う時代に入ったともいえます。
たとえば、四国地方にある製造業の会社は幸福度が高いことで知られていますが、やっているのは挨拶、掃除、コミュニケーションです。「目を見て大きな声であいさつをしよう」というと小学校の目標のようですが、実際にそれで幸福度が高くなっています。
また、この会社では毎朝1時間朝礼を行っています。これは長すぎると思うかもしれませんが、チームで話し合うことで仲よくなって、理念の共有も行っている。当然、目指す方向が一致した会社というのは競争に強いです。
昔は軍隊のような、徹底した上意下達の組織もありましたが、それは不幸な気持ちによって一丸となっている状態です。心のつながりを根底にして、それぞれが自立しながらも共感によって一致するという「大家族主義経営」がやりがいにつながると思います。こうした掃除や朝礼は、もともと日本企業で盛んでしたよね。ウェルビーイングというのは、昔の日本企業にあったものを英語で上手に表現しているともいえます。
──最後に、今後の社会におけるウェルビーイングの重要性についてお聞かせください。
前野 近代に入るまで、倫理を担っていたのは宗教でした。しかし宗教によって幸せになるというメカニズムは、特に産業革命以降は薄れていったわけです。その後到来した資本主義社会では、最初はみんなが自分勝手にやっていても全体で発展するから問題ありませんでした。ところが、環境や貧困など現代の課題は自分勝手主義では解決できません。それぞれが倫理感を持ち、他者に目を向けようとすることが必要です。
これは言い過ぎかもしれませんが、現代の課題を解決し、資本主義の限界を超えるためには、私はウェルビーイングしかないと思っています。人類が生き延びるためには、4つの因子を満たしてウェルビーイングを向上させ、生産性を上げて、よい社会をつくることが必要である。このことをより広めていく必要があると考えています。
(2024年8月6日/構成・本誌編集部 川村岳也)