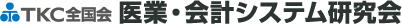“事故につなげない”ために エラーに気づく仕組みの構築を
小さなヒューマンエラーがきっかけとなって取り返しのつかない事故に至ってしまったという事例は少なくない。しかしさまざまな対策を講じたとしても、ヒューマンエラーを完全に防ぐことは難しい。それでは、ヒューマンエラーによる事故を回避するためにはどのような考え方が必要となるのか。心理学を専門とする松尾太加志教授に話をうかがった。
松尾 太加志
北九州市立大学 特任教授
Matsuo Takashi
九州大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(心理学)。佐賀女子短期大学講師、北九州市立大学文学部人間関係学科教授、同大学文学部長等を経て2017年に同大学学長に就任。2023年より現職。
聞き手/TKC全国会医業・会計システム研究会 九州エリア統括リーダ 加藤潤一
間違いは自分で気づけない
仕組みで気づかせる
──今回は「ヒューマンエラー」をテーマにお話をうかがいます。松尾先生はヒューマンエラーをどのように定義されていますか。
松尾 人の判断や行為が期待された範囲を逸脱し、その結果も期待された範囲を逸脱した場合に、その判断や行為がヒューマンエラーである、と定義しています。
これはつまり、「本来できていたはずなのに」(=判断や行為の逸脱)「できなかった」(=結果が期待された範囲から逸脱)ことがヒューマンエラーであるという意味です。私たちが「間違った」と思うのは、自分ができるはずだと思っていたことができなかったからです。
しかし、実はヒューマンエラーの原因は人間の問題だけとは限りません。私はもともとヒューマンインターフェース、人と機械のコミュニケーションに関する研究を行っていましたが、機械の設計が人間に適合していないために、それを取り扱う人間が間違えてしまうことがあります。
それでも、機械やモノそのものの問題ではなく、あくまで機械やモノとかかわる人間が間違えたので、ヒューマンエラーと呼ばれます。ですから、人間側が気をつけるよりも、機械やモノの改善が重要になることもあるわけです。
──医療機関におけるエラーの起こり方というのは、一般の職場と異なるのでしょうか。
松尾 異なるところもあると思います。多くの企業、職場では決められた仕様の製品を製造し続けたり、誰に対しても提供するサービスが画一的であったりしています。一方で医療現場の場合、患者さん個々人に合わせて別々の対応をしなければなりません。患者さんの体は1人ひとり異なりますから、同じ病気の患者さんだったとしても、対応する方法は個々で変わっていきます。
このため、患者さんに関する情報のコミュニケーションが重要になってくるのですが、医療現場ではひとりの患者さんに対して多職種の人がかかわります。職種が異なると医療における考え方や立場、知識が異なります。その結果、職種間でのコミュニケーションのミスなどによってエラーが起こりやすくなっている側面もあるようです。
──エラーを減らすためには、どうするべきだとお考えでしょうか。
松尾 私は「外的手がかり」という考え方を導入することが有効だと思っています。外的手がかりとは、エラーに気づくための手がかりになるもののことで、具体的には、「対象」「表示」「文書」「電子アシスタント」「人」の5種類(下図参照)に分類できると考えています。
人はエラーを起こすとき、あくまで自分自身では「正しい」と思って行動しているわけです。自分で間違いに気づくことができれば修正できますが、正しいかどうかを判断できていない。そこで、その場面で外から気づかせる「手がかり」を仕組みとしてつくるのです。
エラーを防ぐ分析方法については、すでにさまざまな手法、技法が提唱されています。しかしそういったものの多くは難解な部分もあり、正直なところ導入するには難しく感じられるでしょう。
また、エラーの原因がどこにあるのかを突き止めるために分析しようとするとかなり手間がかかります。そのため、現場で実際にどうすべきなのかがわかりにくくなっていることが多いでしょう。
そこで私は、まずはエラーを防ぐ方法のヒントになるような枠組みを用意するのがいいのではないかと考えました。エラーを防ぐには人が行動を起こそうとしている最終的な場面でエラーに気づかせればよいわけで、気づかせる「何か」を外的手がかりとして設けることだけを考えれば、原因を掘り下げて分析せずに対策を用意できます。
何もないところからエラーの防止策を考えるのではなく、外的手がかりの枠組みで考えればアイデアが浮かびやすくなると思います。
──対策となる手がかりを考える際のコツは何かあるのでしょうか。
松尾 まずは、実現可能性を意識しないでアイデアを出す。それが実現できるかどうかを先に考えないことです。
心理学の観点から考えると、「精緻化」のプロセスが重要なのです。実際にあったエラーの場面について深く考える。実現可能性は置いておいて、その上で5つの手がかりに基づいて、アイデアを考えることが必要になります。思考を活性化させていくことで、本当に行うべき対策がどこかで生まれてきます。
考えるときには、あくまで外的手がかりを導入する現場の状況にもとづいていることも重要です。机上だけではアイデアが浮かびませんので、現場に出向いて考えるべきでしょう。
すべてをマニュアルに載せることはできない
──外的手がかりのなかには「文書」がありますが、エラーを防ぐための対応として、現場ではマニュアル作りをすると思いますが、大変な労力が必要になります。
松尾 理想的には、マニュアルはそもそも作らずに済むようにするのが一番よいことだと思います。マニュアルは想定された場面において、単純に手順を決めているものに過ぎません。すべてのことをマニュアルに載せることはできません。むしろマニュアルになくてもやらなければならないことはたくさんあります。どうすればマニュアルがなくても作業できるようにするかが重要なのです。
外的手がかりでいえば、文書よりも表示や対象、電子アシスタントなどで何をすればよいかわかるようにするということです。逆に、マニュアルを作っただけで「防止策になった」と思ってしまうと、かえってよくありません。
──ちなみに、近年のIT技術やAIなどの発達にはめざましいものがみられますが、外的手がかりの1つに「電子アシスタント」があるように、技術の進歩によってやがてはエラーは少なくなっていくのでしょうか。
松尾 もちろん、エラーを減らすためには電子化は重要で、積極的に取り組む必要があります。しかし電子化を進めたとしても、エラーが少なくなるとは限りません。
たとえ電子化しても、人が情報を入力するとか、情報をわれわれが見て判断するというように、最終的にはどこかで人間が介在する場面が出てきます。当然、そこで間違いは起こり得ます。電子化によって新しいエラーが生まれる可能性もありますから、対策については引き続き考えていかなければなりません。
また、逆説的な言い方にはなりますが、おそらくAIが人間に限りなく近づいていくと、やがてはAIがヒューマンエラーのような間違いを起こしてしまうのではないか、とも思っています。
ただ、AIは生成AIのような確率論的なベースのものと、エキスパートシステムのように専門家の知識を論理ベースに載せるものがあります。これらをうまく組み合わせてエラーを減らせる可能性もあると思います。
──人に気づかせる外的手がかりがエラーを減らす有効な方策になるのですね。
松尾 ケースバイケースだとは思うのですが、識別しやすい言葉であればおそらく問題ないのではないでしょうか。
間違いやすい言葉については識別性を高めることが重要です。たとえば自衛隊などでは、1(イチ)と7(シチ)では聞き間違いやすくなりますから、「イチ」「ナナ」と言っています。
略語であるかどうかにかかわらず、ある表現が「職場内/院内でのローカルルール」として特定の意味を持つように使われているケースがありますが、これはやめたほうがよいでしょう。略語などの表現では情報を伝える側と受け取る側ではギャップがありますから、必要な情報をうまく付加していくことで、間違いを少なくできると思います。
エラーが事故につながらないようにする「Safety-Ⅱ」が必要
──ここまで、いかにヒューマンエラーを減らすかというお話をうかがってきました。しかし、そもそもの話になってしまいますが、エラーというのは完全にゼロにできるものなのでしょうか。
松尾 もちろん完全に防ぐのは難しいでしょう。
そもそも人間は動物であり、動物というのは環境に適応し、効率的に行動して生き延びてきた存在です。人間は環境へ適応するために柔軟な判断ができるからこそ、間違いも起こすのです。生き延びるなかでは、エラーをなくすこと自体が必ずしも一番重要なわけではありません。もしエラーをゼロにするために注意力を使ってしまえば、それがかえって負担になってしまいます。
エラーをなくせないのですから、エラーをしたとしても、それが大きな事故につながらないようにすることが大事です。
たとえば医療現場をはじめとして、何かの作業に取り組む際、見落としを防ぐために複数人でダブルチェックを行うことがありますが、何度やっても見落としてしまうことは起こり得ます。それよりも、もしチェックを見落としたとしても大丈夫なようにする方法を考えるべきなのです。
ミスを完全になくそうとする考え方を「Safety-Ⅰ」と呼ぶ一方で、このようにミスが起こったとしても事故にならないようにしようとする考え方を「Safety-Ⅱ」といいます。
システムが単純なものや、銀行のシステムなど厳密さが求められるものにはSafety-Ⅰの考え方が必要です。しかし、医療をはじめとして人間が直接かかわるところや、システムが複雑化している場合は、エラーを完全になくすことはできません。Safety-Ⅱの考え方を取り入れた対策を検討するべきです。
先ほど申しました外的手がかりの考え方は、エラーが起こっている、あるいは起こりうることに気づかせる方法であり、エラーが発生することを前提としています。ですから、Safety-Ⅱの理念に近い考え方といえます。
──クリニックの院長先生など職場を管理する立場にある人が、職場内でのエラーに対応するにあたって、どのようなことを意識するべきだと思われますか。
松尾 なかなか難しいところですが、まずは問題点があったときに指摘できる雰囲気をつくることが必要でしょう。最近は「心理的安全性」という言い方もなされます。
しかし、クリニックのようにドクターが中心になっている職場では、意識せずともタテ社会的な構造ができやすい面もあるかと思います。
問題は報告されなければ改善につながりません。誰であれ問題を見つけたらお互いに言い合えるようにする。それに加えて、どうしてもエラーは起きるわけですから、しっかりとエラーを報告し合えるようにすることが求められるでしょう。
また、これはクリニックなどの医療現場に限りませんが、最初から完全にベストの体制で始められる仕事はありませんし、システムや制度もいきなり完全無欠な状態で始められるわけではありません。やり始めてから実際に問題が起こるわけですから、判明した問題を改善につなげる環境づくりが必要です。
精神論では事故の再発防止につながらない
──エラーが起こったとき、つい「次からは気をつけなさい」と言ったり、言われたりします。
松尾 エラーは精神論では解決できません。というのも、先ほども申しましたように、エラーを起こしているときは自分で間違っているという認識自体がありません。気をつけようとしても気づけないのです。
また、ヒューマンエラーが原因で大きな事故が起こってしまった場合、最初のきっかけはひとりのエラーではあるのですが、事故に至るまでにはいくつかの段階でエラーが生じています。エラーに気づいていれば事故を防げたにもかかわらず、どの段階でもエラーに気づけなかったから事故に至っているのです。
ですから、たまたま最初のきっかけとなってしまった人を責めても、結局は何の対策にもならず同じ事故が繰り返されてしまいます。エラーをした人を罰することは、再発防止について何のメリットもないと考えたほうがよいと思います。
──ヒューマンエラーが起こったとしても事故につながらないようにするためには、まず意識を変える必要があるということですね。
松尾 精神論だけでは再発防止にはつながらないことを、より多くの人に理解いただくことが必要になるでしょう。
特に医療分野というのは、患者さんは「治してもらえるだろう」という期待が高く、患者さんが治療の結果も含めSafety-Ⅰのようにゼロリスクを追求してしまいがちです。
そうなると、医師をはじめとする医療従事者はその期待に応えることができないため、リスクの高い診療科を敬遠するようになってしまいます。それはリスクの高い診療科の人手不足につながり、ひいてはそれが原因となった事故を引き起こしかねません。社会的にも、Safety-Ⅱの考え方が周知される必要があると思っています。
(2024年9月18日/構成・本誌編集部 川村岳也)