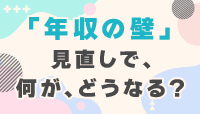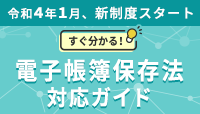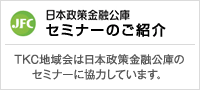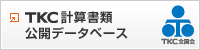中小企業向けの新しい会計ルール「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、「中小会計要領」)が公表された。中小企業の実態に即した「経営者の役に立つ」視点が貫かれているのが大きな特徴で、全国約260万社ともいわれる大多数の中小企業が適用対象になると考えられる。従来の指針とどこが異なり、中小企業の経営にどのような影響をもたらすのか。新会計ルールが生まれた背景やその内容、それを活用した経営力の強化などについてまとめた。
2012年2月に公表された「中小会計要領」は、中小企業が会計法上の計算書類などを作成する際に、中小企業の実務的な慣行を踏まえ、かつ経営者の役に立つような会計処理や注記の方法を示すもの。法令などによって強制されるものではなく、あくまでも中小企業の多様な実態に配慮しその成長に資するために活用することが想定されている文書だが、的確な財務状況の認識によってさらなる成長を望む中小企業経営者にとっては、ぜひ一読しておきたい文書である。本稿ではこの中小会計要領が生まれた背景やその主旨、各論の内容、これを活用した経営力の強化について概観する。
中小会計要領の詳細な内容に入る前に、このような新ルールがつくられた背景についておさらいしておこう。まず押さえなければならないのは、中小企業を取り巻く事業環境とそれに対する施策の方向性をどう政府が認識しているか、ということだ。その一つの答えを、中小企業政策審議会企業力強化部会が「グローバル競争下における今後の中小企業政策のあり方」と題し発表した中間取りまとめ文書にみることができる。それによると、人口減少などによる国内需要の減少、アジア新興国などとの競争激化、大企業の海外移転など事業環境が不透明さを増しているなか、政府は「厳しい内外環境を勝ち抜く自立的な中小企業」像の確立を目指していることが明記されている。そしてそれには中小企業が持つ潜在力・底力を最大限引き出し、戦略的経営力を強化する必要があり、その強化すべき「戦略的経営力」の重要なポイントの一つとして「財務経営力」(財務状況を認識し、それに基づいた的確な経営方針を構築する力)の強化を取り上げているのだ。
当然、財務経営力を強化するためには、中小企業の実態に即した会計ルールにのっとり適切な会計処理を行う必要がある。そこで各種中小企業団体が中心となって議論を重ね、経営者にとって役立つ新たな会計ルールを策定する試みが、「中小会計要領」となって具体化したというわけである。
中小会計指針とどう違うのか
ここで読者の中には「中小会計指針があるじゃないか」と疑問に思う方がいるかもしれない。中小会計指針とは、中小企業に関係する会計の指針として05年に発表された「中小企業の会計に関する指針」のことだが、従来からあるこの「中小会計指針」と、今回定められた「中小会計要領」はルール策定の視点が大きく異なっている。「中小会計指針」は情報提供機能を重視した大企業向けの企業会計基準(上場会社などを規制する金融商品取引法における「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」をいう)と軌を一にしている一方、中小会計要領は日本型会計モデルともいえる伝統的な企業会計原則をベースにしているからだ。両者の基準に上下はなく、企業の属性に応じて会計ルールを選択するべきだが、基本的な資産評価方法に時価主義を大幅に導入したり、国際会計基準(IFRS)の毎年の改正の影響を受ける「中小会計指針」が中小企業にとって手の届かない存在になってしまっているのが実態である。
一方、中小会計要領には「『一定の水準を保ったもの』とされている『中小会計指針』によることを求めることが必ずしも適当ではない中小企業を対象」とすることが明記されており、大多数の中小企業が対象になると考えられる。株式会社のみならず特例有限会社、合名会社、合資会社・合同会社も利用できる。
ただ、あくまでもどの会計ルールを選択するかというのは企業の裁量による。中小会計指針を完璧に適用している企業はこれまで通り中小会計指針の適用が求められるし、中小会計要領の適用企業であって中小会計指針や企業会計基準を適用してもいっこうにかまわない。しかし中小会計指針などを採用する場合には、今後も国際的な会計標準化の動向を受け毎年のように頻繁に改正されることが予想されるので、相応の事務負担を覚悟しておく必要がある。やはり圧倒的多数の中小企業は中小会計要領を適用することになるだろう。
中小企業の実務に配慮
さて、いよいよ本題に入ろう。中小会計要領の中身である。冒頭で触れたように、基本的な狙いは中小企業の実態に即しかつ経営者の役に立つ会計を追求する視点を貫くことで「中小企業の成長」を実現することにある。したがって基本方針として(1)中小企業の経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく自社の経営状況の把握に役立つ会計(2)中小企業の利害関係者(金融機関、取引先、株主など)への情報提供に資する会計(3)中小企業の実務における会計慣行を十分考慮し、会計と税制の調和を図った上で、会社計算規則に準拠した会計(4)計算書類などの作成負担は最小限にとどめ、中小企業に過重な負担を課さない会計――の4つが掲げられている。「中小企業の実態に即し」と明記されているだけあって、当然、国際会計基準の影響は受けない。つまり毎年のように頻繁に改訂されることがないのである。
そのうえで、収益/費用、資産/負債の基本的な会計処理について説明されていくのだが、その内容は、今まで多くの中小企業が行ってきた会計処理の方法を尊重し原則として踏襲し、実務に配慮したものになっている。具体的には、売上高など収益は原則として現金や預金、売掛金などを受け取った時に認識する「実現主義」、経費などの費用は費用の発生原因となる取引やサービスが発生したときに認識する「発生主義」、収益とそれに関連する費用の両者を対応させて期間損益を計算する「費用収益対応の原則」などで、ごく一般的な事項だ。また収益と費用を総額で計上することとする「総額主義」についても言及しているが、これはたとえば、貸借している建物を転貸する場合、受取家賃と支払家賃の双方を計上する必要があるというルールである。
金銭債権、有価証券、棚卸資産、固定資産などの資産は、資産を取得するために要した金額をベースとして貸借対照表に計上する「取得原価主義」を採用している。個別の内容について少し詳しくみていこう。
1 金銭債権
まずは受取手形や売掛金、貸付金の金銭債権。原則として取得価額で計上するが、注意したいのは受取手形の扱いだ。取引金融機関などで割り引いたり裏書きして取引先に譲渡したりした場合は貸借対照表には計上されなくなるが、注記することが求められている。経営者や金融機関が企業の資金繰り状況を判断するうえで、受取手形の割引額や裏書譲渡額の情報はかなり重要だからだ。
2 有価証券
有価証券の扱いにも気をつけよう。法人税法上の売買目的有価証券を保有する場合は、時価で計上しなければならない。これは短期間の価格変動で利益を得ることを目的に売買を繰り返すようなケースで、時価が著しく購入時よりも下落し、回復の見込みがないと判断される場合は評価損を計上する必要が出てくる。ただしここで重要なことは、回復の見込みを判断するのはあくまでも経営者自身だということ。中小会計要領ではその目安として、上場株式のような市場価格があるものについては「50%程度以上下落した場合」、非上場株式のように時価の把握が難しいものについては「大幅な債務超過などでほとんど価値がないと判断できるもの」などと基準を示している。
3 棚卸資産
同様に取得原価計上が原則の棚卸資産も著しく時価が下落したときには経営者の判断で評価損を計上する。時価下落の把握が難しい場合には、「著しく陳腐化したとき」「災害で著しく損傷したとき」「賞味期限切れや雨ざらしなどでほとんど価値がないと判断できるもの」などの基準が例に挙げられている。また事務処理が簡便で多くの中小企業が利用している「最終仕入原価法」を容認することが明記されていることも特筆すべきポイントだろう。
4 減価償却費
固定資産にかかる減価償却費の取り扱いにも注目したい。従来通り法人税法などに基づき計算することに変わりはないが、今回、「相当の減価償却」という用語の定義が「一般的に、耐用年数にわたって、毎期、規則的に減価償却を行うこと」となっている。わざわざ「一般的に」という言葉を入れたことがポイントだ。減価償却費の計算にあたっては普通、法人税法に定められた耐用年数などを使うが、合理的な理由がある場合には会社の実態に応じた償却費の計算や計上が可能なのである。たとえば、ある期において会社の業績が悪く、機械などの稼働率が通常の半分程度であった場合には、稼働率などの基準をもって償却費の計算をすることも「相当」の範囲内だと考えられる。減価償却費の計算についての経営判断の重要性がますます高まったのである。
5 引当金
引当金についてはどうだろうか。中小会計要領では引当金を計上する要件として(1)将来の特定の費用または損失であること(2)発生が当期以前の事象に起因すること(3)発生の可能性が高いこと(4)金額を合理的に見積もることができること――の4点に整理、とくに法人税法ではすでに廃止になった賞与引当金と退職給付引当金について詳説している。
まず賞与引当金については、翌期に従業員に対して支給する賞与の支給額を見積もり、当期の負担と考えられる金額を引当金として費用計上する。具体的には、決算日後に支払われる賞与の金額を見積もり、当期に属する分を月割りで計算し計上する方法が考えられるだろう。法人税法などで利用される具体的な算式も例示されているので便利だ。
従業員との間に退職金規程や退職金などの支払いに関する合意がある場合、企業は従業員に対して債務を負っているため、当期の負担と考えられる金額を退職給付引当金として計上することになる。退職金一時金制度を採用している場合には、「決算日時点で、従業員全員が自己都合によって退職した場合に必要となる退職金の総額を基礎として、たとえば、その一定割合を退職給付引当金として計上する方法が考えられます」と説明している。
また中小企業退職金共済、特定退職金共済、確定拠出金など将来の退職給付について拠出以降に追加的な負担が生じない制度を採用している場合は、毎期の掛け金を費用処理する。なお引当金はいずれも金額的に重要性が乏しいものは計上する必要がない。
中小会計要領では、リース取引や繰延資産、外貨建て取引など計14項目の各論をわかりやすい言葉で簡潔に説明している。巻末には貸借対照表や損益計算書、製造原価明細書、個別注記表の様式集も収められている。金融庁や中小企業庁のホームページから簡単にダウンロードできるので、ぜひ参考にしていただきたい。
資金調達力強化につなげる
ここまでこの新しい会計ルールが誕生した背景とその内容についてみてきたが、大切なのは、この中小会計要領に基づいた信頼性の高い決算書を作成してそれを経営に役立てるという視点だ。最後にどのような具体的なメリットが期待できるのか考えてみたい。
一つに「資金調達力の強化」がある。今まで中小企業は、金融機関から融資を受ける場合、どうしても不動産などの担保や第三者保証に頼った資金調達となりがちだった。しかし今後は物的担保や第三者保証に依存しない新しい融資制度の到来も予想される。その場合、決算書の信頼性がますます重要になってくることはいうまでもない。日頃から金融機関に自社の財務情報や経営状況を適時かつ正確に説明できるよう要求される場面が増えてくるのは間違いなく、そのためにも、期中における経営状況の早期把握や、説明能力向上のトレーニングの場ともなる金融機関との対話を促進することが必要になってくる。
さらに中小会計要領に基づく質の高い決算書を作成し、いつでも開示できるようにしておけば、「格付けアップ」も夢ではない。黒字決算を積み上げ、(1)貸借対照表で資産の流動化と資金調達の強化を進める(2)損益計算書で営業利益を増やす努力をする(3)キャッシュフロー計算書で余剰資金を多くする――などの事項に留意し、評価の高まる決算書になるよう意識することが大切だ。場合によっては金利低減などの優遇を得られる可能性もあるし、税務署をはじめとする公的機関からの信頼も厚くなるかもしれない。債権者や得意先などとの関係が有利に展開したり、出資者や従業員に対する説明責任が果たしやすくするなどの効果も期待できるだろう。
(本誌・植松啓介)
参考文献:『経営に役立つ Q&A中小企業の新しい会計ルール』(TKC全国会中央研修所監修)