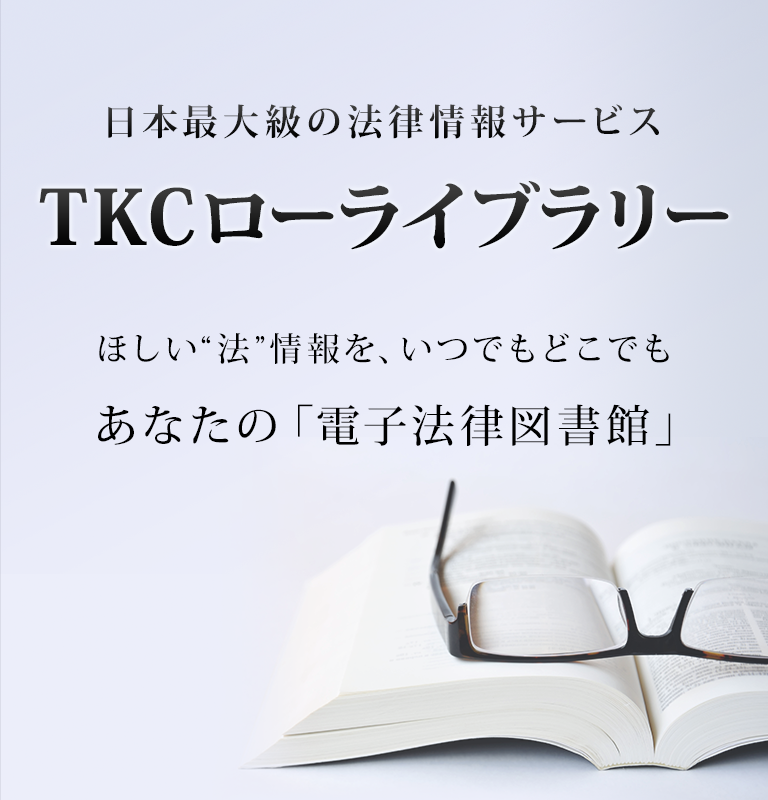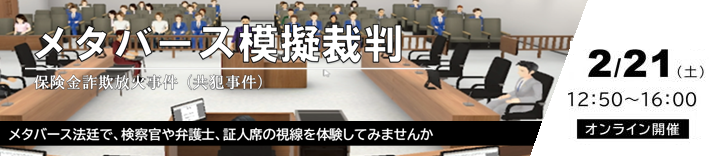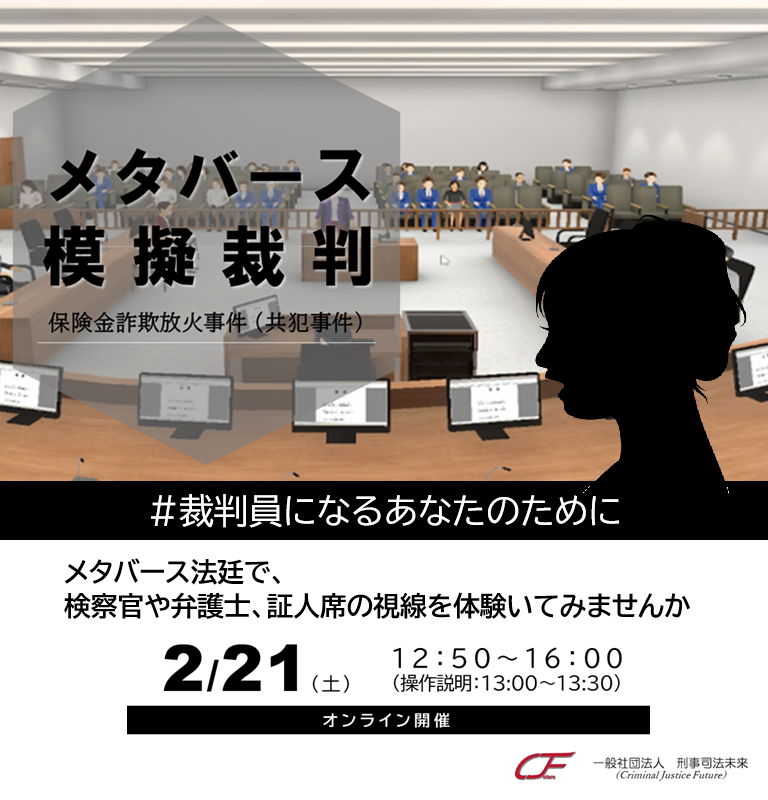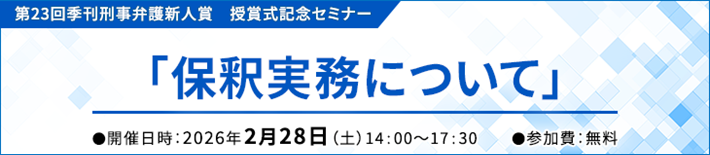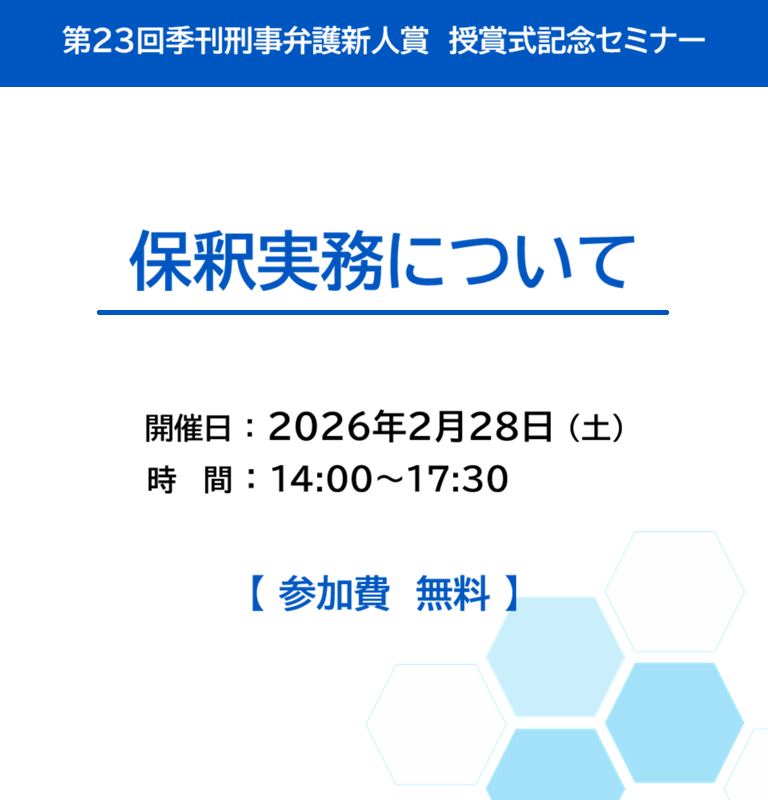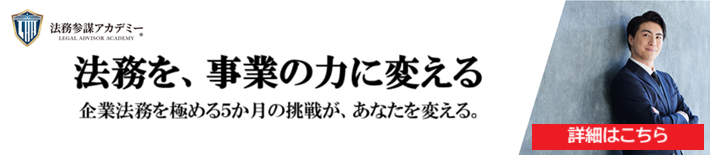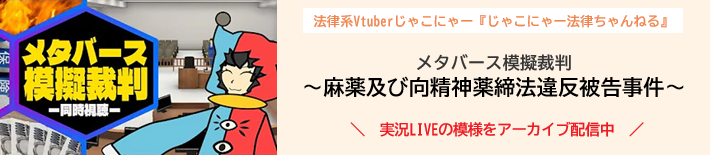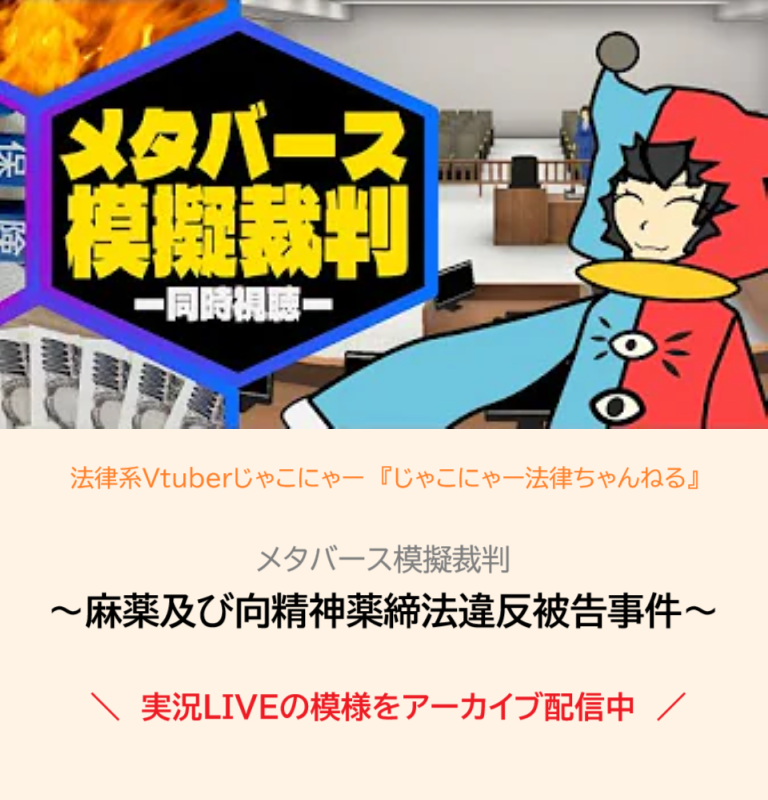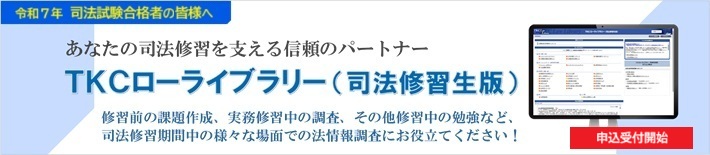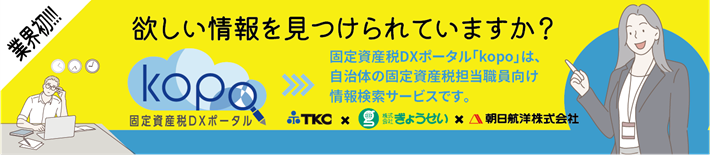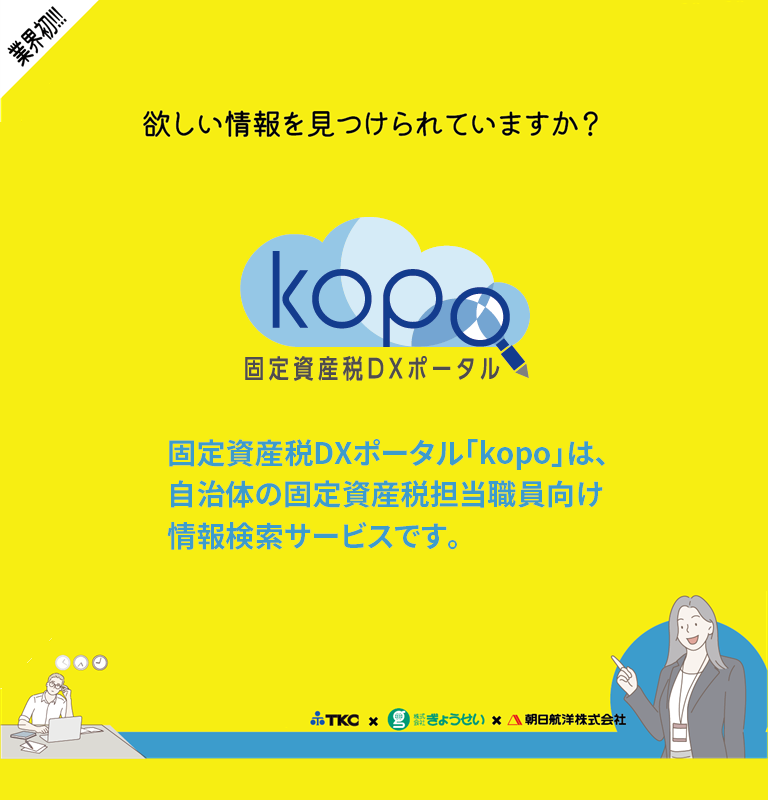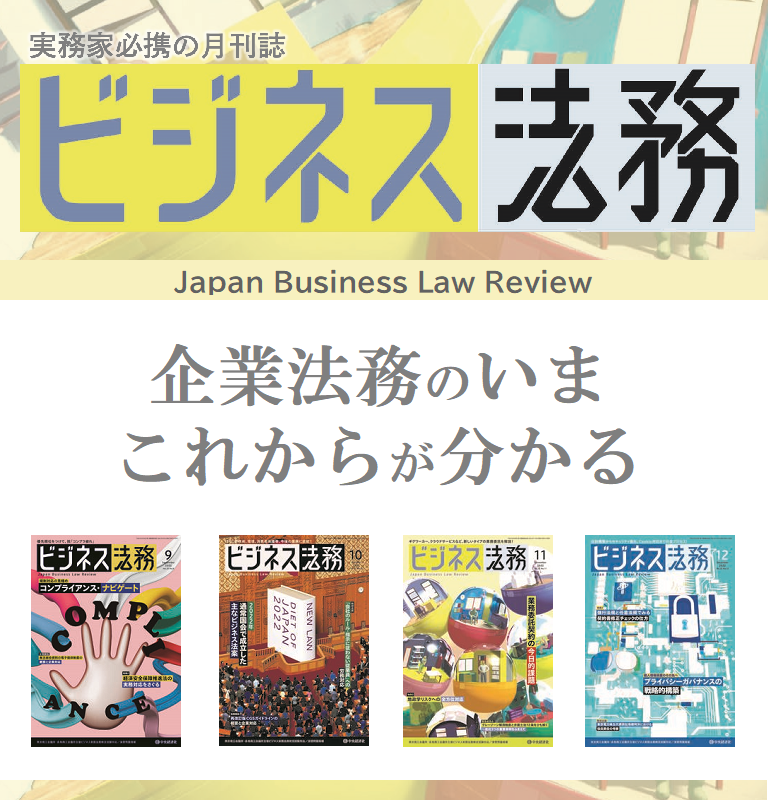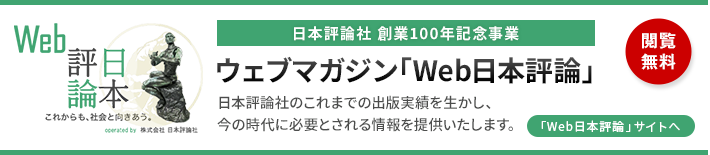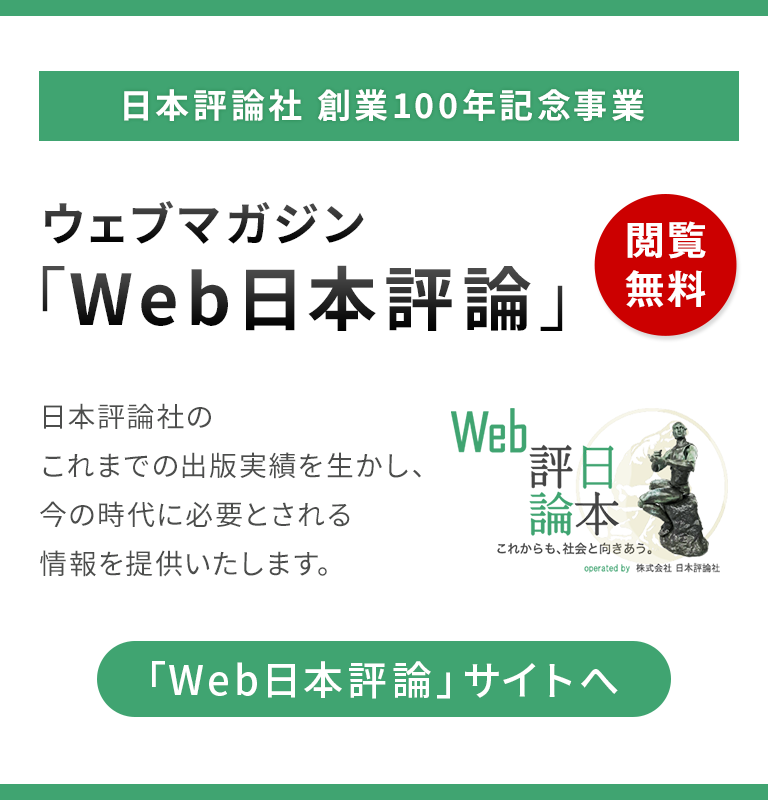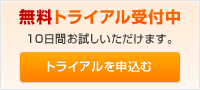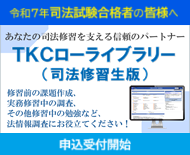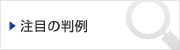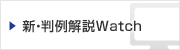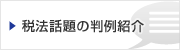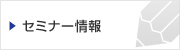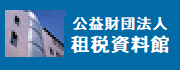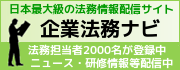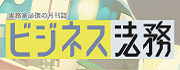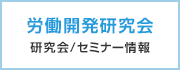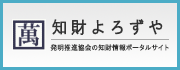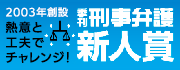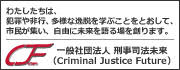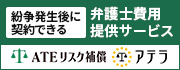2026.02.03
残存費用等請求事件

LEX/DB25574693/最高裁判所第三小法廷 令和 7年12月23日 判決(上告審)/令和6年(受)第204号
被上告人は、T社が販売する戸建て住宅にLPガスの消費設備に係る配管及びガス栓を設置したが、本件消費設備の部品代金や設置費用、給湯器やそのリモコンの設置費用等をT社に請求しなかったところ、上告人は、T社から本件住宅を購入したことから、被上告人が、LPガスの供給等に関する契約の条項は、本件設置費用に関し、上告人に本件算定額の支払義務があることを定めた合意である旨主張し、上告人に対し、本件算定額である17万3775円及び遅延損害金の支払を求め、第一審が請求を棄却したことから、被上告人が控訴し、控訴審が、本件条項は、10年間にわたって上告人から被上告人に対して支払われるガス料金の中から回収することが予定されていた本件設置費用について、その未回収分を上告人において支払う旨の合意であって、違約金等条項に当たらないと判断し、被上告人の請求を認容したところ、上告人が上告した事案で、本件条項は、本件消費設備等の設置の対価を定めたものではなく、本件供給契約が供給開始日から10年経過前に解約されるなどして被上告人がその後のガス料金を得られなくなった場合に本件算定額の支払義務を負わせることで、短期間の解約が生ずることを防止し、本件供給契約を長期間維持することを図るとともに、併せて先行投資された本件設置費用に関して被上告人が被る可能性のある損失を補てんすることも目的の一つとするものというべきであり、実質的にみると、解除に伴う損害賠償の額の予定又は違約金の定めとして機能するものということができるから、本件条項は、違約金等条項に当たるというべきであり、以上と異なる見解の下に、本件条項が違約金等条項に当たらないとした原審の上記判断には法令の解釈適用を誤った違法があるとしたうえで、本件条項は、その全部について消費者契約法9条1号により無効となるというべきであるとして、原判決を破棄し、被上告人の控訴を棄却した事例。
2026.02.03
個人事業税賦課決定処分取消請求控訴事件
 ★
★「新・判例解説Watch」租税法分野 令和8年3月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
★LEX/DB25624701/東京高等裁判所 令和 7年10月 2日 判決(控訴審)/令和7年(行コ)第105号
控訴人(原告)らが、東京都知事の権限の委任を受けた渋谷都税事務所長ら(本件各処分行政庁)から、控訴人らが行った本件各業務が個人事業税の課税客体である地方税法(令和5年法律第1号による改正前)72条の2第8項23号の「代理業」に当たるとして、本件各処分を受けたため、本件各処分が違法であるとして、被控訴人(被告)・東京都に対し、その取消しを求めたところ、原審が、本件各業務は上記の「代理業」に当たるから本件各処分は適法であるとして、控訴人らの請求をいずれも棄却したため、控訴人らが控訴した事案で、個人の事業が「代理業」に当たるか否かは当該個人が使用人であるか否かとは関係なく判断されるべきものであり、商人の使用人が使用人として行う業務が「代理業」に当たる場合があるとしても、文理解釈として不合理とはいえないとし、当裁判所も、原審と同様、本件各業務は地方税法72条の2第8項23号の「代理業」に該当するから本件各処分は適法であり、控訴人らの請求はいずれも理由がないものと判断するとして、本件控訴をいずれも棄却した事例。
2026.01.27
旅券不発給処分無効確認等請求事件
LEX/DB25574628/大阪地方裁判所 令和 7年 9月30日 判決(第一審)/令和4年(行ウ)第182号
日本国民である父の子として出生し、日本の国籍を取得し、その後カナダ市民権法5条1項に基づき、自らの申請によりカナダ市民権を取得した原告が、〔1〕主位的に、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失うとの国籍法11条1項の規定は憲法に違反して無効であると主張して、(1)原告が日本の国籍を有することの確認、(2)外務大臣が原告に対してした一般旅券の発給をしない旨の処分が無効であることの確認、(3)外務大臣が一般旅券を発給することの義務付け、並びに(4)同項の改廃をしなかった立法不作為、同項を周知しなかったこと及び原告に対する本件処分は国家賠償法上違法である旨主張して、同法1条1項に基づき、原告の被った損害のうち一部の金員及び遅延損害金の支払を求め、〔2〕予備的に、法務大臣が原告の国籍喪失届を不受理として原告に在留資格を付与しなかったことは国賠法上違法である旨主張して、同法1条1項に基づき、原告の被った損害のうち一部の金員及び遅延損害金の支払を求めた事案で、国籍法11条1項の規定は、立法目的に合理性があり、立法目的と手段との間の合理的関連性も認められるから、立法府の裁量権の範囲を逸脱するものではなく、憲法10条、98条2項、31条及び11条に違反するともいえず、また、国籍法11条1項の規定は、憲法11条、13条、22条2項の規定により保障される権利を侵害するものでもなく、これらの各規定に違反するともいえず、さらに、国籍法は、重国籍の防止又は解消方法につき、同法11条1項の適用対象となる自己の志望によって外国の国籍を取得した場合とそれ以外の場合とで一定の区別を設けているものの、そのような区別を設けることの立法目的には合理的な根拠があり、かつ、その区別の具体的内容は上記の立法目的との関連において不合理なものではなく、立法府の裁量判断の範囲を超えるものでもないから、上記の区別は、憲法14条1項に違反するともいえないなどとして、本件訴えのうち、一般旅券の発給の義務付けを求める部分を却下し、その余の請求をいずれも棄却した事例。