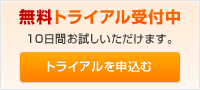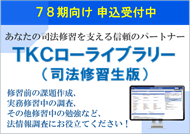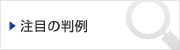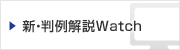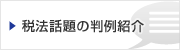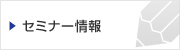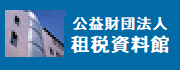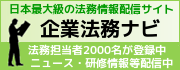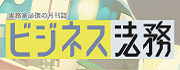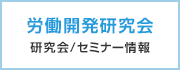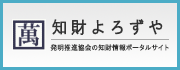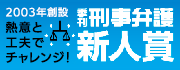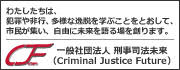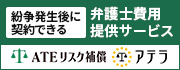2014.04.08
認知無効確認請求事件
LEX/DB25446328/最高裁判所第二小法廷 平成26年3月28日 判決 (上告審)/平成25年(受)第442号
血縁上の父子関係がないことを知りながら上告人の母であるAと婚姻し、上告人を認知した被上告人が、上告人に対し、認知の無効確認を求めたところ、原審は、血縁上の父子関係がない場合において、認知者による認知の無効の主張を認めても、民法785条の趣旨に反するものとはいえず、また、認知者も民法786条の利害関係人に当たるとして、被上告人による本件認知の無効の主張を認め、被上告人の請求を認容すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならないとし、被上告人は本件認知の無効を主張することができるとして、被上告人の請求を認容すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができるとし、本件上告を棄却した事例。
2014.04.08
損害賠償、民訴260条2項に基づく仮執行の原状回復及び損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503098/大阪高等裁判所 平成26年2月27日 判決 (差戻控訴審)/平成25年(ネ)第2334号
亡Aの相続人である第一審原告(控訴人・被控訴人)らにおいて、Aが鉄道高架下に設置された貸建物内で稼働中、建物内部に吹き付けられたアスベストの粉じんに曝露したため、悪性胸膜中皮腫に罹患し、自殺を余儀なくされたと主張して、第一審被告(被控訴人・控訴人)に対して、債務不履行、不法行為又は土地の工作物の設置、保存上の瑕疵に係る責任に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた事案の差戻控訴審において、第一審被告の責任期間内のAの石綿粉じん曝露とAの悪性胸膜中皮腫発症との間の相当因果関係、Aの悪性胸膜中皮腫と自殺による死亡との間の相当因果関係はいずれも認められるから、本件建物の設置又は保存上の瑕疵とAの死亡との間には、相当因果関係が認められるとして、第一審原告らの控訴に基づき、原判決中、第一審被告に関する部分を変更し、第一審被告の控訴をいずれも棄却した事例。
2014.04.01
遺留分減殺請求事件
LEX/DB25446288/最高裁判所第二小法廷 平成26年3月14日 判決 (上告審)/平成25年(受)第1420号
亡Bの妻である上告人が、Bがその遺産の全てを長男である被上告人に相続させる旨の遺言をしたことにより遺留分が侵害されたと主張して、被上告人に対し、遺留分減殺を原因として、不動産の所有権及び共有持分の各一部移転登記手続等を求めたところ、原審は、上告人が相続の開始等を知った時を平成20年10月22日とする上告人の遺留分減殺請求権の消滅時効について、時効の期間の満了前に後見開始の審判を受けていない者に民法158条1項は類推適用されないとして時効の停止の主張を排斥し、同請求権の時効消滅を認め、上告人の請求を棄却すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、上告人についての後見開始の審判の申立ては、1年の遺留分減殺請求権の時効の期間の満了前にされているのであるから、上告人が上記時効の期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあったことが認められるのであれば、民法158条1項を類推適用して、A弁護士が成年後見人に就職した平成22年4月24日から6箇月を経過するまでの間は、上告人に対して、遺留分減殺請求権の消滅時効は、完成しないことになり、上告人の遺留分減殺請求権の時効消滅を認めた原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決は破棄し、原審に差し戻した事例。
2014.04.01
面会禁止等仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
LEX/DB25446282/名古屋高等裁判所 平成26年2月7日 決定 (抗告審(即時抗告))/平成25年(ラ)第392号
債権者(抗告人)の任意後見人が、債権者を代理して弁護士を委任して、債権者の人格権に基づく妨害排除請求権を被保全債権権利として、債務者(相手方)に対し、債権者との面会等を禁止する仮処分命令の申立てをしたところ、申立てが却下されたため、債権者が即時抗告した事案において、債権者の任意後見人に授与されている代理権限には、債権者の人格権に基づく妨害排除請求権は含まれていないため、本件仮処分命令申立ては、代理権限のない者が提起した仮処分命令申立てとして不適法であるとし、抗告を棄却した事例。
2014.02.24
遺産確認,建物明渡等請求事件
LEX/DB25446212/最高裁判所第二小法廷 平成26年2月14日 判決 (上告審)/平成23年(受)第603号
亡Aの共同相続人(代襲相続人又は共同相続人の権利義務を相続した者を含む。)である被上告人(原告)らが、同じくAの共同相続人である上告人(被告)らとの間で、本件不動産がAの遺産であることの確認を求めた事件(第1事件)と、上告人Y1が、建物の一部を占有している被上告人X1に対し、所有権に基づき、上記占有部分の明渡し等を求めた事件(第2事件)が併合審理された訴訟で、第一審は、第1事件につき、原告らの訴えの取下げによりEらが当事者ではなくなったことを前提に、原告らの請求を棄却する旨の判決をし、第2事件につき、上告人Y1の請求を棄却する旨の判決をしたが、原審は、固有必要的共同訴訟である遺産確認の訴えの係属中にした共同被告に対する訴えの取下げは効力を生じないと解されるところ、自己の相続分の全部を譲渡したEらも共同相続人として遺産確認の訴えの当事者適格を失うものではないから、第1事件につき、Eらに対する訴えの取下げが効力を生じないことを看過してされた第一審の訴訟手続には違法があり、第2事件は、第1事件と整合的・統一的に解決すべきであるとして、第一審判決を取り消し、被告らに関する部分につき本件を第一審に差し戻しを命じたため、上告人らが、本件上告をした事案において、Eらは、いずれも自己の相続分の全部を譲渡しており、第1事件の訴えの当事者適格を有しないことになるから、原告らのEらに対する訴えの取下げは有効にされたことになり、第1事件につき第一審の訴訟手続には違法があるとし、また、第2事件につき本案の審理をせず第1事件と整合的・統一的に解決すべきであるとして、第一審判決を取消した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中上告人らに関する部分は破棄を免れないとし、本案の審理をさせるため、原審に差し戻すのが相当であるとした事例。
2014.02.10
LEX/DB25502568/最高裁判所第二小法廷 平成25年11月20日 決定 (上告審)/平成22年(オ)第1943号
(1)Aの法定相続人一審原告B及び一審原告Cが、Aの法定相続人一審被告らに対し、土地の持分72分の3がAの遺産であることの確認を求めると共に、(2)一審原告らが一審被告らに対し、前記土地の共有物分割として、Aの遺産である持分を一審原告Dに取得させて、その価格をその余の一審原告ら及び一審被告らに賠償させる全面的価格賠償を求めたところ、(1)の訴えは確認の利益がないとして却下し、(2)の請求は形式的競売による分割が相当であるとしたため、双方がいずれも控訴し、(3)一審被告らが一審原告らに対し、前記土地の持分72分の21がAの遺産であることの確認を求め附帯控訴(反訴)した事案で、(2)については原判決を一審原告の請求のとおり変更し、一審被告らの控訴を棄却し、(3)については請求を却下・棄却したため、一審被告らが上告した事案において、一審被告らの本件上告を棄却した事例。
2014.01.21
認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件
LEX/DB25446147/最高裁判所第三小法廷 平成26年1月14日 判決 (上告審)/平成23年(受)第1561号
一審被告(上告人)Y2の夫である一審原告(被上告人)が、一審被告Y2の子で一審原告が認知した一審被告Y1に対し、認知の無効を求めるとともに、妻である一審被告Y2に対し、離婚とこれによる慰謝料の支払を求めた事件で、原々審では、民法785条の規定から認知者による認知無効が許されないとはいえず、一審原告による認知無効請求が権利の濫用に該当するとはいえないなどとして、一審原告の認知無効請求及び離婚請求を認容したため、一審被告が控訴し、原審でも、民法785条及び民法786条は、血縁上の父子関係がない場合であっても認知者による認知の無効の主張を許さないという趣旨まで含むものではないなどとして、一審原告による本件認知の無効の主張を認め、一審原告の請求を認容すべきものとしたため、一審被告が上告した事案で、認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができるというべきで、この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはないとし、一審原告は本件認知の無効を主張することができるとして、一審原告の請求を認容すべきものとした原審の判断は、是認することができるとした事例(補足意見、意見及び反対意見あり)。
2014.01.14
LEX/DB25501705/最高裁判所大法廷 平成25年9月18日 決定 (特別抗告審)/平成25年(ク)第132号等
平成3年3月に死亡した男性Aの被相続人とする遺産の分割に係る事件及びAの子で平成15年3月に死亡したBを被相続人とする遺産の分割に係る事件において、抗告人はBの嫡出子でない子であり、相手方はBの嫡出子であるところ、原審が、民法900条4号ただし書きの規定のうち嫡出子でない子の相続分の2分の1とする部分(本件規定)を適用し、A及びBの遺産を分割すべきものとしたため、抗告人が特別抗告した事案において、本件規定は、平成15年3月当時、憲法14条1項に違反して無効であり、本件においてこれを適用することはできない(最高裁平成24年(ク)第984号、第985号平成25年9月4日大法廷決定・裁判所時報1587号参照)とし、原決定を破棄し、本件を原審に差し戻すこととした事例。
2014.01.14
面会交流審判に対する抗告申立事件
LEX/DB25502284/東京高等裁判所 平成25年7月3日 決定 (抗告審)/平成25年(ラ)第1205号
相手方(父)が、新潟家庭裁判所に対し、未成年者(子)との面会交流を求める調停事件を申し立てたが、本件調停は不調となり、審判に移行したところ、同裁判所は、抗告人に対し、未成年者と相手方との面会交流をさせる義務があることを定め、同義務を履行することを命じる原審判をしたため、抗告人(母)が、原審判を取り消し、相手方の面会交流の申立てを却下することを求めて抗告した事案において、原審判が定めた面会要領のうち、頻度等(実施日)や受渡場所、未成年者の受渡しの方法は、その根拠となる情報等が一件記録からは窺えず、その相当性について判断することができないばかりか、これらについて当事者間で主張を交わす等して検討がされた形跡も認められない等として、原審判を審理不尽といわざるを得ないなどとして、原審判を取り消し、本件を新潟家庭裁判所に差し戻すとした事例。
2013.12.24
戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25446084/最高裁判所第三小法廷 平成22年12月10日 決定 (許可抗告審)/平成25年(許)第5号
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた抗告人X1及びその後抗告人X1と婚姻をした女性である抗告人X2が、抗告人X2が婚姻中に懐胎して出産した男児であるAの、父の欄を空欄とする等の戸籍の記載につき,戸籍法113条の規定に基づく戸籍の訂正の許可を求めた事案の上告審で、Aについて民法772条の規定に従い嫡出子としての戸籍の届出をすることは認められるべきあり、Aが同条による嫡出の推定を受けないことを理由とする本件戸籍記載は法律上許されないものであって戸籍の訂正を許可すべきであるとし、原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原決定を破棄し、本件戸籍記載の訂正の許可申立ては理由があるから、これを却下した原々審判を取消し、同申立てを認容することとした事例(補足意見及び反対意見あり)。
2013.12.16
共有物分割等請求事件
LEX/DB25446054/最高裁判所第二小法廷 平成22年11月29日 判決 (上告審)/平成22年(受)第2355号
被上告人らが、上告人らに対し、被上告人らと上告人らとの共有に属する土地の共有物分割を求めた事案の上告審において、共有物について、遺産共有持分と他の共有持分とが併存する場合、共有者(遺産共有持分権者を含む。)が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として裁判上採るべき手続は民法258条に基づく共有物分割訴訟であり、共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に分与された財産は遺産分割の対象となり、この財産の共有関係の解消については民法907条に基づく遺産分割によるとした上で、裁判所は、遺産共有持分を他の共有持分を有する者に取得させ、その者に遺産共有持分の価格を賠償させてその賠償金を遺産分割の対象とする価格賠償の方法による分割の判決をする場合には、遺産共有持分権者に支払われる賠償金は、遺産分割によりその帰属が確定されるべきものであるから、賠償金の支払を受けた遺産共有持分権者は、これをその時点で確定的に取得するものではなく、遺産分割がされるまでの間これを保管する義務を負うところ、その判決において、各遺産共有持分権者において遺産分割がされるまで保管すべき賠償金の範囲を定めた上で、遺産共有持分を取得する者に対し、各遺産共有持分権者にその保管すべき範囲に応じた額の賠償金を支払うことを命ずることができるとして、原判決中共有物分割請求に関する部分についての上告を棄却した事例。
2013.12.10
養子縁組無効確認請求事件
LEX/DB25502154/東京家庭裁判所 平成25年10月15日 判決 (第一審)/平成25年(家ホ)第599号
原告が、原告と被告との間の養子縁組は、原告に無断で何者かによってなされたものであるとして、養子縁組の無効確認を求めた事案において、請求を認容した事例。
2013.11.19
親子関係存在確認請求事件
LEX/DB25501809 / 大阪家庭裁判所 平成25年9月13日 判決 (第一審) / 平成25年(家ホ)第171号
原告(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項に基づき女性から男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者)が、その妻が原告との婚姻中に原告との合意のもと第三者から精子提供を受ける人工授精により懐胎した被告との間に、原告を父、被告を子とする父子関係が存在することの確認を求めた事案において、母が夫である原告との同意のもと非配偶者間人工授精により被告を懐胎し、原告が父として被告を養育しているとの事情の存在をもってしても、原告と被告との間に父子関係を認めることはできないとして、原告の請求を棄却した事例。
2013.11.12
遺言有効確認請求控訴事件
LEX/DB25501717 / 東京高等裁判所 平成25年3月6日 判決 (控訴審) / 平成24年(ネ)第6567号
被控訴人が、控訴人らに対し、亡Aによる本件遺言が有効であることの確認を求めたのに対し、控訴人らが、本件遺言当時、亡Aが重度のうつ病、認知症であり、本件遺言時以前に高熱を出して不穏行動を繰り返し、重篤な肺炎に罹患し危機的状況にあったから、Aには遺言能力はなく、妻Bの生存中に妹である被控訴人に全財産を相続させるとの遺言をするはずがないなどと主張して、その有効性を争った事案の控訴審において、Aは、本件遺言時に遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力たる意思能力を備えておらず、遺言能力があったとはいえないから、本件遺言は有効とは認められないとして、原判決を取り消し、被控訴人の請求を棄却した事例。
2013.10.22
住民票記載義務付け等請求事件
LEX/DB25445893 / 最高裁判所第一小法廷 平成25年 9月26日 判決 (上告審) / 平成24年(行ツ)第399号
原告(控訴人、上告人)父が、原告母との間の子である原告子に係る出生の届出をしたが、戸籍法49条2項1号所定の届書の記載事項を記載しなかったため受理されなかったところ、原告らが、同号の規定のうち届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分(本件規定)は憲法14条1項に違反するなどと主張して、被告ら(控訴人、被上告人)に対し慰謝料を求めたところ、原判決が、訴えを却下した第一審判決を維持し、控訴を棄却したため、原告らが上告した事案において、本件規定は、法律婚主義の制度の下における身分関係及び戸籍処理上の差異を踏まえ、戸籍事務を管掌する市長村長の事務処理の便宜に資するものとして、出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきことを定めているにとどまり、本件規定それ自体によって、嫡出でない子について嫡出子との間で子又はその父母の法的地位に差異がもたらされるものとはいえず、憲法14条1項に違反するものではないとし、上告を棄却した事例(補足意見あり)。
2013.10.15
遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25501698 / 最高裁判所大法廷 平成25年 9月 4日 判決 (特別抗告審) / 平成24年(ク)第1261号
A(平成2年死亡)の遺産につき、C及び相手方X1らが、相手方Y3及び抗告人らに対して遺産の分割の審判を申し立てた事件と、B(平成13年11月死亡)の遺産につき、抗告人Y1が、C、相手方X1ら及び抗告人Y2に対して遺産の分割の審判を申し立てた事件とが併合された事件であるが、原審係属中にCが死亡したため、その地位を相手方X1らが承継したが、原審は、民法900条4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の2分の1とする部分(本件規定)は、憲法14条1項に違反しないと判断し、本件規定を適用して算出した相手方X1ら及び抗告人らの各法定相続分を前提に、A及びBの各遺産を分割すべきものとしたため、抗告人らが特別抗告した事案において、遅くともBの相続が開始した平成13年11月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきであるとし、本件規定は、遅くとも平成13年11月当時において、憲法14条1項に違反していたとし、原決定に差し戻した。なお、本決定の違憲判断は、Bの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当であるとした事例(補足意見あり)。
2013.09.10
遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25445838 / 最高裁判所大法廷 平成25年 9月 4日 決定 (特別抗告審) / 平成24年(ク)第984号等
平成13年7月に死亡したAの遺産につき、Aの嫡出子(その代襲相続人を含む。)である相手方らが、Aの嫡出でない子である抗告人らに対し、遺産の分割の審判を申し立てた事件で、原審は、民法900条4号ただし書の規定のうち、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分(本件規定)は、憲法14条1項に違反しないと判断し、本件規定を適用して算出された相手方ら及び抗告人らの法定相続分を前提に、Aの遺産の分割をすべきものとしたため、抗告人らが特別抗告した事案で、Aの相続が開始した平成13年7月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたとして、本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反し無効であるとし、本決定の違憲判断は、Aの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当であるとした事例(補足意見あり)。