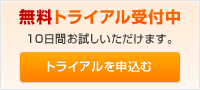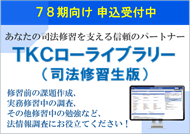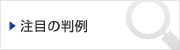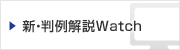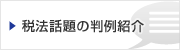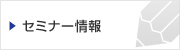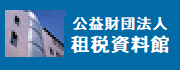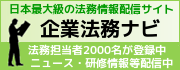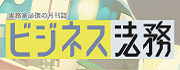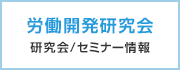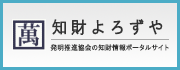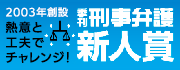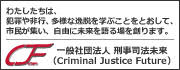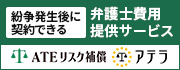2018.11.06
公金違法支出損害賠償等請求事件
LEX/DB25449756/最高裁判所第三小法廷 平成30年10月23日 判決 (上告審)/平成29年(行ヒ)第185号
鳴門市が経営する競艇事業に関し、市が平成25年度において漁業協同組合である上告補助参加人らに対して公有水面使用協力費を支出したことが違法、無効であるとして、市の住民である被上告人(原告・被控訴人)らが、地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づき、上告人(被告・控訴人)を相手に、当時の市公営企業管理者企業局長の職にあった者に対する損害賠償請求及び参加人らに対する不当利得返還請求をすること等を求める住民訴訟の事案の上告審で、市が本件各請求権を放棄することが普通地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする地方自治法の趣旨等に照らして不合理であるとは認め難いというべきであり、本件議決が市議会の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるということはできないとし、本件議決を受けて、上告人がA及び参加人らに対し、本件各請求権を放棄する旨をそれぞれ通知したことにより、その放棄は有効にされ、同請求権は消滅したものと判断し、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、第1審判決中上告人敗訴部分を取消し、同部分に関する被上告人らの請求をいずれも棄却した事例。
2018.06.05
婚姻費用分担審判に対する抗告事件
LEX/DB25560120/東京高等裁判所 平成30年 4月19日 決定 (抗告審)/平成30年(ラ)第125号
妻である相手方(原審申立人)が、夫である抗告人(原審相手方)に対し、婚姻費用分担金の支払を求める調停を申し立てたが、不調により審判手続に移行し、原審は、抗告人に対し、平成28年8月分から平成29年10月分までの未払婚姻費用分担金合計90万円及び同年11月から当事者の同居又は婚姻解消に至るまで毎月6万円の各支払を命じる旨の審判をしたため、抗告人は、これを不服として、本件抗告を申し立てた事案において、原審判を一部変更し、抗告人は、本件調停が申し立てられた平成28年8月から、毎月4万7000円を支払うべきところ、これを全く支払っていないから、平成28年8月から平成30年3月まで、20か月分合計94万円を直ちに支払うべきであり、平成30年4月1日以降は、当事者の同居又は婚姻解消に至るまで、毎月末日限り、月額4万7000円を支払うべきであるとした事例。
2018.05.15
子の引渡し仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
(平成29年12月 5日最高裁判所第三小法廷(平成29年(許)第17号)(LEX/DB 25449093)の原審)
LEX/DB25549514/福岡高等裁判所那覇支部 平成29年 6月 6日 決定 (抗告審(即時抗告))/平成29年(ラ)第21号
抗告人が、長男の親権に基づく妨害排除請求として、相手方に対し、長男の仮の引渡しを求めた事案の即時抗告審において、長男の親権者を抗告人と定めた上で協議離婚がされたが、実際には親権者で父である抗告人と別居後長男を監護してきた母である相手方との間で、長男の監護に関し、いずれが長男の監護をするにふさわしいかをめぐる紛争が存在しているのであるから、長男を抗告人に引き渡すべきか否かの判断を行うに当たっては、父又は母のいずれの監護に服することが子の福祉に沿うかという観点からの検討を加えることが必要不可欠であり、その判断は、本件では親権者変更の調停の審理の経過及び経過を踏まえてされることが望ましいものであるから、本件の本案については、子の監護に関する処分として、家事審判事項に該当するというべきであり、地方裁判所に対してされた家事審判事項を本案とする本件申立ては不適法であるとして、本件抗告を棄却した事例。
2018.05.15
子の引渡し仮処分申立事件
(平成29年12月 5日最高裁判所第三小法廷(平成29年(許)第17号)(LEX/DB 25449093)の原原審)
LEX/DB25549513/那覇地方裁判所 平成29年 4月26日 決定 (第一審)/平成29年(ヨ)第31号
債権者が、長男の親権に基づく妨害排除請求として、債務者に対し、長男の仮の引渡しを求めた事案において、本件の本案は、家事審判事項であり、地方裁判所に管轄がない不適法なものであり、そして、家事審判事項については、審判又は調停が係属する家庭裁判所が審判前の保全処分をすることができるとした家事審判法105条、157条1項3号の趣旨に照らすと、本件申立ても、やはり地方裁判所に管轄がない不適法なものというべきであるとして、本件申立ては、審尋を経るまでもなく、却下するほかないと示し、なお書きにおいて、本件申立ての趣旨及び理由に照らし、本件を家事事件手続法に基づく審判前の保全処分の申立てと見る余地はないから、本件を家事事件手続法9条1項により家庭裁判所に移送することもできないと示した事例。
2018.03.06
性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する即時抗告事件
LEX/DB25549283/広島高等裁判所岡山支部 平成30年 2月 9日 決定 (抗告審(即時抗告))/平成29年(ラ)第17号
抗告人(申立人)が、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき、性別の取扱いを女から男にすることを求めたところ、原審が抗告人の申立てを却下したため、抗告人がこれを不服として抗告した事案において、性別の取扱いの変更を認める要件の一つとして、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号が定めることが、立法府が有する裁量権の範囲を逸脱するとは認めることはできないとして、憲法13条に反しないとし、申立てを却下した原審判を相当であるとして、抗告を棄却した事例。
2018.02.20
損害賠償請求事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 H30.2月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
★「新・判例解説Watch」家族法分野 H30.3月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25548884/神戸地方裁判所 平成29年11月29日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第1653号
原告D(原告Aの母)は、夫(婚姻関係にある配偶者)から継続的に暴力を振るわれ、離婚の手続を取ることができないまま別居し、夫との婚姻継続中、原告Aの生物学上の父と交際し、原告Aを懐胎し出産し、原告Dは、夫に原告Aの存在を知られることを恐れ、その出生届を提出することができず、原告Aの実父が提出した原告Aの出生届は、夫の嫡出推定が及ぶことを理由に不受理とされ、原告D及び原告Aは、妻や子に夫に対する嫡出否認の訴えの提起が法律上認められていないことから、結果として、原告Aは無戸籍となり、原告B(原告Aの子)及び原告C(原告Aの子)は、原告B及び原告Cは、母である原告Aに戸籍がないため、その戸籍に入ることができず、原告Aと同様に無戸籍となったことにつき、民法774条~民法776条(本件各規定)は、父(夫)にのみ嫡出否認の訴えの提訴権を認めることによって、合理的な理由なく、父と子及び夫と妻との間で差別的な取扱いをしており、社会的身分による差別(憲法14条1項)に該当し、同項及び憲法24条2項に違反していることが明らかであり、国会(国会議員)は本件各規定の改正を怠っており、その立法不作為は、国家賠償法上違法であると主張した原告らが、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、精神的損害に対する慰謝料及び弁護士費用として、金員の支払を求めた事案において、本件各規定についての憲法適合性に関する原告らの主張はいずれも理由がないとし、原告らの請求を棄却した事例。
2017.12.19
子の引渡し仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
★「新・判例解説Watch」H30.2月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25449093/最高裁判所第三小法廷 平成29年12月 5日 決定 (許可抗告審)/平成29年(許)第17号
離婚した父母のうちその長男の親権者と定められた父である抗告人が、法律上監護権を有しない母を債務者とし、親権に基づく妨害排除請求権を被保全権利として、長男の引渡しを求めた仮処分命令の申立てをしたところ、原審が、本件申立ての本案は家事事件手続法別表第2の3の項所定の子の監護に関する処分の審判事件であり、民事訴訟の手続によることができないから、本件申立ては不適法であるとして却下したため、抗告人が許可抗告した事案において、抗告人が母に対して親権に基づく妨害排除請求として長男の引渡しを求めることは、権利の濫用に当たるというべきであるとし、本件申立ては却下すべきものであり、これと同旨の原審の判断は、結論において是認することができるとして、抗告を棄却した事例(補足意見がある)。
2017.12.12
相続財産の分離に関する処分及び相続財産管理人選任審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25449076/最高裁判所第三小法廷 平成29年11月28日 決定 (許可抗告審)/平成29年(許)第14号
相続人がその固有財産について債務超過の状態にあり又はそのような状態に陥るおそれがあることなどから、相続財産と相続人の固有財産とが混合することによって相続債権者等がその債権の全部又は一部の弁済を受けることが困難となるおそれがあると認められる場合、民法941条1項の規定に基づき、家庭裁判所は、財産分離を命ずることができるものと解するのが相当であるとして、原審の判断を是認し、本件抗告を棄却した事例。
2017.09.12
慰謝料請求事件
LEX/DB25546464/名古屋地方裁判所 平成29年 3月31日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第4413号
原告が、被告に対し、被告が原告の夫cと不貞行為を繰り返してきたとして、不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料等の支払を求めた事案において、少なくとも原告とcとの婚姻関係が破綻していると被告が認識したことについての過失があるとし、また、被告は、約5年間、cと継続的に不貞関係を持っていたことが認められ、原告がこれによって精神的苦痛を被ったとして、原告の請求を一部認容した事例。
2017.04.25
子の監護者の指定及び子の引渡し審判に対する抗告事件
(平成28年11月9日横浜家庭裁判所横須賀支部(平成28年(家)第181号)の抗告審)
LEX/DB25545290/東京高等裁判所 平成29年 2月21日 決定 (抗告審)/平成28年(ラ)第2102号
相手方(原審申立人。子の母。妻)が、別居中の夫であり未成年者を事実上監護している抗告人(原審相手方。子の父)に対し、未成年者の監護者を相手方と指定し、未成年者を相手方に引き渡すよう求め、原審が相手方の申立てを全部認めたため、抗告人が抗告した事案において、原審判は相当であるとして、抗告を棄却した事例。
2017.04.25
子の監護者の指定申立事件、子の引渡し申立事件
(平成29年2月21日東京高等裁判所(平成28年(ラ)第2102号)の原審判)
LEX/DB25545289/横浜家庭裁判所横須賀支部 平成28年11月 9日 審判 (第一審)/平成28年(家)第181号
相手方(子の父。夫)は、共同で監護していた未成年者(子)を、申立人(子の母。妻)の同意なく、予期できない時期に突然、一方的に連れ出し、所在さえ明らかにしないとして、申立人が、相手方に対し、未成年者の監護者を申立人と指定した上、未成年者を申立人に引き渡すよう命じた事案において、申立てを認め、未成年者の監護者を申立人と指定し、相手方に対し、引き渡しを命じた事例。
2017.04.18
預金返還等請求事件
LEX/DB25448583/最高裁判所第一小法廷 平成29年 4月 6日 判決 (上告審)/平成28年(受)第579号
被上告人(亡Cの子)が、上告人(信用金庫)に対し、亡Cが有していた普通預金債権、定期預金債権及び定期積金債権を相続分に応じて分割取得したなどと主張し、その法定相続分相当額の支払等を求め、原審は、上記預金等債権は当然に相続分に応じて分割されるなどとして、被上告人の請求を一部認容したため、上告人が上告した事案において、共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきであるとして、原審の判断には明らかな法令の違反があるとし、原判決中上告人敗訴部分のうち預金及び積金に係る請求に関する部分は破棄し、上記部分に関する被上告人の請求については、同部分につき第1審判決を取消し、同部分に関する被上告人の請求をいずれも棄却し、その余の上告については、上告人及び上告補助参加人らは上告受理申立ての理由を記載した書面を提出しないため、却下した事例。
2017.04.11
性別の取扱いの変更審判申立事件
★「新・判例解説Watch」H29.5月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25545225/岡山家庭裁判所津山支部 平成29年 2月 6日 審判 (第一審)/平成28年(家)第1306号
申立人が、申立人の性別の取扱いを女から男に変更する審判を求めた事案において、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号が、憲法13条に違反するほどに不合理な規定であるということはできないとし、本件申立てを却下した事例。
2017.03.07
離婚等同反訴請求控訴事件
LEX/DB25544905/大阪高等裁判所 平成28年 7月21日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第62号
本訴として、控訴人(夫)が、被控訴人(妻)に対し、被控訴人の不貞及び子らの連れ去りにより婚姻関係が破綻したと主張して、民法770条1項1号5号に基づき、離婚を求めるとともに、子らの親権者を控訴人と定めること、慰謝料1000万円の支払を求めたのに対し、反訴として、被控訴人が、控訴人に対し、控訴人が根拠なく不貞の疑いをかけ、監視、攻撃的な追及、非難等による精神的虐待をしたことにより婚姻関係が破綻したと主張して、民法770条1項5号に基づき、離婚を求めるとともに、子らの親権者を被控訴人と定めること、慰謝料1000万円の支払、子らの養育費一人月額6万円の支払、財産分与、年金分割の請求すべき按分割合を0.5と定めることを求め、原判決は、控訴人が慰謝料請求を棄却し、子らの親権者を被控訴人と定めたことを不服とし、被控訴人が慰謝料請求を棄却したこと、子らの養育費の額、財産分与の額を不服として、双方が控訴した事案において、控訴人の慰謝料請求は、原判決中の該当部分は相当であるとし棄却した一方で、被控訴人の慰謝料請求は200万円の限度で理由があり、財産分与は、控訴人から被控訴人への本件各不動産の持分10分の1の移転、被控訴人から控訴人への11万0282円の支払とすべきであるとし、これと異なる原判決の部分を変更し、長男及び二男の養育費は一人につき月額5万円とし、これと同旨の原判決中の該当部分は相当であるとして棄却した事例。
2017.02.07
養子縁組無効確認請求事件
LEX/DB25448430/最高裁判所第三小法廷 平成29年 1月31日 判決 (上告審)/平成28年(受)第1255号
被上告人ら(亡Aの長女と二女)が、上告人(亡Aの長男であるBとその妻であるCとの間の長男で、亡Aと養子縁組をした)に対して、養子縁組は縁組をする意思を欠くものであると主張して、その無効確認を求め、原審は、養子縁組は専ら相続税の節税のためにされたものであるとした上で、かかる場合は民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとして、被上告人らの請求を認容したため、上告人が上告した事案において、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできないとし、被上告人らの請求を認容した原審の判断には、法令の違反があるとして、原判決を破棄し、被上告人らの請求を棄却した第1審判決は正当であるとして、被上告人らの控訴を棄却した事例。
2017.01.31
離婚等請求事件
LEX/DB25544411/千葉家庭裁判所松戸支部 平成28年 3月29日 判決 (第一審)/平成24年(家ホ)第19号
離婚等請求事件の事案において、原告(妻)と被告(夫)の婚姻関係は、共にプライドの高い原告と被告が、事ごとに衝突を繰り返した結果、険悪な状態となって別居するに至り、その後、長女の監護者を巡る紛争を繰り広げるうちに相互不信が募り、遂に破綻するに至ったものと認められるから、婚姻破綻の原因は双方にあり、いずれか一方に特に非があるということはできないから、原告の離婚請求は理由があるが、慰謝料請求は理由がないというべきであると示したほか、長女の親権者については、被告と指定するのが相当であるとして、その理由として、今後、長女が身を置く新しい環境は、長女の健全な成長を願う実の父親が用意する整った環境であり、長女も現在に比べて劣悪な環境に置かれるわけではないことなどを挙げ、原告と長女との面会交流の要領を定め、原告と被告との間の年金分割についての按分割合を定めた事例。
2017.01.24
面会交流申立事件
LEX/DB25544598/名古屋家庭裁判所 平成28年 8月31日 審判 (第一審)/平成27年(家)第1913号 等
婚姻中の夫婦間で、申立人(夫)が、相手方(妻)に対し、現在相手方の下で監護養育されている未成年者A(長女)及び同B(長男)について、面会交流を求めた事案において、相手方が主張する性的虐待等の存在につき、これを基礎付ける具体的な根拠は認められないから、未成年者Aについて面会交流を禁止制限する事由は認められないなどとし、未成年者A及びBと申立人との間の面会交流を認めるべきであるとした事例。
2017.01.10
離婚、損害賠償請求控訴事件、損害賠償等請求反訴事件、損害賠償請求附帯控訴事件
LEX/DB25544250/札幌高等裁判所 平成28年11月17日 判決 (控訴審)/平成27年(ネ)第226号 等
夫である被控訴人(当審反訴被告)甲が、妻である控訴人(当審反訴原告、附帯被控訴人)乙との間の婚姻関係は既に破綻しているとして、控訴人乙に対し、民法770条1項5号に基づいて離婚を請求するとともに、長男及び長女の親権者をいずれも控訴人甲と定めることを求め(第1事件)、また、控訴人乙が、被控訴人(附帯控訴人)丙に対し、被控訴人らの不貞行為により精神的苦痛を被ったとして、不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき、賠償金の支払いを求め(第2事件)、原審が第1事件については、被控訴人甲の離婚請求を認容し、子らの親権者をいずれも控訴人乙と定め、第2事件については、請求を一部認容した事案において、原判決を変更し、控訴人乙の請求を一部認容し、被控訴人丙の賠償額を増額させた事例。
2016.12.27
遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25448337/最高裁判所大法廷 平成28年12月19日 決定 (許可抗告審)/平成27年(許)第11号
Aの共同相続人である抗告人(Aの弟の子でAの養子)と相手方(Aの妹でAと養子縁組をしたB(平成14年死亡)の子)との間におけるAの遺産の分割申立てをし、原審は、本件預貯金は、相続開始と同時に当然に相続人が相続分に応じて分割取得し、相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象とならないなどとした上で、抗告人が不動産を取得すべきものとしたため、上告した事案において、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当であるとし、最高裁平成15年(受)第670号同16年4月20日第三小法廷判決・裁判集民事214号13頁の判例の変更をすべきとした上で、本件預貯金が遺産分割の対象とならないとした原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原決定を破棄し、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻しを命じた事例(補足意見、意見がある)。
2016.11.22
氏名権侵害妨害排除等請求事件
★「新・判例解説Watch」H29.1月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25544090/東京地方裁判所 平成28年10月11日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第5802号
被告の設置する中高一貫校の教員である原告が、業務に当たり通称として婚姻前の氏を使用することを希望したにもかかわらず、被告により戸籍上の氏を使用することを強制されたと主張して、被告に対し、人格権に基づき、時間割表等において原告の氏名として婚姻前の氏名を使用することを求めるとともに、人格権侵害の不法行為又は労働契約法上の付随義務違反による損害賠償請求権に基づき、慰謝料の支払等を求めた事案において、職場という集団が関わる場面において職員を識別し、特定するものとして戸籍上の氏の使用を求めた行為をもって不法行為と認めることはできず、また、違法な人格権の侵害であると評価することもできないとし、仮に、被告の上記行為が業務命令に該当するとしても、原告が婚姻前の氏を使用することができないことの不利益を考慮してもなお、当該業務命令の適法性を基礎付けるに足りる合理性、必要性が存するというべきであるとし、被告が労働契約法上の付随義務に違反したとは認められないとして、原告の請求を棄却した事例。