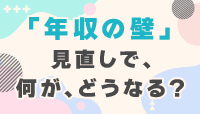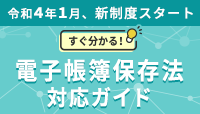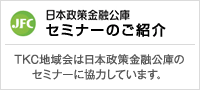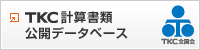低迷する業績にギスギスと軋轢が絶えない社内。が、これを低成長時代の宿命と諦めてしまうのはまだ早い。世界中にファンを持つオットー・シャーマー博士の『U理論』の翻訳者で、同理論に基づくコンサルティング活動においては日本で第一人者と目される中土井僚氏に、組織活性化のためにいま何が必要とされているのかを聞いた。
- プロフィール
- なかどい・りょう●アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)で、IT技術を活用した業務改善コンサルティングに従事。その後、インタービジョン社(現ヒューマンロジック研究所)、ウィルソン・ラーニングワールドワイド社で経営・組織・人材関連のコンサルティングに携わった後、2005年にオーセンティック・アソシエイツ代表に就任。10年間にわたる述べ3000時間以上のパーソナル・ライフ・コーチとしての活動とともに、一部上場企業を中心に経営者30名以上のコーチング実績、50社以上の組織進化プロセスコンサルテーションの実績を持つ。

中土井 僚 氏
――簡単に経歴を教えてください。
中土井 もともとアンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)でCRMや生産管理など業務プロセス改善に関するシステムの戦略立案・設計・開発を手がけていましたが、5年で限界を感じてやめました。向いていなかったんですね(笑)。私は文系人間なので、もっと“人間寄り”のことをしたかった。ちょうどそのころコーチングに出会い、組織変革や人材開発を手がける会社に勤めながら、自分でも個人向けのコーチングを行っていました。すると、いまの会社や組織が迷走し、病んでいることがよく理解できるようになったのです。
リレーションシップクライシス
――病んでいるとは?
中土井 リレーションシップ・クライシスと呼ぶべき状況です。大量生産・大量消費で放っておいても業績の上がった高度成長時代はとっくに終わりました。慢性的な業績低迷の渦中に置かれた組織内で何が起こるかというと、まず、初期段階では先行きへの懸念が問答無用に退けられます。次にリスクが顕在化しはじめると「会社としてこうすべき」という他責的なあるべき論が蔓延し、全社的ないらだちのなかで「あの人は技術職だから、○○出身だから(話が通じない)」と決めつけ合う状況ができてきます。そして「あの人には何を言っても無駄」と人格非難へと進み、さらには「あいつさえいなくなれば」「この会社に先はない」「手遅れ」などというののしり合い。対立、造反、社内紛争が頻発し、最終的には組織崩壊に至る。いまの日本企業の多くは、そんなプロセスのどこかに位置しているのではないでしょうか。
――そのような迷走状態を何とかしたいと……。
中土井 独立直後に野村総研と協働して意識変革事業を立ち上げたのですが、組織を良くするには、まず理念やビジョンを、腑に落ちる形で社員全体に浸透させることだと分かってはいても、それを効果的に達成するやり方が見つからない。そんなとき、大学院で組織開発を勉強していた妻が「こんなのがあるよ」と、グーグルやダイムラーあるいは南アフリカのアパルトヘイト問題やコロンビア内戦など、世界の数多くの企業や社会活動で援用されているオットー・シャーマーのU理論の存在を教えてくれたのです。
――U理論のどんなところに引かれたのですか。
中土井 それまでの経験で、個人の意識が変容していくプロセスは私なりにイメージできていました。それが4つのレベル(階層)に明確に区分されて表現されていた(『戦略経営者』2012年9月号73頁図表1参照)のにまず驚きました。
それから当時のコーチングはモチベーション管理や部下指導といった文脈でしか語られていませんでした。ところがU理論では、図で見れば一目瞭然なのですが、Uの谷にぐっと沈み込んで、そこから「創造」へと上がっていくプロセス(プロトタイピング)が“イノベーション”を誘引すると主張しています。ここが私がぼんやりと感じていたことに明確な形を与えてくれたのです。「これだ!」と思いました。
U理論のエッセンスとは
――U理論のエッセンスとは何なのでしょう。
中土井 私は「手放す」(letting go)と「迎え入れる」(letting come)の2つの概念だと思います。つまり「アインデンティティーたる古い自己」を手放し「新しい大いなる自己」を迎え入れることで、「これだ!」という直観を生み出す素地をつくるという考え方です。
――難しいですね(笑)。
中土井 いま企業の組織マネジメントで常識となっているPDCAは、いわば過去から学んだサイクルを繰り返すだけともいえます。そのため、そこから本当に新しい革新的なものは生まれにくい。一方、U理論は、深く内省し、表層の自己を手放すことで、個人あるいは組織の深層心理にまで到達し、まったく新しいビジョンを具現化させることを意図しています。この革新性がU理論の魅力でもあります。
みなんさんも、ふとしたきっかけに「これだ!」と確信に満ち溢れた発想を得ることがおありになるのではないでしょうか。また、経営者の方なら、修羅場のなかで腹をくくった時、吹っ切れて新たな未来が見えてきた経験をお持ちの方も少なくないと思います。U理論ではこれらの現象は「出現する未来から学んだ」結果であると表現します。
――出現する未来から学ぶ……ですか。
中土井 はい。図表1(『戦略経営者』2012年9月号73頁図表1参照)でいうプレゼンシング、つまりUの底の部分がポイントで、ここで、未来の領域が生まれてくるもっとも深い源につながるのです。その後反転し、固定概念の外れた新しい自己を迎え入れてイノベーションへと向かうわけです。
――内省し自己を手放すというのは仏教的な「放下」の感覚に通じるものがあるような気がします。
中土井 東洋思想の影響は受けているようです。その一方でピーター・センゲが『学習する組織』で強調した西洋的な「システム思考」の流れもくんでいる。その意味では、東洋と西洋を融合した折衷理論ともいえるかもしれません。
それと、個人レベルの意識変容については、宗教を含めて巷で無数の言及がありますが、U理論では、組織や社会においての意識変容について明確に語っています。このあたりも実際には前例は少なく、新しいと感じました。
本音を吐露し共有する
――U理論をベースにしながら中土井さんは独自に組織変革メソッドを構築されています。その概要を教えてください。
中土井 ベースにはシステム思考に基づいた「内的システムと外的システムの融合」があります。たとえば、業績が悪いのは「景気のせい」「社長の決断が遅い」「営業が動かない」「開発が無能」などと人は外部システムに原因を求めがちです。あるいは、経営者や上司の場合には「いまの若者はおかしい」「俺の時代とは違う」となりますよね。「うちの会社は評論家ばかり」と言う本人が一番の評論家であることに気づいていないのです。これがいまの一般的な組織内部のメンタリティーであり、このままだと堂々巡りを繰り返すばかりで事態は一向に好転しないのは明らかです。この状態を突破するには、図表2(『戦略経営者』2012年9月号74頁図表2)の“「選択」への直面”の状況が生まれるよう支援する必要がある。実際、われわれファシリテーター側にとってもここが最大の壁になります。
――どんな壁ですか。
中土井 「評論家・分析家姿勢」はU理論でいう「ダウンローディング」つまりは「過去のパターンで思考する」の状態ですが、そこから「(実は)自分が変わらなければ何も変わらない」ことに気づくことは並大抵のことではありません。人間は自分本位の生き物ですからね。ここを突破するために内省し、自己の内部に深く入り込む必要があるのです。
こうして「自分が組織に影響を与えている」ことを実感することができれば、いずれは自らが決断する「のるかそるか」の状況が出てきます。身を引きたくなる恐れや衝動にも駆られるでしょう。そこを乗り越えて意思決定をすることで、個人はもちろん組織も「自走」しはじめるのです。
――具体的に何をどうすればよいのでしょうか。
中土井 評論家・分析家から自らコミットする人間へと“目覚める”ために、まずは、各人の本音をできるだけ吐露してもらい、みんなで共有することです。当社の実践例では、ポストイットに各人の抱えている問題や気がかりな点を記入してもらい、縦軸に難易度の高低、横軸に継続時間の長短をとったボードに一人ずつ貼りだします。すると面白いことに、左上の「以前から継続して存在し」「難易度が高い」領域にポストイットが集中します。つまり、この部分の問題こそ今後も解決できずに残る可能性の高い難問であり、だからこそみんなで知恵を出し合う必要があることを理解させるのです。
――これだと、すぐに実践できそうです。
中土井 大企業であれ中小・零細企業であれ、絶対に頭痛の種はあります。それをまずは吐き出すことがスタートラインだと思います。これだけでも意味があります。
――手間はかかりますね。
中土井 アンケートをグルーピングしてすぐに解決策を打ち出すという従来のプロセスでは、まさに過去の経験から一歩も出ない「ダウンローディング」で終わってしまいます。そうならないようU理論のレベル2に当たる「観察」つまりUの谷をくぐる準備をしてもらう必要があるということです。
――次の段階は?
中土井 これもひとつの例ですが、「観察」後の「内省」のために当社では「エピソードインタビュー」&「センシング・ウォーク」という施策を行っています。これは、実際に職場で体験しているポジティブ&ネガティブエピソードを2人1組の相互インタビューであぶり出し、それを書いた紙を床にばらまいて、各自用紙の上を練り歩き、今組織内で起きていることと自分がその一部であることを実感するという試みです。これを行うと、「そんな状況があったのか」「それはひどいな」などと共感の声が上がると同時に、内省力の高い人から深いコメントが出されるようになり、他の参加者も「そういう視点もあるのか」などと内省を深める姿勢が生まれます。
――人材力の弱い中小企業でも実践できますか。
中土井 十分可能です。私も中小企業での実践経験があるのですが、正直、セッションでの話し合いはあまり盛り上がりませんでしたが、後で喫煙所などで侃々諤々の議論がはじまりました。みんな、しゃべりたくて仕方がない心理傾向になっていたのです。
――つまり、U理論でいう「視点を転換し」「自らを手放す」状況へ向かうわけですね。
中土井 はい。他責に終始するのではなく、自らが当事者になり、相手にも共感する。そのことが、リスクをとって動くための動機づけとなるのです。各人が図表3(『戦略経営者』2012年9月号75頁図表3参照)のモデルにあるような“地層”を突き抜ける現象が次々に起きてくるとしめたものです。
関係の質の向上が結果を生む
――そのような施策の実践によって、明確に成果の上がったケースはありますか。
中土井 9期連続赤字に陥っていた大手化粧品メーカーの子会社P社が、当社のたった2度のファシリテーションで組織が活性化し結果的に黒字に転換した例があります。
この会社では、もともと親会社から出向してきた経営陣とプロパー社員との間に深い溝があり、さらに営業と商品開発部門が売れない理由をめぐって対立していました。結果として、有効な改善策を打ち出すことができないままだったのです。そこでわれわれは「ワールドワーク」というプロセス指向心理学の手法を使って風穴をあけようとしました。具体的には、トップからミドルまでを集めて、経営陣とスタッフ、経営陣と競合会社、営業担当と開発担当など対立構図を再現する即興劇のようなものを行ったのです。もちろん罵詈雑言の嵐でした。さらには、お互いに役割を転換して(ロールスイッチ)、劇をやり直すセッションも行いました。相手の立場や気持ちに共感するためです。
2日目の半日を費やしたセッションで大きく動きました。社員たちの当事者意識が呼び覚まされ、全社一丸で危機を乗り越えるための一体感が醸成されたのが分かりました。その後、たとえば、これまで対立していた営業と開発が一緒に顧客先に足を運び、商品や販促ツールを製作するなど、社内に協働関係が生まれ、10年ぶりの黒字を達成。翌期も東日本大震災の影響があったにもかかわらず2期連続の黒字となりました。黒字がすべてセッションのおかげだとは言いませんが、かなりの部分に貢献したことは確かだと思います。
――つまり、社員の「関係の質」の変容が、早速、結果(業績)へと結びついたわけですね。
中土井 マサチューセッツ工科大学のダニエル・キム教授が提唱する「成長の循環モデル」によると、「関係の質」が「思考の質」に、「思考の質」が「行動の質」に、「行動の質」が「結果の質」に影響を及ぼすとしています。つまり、このサイクルのレバレッジとなりやすい「関係の質」を改善することこそ、結果を出す早道なのです。日本の企業はこれを軽視しすぎているのではないでしょうか。
――「関係の質」というと、社員旅行や親睦会などによる仲良しクラブ的な取り組みをイメージしてしまいますが……。
中土井 組織マネジメントの分野でも、「みんなで成功体験をつくろう」などという取り組みが主流でした。富士登山をやろうとかね(笑)。でも、いくら仲良くなっても、根本問題が解決しないと同じ。「やっぱりあの人は変わらない」「あの富士登山は何だったんだ」と、むしろ逆効果になる懸念さえあります。組織の真価は土壇場でこそ問われます。エクセレントカンパニーの条件は、ピンチの時に優れたリーダーシップを持つ人が現れ、取り巻く社員たちも一丸となって困難を切り抜けることができるかどうかです。逆にそこで社員の離脱が起きてしまうようでは終わり。空中分解するか結集して乗り越えるか……日本の企業に共通の課題だと思うし、この課題をクリアするためにU理論は有力な実践法だと確信しています。
(本誌・高根文隆)