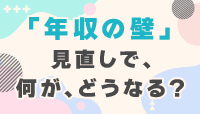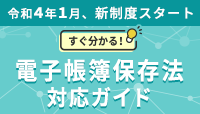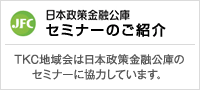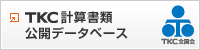農業、林業、伝統工芸、不動産──。高い成長率が見込めないとされてきた成熟産業だが、ITや最新技術の導入によってイノベーションを起こすことは十分可能だ。レガシーマーケットで果敢に挑戦する中小企業やベンチャーを取材した。
- プロフィール
- ながい・しゅんすけ●1986年群馬県生まれ。早稲田大学卒。ジャフコでM&Aやバイアウトに携わった後、父親が経営するクレストに入社。CRMやマーケティングオートメーションを活用し4年間で売り上げを2倍に拡大し、同社をサイン&ディスプレー業界の大手企業に成長させる。2016年に社長に就任。

成長性が低く、かつ生産性も低い市場のことをレガシーマーケット、そこで事業を展開している会社をレガシーカンパニーと呼ぶことがある。「レガシー」という言葉はどちらかというと、マイナス的な意味で使われることが多い。例えば金融業界で「レガシーアセット」といえば負の遺産のことを示す。高値で購入した不動産、減損処理をしなければならないほど価格が暴落したゴルフ会員権、高値でつかまされた保険契約などを想像してもらえれば分かりやすいだろう。
一方、2000年ごろからベンチャーを中心に世界的な規模でイノベーションが起こってきた。GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)に代表されるインターネット企業が世の中の産業に大変革をもたらしてきたのは周知の事実である。現在世界の時価総額ランキングをみても、上位にレガシー企業の姿は少ない。しかし私は、ここにきて潮目が変わりつつあるのではないかと感じている。米国ではベンチャー企業に対する投資額が頭打ちになっており、「スタート・アップ・イズ・ゴッド」の時代は過ぎ去ったようだ。ウーバーがタクシー業界に激震をもたらし、エアビー・アンド・ビーがホテル産業に根底から揺さぶりをかけるなど、レガシー産業は最近までやられっぱなしだったが、今後はイノベーションの主役の座を取り戻す事例が増えていくと予想している。レガシーアセットがあるということがメリットになることも多いからだ。
デジタル化で生産性向上
父親が経営していた看板屋を継いだ私にとって、レガシーという言葉に悪い印象はまったくない。レガシーアセットとは本来、会計上の資産にとどまらない広義の意味を持つと考えているからだ。数十年かけて築いてきた顧客の信頼、研究員の経験、配送拠点、物流網、所属する産業についての深い知識、業界特有の悩みや課題、問題点を知っているということ……これらがレガシーアセットの本質であり、レガシープロフィットを生みだす源泉になるのである。そしてその利益が、イノベーションを生み出す資金源となる。
歴史を振り返ってみれば、日本でも富士フイルムのように、レガシー産業がイノベーションを起こしている事例はたくさんある。しかし、なぜその難易度が高いのか、なぜレガシー企業の経営者にイノベーションの意欲が薄いのか、といった疑問から出発し、レガシー市場で既存企業がイノベーションを巻き起こす方法論としてまとめたのが、レガシー・マーケット・イノベーション(LMI)である。
図表1(『戦略経営者』2019年12月号P9)を見てほしい。これはLMIの概念を分かりやすく説明したものだ。縦軸を成長性、横軸を生産性とするとレガシー産業が位地するのは縦軸横軸ともに低い左下の領域。これを右上に持っていくのが目標だが、第一ステップは左下から右下へ行く「L(Legacy)の世界」の成長戦略である。自らの経験から私は、この戦略には次の七つのフェーズがあると考えている。
①オーガニックフィットフェーズ
会社の文化に自分をフィットさせ、LMIを主導するリーダーの適正を理解する。
②共感フェーズ
LMIの重要性や方向性に共感し、ともに戦ってくれる同志を見つける。
③構造化フェーズ
レガシーアセットの有無や価値を明らかにし、今の事業活動の弱みと強みを把握する。
④デジタル化フェーズ
無料または安価なデジタルツールを導入し、非効率なアナログ業務を改善する。
⑤クイックウィンフェーズ
デジタルツールを実際に使う環境を作り、「便利だ」「これはいい」と実感する小さな成功体験を生み出す。
⑥データドリブンフェーズ
構造化とデジタル化を通じて蓄積したデータに基づき、客観的な視点で仕事の評価や改善に取り組む。
⑦経営理念の浸透フェーズ
経営理念を最上位の概念として位置づけ、社内に浸透させる。
要するにMBAの教科書に書いてあるような普通のことを普通にしよう、ということである。経営戦略の決定にはじまり、それを実行できる人材の採用と育成を担う人事制度、営業戦略、経理やファイナンスに関する財務戦略、PR戦略、労働環境の整備や社内の空気づくり……非常に幅広い領域になるが、これまで言われてきたことをまじめにコツコツと実行すればおのずと道は開けてくるはずだ。
例えば営業戦略。飛び込み営業が全く無駄かといえばそうではないが、もはや気合と根性で契約がとれる時代ではない。何もしないよりはましという程度で、戦略とは言えない。やはりターゲットをしぼり、自社のサービスや製品を欲しいと思ってもらえるような人に効率的に営業をかけることが重要だ。マーケティングオートメーションやCRMの導入がもはや当たり前の時代で従来型の営業を漫然と続けるのは、銃で武装した敵に剣で向かっていくようなものである。「Lの世界」の成長戦略において、デジタル化による効率化は必須の条件といえるだろう。
先進技術×既存事業
デジタル化によって生産性向上などの成果が表れ、着実に利益を生み出せるようになれば、第2ステップの実行だ。「I(Innovation)の世界」の成長戦略である。概念図で右下に移行した企業は投資にまわすだけの資金的な余裕ができているはずで、目指すはイノベーション。ここで必要なのは経営者自らが全力で時流を読みに行くことである。
例えばサプライ・チェーン・マネジメント(SCMSの構造変化を例に挙げてみよう。原料工場から原料を仕入れて1次加工業者が製造、2次加工会社が完成させた製品が1次卸会社、2次卸会社と経てようやく販売する小売店の店頭に並ぶ……中間プレーヤーがそれぞれ利益を乗せることで最終的に数倍もの価格になるこのような商流は完全に時代遅れになっており、最近ではDtoC、すなわちメーカーが直接消費者に製品を販売する「ダイレクト・トゥー・カスタマー」と呼ばれる手法がさかんに取り入れられている。デザイナーがデザイン会社に勤務するのではなく、「ランサーズ」や「クラウドワークス」などを通じて個人で営業活動をする時代に、中間流通でビジネスを展開するのはやはりリスクが高いだろう。
私は時々、経営者の三つの視点を鳥の目と虫の目、魚の目に例えて意識するときがある。鳥の目は文字通り高いところから地上を見下ろし、「森が生い茂っていて見込みがある」とか、「枯れてしまっていて将来性がなさそうだ」と感じる、マクロの位置から全体を俯瞰(ふかん)して最適な解を見つけるやり方だ。そして虫の目は、まさに現場で何が起こっているのか、細かなところまで深く入り込んでいくミクロの目線である。魚の目は、自分が今泳いでいる海の中の潮の流れを感じる方法。生き延びるためには潮の流れをうまく利用し、餌(えさ)、つまりビジネスの源泉が間違いなく発生するであろう経済の流れをしっかりと読まなければならない。
最新アプリを試してみる
時流を読んだ上で、その次の事業化において重要なのは、テクノロジーやITについてとにかく勉強すること。カメラ・画像認識技術、IoTとセンサー、ビッグデータ、ブロックチェーン……対象は幅広い。何を学べばよいかわからない人は、ガートナーが毎年公表している「先進テクノロジーのハイプ・サイクル」で全体像を把握するとよいだろう。一通り原理を理解し、できれば他人に一から説明できるレベルまでもっていきたい。上場企業の経営者とたまに会う機会があるが、かなり深いところまで勉強している社長が多くてびっくりさせられる。
知識を自分のものにするには、構えることなく最新のツールを気軽に使ってみるのがよいだろう。例えば20歳代の若者の多くが、「Zenly(ゼンリー)」というアプリを使っている。これは自分が今いる位置情報をシェアするアプリだが、居所が他人に知られてしまうことに抵抗のある人もいるかもしれない。しかし使ってみると、知人がたまたま近くにいてすぐに食事に誘うことができるなど意外に便利だ。とにかく触れてやってみることをおすすめする。自社のビジネスと位置情報を組み合わせたアイデアが浮かんでくるかもしれない。
先進テクノロジーに精通すれば、それらと既存の事業をどのように組み合わせたらよいかアイデアが浮かんでくるようになる。私が最近注目しているレガシーマーケットの一つ、印鑑業界を例に説明しよう。5月にデジタルファースト法という法律が成立したが、法案をまとめる過程で当初は、デジタル署名によって行政手続きや本人確認を行うなどといった内容が盛り込まれる計画だった。行政サービスのデジタル化やペーパーレス化の一環だが、当然この動きに印鑑業界が猛反発。結局法案にはデジタル署名に関する項目を含めることは見送られた。
ひとまず危機は去ったように思われるが、このまま安泰のはずはない。実際ドキュサインやクラウドサインといった電子署名サービスを使う企業は増えつつある。私はすべてのはんこ企業が、自然淘汰されてしまう可能性が高いと思う。利益を生み出せている間に、印鑑が不要になる世界を前提にしたイノベーションを、レガシー企業自らが起こしていく必要があるだろう。ブロックチェーンのエンジニアを採用すれば新しい認証プラットフォームを開発できるかもしれない。印鑑というハードを残しながら、エッジコンピューティングの技術を応用するのもありだ。指紋認証などの生体認証の技術を組み合わせれば、画期的な認証デバイスが生み出せるかもしれない。組み合わせは無限に考えられる。
社員と対話し経営理念浸透
最後に私が現在進めているプロジェクトをご紹介しよう。2019年8月、当社はホールディングスカンパニーを親会社とし、新設分割した各事業会社がぶら下がる形にグループを再編成した。と同時に、集成材の製造販売を手掛けている東集という会社を傘下に収めた。木材業界といえば大昔からあるレガシーマーケットである。概念図でいえばまさに左下の領域に位置している会社だ。
子会社化して早速私は「Lの世界」の成長戦略にとりかかった。各店舗、営業所を回り、多くのスタッフにLMIの概念を説明、「一緒に木材産業にイノベーションを起こし、世界を変えていこう」と呼びかけ、全社員の心をつかむことに成功した。
買収後1週間以内には、業務用のスマートフォンとノートパソコンを全スタッフに配布した。コミュニケーションには社内SNSを活用し、顧客とのファクスでのやり取りもITの力で少しでも減らせるように努力している。固定電話も今後は減らす方針だ。スマホで固定電話の通話ができるアプリには、通話記録を自動で文字起こしし、通話内容の確認や分析を容易にする機能があるものもあり、導入を検討している。
イノベーションのための有志メンバーとは、ハイプ・サイクルの研究を通じ自社の事業と組み合わせてどのようなイノベーションの可能性があるか延々と議論を重ねており、すでに数十ものアイデアが候補に挙がった。独自に開発した構造化モデルによる成功確率の推定によれば、そのうちのいくつかの事業は見込みがあることが分かっている。
富士フイルムは確かに銀塩フィルムの需要消滅という事態を乗り切った稀有(けう)な事例である。しかし例えば、自らがフィルムをディスラプト(破壊)して、デジタルカメラへの参入をしていくという道のりもあったかもしれない。マーケットそのものにイノベーションを起こすレガシー企業が次々と誕生する世の中になっていくことを期待している。
(構成/本誌・植松啓介)