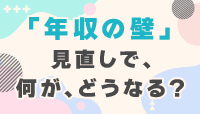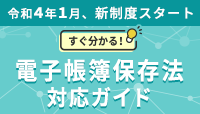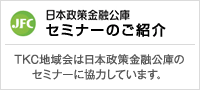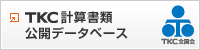幅広い消費財に用いられ、日常生活の隅々にまで行き渡っているプラスチック素材。近年は海洋汚染をもたらす原因として批判を浴びるなか、代替素材を積極的に採用する企業が見受けられるようになってきた。潮流の変化をとらえ、イノベーションを起こすチャンスにできるか。日本はいま、分水嶺に立っている。
- プロフィール
- なかむら・ようすけ●2003年東京大学経済学部卒業後、日本生命保険相互会社入社。株式投資、ベンチャー・キャピタリスト業務などに従事後、17年ニッセイ基礎研究所に移籍。
──国際社会におけるプラスチックごみ(プラごみ)規制の動向について教えてください。

中村 海洋プラごみをめぐる問題は国際的な関心が高まっていて、2019年6月に開催されたG20大阪サミットでも議論されました。
サミットでは、50年までに海洋プラごみによる追加的な汚染をゼロにすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」が共有され、首脳宣言にも盛り込まれました。さらに日本政府はビジョン実現に向け、①廃棄物管理②海洋ごみの回収③イノベーションの推進④途上国の能力強化支援からなる、「マリーン・イニシアティブ」を打ち出しています。
世界の中で特に踏み込んだ規制を設けているのは、欧州です。使い捨てプラスチック製品の流通を21年までに禁止する法案が19年5月、EU理事会で採択されました。これによりEU加盟国には、代替品が存在する使い捨てプラスチック製品の流通を禁ずる国内法を整備することが求められます。規制の対象となるのは、皿やフォーク、ナイフなどのカトラリー、ストロー、マドラー、コップ等です。
政府も脱プラを後押し
──新興国でも規制の動きはありますか。
中村 これまで中国や東南アジア諸国は廃棄プラスチック(廃プラ)の主要な輸出先として知られていましたが、近年輸入規制を強化しています。
中国は17年末以降、廃プラの輸入に関するルールを厳格化しており、結果、廃プラの輸入量は激減しました。中国では従来、世界各国で発生する廃プラを多く受け入れていたため、その影響が広がっており、日本も無縁ではありません。日本は年間150万トンの廃プラを輸出し、そのうち約80万トンを占めていた中国が最大の輸出先でした(16年統計)。
中国の代替輸出先に見込まれていた東南アジア諸国でも、廃プラの輸入規制が敷かれはじめています。たとえばマレーシアやタイ、ベトナム、インドネシアなどでも規制が強化されつつあります。日本は廃プラの処分先の確保という新たな問題に直面しているのです。
──日本の対応は?
中村 日本政府は19年5月、「プラスチック資源循環戦略」を取りまとめ、廃プラの3R(リデュース、リユース、リサイクル)を推進し、廃プラ問題や海洋プラごみ問題などの課題解決に寄与することをうたっています。30年までにプラスチック製容器包装の6割をリユースまたはリサイクルすることや、同年までにバイオマスプラスチックを約200万トン導入することといった数値目標も掲げ、脱プラスチックに向けた取り組みを加速しています。
また、「省CO2型リサイクル等高度化設備導入促進事業」として、国内で資源を循環させるリサイクル設備導入に対する国庫補助を開始しました。これによりプラごみの分別回収、高度選別、洗浄、原材料化、国内循環というプロセスの確立を目指しています。
プラスチック製容器の小型化やゴミの分別回収をはじめ、日本は省資源に熱心な環境立国であるとの印象を持っている人は少なくないと思います。しかしながらプラごみ規制の議論では欧州が主導している現状にあって、日本はG20などの国際会議の場を活用して、巻き返しを図っている印象を受けます。
──そもそもプラスチックを利用するメリットは何でしょう。
中村 プラスチックは食品容器、電化製品から住宅断熱材、自動車の車体まで、さまざまな用途で活用されています。
たとえば食品のプラスチック包装では、安全衛生や鮮度保持、栄養価維持などに役立てられています。メリットを得られるのは消費者サイドだけではありません。企業も軽量化により輸送効率を高めたり、コストを抑えたり、数多くの恩恵を享受してきました。
これは私見ですが、日本の消費者は品質に対する要求水準が高いため、企業は課題をクリアするべく改良を重ね、高品質な商品を開発してきた面がありました。私たちの日常生活のさまざまな領域に浸透しているプラスチックとただちに決別するのは容易ではないでしょう。ただ、プラスチックに代わる素材を活用した製品を開発したり、採用したりする企業が増えているのも事実です。
一長一短のバイオプラ
──プラスチック代替素材の例を教えてください。
中村 昨今注目されているのは、植物や動物などの生物由来の有機性資源(バイオマス)を原料とする「バイオプラスチック」です。
バイオプラスチックには二つのジャンルがあり、ひとつは「生分解性プラスチック」。使用後、微生物により水と二酸化炭素(CO2)に分解され、自然界に循環するのが特徴です。もうひとつは「バイオマスプラスチック」で、再生可能なバイオマス資源を原料に、化学的または生物学的に合成して得られる素材を指します。
──それぞれどんな用途で用いられていますか。
中村 生分解性プラスチックは土のうや植生ネットなどの農業、土木資材や生ゴミの回収袋等に活用されています。回収袋の例では、回収した生ゴミは、たい肥やメタンガスに再資源化され、回収袋も生分解されるので、廃棄物を削減できます。
一方、バイオマスプラスチックは、食品容器包装や衣料繊維、情報機器、自動車などに幅広く取り入れられています。
これらのバイオプラスチックの製造コストは石油由来のプラスチックより高いため、使用量が少ない点が課題として挙げられます。毎年1100万トン使用されるプラスチックのうち、バイオプラスチック使用量は4万トンに過ぎないとの推計もあります。
──コスト面以外に議論されている論点は?
中村 生分解性プラスチックは海洋中で生分解されるまで長期を要し、マイクロプラスチック化してしまう点や他のプラスチック素材と混在するとリサイクルの阻害要因となる点、分解されるのを見込んでポイ捨てを助長するおそれがある点などが指摘されています。
また、バイオマスプラスチックにも課題があり、トウモロコシやサトウキビ等を原料にすると、食品や家畜の飼料用途と競合し価格の高騰が懸念されるため、将来、発展途上国における食料品不足の深刻化につながるおそれもあります。現状ではプラスチックに代わる100点満点の素材がないのは悩ましいところです。
──企業における脱プラスチックの取り組みを教えてください。
中村 国内企業で取り組みが顕著なのは外食、食品、アパレル業界などです。
すかいらーくホールディングスは20年開催の東京五輪・パラリンピックまでに、プラスチック製ストローの原則廃止を決定しました。19年7月にグループ全店で廃止を完了し、希望客にはトウモロコシを原料とする生分解性ストローを提供しています。デニーズやロイヤルホールディングスも紙製のストローに切り替えたり、プラスチック製ストローの提供を順次中止しています。
衣料チェーンのH&Mジャパンも18年12月以降、プラスチック製買物袋を紙製に切り替えるとともに、有料化に踏みきりました。アクセサリー包装用の最小サイズを除いて、1枚20円で販売しています。このほか、社員食堂でプラスチック製ストローや飲料カップの提供を廃止したりする企業も見受けられます。
問われるCSR
──新素材開発のベンチャー企業も現れはじめています。
中村 もともと石灰石由来のストーンペーパーとよばれる紙の代替素材を開発していたTBM(東京都中央区)は、新素材の「ライメックス」を製造しています。石灰石とプラスチック材を原料とするライメックスに改良を施し、バイオマス資源を原料に使用した「バイオライメックス」を開発。レジ袋やゴミ袋等に活用されています(ライメックスのボールペンへの活用例は『戦略経営者』2020年2月号P18)。
──バイオプラスチックの認証制度はありますか。
中村 日本バイオプラスチック協会は、生分解性プラスチック製品を対象とする「グリーンプラ識別表示制度」と、バイオマスプラスチック製品向けの「バイオマスプラ識別表示制度」を設けています。識別表示基準に適合した製品は認証マークの使用が認められ、一般消費者に対してアピールすることができます。
──プラスチック製品に対する世論の変化は感じますか。
中村 持続可能な開発目標(SDGs)に掲げられている17の項目に取り組む企業は年々増えていると感じます。背景には、政府や経済団体による推進に向けた旗振りもありますが、一般消費者の感度も変化しつつあります。多少値がはっても、環境負荷の少ない商品を好む人も現れはじめています。社会や環境問題の解決に貢献する「エシカル消費」が注目され、投資の世界では、社会的責任を果たす企業に積極的に投資する「ESG投資」という言葉も聞かれるようになりました。
こうした環境変化をピンチではなく、ビジネスチャンスととらえられるかが肝要です。社会課題に向き合わなければ、企業として成長が見込めないと考える経営者は増えていると思います。
──今後の動向は?
中村 今年7月にはレジ袋の有料化が開始されます(制度詳細は『戦略経営者』2020年2月号P14)。新たなコストが発生するため、消費者にとって負担になるのは間違いありませんが、製品やレジ袋にバイオプラスチックを取り入れてみたり、企業として環境問題の解決に熱心な姿勢を示す良い機会になればと思います。国際的に議論される機会が増え、さまざまな規制や数値目標が示されるなか、脱プラスチックの機運が今後急速にしぼむ可能性は低いでしょう。
(インタビュー・構成/本誌・小林淳一)