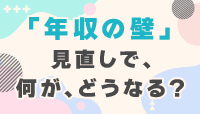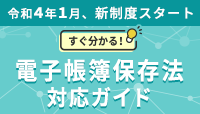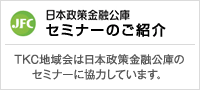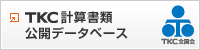オフィス業務や日常生活において急速に浸透しつつある生成AI。生成AIに潜在するリスクと足元で広がるビジネス領域を概観する。
- プロフィール
- かきぬま・たいち●日本ディープラーニング協会(JDLA)理事。1997年京都大学法学部卒。2000年弁護士登録。11年中小企業診断士登録。15年STORIA法律事務所を共同設立。専門分野はスタートアップ法務およびデータ・AI法務。

生成AI利用時に注意すべき法律上の問題点を知りたい、生成AIを業務に活用する際のルールを設けたい……最近、中小企業からこうした相談が相次いで寄せられています。ビジネス文書やプレゼン資料の作成など、企業において生成AIはさまざまな用途で利用されはじめていますが、特に注意したいのが「著作権」との兼ね合いです。生成AIと著作権に関する論点は、以下の2つの段階に分けて検討する必要があります。
- 生成AIをつくることと著作権侵害(AI開発・学習段階)
- 生成AIを利用してAI生成物を生成・利用することと著作権侵害(生成・利用段階)
①の段階では、生成AIモデル制作者が「著作物」を複製等した上で、学習用データセットを作成し、学習済みモデルを制作します。そして②の段階で生成AIのユーザーが行った入力、指示内容に応じて、「AI生成物」が出力されます(『戦略経営者』2023年10月号 P25左図参照)。
著作物とは著作権法第二条において「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。単なる事実やありふれた表現、表現でないアイデア(作風・画風など)は、著作物に含まれません。著作物を創作した時点で著作物を創作した著作者は、手続きを何ら行わなくても著作権を自動的に取得します。
ここでポイントとなるのは、複製、公衆送信、譲渡等複数の利用行為がある場合、著作権侵害の有無は、利用行為ごとに検討する必要がある点です。生成AIと著作権の関係においても、図表(『戦略経営者』2023年10月号 P25)にある複製等、機械学習、入力……といった著作物の利用行為ごとに検討することになります。ただ、皆さんの多くは生成AIの開発者というよりユーザーであると見込まれるため、②の「利用段階」を中心に解説します。
類似性と依拠性が要件
著作権には複製権や公衆送信権、譲渡権などがあり、著作権の対象となる利用行為をしようとする際は、著作権者から許諾を得なければなりません。他人の著作物を権利者から許諾を得ないで利用した場合や、権利制限規定(※)に該当しないにもかかわらず利用した場合は、著作権侵害となります。裁判例において、著作権侵害の要件として、以下の両方を満たすことが必要とされています。
- 〇後発の作品が既存の著作物と同一、または類似していること(類似性)
- 〇既存の著作物に依拠して複製等がされたこと(依拠性)
生成AIを利用する際、著作権侵害となる行為として、特定の作家の作風を模倣する意図をもって指示し、出力されたAI生成物を使用するケースがあります。AI生成物は画像、文章を問いません。あるいは、ユーザーが生成AIに指示したところ、AIの開発・学習段階で使用した画像などと同一のデータが偶然出力されるケースもあります。画像生成AIの開発・学習には、数十億単位の膨大な画像が用いられます。AI生成物が学習用データと一致していることを知らずに、第三者に提供などしてしまった場合、著作権侵害となるか議論の分かれるところですが、侵害となるという見解が大勢を占めるようです。
著作権侵害を防ぐには第一に、「特化型AI」を使用しないこと。特化型AIとは、特定の作者や作家の作品のみを学習して開発された生成AIを指します。対話型AIの利用を検討している場合は、ChatGPTやBard、Bing AIといったサービスを利用することをおすすめします。第二に、著作権侵害を引き起こす可能性のある指示をしないこと。生成AIでは通常「プロンプト」と呼ばれるテキストで指示しますが、既存の著作物や作家名、作品名などを入力することは避けるべきです。第三に、AI生成物を配信、公開等する場合、生成物が既存の著作物に類似していないか調査すること。学習用データがオープンになっていれば類似しているかどうかを確認できますが、非公開になっているサービスも少なくありません。大手検索サイトの画像検索機能を用いて確認する方法が現実的です。
※権利制限規定…私的に鑑賞するため画像等を生成するなどの行為
活用事例の収集を
生成AI利用時に注意したい著作権侵害以外のリスクとして、プロンプト入力時の情報漏えいリスクがあります。生成AIに個人情報を入力する行為が適法といえるかどうかは、サービス提供事業者やデータの取り扱いによって判断が分かれます。例えば、ChatGPTでは対話履歴をオフに設定すれば、学習に使われないようにすることもできますが、提供元のOpenAI社は外国企業であるため、個人データを入力する際に、個人情報保護法上特別な法規制がかかります。社員や顧客の個人情報をむやみに入力することは控えるべきです。
また、外部事業者が提供する生成AIに、他社と秘密保持契約(NDA)を結んで取得した秘密情報を入力すると、NDA違反となる可能性があります。自社の機密情報についても生成AIの処理や規約内容によって、法律上保護されなくなったり特許出願できなくなったりするおそれがあるので、入力するべきではありません。生成AIを業務で使用する場合は利用規約に目を通し、入力したデータの活用用途などを確認しておきましょう。
AI系のスタートアップのみならず、一般企業まで生成AI利用のすそ野が拡大しているいま、社内ルールづくりを検討している企業が増えています。ルールを策定する際に参照することをおすすめしたいのが、日本ディープラーニング協会が公表している「生成AIの利用ガイドライン」です。同ガイドラインには、生成AI利用時に想定される注意事項が網羅されており、ひな型として活用できます。
著作権をはじめとする生成AI利用時に想定されるさまざまなリスクについて述べてきましたが、リスクを強調しすぎると利用する社員が誰もいなくなる可能性があります。ガイドラインを策定する場合、注意事項だけでなく活用事例も盛り込めば、利用を促せるはずです。
AI生成物の著作権は
生成AIと著作権をめぐる論点は、生成AIの開発・学習段階と生成・利用段階に分けて検討すべきであると先に説明しました。これと次元の異なる論点として、AI生成物は著作物に当てはまるのかという問題があります。この問題はとりわけ映像、ゲーム、イラスト等のコンテンツ制作会社に深刻な影響をおよぼしかねません。AI生成物は著作物に該当しない場合、作品が模倣され放題となってしまうためです。
生成AIが自律的に作成したものは、思想又は感情を創作的に表現したものではなく、著作物に該当しないと考えられます。一方、思想、感情を表現しようとする「創作意図」と「創作的寄与」が認められる場合、著作物に当てはまることになります。生成AIサービスの中には、AI生成物に「made by AI」といったクレジットを付すことを利用規約でうたっているケースもあります。日本政府は生成AIの事業者向けガイドラインづくりを進めており、議論の行方を注視する必要があります。
現在提供されている生成AIは、事実と異なる回答を導き出すこともあり、回答の根拠も明確ではありません。ただ、生成AIの近年の進化は目覚ましく、根拠を明示できるレベルに達するのは5年もかからないと思います。生成AIをうまく活用して生産性を向上させる企業と、業務に活用しない企業の間で今後二極化が進展していくでしょう。
(インタビュー・構成/本誌・小林淳一)