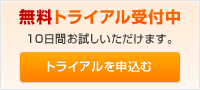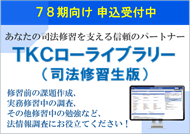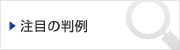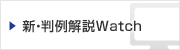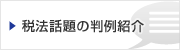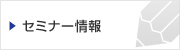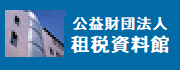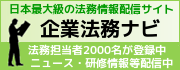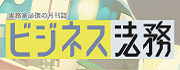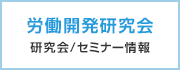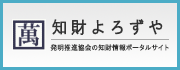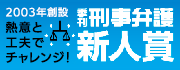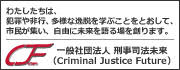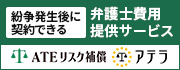2016.07.19
清算金請求事件(民事再生手続開始後の3者間相殺無効)
LEX/DB25448048/最高裁判所第二小法廷 平成28年 7月 8日 判決 (上告審)/平成26年(受)第865号
再生手続開始の決定を受けた上告人(原告・控訴人。証券会社)が、被上告人(被告・被控訴人。信託銀行)との間で基本契約を締結して行っていた通貨オプション取引等が平成20年9月15日に終了したとして、上記基本契約に基づき,清算金11億0811万1192円及び約定遅延損害金の支払を求め、被上告人は、上記再生手続開始の決定後、自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が上告人に対して有する債権(再生債権)を自働債権とし、上告人が被上告人に対して有する上記清算金の支払請求権を受働債権として上記基本契約に基づく相殺をしたことにより、上記清算金の支払請求権は消滅したなどと主張し、原審が本件清算金債権は本件相殺によりその全額が消滅したと認め、原告の請求を棄却したため、上告人が上告した事案において、本件相殺が民事再生法92条により許容されるとした原審の判断には法令違反があるとして、原判決を変更し、上告人の請求は、被上告人に対し、清算金4億3150万8744円並びに期限前終了日である平成20年9月15日から同年10月1日までの確定約定遅延損害金16万6841円及び上記清算金に対する同月2日から支払済みの前日まで2%を365で除した割合を日利とする各日複利の割合による約定遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余の請求は棄却した事例(補足意見がある)。
2016.07.05
共有物分割請求控訴事件
LEX/DB25542989/東京高等裁判所 平成27年 1月28日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第4929号
原告(控訴人)らが、被告(被控訴人)に対して、原告ら及び被告3名の共有に係る土地建物(原告Aの持分60分の43、原告Bの持分60分の15、被告の持分60分の2)について、被告の持分を原告らに取得させて、その価格を原告らに賠償させる全面的価格賠償の方法による分割を求めたところ、原判決は、共有物分割の方法として形式的競売の方法による分割を命じたことから、原告らがこれを不服として控訴した事案において、上記土地建物に係る被告の持分30分の1を原告らにそれぞれ60分の1ずつ取得させ、原告らが被告に対してそれぞれ59万5834円ずつの価格賠償をするという全面的価格賠償の方法によることが相当であるとし、これと異なる原判決を変更し、原告らの控訴を認容した事例。
2016.06.14
損害賠償等本訴請求事件、請負代金反訴請求事件
(ゴミ焼却施設訴訟 京都市VS住友重機械工業(株))
★「新・判例解説Watch」H28.8下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25542802/京都地方裁判所 平成28年 5月27日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第802号 等
原告と被告との間で締結された焼却灰溶融施設のプラント設備に関する工事請負契約について、請負人である被告が、期限までにプラントの工事を完成させ、注文者である原告に引き渡すことが不可能となり、原告が、被告に対し、請負契約を解除するとの意思表示をするとともに、原告及び被告の間では、プラント全体の解体撤去、損害賠償に関する合意が成立したと主張して、主位的に〔1〕解体撤去合意に基づく解体撤去請求又は請負契約の解除に基づく原状回復請求とし、プラント全体の解体撤去を求め、〔2〕賠償合意又は債務不履行(履行不能)に基づき、損害賠償金の支払を求め、〔3〕賠償合意に基づく損害賠償請求、請負契約の解除に基づく原状回復請求又は債務不履行(履行不能)に基づく損害賠償請求として既払請負代金の支払を求め、〔4〕前記〔1〕のプラント全体の解体撤去請求について、予備的に、請負契約の解除に基づく現状回復請求又は債務不履行に基づく損害賠償請求として、プラント全体の解体撤去費用相当額の損害賠償金をそれぞれ請求(本訴)した事案、また、原告による請負契約の解除は無効であり、原告は、被告のプラントの工事の進捗を妨害し、そのために被告の債務の履行ができなくなったと主張し、被告が原告に対し、民法536条2項に基づき、請負残代金の支払を請求(反訴)した事案において、原告の被告に対する本訴請求及び被告の原告に対する反訴請求は、いずれも理由がないとして、原告の本訴請求及び被告の反訴請求を棄却した事例。
2016.06.07
損害賠償等請求事件
LEX/DB25447929/東京地方裁判所 平成28年 4月28日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第18469号
原告が、新聞社である被告に対し、被告が発行する新聞の記事に原告の執筆したブログの一部を引用したことが原告の複製権及び同一性保持権の侵害に当たるとともに、原告を取材せずに記事を掲載した行為が不法行為に当たると主張して、損害賠償等を求めた事案において、上記原告記事と被告記載1及び2が表現上共通するのは「重力波と想定される」「波動による(もの)」との部分のみであるが、この部分はEMの効果に関する原告の学術的見解を簡潔に示したものであり、原告の思想そのものということができるから、著作権法において保護の対象となる著作物に当たらないと解するのが相当であるとし、請求を棄却した事例。
2016.06.07
保証債務請求控訴、同附帯控訴事件
(反社会勢力的勢力への融資が後で判明 差し戻し審も保証有効)
LEX/DB25542672/東京高等裁判所 平成28年 4月14日 判決 (差戻控訴審)/平成28年(ネ)第465号
主債務者(E建設)から信用保証の委託を受けた控訴人と保証契約を締結していた被控訴人が、控訴人に対し、同契約に基づき、保証債務の履行を求め、被控訴人の融資の主債務者は反社会的勢力であり、控訴人は、〔1〕このような場合には保証契約を締結しないにもかかわらず、そのことを知らずに同契約を締結したものであるから、同契約は要素の錯誤により無効である、〔2〕被控訴人が保証契約に違反したから、控訴人と被控訴人との間の信用保証に関する基本契約の定める免責事由に該当し、控訴人は、上記保証契約に基づく債務の履行を免れると主張して,被控訴人の請求を争い、原判決は、上記〔1〕につき要素の錯誤は認められない、上記〔2〕につき免責事由に該当するとは認められないとして、被控訴人の請求を認容したので、控訴人がこれを不服として控訴し、被控訴人が附帯控訴して請求を拡張したところ、差戻し前の控訴審は、控訴を棄却するとともに、附帯控訴に基づき、上記の請求拡張部分を認容したため、控訴人が上告受理申立てをし、最高裁判所は、上告審として本件を受理し、上記〔1〕につき要素の錯誤はないが、上記〔2〕は、被控訴人及び控訴人は、上記基本契約上の付随義務として、個々の保証契約を締結して融資を実行するのに先立ち、相互に主債務者が反社会的勢力であるか否かについてその時点において一般的に行われている調査方法等に鑑みて相当と認められる調査をすべき義務を負い、被控訴人がこの義務に違反して、その結果、反社会的勢力を主債務者とする融資について保証契約が締結された場合には、本件免責条項にいう被控訴人が「保証契約に違反したとき」に当たるとして、この点について更に審理を尽くさせるため、差戻し前の控訴審判決を破棄し、高等裁判所に差戻した事案において、被控訴人の本訴請求は、附帯控訴による請求拡張分も含め理由があるとし、控訴を棄却し、附帯控訴を認容した事例。
2016.06.07
損害賠償請求控訴事件(認知症の男性転落死 施設に賠償命令 遺族側逆転勝訴)
★「新・判例解説Watch」H28.7下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25542671/東京高等裁判所 平成28年 3月23日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第5371号
原告(控訴人)らの父P5が、被告(被控訴人)が開設する介護老人保健施設の認知症専門棟に短期入所していたところ、2階食堂の窓から雨どい伝いに降りようとして地面に落下して死亡した事故で、原告らが、父P5の死亡は上記施設における安全配慮義務違反又は上記食堂の窓に係る瑕疵によるものである旨主張し、被告に対し、債務不履行又は不法行為(使用者責任若しくは工作物責任)に基づき、父P5に生じた損害のうち控訴人らの相続分に係る各1177万3741円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、原審は、父P5が上記窓から外に出ることの予見は不可能であったなどとして、被告の責任を否定して原告らの請求を棄却したため、原告らが控訴した事案において、上記2階食堂の窓は、その設置又は保存に瑕疵があったというべきであり、ストッパーによる開放制限措置が通常有すべき安全性を欠いていたことと父P5の死亡との間に相当因果関係があることも認められ、原告らの請求を全て棄却した原判決は一部失当であるとして、原判決を変更した事例。
2016.05.31
損害賠償請求事件
★「新・判例解説Watch」H28.7下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25447956/札幌地方裁判所 平成28年 3月18日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第2188号
東日本大震災に伴い福島第一原子力発電所から放射性物質が放出される事故により福島県内における5店舗の閉店等を余儀なくされた原告が。福島第一原発を設置、運転していた被告に対し、原子力損害の賠償に関する法律3条1項本文に基づき、原子力損害として、〔1〕休業損害7077万3163円、〔2〕9年分(上記事故の10年後まで)の逸失利益10億0608万2962円、〔3〕違約金損害7195万1734円、〔4〕有形固定資産の損害4808万1616円及び弁護士費用5000万円の合計12億4688万9475円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、原告の請求は、〔1〕損害金元本1億8590万9472円と、〔2〕上記〔1〕に対する平成23年3月11日から平成26年5月16日までの確定遅延損害金の残額1648万5888円(〔1〕と〔2〕の合計は2億0239万5360円)、〔3〕上記〔1〕に対する平成26年5月17日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める限度で理由があるとして、請求を一部認容した事例。
2016.05.17
損害賠償請求事件(女性アイドル交際、認める判決)
LEX/DB25542337/東京地方裁判所 平成28年 1月18日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第1759号
芸能プロダクションである原告が、原告との間で専属マネージメント契約を締結した上で原告に所属する女性アイドルであった被告甲、被告甲と交際していたファンである被告乙、に対しては、同契約の債務不履行又は不法行為に基づき、逸失利益等の損害賠償を、被告甲の父母である被告丙夫妻に対しては、信義則上の管理監督義務違反の不法行為に基づき、損害賠償を請求した事案において、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2016.05.10
債務不存在確認等請求本訴,不当利得返還請求反訴事件
LEX/DB25447923/最高裁判所第一小法廷 平成28年 4月28日 判決 (上告審)/平成27年(受)第330号
被上告人らが、死亡共済金及び死亡保険金の各請求権が上告人Y1又はAの各破産財団に属するにもかかわらず、上告人Y1が金員を費消したことは、上告人Y1において金員を法律上の原因なくして利得するものであり、また、上告人Y2には上告人Y1が金員を費消したことにつき弁護士としての注意義務違反があると主張して、上告人Y1に対しては不当利得返還請求権に基づき、上告人Y2に対しては不法行為による損害賠償請求権に基づき、被上告人X1において800万円及び遅延損害金等の連帯支払を、また、被上告人X2において200万円及び遅延損害金等の連帯支払を求め(本訴請求)、上告人Y1が、上記保険金等請求権が上告人Y1の破産財団に属しないにもかかわらず、被上告人X1が法律上の原因なくその一部である1400万円を利得していると主張して、被上告人X1に対し、不当利得返還請求権に基づき、1400万円及び遅延損害金の支払を求め(反訴請求)、原審は、上記保険金等請求権は,破産法34条2項にいう「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものとして、各破産財団に属することになるから、上告人Y1が本件金員を費消したことは、上告人Y1において金員を法律上の原因なくして利得するものであり、また、上告人Y1が本件金員のうち800万円を費消したことについて、上告人Y2に弁護士としての注意義務違反が認められるとして、被上告人らの本訴請求のうち上告人Y1に対する請求を認容するとともに上告人Y2に対する請求を一部認容し、上告人Y1の反訴請求を棄却すべきものとしたため、上告人Y1、同Y2が上告した事案において、当該生命共済契約及び生命保険契約はいずれも本件各開始決定前に成立し、当該生命共済契約に係る死亡共済金受取人は上告人Y1及びAであり、当該生命保険契約に係る死亡保険金受取人は上告人Y1であったから、上記保険金等請求権のうち死亡共済金に係るものは本件各破産財団に各2分の1の割合で属し、上記保険金等請求権のうち死亡保険金に係るものは上告人Y1の破産財団に属するとして、原審の判断は正当として是認することができるとし、上告を棄却した事例。
2016.05.10
立替金等請求控訴事件(安藤・間VS新潟大学)
LEX/DB25542516/東京高等裁判所 平成28年 3月10日 判決 (控訴審)/平成27年(ネ)第3355号
A建設の権利義務を包括的に承継した控訴人が、被控訴人に対し、主位的には、A建設において米国法人であるO社との間で、A建設を買主、O社を売主として、米国ロマリンダ大学の保有する特許技術に係る陽子線がん治療機器等について購入、導入、メンテナンス等を内容とする国立大学の陽子線がん治療センター 物品の購買・設置・メンテナンス及びライセンスに関する基本契約を締結することを前提に、被控訴人との間で、上記契約上のA建設の買主たる地位を被控訴人に譲渡すること、当該譲渡実行日までに上記契約に基づいてA建設が支払い又は負担した売買代金、費用等相当額を被控訴人がA建設に支払うことなどを内容とする合意をし、その後上記契約を締結してその地位を被控訴人に譲渡したと主張して、当該合意の補償請求権に基づき、〔1〕A建設が上記契約に基づいてO社に支払った代金(頭金)、立替金利及び送金等手数料の合計16億7932万6987円並びにこれに対する遅延損害金、〔2〕A建設が負担した費用である7493万5635円及びこれに対する遅延損害金、〔3〕本件訴訟に係る弁護士費用と訴訟提起手数料の合計額1億5442万3795円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、予備的には、被控訴人の副学長兼学長室長が被控訴人の事業の執行として被控訴人学長作成名義の本件合意に係る「損害等補償及び契約上の地位譲渡等に関する合意書」を偽造してこれをA建設に交付したことにより、A建設が上記契約を締結し、上記陽子線がん治療機器等の代金(頭金)を支払うなどの損害を被ったと主張して、不法行為の使用者責任に基づく損害賠償として上記と同額を求め、原審は、上記合意書の被控訴人学長名義部分が真正に成立したと認めることはできず、A建設と被控訴人との間で上記合意が成立したとは認められないから、控訴人の上記合意の補償請求権に基づく請求は理由がなく、また、副学長が上記合意書の被控訴人学長名義部分を偽造したという事情を知らずに上記合意書を締結し、その上で上記契約を締結するに至ったとしても、A建設代表者がそのことを知らなかったことにつき重大な過失があるから、控訴人が使用者責任に基づく損害賠償を請求することはできないなどとして、控訴人の請求をいずれも棄却し、これを不服とする控訴人が控訴した事案において、学長証明書の体裁及び内容が不自然であることに加え,学長証明書と合意書とに押印された印影が異なっているにもかかわらず、合意書の成立の真正に疑いを抱かずに何らの確認をもしなかったA建設の対応をもって、A建設には合意書の成立の真正を信じたことについて重過失があると評価する根拠とした原判決の認定は相当であり、これを不当とする控訴人の上記主張も採用できないとし、控訴人の被控訴人に対する請求はいずれも理由がなく、それらをいずれも棄却した原判決は相当であり、控訴を棄却した事例。
2016.05.10
損失填補請求事件、独立当事者参加事件
(全九州電気工事業厚生年金基金VS日本トラステイ・サービス信託銀行ほか)
LEX/DB25530845/東京地方裁判所 平成27年 7月 3日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第32336号 等
厚生年金基金である原告が、金融機関である被告らに対し、被告らの委託を受けた証券業者が偽装等の不正を行っていたのに、これに気付かずに運用を任せ原告が運用損を被ったのは、原告との間の年金特定信託契約及び三者間合意に基づく被告らの信託事務の処理に任務懈怠(監査報告書確認義務違反、報告説明義務違反、名義登録義務違反)があったことによるものであるとして損害賠償等を求めた事案につき、任務懈怠があるというには、証券業者の運用が明らかに不当で原告に重大な損失が生ずる危険性が高いことを被告らが認識していたか又は容易に認識し得た一方、委託者である原告においてはそれを認識し得なかったのに、被告らが原告にそのことを告げなかったなどの例外的な事情が認められる場合に限られ、本件においてそのような事情は認められず、また被告らがその任務を怠った事実を認めることもできないとして、請求を棄却した事例。
2016.04.26
損害賠償請求事件(日本生命への請求棄却 顧客から詐取 元外交員に賠償命令)
LEX/DB25542103/静岡地方裁判所浜松支部 平成28年 2月 1日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第598号
被告P12に金銭を貸し付けた原告らが、本件各貸付は被告P12の詐欺により行われたものであると主張した上で、被告P12に対しては、不法行為に基づき、被告N生命に対しては、本件各貸付の際に被告N社から契約貸付を受けたと主張する原告らが、被告P12の不法行為は雇用主たる被告N社の事業の執行の範囲に含まれると主張して、使用者責任に基づく等して、それぞれ損害賠償を求めた等の事案において、被告P12は、原告らに対し、真実は借りた金銭を原告らに伝えた用途で使う意思も、約束通り返済する具体的見込みもその能力もないのに、嘘を述べ、原告らにその旨誤信させて本件各貸付を行わせたと認定する一方、被告N社が原告らに対し、被告P12の詐欺行為について使用者責任を負うことはないと示し、原告らが被告P12が被告P13に対して有する不法行為に基づく損害賠償請求権を代位行使することは認めた事例。
2016.04.19
損失填補請求控訴事件
LEX/DB25542150/東京高等裁判所 平成28年 1月21日 判決 (控訴審)/平成27年(ネ)第4127号
厚生年金基金である原告(控訴人)が、原告との間で年金特定信託契約を締結したR信託銀行の承継人である被告(被控訴人)R銀行及び同契約に関する信託事務の処理につき被告R銀行と同一の責任を負うことを三者間で合意した被告(被控訴人)T信託銀行に対し、控訴人との間で年金投資一任契約を締結して被告らに信託財産の運用につき指示した投資一任業者であるAIJが運用実績の偽装等の不正を行っていたのに、これに気付かずにAIJに資産の運用を任せたことにより、原告が約28億6000万円の運用損を被ったのは、原告との間の年金特定信託契約及び三者間合意に基づく被告らの信託事務の処理に任務懈怠(監査報告書確認義務違反、報告説明義務違反、名義登録義務違反)があったことによるものであり、また、被告らの上記任務懈怠は、委託者である原告に対する債務不履行及び不法行為にも当たると主張して、被告らに対し、〔1〕主位的に、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として、連帯して21億円等の金員を控訴人に支払うことを求め、〔2〕予備的に、信託法40条に基づく損失填補として、上記と同額を原告の信託財産に支払うことを求めるとともに、〔3〕被告R銀行に対し、被告R銀行の信託事務の処理には重大な債務不履行があるので、原告は被告R銀行に対する信託報酬の支払義務を負わないと主張して、不当利得返還請求権に基づき、既に支払った信託報酬相当額である452万0764円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、原審は、被告らについて任務懈怠が認められないとして、各請求をいずれも棄却したため、原告が控訴した事案において、原告が当審において主張する監査報告書の確認義務違反及び口座管理に関する説明義務違反はいずれも認められないとし、本件請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、控訴を棄却した事例。
2016.04.19
損害賠償等請求事件
LEX/DB25542149/東京地方裁判所 平成27年12月25日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第23164号
厚生年金基金である原告が、原告との間で年金特定信託契約を締結して信託事務の処理を受託した被告U信託銀行及び上記信託事務の処理を被告U信託銀行と共同受託した被告M信託銀行に対し、被告らが上記年金特定信託契約等に基づいて負う義務を怠ったために、原告が投資一任業者であるAIJによる運用成績の粉飾等の不正にも気付くことができないままに同社に資産の運用を任せたことにより、少なくとも32億9000万円の運用損を被ったと主張して、主位的に、信託法40条1項1号に基づき、連帯して、上記運用損の一部である30億円及びこれに対する遅延損害金を信託財産に損失填補することを求め、予備的に、債務不履行又は不法行為に基づき、連帯して、上記と同額の損害賠償金及び遅延損害金を原告に支払うことを求めた事案において、被告らが信託事務を処理するに当たりその任務を怠った事実を認めることはできないとし、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2016.04.19
根抵当権設定登記抹消登記手続等請求、 貸金請求控訴事件
(山陰合銀訴訟 山陰合同銀行が逆転勝訴)
LEX/DB25542028/広島高等裁判所松江支部 平成28年 1月13日 判決 (控訴審)/平成27年(ネ)第49号
本件各不動産を所有している控訴人会社らが、いずれも根抵当権者である控訴人銀行が本件各不動産について競売による差押えを申し立てた後に被担保債権である各債権を譲り受けた被控訴人会社に対し、主位的に、本件各根抵当権の設定契約の無効を主張した等の根抵当権設定登記抹消登記手続等請求、貸金請求控訴事件の控訴審において、既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには、受働債権につき、期限の利益を放棄することができるというだけでなく、期限の利益又は喪失等により、その弁済期が現実に到来していることを要し、また、時効により消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには、消滅時効が援用された自働債権は、その消滅時効期間が経過する以前に自働債権と相殺適状にあったことを要すると示して、控訴人会社らによる相殺の主張を斥ける等して、原判決を取り消し控訴人会社らの請求を棄却した事例。
2016.04.12
供託金払渡認可義務付等請求事件
LEX/DB25542292/最高裁判所第一小法廷 平成28年 3月31日 判決 (上告審)/平成27年(行ヒ)第374号
宅地建物取引業の免許の有効期間が満了した原告(控訴人・上告人)が、宅地建物取引業法25条1項に基づき供託した営業保証金につき,宅地建物取引業法30条1項に基づき取戻請求をしたところ、東京法務局供託官から、本件保証金の取戻請求権の消滅時効が完成しているとして、上記取戻請求を却下する旨の決定を受けたため、被告(被控訴人・被上告人。国)を相手に、本件却下決定の取消し及び上記取戻請求に対する払渡認可決定の義務付けを求め、原審は、原告の本件却下決定の取消請求を棄却し、本件保証金の払渡認可決定の義務付けの訴えを却下すべきものとしたため、原告が上告した事案において、原告につき宅建業の免許の有効期間が満了し本件保証金の取戻事由が発生したのは平成10年4月1日であるところ、その後原告は取戻公告をしていないため、本件取戻請求権の消滅時効は同日から10年を経過した時から進行し、本件保証金の取戻請求がされたのはその約5年6か月後である同25年9月20日であるから、本件取戻請求権の消滅時効が完成していないことは明らかであるとし、原審の判断には法令違反があるため、原判決を破棄し、本件却下決定は取り消されるべきものであり、上記義務付けの訴えは適法であり、東京法務局供託官が本件保証金の払渡認可決定をすべきであることも明らかで、原告の請求はいずれも理由があるとし、上記取消請求を棄却し上記義務付けの訴えを却下した第1審判決を取消した上、その請求をいずれも認容することとした事例。
2016.04.05
損害賠償等請求控訴事件(新聞の実名報道訴訟 東京高裁)
LEX/DB25542147/東京高等裁判所 平成28年 3月 9日 判決 (控訴審)/平成27年(ネ)第5700号
原告(控訴人)が、被告(被控訴人)らに対し、被告らがそれぞれ発行する日刊新聞の朝刊に掲載された実名による原告の逮捕事実等に関する記事によって名誉を毀損され、名誉感情及びプライバシーを侵害されたとして、共同不法行為に基づく損害賠償として、2200万円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求めるとともに、民法723条に基づき、謝罪広告をそれぞれ掲載することを求め、原判決は、原告の請求を一部認容、一部棄却したため、原告が控訴した事案において、原告の請求のうち、被告d新聞社に対する請求を110万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余の請求をいずれも棄却すべきところ、これと異なる原判決は一部失当であり、控訴の一部は理由があるから、原判決を変更した事例。
2016.03.29
損害賠償請求事件(新入社員歓迎会の2次会でセクハラ 会社と連帯で賠償命令)
★「新・判例解説Watch」H28.4下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25541909/福岡地方裁判所 平成27年12月22日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第3814号
被告会社に派遣社員として入社した原告が、同人らの新入社員歓迎会において、被告会社の従業員である被告甲と一緒にカラオケをしている際、同人から抱え上げられたことにつき不法行為が成立する旨主張し、被告甲に対しては不法行為に基づき、被告会社に対しては職場環境配慮義務違反の債務不履行又は使用者責任に基づき、慰謝料等を請求した事案において、被告甲の行為は、女性である原告の承諾なしに、突然その太腿に触れて持ち上げるというものであり、その結果、他の従業員がいる中で原告のスカートがずり上がる状態になったというのであるから、原告の性的羞恥心を害する行為であったことは明らかであり、故意に原告の人格的利益を侵害し、原告に精神的苦痛を被らせるものと評価できるから、不法行為を構成するとして、原告の請求を一部認容した事例。
2016.03.22
損害賠償請求事件
LEX/DB25447842/最高裁判所第三小法廷 平成28年 3月15日 判決 (上告審)/平成26年(受)第2454号
更生会社であるA社の管財人である原告(控訴人・被上告人)が、A社において、被告(被控訴人・上告人)Y1により組成され被告(被控訴人・上告人)Y2の販売する仕組債を運用対象金融資産とする信託契約を含む一連の取引を行った際、被告らに説明義務違反等があったと主張して、被告らに対し、不法行為等に基づく損害賠償を求め、第1審では請求を棄却し、控訴審では、被告らが、原告に対し、共同不法行為に基づく損害賠償責任を負うべきとして一部認容したため、被告らが上告した事案において、原告の請求は理由がなく、これを棄却した第1審判決は正当であるとして、原判決中被告ら敗訴部分を破棄し、原告の控訴を棄却した事例。
2016.03.15
保険金請求本訴,不当利得返還請求反訴事件
LEX/DB25447821/最高裁判所第二小法廷 平成28年 3月 4日 判決 (上告審)/平成27年(受)第1384号
亡Aの子である上告人が,Aが老人デイサービスセンターの送迎車から降車した際に負った傷害により後遺障害が残ったと主張して、被上告人に対し、上記送迎車に係る自動車保険契約の搭乗者傷害特約に基づき、後遺障害保険金の支払を求め(本訴)、上記特約に基づきAに入通院保険金を支払った被上告人が、その金員の支払について法律上の原因がなかったと主張して,上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,上記金員の返還を求め(反訴)、原審は、上告人の本訴請求を棄却し、被上告人の反訴請求を認容したため、上告人が上告した事案において、Aは本件特約に基づく入通院保険金及び後遺障害保険金の各請求権を有しているとはいえないから、上告人の本訴請求を棄却し、被上告人の反訴請求を認容すべきものであるとし、原審は、上記事故が老人デイサービスセンターの職員が安全配慮義務を怠ったことから発生したものであるとして直ちに本件における運行起因性を否定しており、この点の説示に問題はあるが、結論自体は是認することができるとし、上告を棄却した事例。