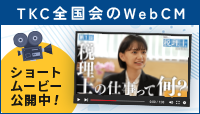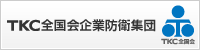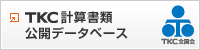寄稿
「租税正義の実現」を目指して──中小企業の存続と発展に資する3つの緊急政策提言
TKC全国政経研究会(政経研)では、令和8年度の「税制改正等要望書」を取りまとめました(記事最下部の「令和8年度税制改正等要望“重点事項”」を参照)。
その重点事項を踏まえて、本号では令和7年6月19日に開催された、自由民主党TKC議員連盟総会において政経研が行った3つの緊急政策提言に絞って、その内容や背景をお伝えしたいと思います。
中間申告の回数が11回(毎月)となる事業者の対象を(直前の課税期間の消費税額) 4,800万円(地方消費税込みで6,153万8,400円)超から※60万円(地方消費税込みで76万9,200円)超に引き下げ、これを原則とする。
※消費税の新規発生滞納53万4,132件、4,382億6,200万円(国税庁令和5年度統計年報)、その平均滞納額が約82万円であることから最低限これをカバーすることを想定。

TKC全国会会長・
TKC全国政経研究会会長
坂本孝司
現状、わが国では、課税期間の消費税額400万円/月(国税のみ)以上の事業者のみが、毎月申告の対象事業者とされていますが、諸外国では異なる状況にあります(出典:経済産業省「各国・地域の税制概要とホットトピックス」)。
一例を挙げるとドイツでは、消費税額約10万円/月以上の事業者(前年度の納税額が7,500EUR=約122万円)を超える場合、または事業を開始して間もない場合は、毎月(中間)申告をする必要があります。
また、フランスでは、毎月申告・納付が原則となっています。ただし、年間売上高が4,000EUR=約65万円未満となるVAT(付加価値税)登録事業者は、四半期ごとの課税期間が認められています(約5万円/月以上の事業者)。
なお、中間申告は、直前の課税期間の確定消費税額を基準とする予定申告方式(消法42①)の他、仮決算方式による申告方式(消法43)を選択できるものとし、「適時に、正確な会計帳簿」に基づく仮決算方式を採用した場合は、何らかのインセンティブ措置を講ずることとします。
今般、政経研として消費税の毎月納付について提言を行う背景には、消費税の滞納の問題が挙げられます。消費税滞納金額は、ピーク時(平成10年度)に比べれば減少しているというものの、足下の令和元年度以降では増加傾向にあります。国税庁令和5年度統計年報「4 国税徴収・国税滞納・還付金」によれば、令和5年度における消費税の期首滞納は3,409億1,300万円、新規発生滞納件数と滞納税額(53万4,132件、4,382億6,200万円)は、法人税(7万8,489件、1,001億1,800万円)と比べると、滞納税額で約4.3倍と大きく上回っています。
消費税は、預り金的性格を有するため、わが国におけるこのような現状は、「租税正義の実現」の観点からも極めて憂慮されます。そこで、消費税を毎月納付する事業者の対象を広げることによって、次のような効果が見込まれます。
(1)納税資金確保の習慣化
消費税は、預り金的な性格を有するため、事業者にとって年1、2回ないし4回程度の納付では、1回当たりの納税資金の負担が大きくなります。また、事業者は、毎月納付することにより、資金繰りや納期を管理しやすくなります。
(2)税金滞納による融資謝絶と倒産等の防止
国税、地方税の滞納がある場合は、原則、金融機関からの融資を受けられません。結果、その時点で倒産等に至るケースが多く、これらを事前に防ぐことができます。
(3)「月次決算」体制構築による健全経営の遂行
仮決算方式により消費税を毎月申告・納付することは、事業者が月次決算を実施する動機付けになり、ひいては、経営改善や経営革新にも繋がります。
(4)徴税コストの軽減
毎月納付とすれば、国税当局は滞納を早めに把握でき、速やかな対応が可能となり、結果、徴税コストの軽減に繋がります。
ちなみに、仮決算方式を採用した際のインセンティブの例としては、①納税準備預金や納税貯蓄組合預金と同様の非課税措置を利用できるようにする②「優良な電子帳簿(主要簿のみ)」を利用して、適時に、正確な会計帳簿を作成、それを基に仮決算方式を採用した際は、※電子帳簿保存法の過少申告加算税の軽減措置のような措置を講じる──などが挙げられます(※電子帳簿保存法8条④)。
金融機関が中小企業者に一定額以上を融資する場合には、決算書の他、「中小会計要領チェックリスト(日本税理士会連合会)」等を付することを要求し、税理士による一定の信頼性付与を明らかにすることとする。
わが国の中小企業等が準拠すべき会計ルールが存在することを今一度、経営者自身はもとより、中小企業の主な利害関係者である金融機関が認識することが重要です。具体的には、「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」等がそれにあたり、中小会計要領等に準拠した計算書類の作成及び活用は、中小企業等経営強化法によって次の通り定められています。
○中小企業等の経営強化に関する基本方針 (平成十七年五月二日)
(総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国士交通省告示第二号)
改正 平成二四年八月三○日総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国士交通省
(略)令和三年七月三十日厚生労働省、経済産業省告示第一号 産業競争力法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行に伴い、及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三条第一項の規定に基づき、中小企業等の経営強化に関する基本方針を次のように定めたので、同条第四項の規定に基づき公表する。
(略)
第3 経営革新
1 経営革新の内容に関する事項
(略)
3 海外において経営革新のための事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営革新の促進に当たって配慮すべき事項 (略)
四 信頼性のある計算書類等の作成及び活用の推奨
国や都道府県は、中小企業に会計の定着を図り、会計の活用を通じた経営力の向上を図ることに加え、中小企業が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力を向上させ、中小企業の財務経営力の強化を図ることが、経営革新の促進のために重要であるとの観点から、中小企業者に対し、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用を推奨する。
(傍線追加)
このような法的バックボーンを備えている中小会計要領等の普及状況は次の通りです。日本税理士会連合会「第7回税理士実態調査報告書(2025年)」によると、関与先における「中小企業の会計に関する基本要領」の適用割合は39.2%で、適用していないは37.8%。一方、「中小企業の会計に関する指針」の適用割合は23.0%となっており、いずれかの適用割合は60%超となっています。なお、TKC全国会会員事務所による中小会計要領等の適用企業数は37万506件に及んでいます(2025年4月末時点)。
ここで、ドイツにおける中小企業金融と「年度決算書の信頼性」確保の仕組みを紹介しておきます。
ドイツでは1961年に信用制度法(Kreditwesengesetz)が公布され、同法は金融機関に対して、1万ドイツマルク以上の無担保無保証融資について、融資先企業の年度決算書の徴求義務を課しました(第18条)。続けて連邦金融制度監督局は、かかる年度決算書の信頼性を担保するため、経済監査士・帳簿監査士・税理士による証明書(Testierung)の添付を求める旨の通知を発出しました(1964年3月11日付け)。その後2002年に「年度決算書の信頼性」に関して、ドイツ全土の貯蓄銀行やその他の金融機関が次の要望書を出しました。
「帳簿記帳に基づく数字がそれ自体として蓋然性があることの説明を、作成された年度決算書に付すこと」
この要望書によって、格付けプロセスの一環として銀行に提出される一切の年度決算書を、税理士は少なくとも蓋然性に関して監査することになりました。その後、証明書の作成基準が策定され、2010年の連邦税理士会の「年度決算書の作成に関する諸原則についての連邦税理士会の声明」に至っています。このような経緯を経て、ドイツでは税理士あるいは経済監査士による決算証明書(ベシャイニグング:Bescheinigung)作成業務が定着しているのです。
この点について、畑中龍太郎金融庁監督局長(当時)は、2011年7月に開催された第38回TKC全国役員大会の特別講演「地域金融機関における地域密着型金融の推進と税理士に期待する役割」の中で、次のように述べています。
ドイツには、税理士が顧客企業の帳簿や財産目録について包括的な監査等を実施した上で決算書を作成し、証明書を発行することにより、税理士自らが決算書の内容を保証する「ベシャイニグング」という制度があると承知しています。金融機関は、税理士の証明書が発行された決算書に基づいて経営状態を開示した企業に対してのみ、不動産担保又は連帯保証人による保証のない75万ユーロ超の信用供与が認められているそうです。これは、ドイツの信用制度法(日本の銀行法にあたるもの)によるものでありますが、法的にも、税理士により保証された決算書の信用性が認められており、金融機関による顧客企業に対する信用供与に際して、税理士の果たすべき役割や責務は大きくなっています。
これを一言で言えば、金融機関が融資をするときに、「この企業は大丈夫ですよ」という税理士による決算書の保証書があれば、お金を貸せる。つまり、企業の信用リスクをカバー(補完)する機能が法的にも確立しているということです。 (『TKC会報』2011年9月号)
日本においては、ドイツの「ベシャイニグング」に代わる証明書として、日本税理士会連合会が作成した「中小会計要領チェックリスト」等を金融機関が自主的かつ積極的に活用することを提言します(「ベシャイニグング」の詳細は、坂本孝司著『ドイツにおける中小企業金融と税理士の役割』(中央経済社)第4章及び同編著『ドイツ税理士による決算書の作成証明業務』(TKC出版)を参照)。
中小企業の経営力強化のため、中小企業支援策に認定支援機関を活用する。
(1)「決算報告会」の開催と金融機関との顔の見える関係構築
認定支援機関である金融機関と税理士が「決算報告会」を通じて、これから成長する見込みのある地域の中小企業を支援する。「決算報告会」を行う中小企業者に一定の補助を行う。
(2)経営力向上に取り組む中小企業に対する支援制度の創設
中小会計要領等に準拠した決算書の作成、月次決算、年度予算計画の策定、業績検討会の実施といったモニタリング体制の構築を認定支援機関と連携して行い、ミラサポ等を通じて報告することを認定要件とした、業績管理を通じた中小企業の黒字化支援の制度を創設する。認定された事業者は、計画期間中の設備投資減税や資金繰り支援、補助金における優先採択、生成AIやデジタルインボイス導入等のデジタル化支援などを受けられるようにし、経営力向上に向けての一層の動機づけを図る。
(3)表彰制度の創設
中小企業等経営強化法第14条の経営革新計画の認定事業者の拡大を図るため、認定事業者を表彰する制度を創設し、その特典として設備投資減税の割増や低利融資制度等の優遇措置の拡充を図る。
認定支援機関制度は中小企業経営力強化支援法(平成24年6月21日成立)によって創設されました。これは経営支援における担い手の多様化・活性化を図る制度的措置であり、商工会等の支援機関に加え、中小企業に対して高度かつ専門的な経営支援を行う金融機関や税理士事務所等が取り込まれました。そして、第二次安倍政権時に中小企業等経営強化法へ改正(平成28年7月1日施行)され、現在に至っています。
○中小企業等経営強化法 (平成十一年三月三十一日法律第十八号)
(略)令和五年法律第六十一号改正
(略) (認定経営革新等支援機関)
第三十一条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
2 前項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。 (略)
一 経営革新又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析 二 経営革新のための事業又は経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
(傍線追加)
このような目的で創設された認定支援機関制度は、多くの士業、商工会・商工会議所、金融機関等が認定を受けている日本で唯一の認定制度となっています。
現在、認定支援機関登録総数は3万6,589件(令和7年4月22日公表)、そのうち最も件数の多い税理士・税理士法人が2万4,743件に上っており、中小企業者の伴走支援にもっと有効に活用されるべきと考えます。
TKC全国政経研究会による
「令和8年度税制改正等要望“重点事項”」
- (1)税務に関するQ&Aの中立性の確保
- (2)複式簿記に係る帳簿等の信頼性向上(帳簿のトレーサビリティの確保等)のための法環境の整備
商法及び会社法に規定されている適時記帳の要件(適時に、正確な会計帳簿を作成すること)を、法人税法にも明文化する。(途中省略)、この適時記帳の要件は納税者の(帳簿の証拠力を高めるという)利益のために設けられるものであって、これに違反してもそれのみで処罰するというものではない。これは諸外国においても同様である。- (3)優良な電子帳簿の普及・一般化のための措置 ※トレーサビリティの確保は主要簿(仕訳帳と総勘定元帳)に限定する。
- (4)人的控除のあり方
人的控除は、日本国憲法第25条「生存権の保障」の租税法における具現化であることを尊重したうえで、税額控除とするなど所得控除制度について抜本的な見直しを行う。特に、基礎控除は、「生存権の保障」の観点から、インフレやデフレ等に応じた控除額の変動はあっても所得に応じて金額を変えるべきではない。また、配偶者控除及び配偶者特別控除は、これらの控除に代えて配偶者の所得と本人の所得税負担とを切り離した制度(例えば、世帯控除)を新設する。- (5)確定決算主義の採用をすべての企業について継続し、堅持する。
- (6)事業承継税制の見直し
- (7)消費税の毎月納付
- (8)償却資産に対する課税制度の見直し
- (9)「中小会計要領チェックリスト」等の活用(金融機関による決算書への添付の要請と定着化)
- (10)政治資金の適正化・透明化(附帯決議の早期実現)
「適時に正確な会計帳簿の作成や、複式簿記の導入」の早期実現を求める。なお、政治資金の収支報告書の記載内容については、寄付者の住所は非表示とするなど個人情報に配慮するよう見直す。
(会報『TKC』令和7年8月号より転載)