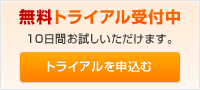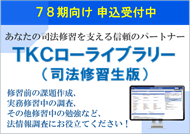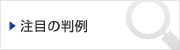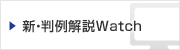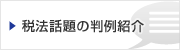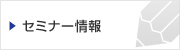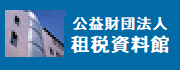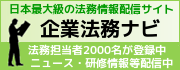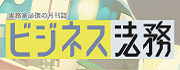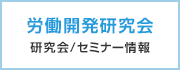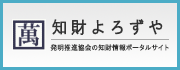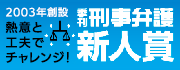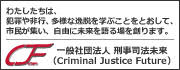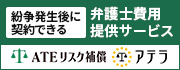2016.09.27
運賃変更命令等差止請求事件(格安タクシー規制 青森のタクシー会社 勝訴)
LEX/DB25543399/青森地方裁判所 平成28年 7月29日 判決 (第一審)/平成27年(行ウ)第6号
原告(タクシー事業者)が、東北運輸局長から、〔1〕本件届出運賃が本件公定幅運賃の範囲内にないことを理由として、〔ア〕特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法17条の3第1項所定の輸送施設の使用停止処分及び〔イ〕同法16条の4第3項所定の運賃変更命令を受けるおそれがあり、〔2〕さらに、同命令に違反したことを理由として、〔ア〕使用停止処分及び〔イ〕同法17条の3第1項所定のタクシー事業許可取消処分を受けるおそれがあるなどと主張して、行政事件訴訟法37条の4第1項の規定により、被告(国)に対し、本件各処分の差止めを求めた事案において、運賃変更命令の差止めを求める原告の請求を認容し、本件訴えのうちその余の請求に関する部分は、却下した事例。
2016.08.23
地位確認等請求控訴事件(参院選差し止め訴えは不適法)
LEX/DB25543116/東京高等裁判所 平成28年 6月 2日 判決 (控訴審)/平成28年(行コ)第21号
参議院議員通常選挙の選挙人となることが予定されている原告ら(控訴人)が、参議院選挙区選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法の定めは、憲法の定める代議制民主制等に違反しているなどとして、原告らが人口に比例して配分された法律に基づいて投票をすることができる地位にあることの確認等を求めたところ、訴えが却下されたため、控訴した事案において、国会が具体的な選挙制度を決定する前に、裁判所が「平等に配分された状態」を示す具体的な選挙制度の内容等を定め、有権者がそれに基づく選挙権の行使をする権利を有することの確認をするようなことは、三権分立の趣旨に反するとし、控訴を棄却し、追加請求に係る訴えを却下した事例。
2016.08.09
請負代金等請求本訴事件(本訴事件)、違約金請求反訴事件(反訴事件)
(F15戦闘機契約解除を巡り 違約金支払い命令)
LEX/DB25543078/東京地方裁判所 平成28年 3月18日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第24885号 等
原告(T社)が、被告(国)に対し、F-15戦闘機を母体とする偵察機を用いた偵察システムを構成する装置等を調達することを内容とする請負契約に基づきDBRP(光学・赤外線偵察ポッド)を製造して被告に納入する義務が被告の帰責事由により履行不能になったと主張して、危険負担の債権者主義に基づき、DBRPの代金の支払を求めた(本訴請求)事案と、被告が、原告に対し、上記偵察システム等契約は、原告が同意内容どおりのDBRPを製造しなかったため、原告の帰責事由によりその全部が履行不能により解除されたと主張して、違約金の支払を求めた(反訴請求)事案において、DBRPを被告に納入する義務が履行不能になったことにつき、原告に帰責事由があり、当該債務不履行を理由に、上記偵察システム等契約は解除されたとして、本訴請求を棄却し、反訴請求を認容した事例。
2016.07.26
鳴門市競艇従事員共済会への補助金違法支出損害賠償等請求事件
LEX/DB25448064/最高裁判所第二小法廷 平成28年 7月15日 判決 (上告審)/平成25年(行ヒ)第533号
鳴門競艇従事員共済会から鳴門競艇臨時従事員に支給される離職せん別金に充てるため、鳴門市が平成22年7月に共済会に対して補助金を交付したことが、給与条例主義を定める地方公営企業法38条4項に反する違法、無効な財務会計上の行為であるなどとして、市の住民である上告人らが、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、被上告人市長を相手に、当時の市長の職にあった者に対する損害賠償請求をすることを求めるとともに、被上告人市公営企業管理者企業局長を相手に、当時の市の企業局長及び企業局次長の各職にあった者らに対する損害賠償請求、当時の市企業局競艇企画管理課長の職にあった者に対する賠償命令並びに共済会に対する不当利得返還請求をすることを、それぞれ求めた住民訴訟で、原判決は、離職せん別金が退職金としての性格を有し、本件補助金の交付が実質的に臨時従事員に対する退職金支給としての性格を有していることは否定できないが、臨時従事員の就労の実態が常勤職員に準じる継続的なものであり、退職手当を受領するだけの実質が存在すること等からすれば、本件補助金の交付が給与法定主義の趣旨に反し、これを潜脱するものとはいえず、本件補助金の交付に地方自治法232条の2の定める公益上の必要性があるとの判断が裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものであるとは認められないから、本件補助金の交付が違法であるということはできないとし、上告人らの請求を棄却したため、上告人らが上告した事案において、職権による検討で、原判決のうち請求を棄却すべきものとした部分には明らかな法令の違反があるとし、当該部分につき、原判決を破棄し、第1審判決を取消し、上記請求に係る訴えを却下し、A、B、C及びDの各損害賠償責任の有無並びに共済会の不当利得返還債務の有無につき更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻すこととした事例。
2016.07.26
鳴門市競艇従事員共済会への補助金違法支出損害賠償等請求事件
LEX/DB25448065/最高裁判所第二小法廷 平成28年 7月15日 判決 (上告審)/平成26年(行ヒ)第472号
鳴門競艇従事員共済会から鳴門競艇臨時従事員に支給される離職せん別金に充てるため、鳴門市が平成23年11月から同24年6月にかけて共済会に対して補助金を交付したことが、給与条例主義を定める地方公営企業法38条4項に反する違法、無効な財務会計上の行為であるなどとして、市の住民である上告人らが、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、被上告人市長を相手に、当時の市長の職にあった者に対する損害賠償請求をすることを求めるとともに、被上告人市公営企業管理者企業局長を相手に、当時の市の企業局長の職にあった者に対する損害賠償請求及び共済会に対する不当利得返還請求をすることを、それぞれ求めた住民訴訟で、原審は、「鳴門市モーターボート競走事業に従事する臨時従事員の給与の種類及び基準に関する条例」の制定経過も踏まえた上で、同条例附則2項及び改正条例附則2項の定めを解釈すれば、平成25年3月26日までに支払われた臨時従事員の退職手当について、鳴門市モーターボート競走事業に従事する臨時従事員の給与の種類及び基準に関する条例12条が遡及的に適用されることは明らかであり、離職せん別金は、市から臨時従事員に直接支払われるものではないが、上記条例の立法趣旨が離職せん別金の支給につき条例上の根拠を明確にする点にあることは、上記条例の制定経過からみて明らかであり、本件補助金を介して支払われた実質的な退職手当としての性格を有する離職せん別金についても、同条は適用され、また、上記条例は、地方公営企業法38条4項にいう「給与の種類及び基準」を定めたものということができるとして、本件補助金を介して支払われた離職せん別金には遡って同項にいう条例の定めがあったことになり、本件補助金の交付は適法であるとし、上告人らの請求(Aによる予算の調製を違法な財務会計上の行為として同人に対し損害賠償請求をすることを求めた請求を除く。)をいずれも棄却したため、上告人らが上告した事案において、原審の判断には明らかな法令の違反があるとし、原判決中、上告人らの請求を棄却した部分は破棄し、A及びEの各損害賠償責任の有無並びに共済会の不当利得返還債務の有無につき審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻すこととした事例。
2016.07.05
不当利得返還等請求行為請求事件
LEX/DB25448026/最高裁判所第三小法廷 平成28年 6月28日 判決 (上告審)/平成25年(行ヒ)第562号
京都府内に主たる事務所を有する特定非営利活動法人である被上告人が、平成14年度から同18年度までの間に、府が京都府議会の4会派に対し、会派運営費として補助金を交付したことは違法であるから、上記各会派は府に対して上記補助金に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに、上告人はその返還請求を違法に怠っているなどとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、上告人に対し、上記各会派に対して上記不当利得の返還請求をすべきこと等を求めたところ、原審は、被上告人の請求を一部認容したため、上告人が上告した事案において、会派運営費について、地方自治法100条旧12項の「調査研究に資するため必要な経費」以外の経費を対象とするものであるか否か、また、仮にそのように認められる場合に地方自治法232条の2に定める「公益上必要がある場合」の要件を満たすものであるか否かについて判断することなく、会派に対する補助金の交付であることをもって直ちにこれを同法100条旧12項及び232条の2に反し違法であるとした原審の判断には法令の違反があるとし、原判決のうち上告人敗訴部分を破棄し、同部分につき原審に差し戻した事例。
2016.07.05
不当利得返還等を求める住民訴訟事件
LEX/DB25448022/最高裁判所第一小法廷 平成28年 6月27日 判決 (上告審)/平成26年(行ヒ)第321号
大洲市が大洲市土地開発公社との間で土地の売買契約を締結し、これに基づき市長が売買代金の支出命令をしたところ、市の住民である被上告人(1審原告)らが、上記売買契約の締結及び上記支出命令が違法であるなどとして、市の執行機関である上告人(1審被告。大洲市長)を相手に、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、上記売買契約の締結及び上記支出命令をした当時の前市長の相続人らに対して不法行為に基づく損害賠償の請求をすること等を求めた住民訴訟で、原判決が、売買契約のうち隣接地に係る部分に財務会計法規上の違法はないとする一方で、同契約のうち土地に係る部分につき、前市長の相続人らに対する損害賠償の請求を求めた被上告人らの請求を一部認容すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、上記公社との間で本件売買契約を締結した前市長の判断は、その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法ではなく、前市長は、市に対して損害賠償責任を負わないとし、これと異なる原判決は法令の違反があるとし、原判決中上告人敗訴部分を破棄し、同部分に関する被上告人らの請求はいずれも理由がなく、同部分につき第1審判決を取消し、同請求をいずれも棄却した事例。
2016.06.28
県営路木ダム事業に係る公金支出差止等請求控訴、同附帯控訴事件
★「新・判例解説Watch」H28.8下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25542900/福岡高等裁判所 平成28年 4月25日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第17号 等
熊本県の住民である原告(被控訴人)らが、治水及び利水の必要を欠くなど路木川河川総合開発事業路木ダム建設事業は違法であり、同事業に係る契約の締結又は債務その他の義務の負担行為並びに公金の支出も違法であると主張して、熊本県の執行機関である被告(控訴人)に対し、〔1〕地方自治法242条の2第1項1号に基づき上記支出等の差止めを求めるとともに、〔2〕同法242条の2第1項4号本文に基づき、熊本県知事は本件支出等をしてはならない財務会計法規上の義務を負っていたにもかかわらずこれを怠って上記事業を継続し、その結果、平成20年4月1日から同25年11月20日までの間に上記事業に係る事業費として計19億9037万0293円を支出させ、同額相当の損害を熊本県に被らせたとして県知事に対し損害賠償請求をすることを求めた住民訴訟で、原判決は、上記差止請求のうち、原審の口頭弁論の終結日である平成25年11月20日までに終了した上記支出等の差止めを求める部分を不適法として却下し、判決確定時までに支払義務が生じた公金の支出を除く部分の差止めを認め、損害賠償請求を含むその余の請求をいずれも棄却したため、被告が上記差止請求の敗訴部分を不服として控訴し、他方、原告らが原判決中の敗訴部分のうち上記損害賠償請求に係る部分を不服として附帯控訴した事案において、原告らの請求のうち、当審の審判対象である判決確定後の事業支出に係る上記差止請求は訴えの利益を欠くから不適法であり却下を免れないとし、また、上記損害賠償請求は理由がないので棄却すべきであり、これと一部異なる原判決は失当であるとして、被告の本件控訴に基づき原判決中被告の敗訴部分を取り消し、他方、原告らの本件附帯控訴をいずれも棄却した事例。
2016.05.24
原爆症認定義務付等請求控訴事件
LEX/DB25542386/大阪高等裁判所 平成28年 2月25日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第102号
被爆者援護法1条所定の被爆者である亡P2(原審係属中の平成23年7月15日に死亡し、亡P2の妻である被控訴人P3並びに亡P2と被控訴人P3との間の子である被控訴人P18(長女)及び被控訴人P19(長男)が亡P2の有する一切の権利義務を共同相続し、亡P2の訴訟手続を受継)が、平成20年3月6日に被爆者援護法11条1項の規定による認定の申請(本件P2申請)をしたところ、厚生労働大臣が平成22年8月26日付けで本件P2申請を却下する旨の処分をしたことから,亡P2が控訴人(国)に対し、本件P2却下処分の違法を主張して、本件P2却下処分の取消し及び本件P2申請に係る原爆症認定の義務付けを求めるとともに、本件P2却下処分が国家賠償法上違法であり、これにより亡P2が精神的苦痛を受けた旨主張して、300万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、原審は、被控訴人らの請求のうち、本件P2却下処分の取消請求及び本件P2申請に係る原爆症認定義務付け請求を認容し、その余の請求を棄却したため、控訴人が自己の敗訴部分を不服として控訴した事案(原審では、亡P1訴訟承継人原審第2事件原告P4の控訴人に対する第2事件に係る訴えが第1事件と併合審理され、原判決で第2事件についても判断が示されたが、亡P1訴訟承継人原審第2事件原告P4及び控訴人がいずれも控訴ないし附帯控訴しなかったため、原判決中、第2事件に関する部分は確定)において、被控訴人の訴えのうち、本件P2申請に係る原爆症認定の義務付けを求める部分は不適法であり、本件P2却下処分取消請求は理由がないところ、これと結論を異にする原判決主文第2項及び第3項は失当であるとし、原判決主文第2項及び第3項を取消して、被控訴人らの訴えのうち、本件P2申請に係る原爆症認定の義務付けを求める部分を却下し、被控訴人らのその余の請求を棄却した事例。
2016.05.17
損害賠償請求控訴事件(緑のオーナー訴訟 控訴審)
★「新・判例解説Watch」H28.6上旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25542349/大阪高等裁判所 平成28年 2月29日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第3086号
国有林野に成育している樹木の共有持分を国以外の者に譲渡し、その費用負担者から持分の対価及び当該樹木について国が行う保育及び管理(育林)に要する費用の一部の支払を受け、育林による収益を国と費用負担者が分収するという分収育林制度(緑のオーナー制度)に関し、被告と分収育林契約を締結した費用負担者又はその承継人である原告らが、被告に対し、被告の担当者の違法な勧誘によって分収育林契約を締結し、払込額に相当する損害を被ったとして、主位的に国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権に基づき、予備的に不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求権に基づき、各「損害額元本」及び「弁護士費用」の賠償並びに損害額元本に対する「確定遅延損害金」及び遅延損害金の支払を求め、原審が、原告らの請求を一部認容・一部棄却、原告らの請求を全部棄却したため、原告ら及び被告の双方が控訴をした事案において、原判決は、一部異なる限度で相当ではないとし、(1)「認容額一覧表1」及び「認容額一覧表2」の各「原告氏名」欄記載の原告らの控訴に基づき、原判決主文1、2項中同原告らに関する部分を変更し、(2)被告の控訴に基づき、一部原告らに関する被告敗訴部分を取消し、同原告らの請求を棄却し、(3)被告の控訴に基づき、原告亡P4訴訟承継人P5(原告番号54)に関する部分を変更し、(4)その余の原告らの控訴及び被告のその余の控訴を棄却した事例。
2016.03.22
個人情報一部不開示決定処分取消等請求事件
★「新・判例解説Watch」H28.5下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25447829/最高裁判所第一小法廷 平成28年 3月10日 判決 (上告審)/平成27年(行ヒ)第221号
被上告人が、京都府個人情報保護条例に基づき、実施機関である京都府警察本部長(処分行政庁)に対し、被上告人の子が建物から転落して死亡した件について京都府警察田辺警察署において作成又は取得した書類等一式に記録されている自己の個人情報の開示請求をしたところ、処分行政庁から、その一部を開示する旨の決定を受けたため、上告人を相手に、当該処分のうち各不開示部分の取消しを求めるとともに、当該各不開示部分に係る個人情報の開示決定の義務付けを求めた事案の上告審において、本件取消しの訴えが出訴期間を経過した後に提起されたことにつき行政事件訴訟法14条1項ただし書の「正当な理由」があるということはできないとし、原判決を破棄し、本件取消しの訴え及び本件義務付けの訴えはいずれも不適法であって、これらを却下した第1審判決は正当であるから、被上告人の控訴を棄却した事例。
2016.03.08
慰謝料請求事件(NZ地震 富山市市長の発言めぐり賠償命令)
LEX/DB25541788/富山地方裁判所 平成27年11月25日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第41号
平成23年2月22日に発生したニュージーランドでの地震により死亡した学生らの親である原告らが、各自、被告富山市に対し、定例記者会見における富山市長の発言により、原告らの名誉が毀損されたと主張して、国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき、慰謝料等の支払を求めた事案において、本件発言3のうち「この間訳の分からない失礼な文章で面会をしたいというお手紙が来たから、即断りました。物事の節度、有り様、礼儀というものをわきまえない手紙でしたよ。」という発言は、一般人の普通の注意と読み方又は聴き方を基準にすると、D市長宛てに本件遺族らから面会を求める手紙が来たという事実を基礎に、同手紙は、物事の節度、有り様及び礼儀というものをわきまえない手紙であったという論評を表明するものであり、原告らの社会的評価を低下させるものである等として、原告らの請求をそれぞれ一部認容した事例。
2016.02.23
輸送施設使用停止命令並びに運賃の変更命令差止請求事件
★「新・判例解説Watch」H28.3中旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25541777/大阪地方裁判所 平成27年11月20日 判決 (第一審)/平成26年(行ウ)第86号
特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の準特定地域に指定された大阪市域交通圏においてタクシー事業を営む原告が、近畿運輸局長から、原告の届け出た運賃が一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項の規定により指定された運賃の範囲内にないことを理由として、一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法17条の3第1項に基づく輸送施設使用停止処分及び一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条の4第3項に基づく運賃の変更命令を受けるおそれがあり、さらに、運賃変更命令に違反したことを理由として、同法17条の3第1項に基づく使用停止処分及び事業許可取消処分を受けるおそれがあるなどと主張して、被告(国)に対し、各処分の差止めを求めた事案において、不適法な請求を却下したうえで、公定幅運賃の下限額は合理性を欠くもので違法であるとして、請求を認容した事例。
2016.02.23
不開示決定処分取消等請求事件(官房機密費の一部開示命じる 大阪地裁)
LEX/DB25541711/大阪地方裁判所 平成27年10月22日 判決 (第一審)/平成26年(行ウ)第186号
行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき内閣官房報償費の支出に関する行政文書(政策推進費受払簿、支払決定書、出納管理簿、報償費支払明細書及び領収書等)の開示を求めた原告が、内閣官房内閣総務官から一部不開示決定を受けたことから、前記決定のうち一部の期間の支出に関する行政文書の不開示決定部分につき、その取消しを求めるとともに、行政事件訴訟法3条6項2号所定の義務付けの訴えとして、前記不開示決定部分に係る文書について開示決定の義務付けを求めた事案において、原告の請求を一部認容した事例。
2016.02.02
都市計画決定無効確認等請求事件(「外環の2」道路計画 住民の訴え却下)
LEX/DB25541629/東京地方裁判所 平成27年11月17日 判決 (第一審)/平成20年(行ウ)第602号
都市計画決定に係る都市計画施設である外環の2(幹線街路外郭環状線の2)の区域内に不動産を所有して居住していた承継前原告Aから同不動産を相続した原告らが、外環の2に係る都市計画は、外環本線(都市高速道路外郭環状線)の構造形式が嵩上式(高架式)であることを基礎となる重要な事実としていたところ、平成19年外環本線変更決定において外環本線の構造形式が嵩上式から大深度地下方式に変更されたことにより、当該都市計画は重要な事実の基礎を欠くこととなって違法なものになったなどとして、〔1〕行政事件訴訟法3条4項所定の無効等確認の訴えとして、都市計画決定が無効であることの確認を求め、〔2〕行政事件訴訟法3条6項1号所定のいわゆる非申請型の義務付けの訴えとして、都市計画の廃止手続の義務付けを求め、〔3〕行政事件訴訟法4条所定の公法上の法律関係に関する確認の訴えとして、(a)都市計画が違法であることの確認、(b)原告らが上記不動産について都市計画法53条1項の規定する建築物の建築の制限を受けない地位にあることの確認、及び、(c)被告が都市計画の廃止手続をとらないことが違法であることの確認を求めるほか、承継前原告Aから上記不動産以外の全ての遺産を相続した原告Bが、〔4〕承継前原告Aにおいて、外環の2に係る都市計画の廃止義務の懈怠という被告による不作為の違法な公権力の行使により、承継前原告Aが、上記不動産を収用されるという不安を抱いたり、同項の規定する建築物の建築の制限等がされたりして、財産権(憲法29条1項)、居住の自由(憲法22条1項)及び平穏に生活する自由(憲法13条)を侵害されたことにより、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料100万円及びこれに対する遅延損害金の支払請求権を有していたところ、これを相続したとしてその支払を求め、〔5〕少なくとも平成19年外環本線変更決定において外環本線の構造形式が嵩上式から大深度地下方式に変更されたことにより、外環の2に係る都市計画の根拠とされた公共的必要性が消滅し、都市計画決定に伴う都市計画法53条1項の規定する建築物の建築の制限が承継前原告Aに対して特別な犠牲を課すものとなったため、承継前原告Aが、憲法29条3項に基づき、建築物の建築の制限による土地の価格の下落分2118万円の損失補償の請求権を有していたところ、これを相続したとして当該損失補償及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、各訴えのうち、都市計画決定の無効確認を求める訴え、都市計画の廃止手続を求める訴え、都市計画の違法確認を求める訴え、原告らが都市計画法53条1項の規定する建築制限を受けない地位にあることの確認を求める訴え及び都市計画決定の廃止手続をとらないことの違法確認を求める訴えを、いずれも却下し、原告Bのその余の請求をいずれも棄却した事例。
2016.01.12
執行停止申立事件(「育休退園」 執行停止 判決でるまで復園認める)
LEX/DB25541441/さいたま地方裁判所 平成27年 9月29日 決定 (第一審)/平成27年(行ク)第17号等
所沢市内の保育所に通園している甲の保護者である申立人が、甲について、所沢市長から、保育の利用継続不可決定及び保育の利用解除処分がそれぞれされたことについて、各決定は、児童福祉法24条1項、子ども・子育て支援法施行規則1条9号の解釈、適用を誤った違法があるなどとして、各決定の取消しを求める訴え(本案事件)を提起するとともに、行政事件訴訟法25条1項に基づき、各決定の執行の停止を求めた事案において、各決定により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があり、本案について理由がないと見えるときには当たらないとして、申立てを一部認容し、本案判決の言渡し後40日を経過するまでの各決定の執行停止を認めた事例。
2015.12.22
開発許可処分取消請求事件
★「新・判例解説Watch」H28.4下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25447647/最高裁判所第一小法廷 平成27年12月14日 判決 (上告審)/平成27年(行ヒ)第301号
鎌倉市長が、都市計画法29条1項による開発許可をしたことについて、開発区域の周辺に居住する被上告人らが、上告人を相手に、上記開発許可の取消しを求め、原審は、上記許可に係る開発行為に関する工事が完了し、検査済証が交付された後においても、本件許可の取消しを求める訴えの利益は失われないと判断し、これが失われるとして被上告人らの訴えを却下した第1審判決を取消して本件を第1審に差し戻すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、原審の判断は、正当として是認することができるとして、上告を棄却した事例。
2015.11.17
開門等請求控訴事件
★「新・判例解説Watch」H27.12下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25541157/福岡高等裁判所 平成27年 9月 7日 判決 (控訴審)/平成23年(ネ)第771号
〔1〕国営諫早湾土地改良事業の施行、特に、同事業において諫早湾干拓地潮受堤防が建設され、同湾の湾奥部の海洋部分が締め切られたことによって漁業被害を受け、漁業行使権(漁業法8条1項にいう「漁業を営む権利」)を侵害されたとする開門請求1審原告らが、その漁業被害を最低限度回復させるために必要があるとして、1審被告(国)に対し、上記権利から派生するとされる物権的請求権に基づき、上記潮受堤防の北部及び南部に設置されている各排水門について、同堤防で締め切られた調整池内に諫早湾の海水を流入させ、海水交換が行われるような開門操作をするよう求めたほか、〔2〕開門請求1審原告ら及び大浦1審原告らが、1審被告において上記事業を実施したこと及び上記開門操作を行わないことは、1審原告らに漁業被害を及ぼしその漁業行使権を侵害するものとして国家賠償法上違法であり、また、1審被告が上記開門操作を行わないことは、上記事業の実施に先立って漁業補償契約が締結された際に1審原告らと1審被告との間で成立した、同事業の実施後も1審原告らが漁業を営めるようにするという合意に反する行為であって、これにより1審原告らの漁業行使権が侵害されている旨主張し、1審被告に対し、国家賠償法1条1項又は債務不履行による損害賠償として1人につき605万円、及び上記開門操作がされるに至るまで年50万円の割合による金員、並びに上記605万円に対する遅延損害金の支払を求め、原判決は、1審原告らの請求中、一部却下、一部認容、一部棄却したため、開門請求1審原告らと控訴人大浦1審原告ら及び1審原告Z1並びに1審被告が、上記各敗訴部分を不服として双方が控訴した事案において、原判決中、被控訴人大浦1審原告ら及び1審原告Aの請求を認容した部分(1審被告敗訴部分)は不当であるから、1審被告の控訴に基づいてこれを取消した上、この部分に係る被控訴人ら及び1審原告Aの請求をいずれも棄却するとともに、控訴人ら並びに1審原告Aの控訴をいずれも棄却するとした事例。
2015.11.17
内海ダム再開発事業公金支出差止等請求住民訴訟事件(第1事件、第2事件)(内海ダム訴訟)
LEX/DB25541113/高松地方裁判所 平成27年 6月22日 判決 (第一審)/平成22年(行ウ)第7号等
香川県の住民である第1事件原告らが、香川県及び小豆島町が起業者である「二級河川別当川水系別当川内海ダム再開発工事並びにこれに伴う県道及び町道付替工事」は治水、利水目的に鑑みても不要であり、安全性にも問題がある上、周辺の景観・環境を損なうことにより失われる利益は重大であるから、同事業に係る公金の支出は違法であるとして、香川県の執行機関である第1事件被告に対し、地方自治法242条の2第1項1号に基づき、同事業に係る公金の支出の差止めを求めるとともに、同項4号本文に基づき、同事業に係る公金の支出を行った香川県の前知事及び現知事に対する不法行為に基づく損害賠償請求を求め(第1事件)、小豆島町の住民である第2事件原告らが、上記と同様の理由で同事業に係る公金の支出は違法であるとして、小豆島町の執行機関である第2事件被告に対し、同項1号に基づき、同事業に係る公金の支出の差止めを求めるとともに、同項4号本文に基づき、同事業に係る公金の支出を行った小豆島町の前町長及び現町長に対する不法行為に基づく損害賠償請求を求めた(第2事件)住民訴訟において、原告らは、本件事業が治水及び利水目的に鑑みても不必要である上、安全性にも問題があり、周辺の景観・環境を損なうことにより失われる利益は重大であるとして、このような合理性を欠く本件事業に係る本件各公金の支出は地方財政法4条1項、地方自治法2条14項に違反し違法であると主張しているが、本件全証拠によっても原告らの主張を認めるには足りないとし、また、本件整備計画についても上記と同様の理由で違法であり、その違法性が本件各公金の支出に承継されるとの第1事件原告らの主張や、本件事業に係る請負契約(支出負担行為)には上記と同様の理由で違法があり、当該契約を解消できる特殊な事情があったにもかかわらず、香川県知事及び小豆島町長が行った各支出命令は財務会計法規上の義務に違反し、違法であるとの原告らの主張についても、上記と同様に本件整備計画あるいは本件事業に係る請負契約(支出負担行為)が違法であることを認めるに足りる証拠がないとして、第1事件原告ら及び第2事件原告らの各請求をいずれも棄却した事例。
2015.10.27
各航空機運航差止等請求控訴事件
★「新・判例解説Watch」H28. 1下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25540973/東京高等裁判所 平成27年 7月30日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第284号
厚木基地周辺に居住する原告(控訴人兼被控訴人)らが、厚木基地に離着陸する航空機の発する騒音により身体的被害及び精神的被害を受けていると主張して、被告(控訴人兼被控訴人)国に対し、主位的に、厚木基地における自衛隊機及び米軍機の一定の態様による運行の差止め等を求め、予備的に、音量規制等を求めたところ、原審は、米軍機差止めの訴えを却下し、米軍機に関する予備的請求のうち人格権に基づく妨害排除請求権としての差止請求等の給付請求を棄却し、確認請求に係る訴えをいずれも却下し、転居原告の自衛隊機差止めの訴えをいずれも却下した一方で、厚木飛行場における自衛隊機の運航のうち夜間に行われるものは、これを差し止める必要性が相当高いとし、転居原告を除く原告らの自衛隊機差止請求を一部認容したため、原告ら及び被告が双方控訴した事案において、主位的請求に係る自衛隊機差止請求について、厚木飛行場に離着陸する航空機による騒音の発生状況が大きく変わる可能性があるとして、一定期間の差止めを認容してその余の請求を棄却し、予備的請求を却下し、その余の控訴を棄却した事例。