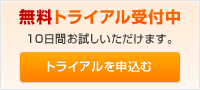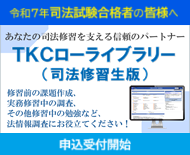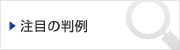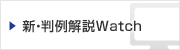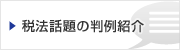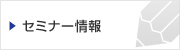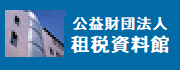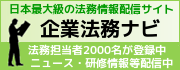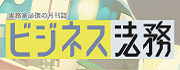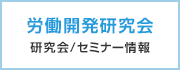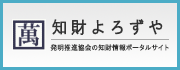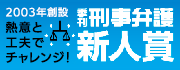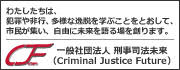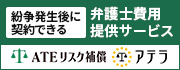2025.12.02
損害賠償請求事件
LEX/DB25622991/京都地方裁判所 令和 7年 6月26日 判決(第一審)/令和3年(ワ)第1146号
被告大学の教職員で構成される労働組合である原告が、被告大学及び被告京都市に対し、被告大学が設置、運営する本件大学の敷地外構部分に設置されていた立看板に関して、被告市が被告大学に行政指導をし、被告大学が原告の設置した立看板を撤去したことは、違憲、違法であるなどと主張して、共同不法行為に基づき、連帯して損害賠償金等の支払を求めるとともに、被告大学に対しては、上記立看板の撤去及び同立看板を撤去した後、原告との間で一切の調整に応じない対応が不当労働行為に当たると主張して、不法行為に基づく損害賠償金等の支払を求めた事案で、本件行政指導は、被告大学に対して行われたものであり、原告主張に係る利用者、すなわち立看板を掲出し、あるいはしようとする者に対する制約を直截の目的とするものではないこと、原告が、被告大学の管理する本部構内について、これを立看板の設置場所として当然に利用する権原を有するとも認められないことなどに照らすと、本件行政指導が違法とはいえないし、被告大学が、被告大学の敷地の管理権に基づき、本部構内の外構部分に立看板を設置することを禁じる規程を制定し、本件規程に基づき本件両撤去行為をしたことが、原告に対する不当労働行為に当たるともいえず、さらに、被告大学は、原告に対し、外構部分への立看板の設置については許容できないことを明確に伝えつつ、原告に生じる不利益を低減させるように代替措置を提案していたと認められるのであるから、団体交渉に臨む態度が不誠実であったとも認められないとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2025.11.11
被告変更許可申立却下決定に対する即時抗告事件(山口県周防大島町)(住民訴訟被告変更許可申立即時抗告事件(山口県周防大島町))
LEX/DB25623517/広島高等裁判所 令和 7年 1月 9日 決定(抗告審(即時抗告))/令和6年(行ス)第2号
抗告人らは、山口県大島郡周防大島町の町立病院に勤務していた医師が、当該病院における診療過程において発生した財産を横領するなどして周防大島町に損害を与え、また、周防大島町病院事業管理者であるCは、上記財産を適正に保管等する義務に違反したのに、相手方が本件医師やCに対して不法行為に基づく損害賠償請求権を行使していないことには、怠る事実の違法があると主張して、相手方・周防大島町長を被告として、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、相手方が本件医師及びCに当該損害賠償の請求をするよう求める基本事件を提起し、相手方が、周防大島町病院等事業に関する損害賠償請求を行う権限は、相手方ではなく、Cにある旨指摘したところ、抗告人らが、基本事件の被告を相手方からCに変更することを許可するよう申し立て、原審が、抗告人らには、同事件の被告を誤ったことにつき重大な過失があったといわざるを得ず、申立人らが「重大な過失によらないで」基本事件の被告を誤ったということはできないとして、本件申立てを却下したところ、抗告人らが抗告した事案で、行訴法15条1項の「重大な過失」とは、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態をいうと解すべきところ、周防大島町長にも権限があるかのような誤解を招く外観的事情が認められることに照らせば、ほとんど故意に近い著しい注意欠如があったとはいえず、抗告人らに行訴法15条1項の「重大な過失」があったとはいえないとして、原決定を取り消し、基本事件の被告を周防大島町長Yから周防大島町病院事業管理者Cに変更することを許可した事例。
2025.08.26
行政処分取消等請求事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和7年9月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25574450/最高裁判所第一小法廷 令和 7年 7月17日 判決(上告審)/令和5年(行ヒ)第276号
被上告人(原告・控訴人)が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律20条1項に基づき、介護給付費の支給決定に係る申請をしたところ、上告人(被告・被控訴人)・千葉市からこれを却下する処分を受けたため、本件処分が違法であると主張して、上告人を相手に、本件処分の取消し及び支給決定の義務付けを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求め、原審(控訴審)が、本件処分の取消請求及び支給決定の義務付け請求を認容するとともに、損害賠償請求を一部認容したところ、上告人が上告した事案で、上告人が原審のいう不均衡を避ける措置をとらなかったことを理由として、本件処分に裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるということはできず、原審の判断には、市町村の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った結果、受けることができる介護給付のうち自立支援給付に相当するものの量を算定することができないとした上告人の判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められるか否かについて審理を尽くさなかった違法があるというべきであるから、原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決中上告人敗訴部分を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻した事例。
2025.08.05
生活保護基準引下げ処分取消等請求事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和7年9月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25574399/最高裁判所第三小法廷 令和 7年 6月27日 判決(上告審)/令和5年(行ヒ)第397号 他
大阪府内に居住して生活保護法に基づく生活扶助を受給していた上告人ら(上告人X3らについてはその各夫)は、平成25年から平成27年にかけて行われた、厚生労働大臣による「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)中の生活扶助基準の改定を理由として、所轄の福祉事務所長らから、それぞれ、生活扶助の支給額を変更する旨の保護変更決定を受けたことから、上告人らが、本件改定は違法であるなどと主張して、〔1〕上告人X1ら及び上告人X2らにおいて被上告人各市を相手に上記の保護変更決定の取消しを求め、〔2〕上告人X1ら及び上告人X3らにおいて被上告人国に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求め、第一審が、X1、X2及びX3を除く者の本件各決定の取消請求については認容し、その余の請求(国家賠償請求)については棄却したところ、双方がそれぞれ控訴し、控訴審が、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるということはできないなどとして、第一審判決中、被上告人ら敗訴部分を取り消し、上告人らの請求を棄却したことから、上告人らが上告した事案で、デフレ調整における改定率の設定については、上記不均衡を是正するために物価変動率のみを直接の指標として用いたことに、専門的知見との整合性を欠くところがあり、この点において、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったものというべきであるから、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法3条、8条2項に違反して違法というべきであり、したがって上記請求を認容した第1審判決は正当であるとして、同部分につき被上告人各市の控訴を棄却する一方、本件改定につき国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできないとして当該部分に係る上告を棄却した事例(反対意見1名、補足意見1名)。
2025.08.05
生活保護基準引下げ処分取消等請求事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和7年9月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25574400/最高裁判所第三小法廷 令和 7年 6月27日 判決(上告審)/令和6年(行ヒ)第170号
愛知県内に居住して生活保護法に基づく生活扶助を受給していた被上告人承継人を除く被上告人らは、平成25年から平成27年にかけて行われた、厚生労働大臣による「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)中の生活扶助基準の改定を理由として、所轄の福祉事務所長らから、それぞれ、生活扶助の支給額を変更する旨の保護変更決定を受けたことから、被上告人らを含む一審原告らが、本件改定は違法であるなどと主張して、〔1〕上告人各市を相手に、上記の保護変更決定の取消しを求めるとともに、〔2〕上告人国に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求め、一審が請求をいずれも棄却したため、一審原告らの一部(上告人ら)が控訴し、控訴審が、一審原告らの請求はいずれも理由があるとして、一審判決を取り消し、上記請求をいずれも認容し、当審における拡張請求を棄却したところ、上告人らが上告した事案で、本件改定は、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法3条、8条2項に違反して違法というべきであるとする一方、厚生労働大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然とデフレ調整に係る判断をしたと認め得るような事情があったとまでは認められず、他に、同大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と本件改定をしたと認め得るような事情があったというべき根拠は見当たらないから、上告人各市の上告を棄却し、他方、本件改定につき国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできないから、損害賠償請求を認容した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、上告人国の論旨は理由があるから、控訴審判決のうち上記請求に関する部分は破棄を免れず、そして、既に説示したところによれば、上記請求を棄却した一審判決は結論において正当であるとして、同部分につき被上告人らの控訴を棄却した事例(補足意見1名、反対意見1名)。
2025.07.22
行政文書不開示処分取消等請求事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25574356/最高裁判所第三小法廷 令和 7年 6月 6日 判決(上告審)/令和6年(行ヒ)第94号
上告人が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、消費者庁長官に対し、平成27年度に消費者庁が外部の機関に委託した、機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業の報告書の開示を請求したところ、本件文書の一部に記録された情報が情報公開法5条6号柱書き及び同号イ所定の不開示情報に該当するなどとして、当該一部を開示しないなどとする決定を受けたため、被上告人を相手に、上記決定のうち、本件各不開示箇所における本件各取消請求事項に係る部分の取消し及び本件文書の本件各取消請求事項に係る部分の開示決定の義務付けを求めたところ、原審が、本件各不開示箇所に記録された検証の手法や基準、検証結果(データ)、考察内容、問題点等の情報は情報公開法5条6号柱書き及び同号イ所定の不開示情報に該当するとして、上告人の取消請求を棄却し、これに係る開示決定の義務付けを求める訴えを却下したことから、上告人が上告した事案で、原審は、本件各不開示箇所を開示することにより検証機関による忌たんのない検討結果の指摘を困難にするおそれがあるものといえる理由を示しておらず、諸点について認定説示することなく、本件各不開示箇所を開示することにより事業者において消費者庁の事後監視や検証機関による問題点の指摘を免れることを容易にさせるおそれがあるなどとして、本件各不開示箇所に記録された情報が情報公開法5条6号柱書き及び同号イ所定の不開示情報に該当するとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、本件を高等裁判所に差し戻した事例(補足意見あり)。
2025.07.08
警察庁保有個人情報管理簿一部不開示決定取消等請求事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和7年8月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25574338/最高裁判所第三小法廷 令和 7年 6月 3日 判決(上告審)/令和5年(行ヒ)第335号
上告人(控訴人・原告)が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、警察庁長官に対し、行政文書の開示を請求したところ、警察庁の保有する保有個人情報管理簿122通につき、それぞれの一部を開示し、その余の部分には、情報公開法5条3号又は4号所定の不開示情報が記録されているとして、これを不開示とする旨の決定を受けたため、被上告人(被控訴人・原告)・国を相手に、不開示部分の取消し等を求め、第一審が、本件処分のうち一部を取り消し、警察庁長官に対して同部分を開示する旨の決定をするよう命じ、本件処分のうちその余の取消請求については棄却し、またその余の義務付け請求に係る部分を不適法却下したため、上告人が控訴し、控訴審が、全10項目のうち3項目の記載欄についてはいずれも3号情報又は4号情報に該当すると認められ、7項目の記載欄については、そのうち分類A及び分類Bの情報については3号情報又は4号情報に該当すると認められる一方、分類Cの情報についてはこれらの該当性を認めることができないとし、7項目の記載欄のうち分類Cに係る部分は、情報公開法6条1項に基づき、開示しなければならないとして、第一審判決を変更したところ、上告人が上告した事案で、控訴審は、別件各決定によっても開示されていない「備考」欄である別紙目録記載2及び3の部分についても、被上告人に対し、文書ごとに、小項目が設けられているか否か、小項目が設けられている場合に、それでもなお当該「備考」欄について一体的に本件各号情報が記録されているといえるか否か等について明らかにするよう求めたうえで、合理的に区切られた範囲ごとに、本件各号情報該当性についての判断をすべきであったということができるが、しかるに、原審はそれぞれ一体的に本件各号情報該当性についての判断をしたものであり、判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとして、原判決中、一部を破棄し、当該破棄部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻し、上告人のその余の上告を棄却した事例(3名の裁判官各補足意見、裁判官1名の意見あり)。
2025.06.10
懲戒免職処分取消等請求事件
★「新・判例解説Watch」労働法分野 令和7年8月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和7年8月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25574225/最高裁判所第一小法廷 令和 7年 4月17日 判決(上告審)/令和6年(行ヒ)第201号
上告人・京都市が経営する自動車運送事業のバスの運転手として勤務していた被上告人が、運賃の着服等を理由とする懲戒免職処分を受けたことに伴い、京都市公営企業管理者交通局長から、京都市交通局職員退職手当支給規程(昭和57年京都市交通局管理規程第5号の2)8条1項1号の規定により一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分を受けたため、上告人を相手に上記各処分の取消しを求め、第一審が本件全部支給制限処分の取消請求は理由がないとして請求を棄却したところ、被上告人が控訴し、控訴審が本件全部支給制限処分の取消請求を認容したことから、上告人が上告した事案で、本件着服行為の被害金額が1000円でありその被害弁償が行われていることや、被上告人が約29年にわたり勤続し、その間、一般服務や公金等の取扱いを理由とする懲戒処分を受けたことがないこと等をしんしゃくしても、本件全部支給制限処分に係る本件管理者の判断が、社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものということはできず、本件全部支給制限処分が裁量権の範囲を逸脱した違法なものであるとした控訴審の判断には、退職手当支給制限処分に係る管理者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであるとして、控訴審判決中上告人敗訴部分を破棄し、被上告人の控訴を棄却した事例。
2025.05.27
α市立保育園廃止処分取消等請求事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和7年6月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25574151/東京地方裁判所 令和 6年 2月22日 判決(第一審)/令和4年(行ウ)第549号
α市議会に提出された、本件保育園の令和5年度における0歳児募集の廃止及び令和9年度末をもっての廃園などを内容とする本件募集廃止条例の制定に係る議案につき、市議会が継続審査としたため、当時のα市長が、「議会において議決をすべき事件を議決しないとき」(地方自治法179条1項本文)に該当するとして、本件募集廃止条例を制定する旨の専決処分(本件専決処分)をし、また、本件保育園に第1子を通園させており、当時0歳児であった第2子につき令和5年度からの本件保育園の利用申請をした原告に対して、本件募集廃止条例の規定が有効であることを前提に、その施設利用を不可とする旨の処分(本件利用不可処分)をしたことについて、原告が、被告に対し、本件専決処分は違法であると主張して、(1)主位的請求として本件専決処分による本件募集廃止条例の制定、その予備的請求として本件募集廃止条例の制定による令和5年4月1日からの本件保育園における0歳児募集の廃止(本件各処分)の各取消しを求めるとともに、(2)本件利用不可処分の取消しを求め、さらに、(3)国家賠償法1条1項に基づき、本件専決処分及び本件利用不可処分によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金等の支払を求めた事案で、本件議案は、特定の緊急性が高い事件であるということはできず、また、何らかの事情により前市長にとって市議会の議決を得ることが不可能であったなどということもできないから、本件専決処分は、「議会において議決すべき事件を議決しないとき」の要件を充足しないものというべきであって、国家賠償法1条1項の違法及び過失があると認められ、原則としてこれに基づいて制定された本件募集廃止条例もまた無効であるといわざるを得ないところ、本件募集廃止条例の制定行為については、処分の取消しの訴えの対象となる処分に該当するとはいえないから、本件訴えのうち、本件各処分の取消しを求める部分は、いずれも不適法であるとして却下し、本件利用不可処分の取消しを求める請求を認容し、国家賠償請求については、本件専決処分と相当因果関係を有する損害賠償を求める限度で一部認容した事例。
2025.04.15
仮の差止めの申立て一部認容決定に対する抗告審の一部取消決定に対する許可抗告事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和7年5月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25574110/最高裁判所第三小法廷 令和 7年 2月26日 決定(許可抗告審)/ 令和6年(行フ)第1号
関東運輸局長が、国土交通大臣から委任された権限により、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(特措法)16条1項に基づき、本件交通圏におけるタクシー事業に係る旅客の運賃の範囲(本件公定幅運賃)を定め、いずれも同法3条の2第1項により準特定地域に指定されている東京都特別区、三鷹市及び武蔵野市の区域に営業所を有する、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)を営む者である相手方らは、それぞれ、本件公定幅運賃の下限を下回る運賃を定めて、同法16条の4第1項による届出をしたところ、相手方R社及び相手方J社が、それぞれ、本件各不利益処分等の差止めを求める訴訟(本案訴訟)に係る差止めの訴えを提起し、併せて、本件各不利益処分等の仮の差止めを求める各申立てをし、第一審が、本件各不利益処分等のうち、運賃変更命令及び事業許可取消処分について、仮の差止めを命じたことから、抗告人・国が即時抗告し、抗告審が、事業許可取消処分に係る部分については、原審と異なり、理由がないとして、原決定を一部取り消し、上記取消部分に係る相手方らの申立てをいずれも却下し、その余の本件抗告をいずれも棄却したところ、抗告人が許可抗告をした事案で、本件公定幅運賃の下限の設定につき、公定幅運賃の変更の程度及び当該変更によるタクシー事業者への影響の程度を考慮していないことを理由として、本件変更が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであると一応認められるとした抗告審の判断には、公定幅運賃の変更に係る裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法があるとして、原決定中、運賃の変更を命ずる処分に関する部分を破棄し、同部分につき原々決定を取り消し、相手方らの申立てを却下した事例(反対意見あり)。
2025.04.15
行政文書不開示決定取消等請求控訴事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和7年5月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25622103/大阪高等裁判所 令和 7年 1月30日 判決(控訴審)/令和5年(行コ)第118号
控訴人(原告)が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条に基づき、財務大臣及び近畿財務局長に対し、学校法人Fに対する国有地の売却に関連する被疑事件の捜査について、財務省及び近畿財務局が東京地方検察庁又は大阪地方検察庁に対して任意提出した一切の文書及び準文書の開示請求をしたところ、財務大臣及び近畿財務局長から、当該行政文書の存否を答えるだけで同法5条4号所定の不開示情報を開示することになるとして、同法8条及び9条2項に基づき当該行政文書の存否を明らかにしないで不開示とする各決定を受けたため、控訴人が、被控訴人(被告)・国に対し、上記各決定の取消しを求め、原審が控訴人の請求をいずれも棄却したことから、控訴人が控訴した事案で、本件各請求対象文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することになるとはいえないし、本件各被疑事件における任意提出の範囲が明らかになることにより、将来の同種事犯のみならず犯罪一般の捜査等に支障を及ぼすおそれがあるものとも認められないところ、財務省及び近畿財務局が控訴人に対してした本件各不開示決定は違法であって、これらはいずれも取り消されるべきであるから、これと異なる原判決は相当でないとして、原判決を取り消したうえ、本件各不開示決定を取り消した事例。
2025.04.08
裁決取消請求事件
LEX/DB25622008/東京高等裁判所 令和 7年 2月19日 判決(差戻第一審)/令和6年(行ケ)第4号
門司地方海難審判所は、原告が船長として操船するa丸とCが船長として操船するb丸とが衝突した本件事故につき、原告にはb丸の動静監視を十分に行うべき注意義務があり、これを怠った職務上の過失がある旨判断して、原告の小型船舶操縦士の業務を1か月停止し、Cを懲戒しない旨の裁決をしたところ、原告が、被告・海難審判所長に対し、本件裁決の取消しを求め、差戻前第1審が、b丸の速力、航跡及びa丸との衝突地点について本件裁決とは異なる事実を認定したものの、原告にはb丸の動静監視を十分に行うべき注意義務に違反する職務上の過失があり、また本件事故と原告の無灯火航行との間には因果関係がある旨判断して、原告の請求を棄却する旨の判決を言い渡したことから、原告が上告受理を申し立て、上告審が、上告を受理したうえで、差戻前第1審には職務上の過失に関する法令の解釈適用を誤った違法がある旨判断して、差戻前第1審判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻した事案で、〔1〕衝突時におけるb丸の速力は少なく見積もっても15ノット以上であり、〔2〕その航跡も、Cが証言するような右小回りではなく、原告が主張・供述するように、それよりも北側を右大回りしていたものであって、〔3〕これにより、a丸との衝突地点についても、原告が主張・供述するように、本件裁決の認定位置よりも更に北側であったものと認めるのが相当であるとしたうえで、Cはb丸の速力を少なくとも15ノット以上に保ったまま、泊船だまりに入航しようとし、もってa丸に衝突したものでもあって、本件事故に係る海難につき、Cに過失は認められないとするのは、困難であるものといわざるを得ず、一方、本件事故の発生につき、原告に職務上の過失があったとみることはできず、原告に職務上の過失があるとして小型船舶操縦士の業務を1か月停止するとした本件裁決は、その前提を欠き、取消しを免れないとして、原告の請求を認容した事例。
2025.04.01
特別地方交付税の額の決定取消請求事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和7年5月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年5月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25574103/最高裁判所第一小法廷 令和 7年 2月27日 判決(上告審)/令和5年(行ヒ)第297号
上告人・泉佐野市が、総務大臣がした特別交付税の額の決定(本件各決定)について、令和元年度における市町村に係る特別交付税の額の算定方法の特例を定めた特別交付税に関する省令附則5条21項(令和2年総務省令第111号による改正前)及び同附則7条15項(令和2年総務省令第12号による改正前)は、いわゆるふるさと納税に係る収入が多額であることをもって特別交付税の額を減額するものであって、地方交付税法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であるなどと主張して、被上告人・国に対し、本件各決定の取消しを求め、第一審が上告人の請求をいずれも認容したところ、被上告人が控訴し、控訴審が、本件訴えは、行政主体としての上告人が、法規の適用の適正をめぐる一般公益の保護を目的として提起したものであって、自己の財産上の権利利益の保護救済を目的として提起したものと見ることはできないから、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」には当たらないとして、原判決を取り消し、上告人の訴えをいずれも却下したことから、上告人が上告した事案で、特別交付税は、地方交付税の一種であり、交付されるべき具体的な額は、総務大臣がする決定によって定められるものである(地方交付税法4条2号、6条の2第1項、15条1項、2項、16条1項)から、特別交付税の交付の原因となる国と地方団体との間の法律関係は、上記決定によって発生する金銭の給付に係る具体的な債権債務関係であるということができ、地方団体が特別交付税の額の決定の取消しを求める訴えは、国と当該地方団体との間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争に当たるというべきであり、また、特別交付税の額の決定は、地方交付税法及び特別交付税に関する省令に従ってされるべきものであるから、上記訴えは、法令の適用により終局的に解決することができるものといえ、以上によれば、地方団体が特別交付税の額の決定の取消しを求める訴えは、裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たると解するのが相当であるとして、原判決を破棄し、本件を大阪高等裁判所に差し戻した事例。
2025.03.18
オンライン資格確認義務不存在確認等請求事件(第1事件、第2事件、第3事件)
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和7年4月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25574026/東京地方裁判所 令和 6年11月28日 判決(第一審)/令和5年(行ウ)第81号 他
保険医療機関及び保険医療養担当規則(療担規則)には、令和5年4月1日に施行された令和4年厚生労働省令第124号による改正の結果、健康保険法63条3項1号の厚生労働大臣の指定を受けた病院又は診療所は、患者が同法3条13項に規定する電子資格確認(オンライン資格確認)によって療養の給付を受ける資格があることの確認を求めた場合には、原則として、同資格があることをオンライン資格確認によって確認しなければならず(3条2項)、また、その資格があることの確認ができるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない(同条4項)旨の規定が設けられたところ、医師又は歯科医師である原告らが、本件改正療担規則3条2項及び4項は、健康保険法70条1項の委任の範囲を逸脱する違法なものであって無効であるなどと主張して、被告に対し、本件各規定に基づく上記のような確認義務及び体制整備義務を原告らが負わないことの確認を求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき、精神的苦痛に対する損害賠償金及び遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案で、本件各規定の適法性について、本件各規定は、健康保険法70条1項の委任の範囲を逸脱した違法なものということはできないものというべきであり、また、原告らの平成25年最判の射程に関する主張について、両事案は前提となる事実関係や性質が異なり、平成25年最判の上記説示部分が必ずしも本件にそのまま妥当するものではなく、さらに、オンライン資格確認の義務化が目的達成の手段として実質的関連性を欠くとはいえないから、オンライン資格確認の義務化によって原告らの憲法上の権利が違法に侵害されたということはできないなどとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2025.01.28
不作為違法確認等、国家賠償等請求事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和7年3月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25573946/最高裁判所第二小法廷 令和 6年12月16日 判決(上告審)/令和5年(行ヒ)第430号
上告人らが、被上告人・国に対し、上告人らがSACO見舞金受諾書を提出しないことを理由に沖縄防衛局長がSACO見舞金の支払手続をとらなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法であるなどと主張して、同項に基づき、上記損害金元金と上記慰謝料の差額に相当する額の損害賠償等を求めたところ、第一審が請求を一部却下し、その余を棄却したため、上告人らが控訴し、控訴審が控訴をいずれも棄却したことから、上告人らが上告した事案で、事実関係等によれば、上告人らと被上告人との間において、SACO見舞金を支給する旨の合意は成立していないというのであるから、上告人らはSACO見舞金の支給を受ける権利を有するものということはできず、また、他に、SACO見舞金の支給に関し、上告人らの権利又は法律上保護される利益が侵害されたというべき事情も見当たらないから、被上告人は、沖縄防衛局長が上告人らに対しSACO見舞金の支払手続をとらなかったことにつき、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負わないとしたうえで、以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、なお、その余の請求に関する上告については、上告受理申立ての理由が上告受理の決定において排除されたので、棄却することとするとして、本件上告を棄却した事例(意見あり)。
2024.12.03
損害金請求事件
LEX/DB25621110/水戸地方裁判所下妻支部 令和 6年10月23日 判決(第一審)/令和4年(ワ)第200号
被告市議会の議員である原告らが、被告市議会からそれぞれ出席停止の懲罰(地方自治法135条1項3号)を受けたことについて、同懲罰を原告らに科したのは被告市議会の裁量権を逸脱するものであって違法な公権力の行使であるとして、国家賠償法1条による損害賠償請求権に基づき、被告に対し、それぞれ、慰謝料等の支払を求めた事案で、本件配布行為はそもそも懲罰事由に当たらないものというべきであるから、本件配布行為を懲罰事由とした本件懲罰1は国家賠償法1条1項の適用上違法というべきであるとし、また、本件懲罰2の相当性を判断するに際しては前件懲罰において出席停止1日という処分がされたことを前提とすることは相当ではなく、議会における議員の発言の自由の重要性にかんがみると、議会の自律性を踏まえても、本件懲罰2において発言機会を奪う結果となる出席停止3日という処分としたことは重きに過ぎ、議会の裁量権を著しく逸脱した又はこれを濫用したものというべきであるから、本件懲罰2は国家賠償法1条1項の適用上違法というべきであるとして、原告らの請求を一部認容し、なお、事案の性質にかんがみ、前件懲罰、本件懲罰1及び本件懲罰2においてはいずれも、議長の指名により懲罰動議を発議した議員のみによって懲罰特別委員会が構成され、前記各懲罰を行うことを求める委員会報告がなされ、前記各懲罰に至ったことが認められるところ、このような委員会の構成方法は、委員会へ付託し慎重な審理を求めた古河市議会会議規則162条の趣旨に反するのではないかとの疑問を禁じ得ないところである、と付言した事例。
2024.10.08
退職共済年金及び老齢厚生年金減額処分無効確認乃至取り消し等請求事件
LEX/DB25573746/最高裁判所第二小法廷 令和 6年9月13日 判決 (上告審)/令和4年(行ヒ)第352号
被上告人(一審原告、控訴審控訴人)が、上告人(一審被告、控訴審被控訴人)・国らを相手に、特老厚年金の一部を支給停止とする処分を除く3個の処分の取消しを求めるとともに、上記支給停止に係る特退共年金の支払を求めるなどし、第一審が訴えのうち処分の取消請求に係る部分を却下し、その余の請求を棄却したことから、被上告人が控訴し、控訴審が、複数の適用事業所を有する法人内での異動等により適用事業所が変更になったが、引き続き同一法人内において継続して就労しており、給与に関する雇用条件が異ならないような場合には、本件規定1に規定する者及び本件規定2に規定する者と同視して、本件配慮措置の適用があるものと解するのが相当であるところ、本件は上記の場合に当たるから、被上告人の平成28年5月分以降の特老厚年金及び特退共年金に本件配慮措置を適用すべきであり、本件各処分は違法であるとして、その取消請求を認容するとともに、特退共年金の支払請求の一部を認容したところ、上告人・国が上告した事案で、被上告人は、平成28年4月1日、一元化法施行日の前から有していたB高校を適用事業所とする厚生年金保険の被保険者資格を喪失したというのであるから、これにより、本件規定1に規定する者及び本件規定2に規定する者に該当しなくなったものというべきであり、被上告人の同年5月分以降の特老厚年金及び特退共年金には本件配慮措置は適用されず、以上によれば、控訴審の上記判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、被上告人の本件各処分の取消請求は理由がなく、また、特退共年金の支払請求のうち原審が認容した部分も理由がなく、これらはいずれも棄却すべきであるとして、原判決を変更した事例。
2024.09.24
出席停止処分差止め請求控訴事件、同附帯控訴事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野 令和6年12月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25620823/大阪高等裁判所 令和6年 8月28日 判決 (控訴審)/令和6年(行コ)第24号 他
市議会は、市議会議員である被控訴人(附帯控訴人・原告)の香芝市教育福祉委員会における発言が懲罰事由に当たるとして、被控訴人に対して陳謝の懲罰を科したが、被控訴人は、陳謝文の朗読を拒否したため、市議会は、その朗読拒否を懲罰事由として新たに被控訴人に陳謝の懲罰を科し、これに対し被控訴人が陳謝文の朗読を拒否し、市議会が更に被控訴人に陳謝の懲罰を科すということが繰り返され、市議会は、合計5回の陳謝の懲罰を被控訴人に科した後、5回目の陳謝の懲罰に係る陳謝文の朗読拒否を懲罰事由として、被控訴人に対し、4日間の出席停止の懲罰の処分をしたところ、被控訴人が、本件処分が違法であると主張して、控訴人(附帯被控訴人・被告)香芝市に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料及び弁護士費用並びに遅延損害金の支払を求め、原審が被控訴人の請求を一部認容し、その余の請求を棄却したところ、控訴人が控訴し、被控訴人が附帯控訴した事案で、本件処分が裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したといえるかの評価をするうえで、本件処分に至る経緯の中でされた陳謝処分についての適法性、相当性の検討は避けられないというべきであって、本件処分は違法との評価を避けられないとし、また、本件処分の内容、程度等に鑑み、被控訴人が指摘する事情を踏まえても、被控訴人が被った議員としての責務に対する侵害、名誉、信頼の棄損等による精神的苦痛の慰謝料は30万円をもって相当と認めるとして、本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却した事例。
2024.08.27
損害賠償請求事件(国家賠償請求)
LEX/DB25620432/東京地方裁判所 令和 6年 7月18日 判決 (第一審)/令和4年(ワ)第5542号
弁護士であった原告が、犯人隠避教唆の被疑者として検察官から受けた取調べに違法があり、精神的苦痛を受けたと主張して、被告・国に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金等の支払を求めた事案で、本件取調べにおけるP4検察官の言動は、事案の内容・性質、嫌疑の程度及び取調べの必要性を考慮しても、社会通念上相当と認められる範囲を超えて、原告の人格権を侵害するものといわざるを得ず、国家賠償法1条1項の適用上違法というべきであり、これにより原告は相当の精神的苦痛を被ったといえるところ、原告の請求は、被告に対し、違法な本件取調べと相当因果関係を有する損害賠償を求める限度で理由があるとして、請求を一部認容した事例。
2024.08.13
公有水面埋立撤回処分に対し国土交通大臣がなした裁決の取消請求控訴事件
LEX/DB25620049/福岡高等裁判所那覇支部 令和 6年 5月15日 判決 (控訴審)/令和4年(行コ)第7号
沖縄防衛局は、沖縄県宜野湾市所在の普天間飛行場の代替施設を同県名護市内に所在する辺野古崎地区及びこれに隣接する本件埋立海域に設置するための公有水面の埋立てにつき、同県知事から公有水面埋立法42条1項の承認を受けていたが、事後に判明した事情等を理由として本件埋立承認を取り消す旨の処分(本件撤回処分)がされたことから、これを不服として国土交通大臣に対し行政不服審査法に基づく審査請求をしたところ、国土交通大臣は、本件撤回処分を取り消す旨の裁決をしたことから、本件埋立海域の周辺に居住する住民であると主張する控訴人(原告)らが、国土交通大臣の所属する被控訴人・国を相手方として、本件裁決の取消しを求め、原審が控訴人らの訴えをいずれも却下したため、控訴人らが控訴した事案で、控訴人らの主張するその余の観点から原告適格の有無について検討するまでもなく、控訴人らは、本件裁決の取消訴訟における原告適格を有するものということができるとし、控訴人らの本件訴えはいずれも適法であり、これを不適法として却下した原判決は取消しを免れないところ、本件訴訟の経過とその内容等に照らすと、本件については、原告適格に係る上記判断内容を踏まえて原審において更に弁論をする必要があると認められるとして、原判決を取り消し、本件を那覇地方裁判所に差し戻した事例。