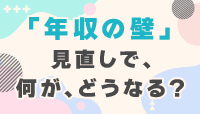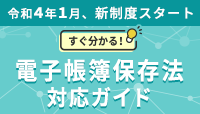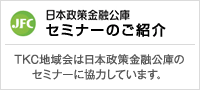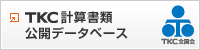年度末を迎え、資金繰りに窮して倒産する企業が続出するかもしれない。どうすればそれに巻き込まれず、会社を守ることができるか――。カギは取引先倒産の予兆をいち早くつかみ、適切な手を打つことにある。

昔から「火のないところに煙は立たない」といわれるが、取引先が倒産する場合も同じで、事前に何らかの“シグナル”が出ているものだ。
例えば昨年2月に会社更生法を申請した日本綜合地所であれば、世間から非難囂々を浴びた、あの“内定切り”が倒産の予兆だったとみることができる。
仮に月商1億円の会社が取引先の倒産で、500万円の焦げ付きを出したとする。これによって、すぐに会社が傾くことはないが、社内的には様々な問題が生ずる。(1)担当営業マンは焦げ付いた債権を回収しなければならいうえに、ペナルティーを科せられるおそれがある。そうなればモチベーションが下がり、新規開拓に及び腰となる。(2)経理や総務部門も事後処理に追われる。(3)500万円程度の焦げ付きが相次げば資金繰りにも影響が出、金融機関などからルーズな会社とみられ、信用を落とすことになる。
確かにここにきて倒産件数は減少しているが(〔『戦略経営者』2010年3月号9頁〕図表1参照)、これは「緊急保証制度」(08年10月施行)や公共工事の前倒し発注などの政策によるところが大きく、水面下では倒産予備軍が相当あるとみられる。このため、「景気対策」が途切れれば一気にそれが表面化(不良債権化)する危険性がある。
取引先が万が一倒産した場合、その焦げ付いた債権を自己資金で穴埋めできればよいが、できなければ金融機関などに頼ることになる。ところが、金融機関は「格付けのいい会社にはお金を貸すが、悪い会社には貸さない」という姿勢を鮮明にしてきている。実際、中小企業向けの銀行貸出金は07年9月以降、ずっと前年同月割れを続けていることが、その何よりの証拠だ(〔『戦略経営者』2010年3月号10頁〕図表2参照)。ということは、今まで以上に“リスクマネジメント”をきっちり行わなければ、連鎖倒産に巻き込まれ、会社と社員を守ることができないということである。
ワンマン経営の驕りが出始めたら要注意
リスクマネジメンとは、簡単にいえば取引先倒産の予兆を嗅ぎ取り、その対策を講じることを指す。
その予兆を「ヒト・モノ・カネ」の観点から、一覧表にしたものが図表3(〔『戦略経営者』2010年3月号11頁〕図表3参照)だ。全部で22個の倒産シグナルを挙げているが、当然、これら以外にも予兆はあるだろうし、こうした現象が起こったからといって、直ちに「危ない会社」というわけでもない。要は、常にアンテナを張っていち早く予兆をつかみとり、それを精査する仕組みを持たなければいけないということだ。
では、まずヒトに関する倒産予兆からみていくことにしよう――。ヒトについては、第一に取引先の社長が「ワンマン経営者」かどうかをみることが重要だ。最近のケースでは07年に破綻した英会話学校「NOVA」が挙げられる。同社は「駅前留学」を謳い文句に、一時は全国に1000店舗近く展開したが、受講生と解約をめぐるトラブルが続き、資金繰りが悪化して倒産した。創業者の猿橋望氏は社員に自らを「本部長」と呼ばせていたワンマン経営者で、その独善ぶりに歯止めをかけられなかったことが倒産に至ったおおもとだろう。そして、受講生との間で起きた“解約トラブル”が倒産の前兆だったとみることができる。
もちろん「ワンマン=悪」ではなく、「意思決定がはやい」といったメリットもある。要するに、ワンマン経営者は良い面と悪い面を併せ持っているため、たとえその取引先がいま飛ぶ鳥を落とすような勢いで伸びていても、背景(裏付け)のある経営者なのか、単なるブームに乗ってやってきただけなのかを見極めなければならないということだ。ここを見誤って取引量を拡大すると、痛い目に遭うおそれがある。
他方、昨年11月に会社更生法を申請した穴吹工務店の場合は、リーマン・ショック以降のマンション不況が破綻の直接的な引き金だが、役員間の不協和音があったこともその一因。不協和音とは、元オーナー社長の穴吹英隆氏と他の取締役との間でゴタゴタがあったこと。一般的に会社が窮地に追い込まれると、オーナー社長は個人資産や会社財産の保護に目が行きがちであるのに対し、サラリーマン役員は取引先や社員へのメンツにこだわる。この立場の違いによって、穴吹工務店の場合も泥仕合が起きたのだ。よって、そうしたゴタゴタが外部に漏れるようになったら、危ない会社とみたほうがいいかもしれない。
ヒトに関しては経営者の言動などに加え、幹部社員の動きにもアンテナを張る必要がある。ある地方都市の大手食品会社の場合は、経理責任者が倒産直前に心労で倒れたケースだ。なぜ病気になったのかといえば取引銀行ごとに10数種類の決算書を作成していたからだ。毎月銀行ごとに資金繰り表を作り替えていたのである。これでは心労で倒れたとしても不思議はない。粉飾決算は、このように経理責任者が必ず絡んでいるため、彼らが突然倒れたとか、退職したといったことが起これば、要注意である。
また、社員に関していえば、しょっちゅう求人募集を行っている企業も要警戒。社員は会社を映す鏡であるがゆえ、仮に社員が100人に満たないような会社で、人の出入りが激しければ、何か問題があると考えたほうがいい。
とくに最近では、やめた社員がインターネットの掲示板に「□□会社は金融機関から切られようとしている」とか、「決算が危ない」とかを書き込むことがある。そういう人が何人も出てくれば、それが事実無根であっても、打ち消すのは大変で、その“噂”が一人歩きすることがある。これを「レピュテーション・リスク(悪い評判が広まり顧客の信頼を失うリスク)」というが、そうした噂が出ること自体、脇の甘い会社と捉えることもできるため、前兆の1つとして頭に入れておくとよいだろう。
手形から現金払いに変更されたときの注意点
さて、今から20年前くらいまでは「事務所をみれば危ない会社がわかる」といわれていた。例えば事務所の蛍光灯がチカチカしていたり、トイレに行ったら花が枯れていたりとか、パッとみた第一印象で、危ない会社かどうかを見分けることができたわけだが、最近は少し「様相」が違ってきている。
むしろ今は「悪い(実態のない)会社」ほどみかけをよくみせようとしているからだ。例えば、倒産したNOVAのように社長室が超豪華であるとか、あるいは政治家や海外の要人と撮った写真を飾っているとかである。今や写真はパソコンで簡単に合成できるため、それだけで信用するのは禁物だ。
いずれにしろ、事務所を訪問したときの印象と経営実態とが合わない場合は注意したほうがいい。
一方、カネに関する倒産シグナルとして第一に挙げられるのは「支払条件の変更」だ。これは、(1)締日・支払期日の変更、(2)現金を手形に変える、(3)手形サイトの延長、(4)小額支払いも手形に変更、(5)手形ジャンプの要請、(6)支払ストップ――などを指す。こうした現象が次々に起これば要警戒である。
例えば、これまでA社では、「20日締めの翌月20日払い」だったのを、もっともらしい言い訳を作って「月末締めの翌月末払い」に変更したとする。「たった10日の違いではないか」と思われるかもしれないが、これも予兆の一つにほかならない。仮にA社の月商が3億円とすれば、その3分の1くらいの仕入金額の支払などを延ばすことができるからだ。だから締日・支払期日の延長を申し込まれたら、資金繰りが厳しくなってきた前兆と捉え、警戒体制に入るべきである。
ところで、ここにきて手形決済が減少し、代わって現金払いが増えてきている。実は、これによって上場企業も含め支払い遅れが増えてきているのである。具体的には何月何日に現金で支払うと約束したにもかかわらず、「10日間待ってください」などといわれるわけだが、それに対する罰則がないのである。1対1の取引だからだ。
一見、手形から現金払いに変われば「よかった」とみえるが、そこに落とし穴があるということだ。現金払いになったからといって、必ずしも即金で支払うとか明日支払うというわけではない。手形と同じで、1ヵ月後とか2ヵ月後に現金で支払う場合もある。手形なら1日遅れれば不渡りとなり、半年以内に2回目を出せば銀行取引が停止され、事実上倒産となるが、現金払いの場合は「待ってください」といわれるだけで、それを過ぎても倒産したことにはならない。だから箍が外れ、支払いが遅れがちになるのである。しかも、手形であれば割り引いたりすることもできるが、売掛金はファクタリングを利用するくらいしかない。それゆえ、現金払いに変更したことで取引先がある日突然倒産ということも考えられるため、ぬか喜びに終わらないように注意すべきである。
金融機関の取引先評価を「貸出金利」でチェック
もう1つカネに関する予兆として指摘したいのは、「貸出金利の変更」である。
中小企業が与信管理(取引先に対して信用を与え、それを金銭で表示して管理すること)を行ううえで難しいのは、取引先と銀行との関係がどうなのかということを、なかなか把握できないことである。
金融機関では、「定量的分析」(取引先の決算書から安全性・収益性などを評価)と「定性的分析」(市場動向や経営基盤などを評価)によって融資先を「正常先」「要注意先」などに格付けしている。現在では、それに応じて貸出金利を設定するのが一般的だ。金利が低い融資先は金融機関の信用が高い会社であり、逆に金利が高い融資先はそれが低い会社である。したがって、貸出金利の推移をみれば、その会社の信用力がどの程度なのかを推し量ることができるが、問題はどうやってそれを調べるかだろう。
1つは取引先の決算書(3期分程度)を手に入れ、支払利息の変化を調べてみる方法。2つ目は営業マンがそれとなく社長から聞き出すというやり方だ。そのためには、こまめに顔を出し、社長や経理担当者と親しくなり、「世間話」ができるようにしておくことが肝心だ。で、例えば「最近は銀行の貸出金利が上がってきていますが、社長のところは業界平均より低いのでは」と水を向けるわけである。すると、案外、社長が「そうだね」とか「うちはもう少し高いよ」などとしゃべってくれることがある。
中小企業の社長が資金繰りについて、関心がないとか話ができなければ、それだけで経営者失格といえる。なぜなら、貸出金利が0.1とか0.2%変われば、それによって何人ものパートやアルバイトの月給が賄えるからだ。この0.1%の金利にこだわる人は、性格がしつこいタイプかもしれないが、それくらいでなければ経営者はつとまらないのだ。だから貸出金利を“ネタ”に話をすれば、社長の才覚をかいまみることができるのだ。
営業がつかんだ情報は社内で共有化せよ!
それでは、そうした倒産シグナルをつかみ、リスクマネジメントをきっちり行うためには、どうすればよいのか――。
第一は社内で与信管理のルールを作り、それに基づいて「商品売買基本契約書」の考え方を徹底的に営業マンなどに教え込むことだ。例えばB社がC社と新規に取引を始めるとき、「何月何日締めの何月何日払いで、第1回目の商品を納品し、月々の上限は100万円まで」などを契約書に謳うわけだが、C社がそれに同意してくれればよいが、なかにはそれを嫌がる会社もある。
これまで中小企業では、契約書を結んで商売するというより、とにかく売上を上げればいいという趣があった。たとえ不良債権を作っても、それ以上に売り上げれば「よし」とする営業スタイルが一般的だったろう。だが、これからは、そうしたやり方は通用しなくなると思ったほうがいい。というのも、コンプライアンス(法令順守)の立場からすれば、契約書を交わさずに取引すること自体問題だからだ。さらに大企業の場合は、契約書だけでなく、正確な決算書の提出も求めている。
こうしたことから、当然、自社もそうなのだが、取引先に対しても契約書に基づいて商売を行うスタイルに改めていくことが大事だ。それが結局、会社と営業マンを守ることにつながるわけである。万が一売掛金が焦げ付いたとしても、それは社内ルールに基づいて販売したのであれば、担当営業マンだけの責任にはならないからだ。逆に、そうしたルールがなければ「君のせいだろう」と営業マンは言われ、そう言われると逃げ道がない。確かに契約書を結んで商売するというのは、現場の営業マンからすれば面倒臭いことかもしれないが、それが会社と自らを守る最大の“保険”なのである。
第二は、営業マンが知り得た情報はすべて社内で共有化することだ。例えば営業マンが得意先のD社長とゴルフを一緒に行くなど仲良くなったところ、「△△さん、ちょっと今月だけ支払いを10日間待ってくれませんか」と言われ、「わかりました」と答えたとする。このとき、営業マンがその話を直属の上司にすぐに報告し、上司が総務部あるいは経理部にその旨を伝えているかどうかがポイントである。つまり、そうした仕組みで与信管理している会社であれば、そのときだけのレアケースで済ませられるが、そうでない会社であれば、それをきっかけにD社からの入金がどんどん遅れるようになり、ある日、突然倒産ということもありうるのだ。
いずれにしろ、与信管理は大企業であれば審査部門が担当するが、中小企業の場合は営業部と総務部あるいは経理部がスキームを組んで行うことが重要である。このとき大事なのはメリハリをつけて行うこと。極端な話、年に1回しか取引がなく、それも現金取引の場合ならほとんどチェックする必要はない。大口の得意先か、継続かつ徐々に取引量が増えているところを、重点的に管理すればいいのである。その際“モノサシ”として活用するのは、これまで述べてきたような倒産シグナルを含む「定性情報」と「定量分析」であり、両者を突き合わせ総合的に判断して与信管理するのが望ましい。
(インタビュー・構成/本誌・岩崎敏夫)
掲載:『戦略経営者』2010年3月号