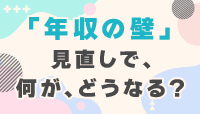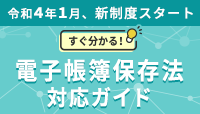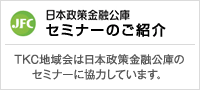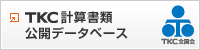昔から中小企業の社長は「数字に弱い」といわれ続けてきた。しかし会計は会社を成長させるための不可欠の要素。どうすれば数字に関心を抱き「会計力」を身につけることができるのか――。その方法論を解説する。

今の時代、中小企業の社長に求められている能力とは何か――。それは「経営力」と「会計力」を磨き、自社を革新させていくことだ。経営力とは商品開発や新規顧客を開拓することなどであり、会計力とはタイムリーに業績をつかむ“技”のことを指す。この両者をうまくかみ合わせてマネジメントしていかなければ現下のデフレ経済を乗り切り、年商を着実に伸ばすことは難しい。
しかしながら、大方の中小企業の社長は、経営力が重要であることは認識しているものの、会計力に関してはなおざりにしているのが実態である。毎月「試算表」が10日前後に社長の手にわたるような中小企業は、おそらく全体の半分にも満たないのではないだろうか。
そもそも中小企業が決算書を作成している大きな理由は、「税務署に申告書を提出しなければならないから」である。「会社を強くするため」という発想より、仕方なく記帳しているのだ。のみならず、なかには会計を社長と経理部長だけが知る“ブラックボックス”にして数種類の決算書を作成している「不届き者」も相変わらずいる。実際、ある金融機関の融資担当者は、「リーマン・ショック以降の急激な売上の落ち込みで、それまで粉飾決算してきた会社が、もはや隠しきれなくなって倒産するケースが増えている」と語っている。
「数字」をみて感動する仕掛けをつくれ!
なぜ中小企業の社長は会計を蔑ろにするのか。どうして「数字」に関心を持とうとしないのか。理由は、数字をみて感動するような仕掛けがないからだと思う。ある関与先企業の社長は「確かに最初の1年間はただ帳簿をつけていくだけなので面白くなかったが、2年目に入り『今月の売上は前年同月に比べてこんなに増えたのか』というようなことがわかると、毎月試算表をみるのが楽しみになりました」と話している。
実際、会計というのは、この会社のように毎月試算表をみていくことによって、何らかの感動があるはずなのだ。例えば、小売店であれば、新商品のチラシを繁華街で1000枚を配布して、「売上が前月に比べて2%増えた」ということがタイムリーにわかれば、自分の考えた打ち手(チラシ配布)がどの程度効果的だったのかを検証することができるわけである。
この仕組みを社内に導入することが、社長が会計力を身につけるための第1ステップにほかならない(〔『戦略経営者』2011年1月号9頁〕図表1参照)。より詳しくいえば、(1)日々発生する取引を複式簿記で会計処理する、(2)その会計取引の実在性を示す証憑書類(領収書・請求書等)を整理・保管し、(3)会計取引データを『戦略財務情報システム(FX2)』に入力して、(4)その会計処理が正しいかどうかを会計事務所の監査担当者が毎月巡回監査するというものだ。
要は『FX2』を導入・活用して「月次決算体制を確立」することである。
次に、会計力を磨いていくためのステップは「部門別業績管理体制を構築」することだ。部門別とは、営業所別、店舗別、得意先別などに分けて損益管理する手法のことだが、これを取り入れることによるメリットは、どの部門が会社の収益に貢献しているのか、どの部門が足を引っ張っているのかがわかるということだ。ただし、その際に注意しなければならないのは社長の戦略・考え方通りに「数字」がつかめるようになっているかどうかである。
例えばA社がイタリア料理店を2店舗(B店、C店)、カフェを2店舗(D店、E店)持っていたとすれば、4店舗別に分けて行うのが普通だが、A社長が「業態」ごとの収益も把握したいと考えていたら、これでは不十分である。その場合は、まず(『FX2』を導入している企業であれば)組コードを使ってイタリア料理店とカフェの2つに分け、次に部門別コードを使ってイタリア料理店組の下にB店とC店、カフェ組の下にD店とE店をぶら下げるわけである。こうすれば「両方」(業態別・店舗別)の業績を正確に把握することができる。
そうすると、仮に「今月B店に期間限定のスペシャルメニューを投入してみよう」と考えて実践し、B店の利益率が他の3店舗に比べてよかったとすれば、A社長もB店長も「やった!」と思うだろうし、それがA社の“活力剤”になっていく。このように「打ち手」とその結果としての「数字」と「喜び」とを結びつけていくことによって、社長の経営力も高まるのである。
さらにもう一つ、部門別会計を導入するうえで注意しなければならないのは、最初から完璧なものを目指すのではなく、社長や経理担当者の部門別会計に関する習熟度に応じて進化させていくということだ。具体的には、第1段階は売上から変動費を引いた「限界利益」までをつかみ、第2段階は限界利益から直接固定費を引いた「貢献利益」、第3段階は役員報酬や本社スタッフ給与などの間接固定費を引いた「経常利益」を正確に把握できるようにするわけである。役員報酬などを各部門に配賦するということは、経理の公開(ガラス張り経営)が部門別会計の前提条件になっているということだ。
計画に“魂”を込められるかどうかが成否のポイント
さて、ここまでくればかなり会計力を身につけてきたといえるが、もう1段上がある。それが第3ステップの「PDCAサイクルを回す」ことである。計画(予算)→実行→検証(評価)→改善というサイクルを回すことだが、とくに重要なのは計画に“魂”を込めることだ。
例えば年商9億円の会社が「来年は10億円を達成したい」と本気で考えていれば、それを必達するための具体的な行動計画を作成しなければ意味がないということ。魂が込められていなければ、当然、感動もないはず。「何がなんでも年商10億円をやるんだ」といって、全社員一丸となって取り組んだ結果、10億円を達成したとき、初めて人は感動するのである。
とはいえ、魂を入れようにも難しい場合も考えられる。商材に恵まれ右肩上がりで売上を増やしているようなところであれば、例えば「今期は月商2500万円だったが、来期は3000万円」と目標設定してもクリアできるだろう。が、リーマン・ショック後の不況で、売上が一気に3割も4割も減少しているような会社では、営業マンに予算を持たせても「絵に描いた餅」で終わる可能性が高い。実際、社長自身が意気消沈していて「予算作成会議」すら開けないようなところもある。
そうした会社の場合、短期(1年間)の経営計画では簡単に浮上できないことから、3~5年先を見据えて、自社が進むべき方向性(シナリオ)を示し、それに基づいて行動計画を作成するとよい。つまり「私(社長)がグランドデザインを考え、数字の責任はすべて負うから、それにしたがって、いろんなアイデア(打ち手)を出し行動計画を作成してほしい」という形でベクトル合わせを行うわけである。この行動計画をベースに『継続MAS』で「5ヵ年経営計画」を作成し、その1年目を切り取って『FX2』に落とし込めば、予実管理を実践していくことが可能になる。
長野県駒ヶ根市で飲食店などを経営するX社も、『継続MAS』と『FX2』を使って、PDCAサイクルを回しているケースである。同社では、「工場兼レストラン」と「Y店」「Z店」「その他事業」に分けて部門ごとに予算を作成しており、それが毎月達成できているかどうかを『FX2』から打ち出される試算表をみてチェックしている。こうした仕組みを構築したことによって、X社は上昇気流に乗り始めている。
実は、PDCAを導入するかどうかというのは“リトマス試験紙”のようなところがある。「『FX2』による予実管理っていいね」と、社長がすぐに反応を示す会社ほど成長度合いは大きく、さらにもう一歩進んだ管理手法である「BSC」(バランス・スコア・カード)を導入した関与先企業のなかには株式上場を果たしたところもある。だから、たかが会計と侮るなかれ。このように「3段階」で会計力を身につけていくことが、とりもなおさず“デフレに負けない会社”になるのである。
(インタビュー・構成/本誌・岩崎敏夫)