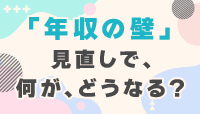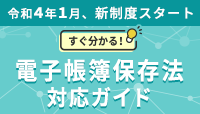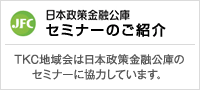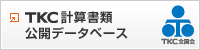地方の中小企業がブランディングで成功したケースとして注目を集めているのが4年後に創業300周年を迎える中川政七商店だ。仕掛け人は13代目の中川淳社長(37)。今や女性に大人気の「遊 中川」や「粋更kisara」ブランドをどのようにして軌道に乗せてきたのか。中川流ブランド戦略を聞いた。
- プロフィール
- なかがわ・じゅん●1974(昭和49)年生まれ。2000年京都大学法学部卒業後、富士通に入社。02年中川政七商店に入社してブランド戦略を展開。08年2月に社長就任。著書に『奈良の小さな会社が表参道ヒルズに店を出すまでの道のり。』(日経BP)などがある。
直営店の拡大で「遊 中川」ブランドを浸透

中川 淳 氏
――長引くデフレや急激な円高によって業績低迷にあえぐ企業が増えているなかで、毎年売り上げを伸ばしておられますが、その最大の要因は中川社長が02年に大企業をやめて戻られてから、本格的にブランド戦略を展開したことにあるといわれています……。
中川 そうかもしれません。当社は初代(中屋喜兵衛)が1716年に起こした会社で、「奈良晒」という手紡ぎ手織りの高級麻織物等の製造卸小売りを行う一方、茶道具の製造卸も手がけています。02年に私が入社したときには、父が仕切る茶道具(第1事業部)のほうが、専務の母が商品企画を担当していた第2事業部(麻織物などを使った和雑貨)より規模は大きかったです。第1事業部が年商約12億円の7割、残りを第2事業部が占めていました。当時、当社には和雑貨を扱う「遊 中川」というブランドしかなく、それを卸(第2事業部売り上げの約8割を占有)と小売り(約2割)の2つのチャンネルで販売していました。
入社当初は第1事業部に籍を置き、配送などの仕事をしていたのですが、週に1回は第2事業部にも顔を出していました。すると、どうも第2事業部の様子がおかしくて何を聞いても、誰からも納得のいく答えが返ってこない状態でした。例えば商品の生産数量を誰が決めているのかはっきりしないし、いま仕掛かり中の商品がいくつあるのかもわからないなど、一事が万事そんな調子でした。「これはまずい」と思い父に麻部門への異動を願い出て、こちらに専心するようになったのです。
――そのときから08年2月に社長になるまでの丸6年間はもっぱら第2事業部に関わり、生産管理のIT化や社内ネットワークの構築などの“改革”に取り組まれたそうですね。
中川 はい。当時、何を考えていたのかといえば、いかにして他社との競争に負けないようにするかです。例えば百貨店の売り場に商品(和雑貨)を卸せば、当然、そこにはいろんなメーカーの商品も並んでいて、お客さまは価格やデザインなどを見比べて選ぶと思いますが、そのときにどうすれば有利な状態で競争に臨めるかを考えていました。それは商品に「ゲタ」(アドバンテージ)を履かせるというイメージですが、問題はどうやったらそれができるかです。答えはブランド力を底上げすることだろうと。つまり遊 中川というブランドをもっと多くの人に知ってもらい、かついい印象を持ってもらえれば、当社の商品を選んでいただけると考えたわけです。
――そのための手段として直営店の拡大をはかったそうですが、その理由は。
中川 ブランドはお客さまの頭のなかで作られるものですが、それはロゴやカタログなどの“タッチポイント”を通じて入ってくるさまざまな情報を、その人なりに頭のなかで整理・編集して作られます。ブランド力を底上げする方法として直営店の拡大を進めた理由は、ショップほどこのタッチポイントを数多く有しているものはないからです。実際、ショップには商品はもちろん、店員による接客やリーフレットなど多くのタッチポイントがあります。
1983年に遊 中川というブランドを立ち上げてバッグやふきんなどを商品化して地元に店を構えて売り出したのが、当社における小売りの始まりですが、それを点から線、面へと広げていけば、遊 中川ブランドを多くの人々の頭に植えつけることができるだろうと。そこで02年に伊勢丹新宿店、03年に玉川高島屋SC店などに相次いで出店して認知度を高めていきました。現在、その数は23店舗にのぼります。
――それは地方の中小メーカーがブランディングを行う上で「小売りをやる」ことが非常に有効な方法ということですか?
中川 そうだと考えています。ただし、それを行うにあたっては注意しなければならないことがあります。メーカーとショップでは開発サイクルが違うということです。メーカーの場合、年に2回カタログを作って展示会を開き、新製品を発表するのが一般的ですが、これではショップの場合、いつ行っても同じ商品しか並んでいないということになり、来店客が徐々に減っていきます。そこでショップの鮮度を保つため、当社では企画やデザイン力を強化して2週間に1度(年約26回)の割合で新商品を店頭に置くようにする一方、直営店の売り上げデータを正確かつ迅速に把握できる業務システムも独自に開発・導入しました。
さらに3つ目として、システム導入を機にアルバイト店長の正社員化をはかるとともに、年2回の考課できちんと評価する人事制度に変えました。そうした結果、遊 中川が扱う商品点数は以前に比べて約5倍増の2500点となり、和雑貨の世界では一目置かれる存在(ブランド)になっています。
贈りものの体裁まで気を配る「粋更」の魅力
――2003年に第2ブランドとして日本の工芸をベースにした生活雑貨のセレクトショップ「粋更」を立ち上げましたが、その狙いについて説明していただけませんか。
中川 第1の理由は、当時、遊 中川は『家庭画報』や『婦人画報』などを読むようなミセスをメーンターゲットにしていたため、私自身がほしいものとは“ズレ”があったこと。2番目はその頃、高級インテリアショップなどに行くと、布物のほとんどが海外製品で、日本製がまったくなかったこと。つまり当社独自の織物技術を生かして、「カッシーナ」のようなインテリアショップに置いてもらえるようなものを作れば、新たな顧客層を掘り起こせると考えたわけです。
きっかけは、03年に開かれたインテリアの専門見本市に出展してほしいという依頼があったことです。ちょうど遊 中川の展示会が終了した直後だったので、いい機会だと思い、前々から考えていた第2のブランドづくりに乗り出したわけです。
――その際、粋更ブランドとしてどのような物を開発して展示会に出展したのですか。
中川 ベッドスプレッドや枕カバーなど約30点を出展しました。商品自体は今みてもそんなに悪くないと思うんですが、見本市後にインテリアショップへ営業に行くと、まったく置いてもらえませんでしたね。2年くらい赤字が続き、このままならおしまいにしなければと思っていた矢先、「表参道ヒルズ」への出店公募を目にしたのです。約80店のテナント募集に対して、資料請求は数千にのぼったと聞いていますが、当社はその狭き門を見事かいくぐってOKをいただき、「粋更表参道ヒルズ店」を06年2月にオープンさせました(今年1月に閉店。5月には新丸ビルに新たなフラッグショップがオープン予定)。
――奈良の老舗企業が表参道ヒルズに出店したということで一躍脚光を浴びましたが、粋更がヒットしたのはそれだけではない。コンセプトを「日本の新しいカタチ」と「贈りもの」にしたことが最大の成功要因とみられますが……。
中川 そう思います。比較的人気の高い商品として「漆の小さなハートピンバッジ」や「筆ペン」などが挙げられますが、いずれも非日常的というか、ちょっとよそいきのときに使いたい物をイメージして企画・商品化しています。
筆ペンもそのままならギフトになりませんが、洗練された桐箱に入れれば贈りものになります。最近、昔の形態のギフトショップがなくなってきていますが、パーソナルな贈りものニーズは依然としてあり、粋更はその受け皿的な役割を果たしています。その際、日本の工芸品を扱うセレクトショップなのに、西洋風のリボンをかけて贈るのは違和感があると思い、その中身にふさわしい贈り方として「折形」を取り入れました。
折形は紙を折って物を包む日本の礼儀作法の一つですが、誰に贈るかによって形や紙の種類が変わってきます。このため、お客さまにどのような理由で誰にプレゼントするのかを聞いた上でお包みします。実は、この折形を有料(100円)にしているのですが、理由は《粋更なら物を贈る体裁まで気をつかってくれる》ということをお客さまに知ってもらいたいからです。たかが折形かもしれませんが、その折形を通じてお客さまと良好な関係を作ることができれば、リピーターになってくれるでしょうし、友人の方にも「贈りものを買うなら粋更がいい」とすすめてくれるのではないかと。
「会社名」をブランドにした理由と背景
――さて2010年に「中川政七商店」という社名そのものを第3のブランドとして立ち上げましたが、その狙いは何ですか。
中川 2007年からお世話になっている水野学さんというアートディレクターに、あるとき「遊 中川と粋更はお客さまに支持されているけれど、300年の歴史は感じられない。そこが今の中川政七商店の最大の課題」と指摘されました。私も常々そう思っていたので、「暮らしの道具」をコンセプトに中川政七商店(以下、政七)を第3のブランドとして起こしました。遊 中川と粋更が日常よりちょっと上のランクの物を対象としているので、政七はそれらとは逆の、日常生活に根ざした物を守備範囲にすることにしました。
――実際、「帆布トートバッグ」などをみると、実用的でおしゃれな感じがしますね。
中川 このバッグは帆布の産地である倉敷のものを使っていて、今や政七の「定番商品」になっています。実は07年頃に「日本の伝統工芸を元気にする!」を、当社のビジョンとして打ち出したことがその背景にあります。
なぜ日本の伝統工芸品を元気にしたいと思ったのか――。当社は数百社の取引先とスクラムを組んで物を作っていますが、毎年3~5社くらい“廃業”の挨拶にこられます。このまま行ったら、当社も物が作れなくなってしまうかもしれないと思ったからです。そこで、彼らを元気にする方法として考えたのが「政七を流通の出口として活用する」ことでした。
――政七が帆布などの素材や商品を仕入れれば、取引先を元気にすることができると。
中川 そうです。物を買うというのが一番手っ取り早い方法ですが、それ以外にも当社の自社商品を作ってもらう(OEM生産)という方法もあるし、当社が取引先のブランディングをコーチ(コンサルティング)してあげるという方法もあります。どちらにしろ、政七に流通の出口を担わせるにはある程度の量をさばけるだけのパワー(店舗数)がなければダメで、その数は47都道府県に1つ以上の60店舗は必要だろうとみています。現在の政七の店舗数は4店舗ですが、自社商品と他社商品の取扱比率は約5対5です。
――中川社長が取引先をコンサルティングして、自社ブランド化に成功したケースというのは。
中川 その好例は、長崎県の焼物メーカー「マルヒロ」さんの「HASAMI」というブランドです。長崎県波佐見町は大衆食器の産地として知られており、窯元が40~50あります。マルヒロさんとは以前から取引があり、08年に私が著した『奈良の小さな会社が表参道ヒルズに店を出すまでの道のり。』という本を、同社の馬場幹也社長が読んだのがきっかけでコンサルの依頼がきました。で、コンセプトを「道具としての器」として開発に取り組んだところ、マグカップなどが商品化され、それがいま市場で大人気になっています。
――3つのブランドを軌道に乗せることができた要因としてブランドマネジャー制を導入していることが挙げられますが、その役割について教えてください。
中川 当社の業務組織は大別すると販売部と商品部からなり、販売部の下に卸売課と小売課と通販課があり、商品部の下に商品企画課と生産管理課があります。これら業務系とは別にブランドごとに「ブランドマネジャー」を置いているわけですが、それはブランドイメージをキープするためです。
例えば生産管理課で、ブランドごとに適している素材や商品を見極めるのは非常に難しい。許容できる範囲とできない範囲があり、それをジャッジするのがほかならぬブランドマネジャーです。また、小売課で販促イベントをやるにしても、例えば粋更なら粋更らしいやり方とらしくないやり方があるので、ブランドマネジャーがその都度チェックしなければ、ブランドの統一感が失われ、お客さまに正しくブランドイメージを持ってもらうことができなくなります。
いずれにしろ、私がこの10年間経営者としてやってきたのは物をいかに売るかではなく、いかにしてブランドを創るかということでした。外からみれば、どちらも物を作って売っているだけではないかといわれるかもしれませんが、まったく違います。発想を転換してブランディングに乗り出せば、会社を“大革新”させることができるのです。
(インタビュー・構成/本誌・岩崎敏夫)
| 名称 | 株式会社中川政七商店 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市東九条町1112-1 |
| TEL | 0742-61-6676 |
| 年商 | 24億円 |
| 社員数 | 200名 |
| URL | http://www.yu-nakagawa.co.jp/ |