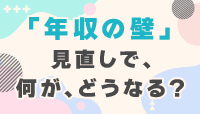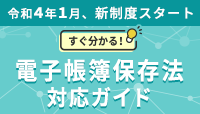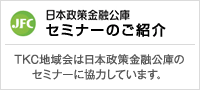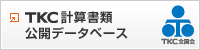経営戦略の実行を担う「現場」の力を底上げすることは、中小企業にとっても重要な課題である。ありふれた「平凡な現場」を卓越した「非凡な現場」に変えていくためには何が必要になるのだろうか──。
- プロフィール
- えんどう・いさお 早稲田大学商学部卒業。米国ボストンカレッジ経営学修士(MBA)。三菱電機、米系戦略コンサルティング会社を経て、現職。早稲田大学ビジネススクールでは、総合経営、オペレーション戦略論を担当。また、欧州系最大の戦略コンサルティング・ファームであるローランド・ベルガーの日本法人会長として、経営コンサルにも従事している。2004年に出した『現場力を鍛える』(東洋経済新報社)は15万部を超えるベストセラーになり、発売後10年経ったいまでも増刷が重ねられている。『見える化』(同)、『現場力の教科書』(光文社)、『現場女子』(日本経済新聞出版社)など著書多数。
──遠藤先生が書かれた『現場論』(東洋経済新報社)を私も読ませてもらいました。ロングセラーを続けている『現場力を鍛える』(同)をはじめ、遠藤先生の著書が売れているのは、それだけ現場に悩んでいる経営者が多いからではないでしょうか。

遠藤 功 氏
遠藤 正直言うと、悩むところまでさえ到達できていない経営者が多いのが実情です。規模の大小を問わず、数多くの現場を見てきた私からすると、企業によって現場力(*1)にはだいぶ格差があります。卓越した現場力をもつ「非凡な現場(*2)」もあれば、「平凡な現場」や「平凡以下の現場」もある。でも、現場力の違いは外からは見えにくいんですね。戦略については、どんな製品を出しているか、どんな宣伝をしているかでだいたい分かりますが、現場力については外からは見えにくい。それをよいことに「うちはそこそこ」だと勝手に思い込んでいる経営者がじつに多いんですよ。そうした経営者にもっと問題意識を持ってほしいというのが、『現場論』を通じて私がもっとも言いたかったことです。
──『現場論』に、「『しか』を『でも』に変える(*3)」という話が出てきます。中小企業の場合、同じ事業規模を同じメンバーで10年、20年とやっているところが多く、社員も「自分しかできない仕事」を囲い込んでいく傾向があります。「○○しかできない」を「誰でもできる」に変えていくためにはまず何が必要ですか。
遠藤 それぞれの従業員が勝手に自分の専門分野を作ってしまい、「私はこれしかやらない」あるいは「これしかできない」という状態になっているのは、確かに中小企業の典型例といえます。経営者もその状況を放置しているし、なかにはむしろエキスパートとしての道を究めさせた方がよいとさえ考えている人もいる。でもそれは、結果的に働く人たちの能力をせばめてしまうことになります。もっと別の仕事ができる能力を持っているかもしれないのに、ある特定分野だけに特化させて、そこに閉じ込めておくのはあまりにもったいない。もちろん専門性を高めることも大事ですが、「その人は本当にそれしかできないのか」「それを他の人がやることはできないのか」と、広い視野を持つ必要があります。
「しか」が多い現場は、競争力がありません。マルチタスク、つまり「多能工化」できている会社のほうが断然強いのです。私が、「しか」が多い会社に対して「お宅の会社は〝しか(鹿)〟ばかり多い奈良公園ですね」と揶揄して改善を促しているのは、そうした理由からです。
──ただ従業員のほうも、ある特定の仕事に執着したがる傾向があります。
遠藤 そのほうが楽だからですよ。自分が長年やり続けてきたことだけをやっているほうが断然楽なんです。だからそこに執着しようとする。しかし、そこから引き剥がさないと、その人が持つ本来のポテンシャルを生かし切れない。実は多能工化は、会社にとってもいいし、従業員にとっても実は楽しいものなんです。「私はこれしかできません」ではなく、いろいろなことができるようになれば働いていて楽しいし、そこから新しいやりがいを見つけることも可能です。こうしたことを経営者自身がきちんと現場に伝えていかないと、いつまでも「しか」だけの会社のままです。
まずは1ミリの改善から

聞き手/本誌編集顧問・
多勢陽一税理士
──大きな改善を一気に目指すのではなく、「微差(*4)」にこだわっていくことが現場力の強化には重要といった話も書かれていました。「微差」がどういうものであるかをもう少し詳しく教えてください。
遠藤 たとえば顧客に対し、「なぜうちに注文してくれているのですか」と聞いたとき、「圧倒的な技術力で他社の追随を許さないから」という回答が返ってくることは中小企業の場合、まずないと思います。そんな圧倒的な差があるのなら、とっくに大企業になっていてもおかしくないからです。おそらく大多数は「他社もいいものを作っているけど、お宅のところは融通がきくよね」とか「ここの部分については品質が安定しているよね」といった、ちょっとした差異で選んでもらっているのだと思います。このわずかな差こそがまさに「微差」です。それを単発ではなく、「たった1ミリでいいから、よりよくしていく」といった改善の努力を組織全体で継続的に行っていける現場は強いといえます。
──継続してとなると、なかなか難易度が高そうですね。
遠藤 非常にレベルが高いです。それでもとにかく、1ミリでもいいから前に進むんだという気持ちで頑張ってみることが大切です。
今はやたらと「イノベーション」や「革新」という言葉がもてはやされていますが、1ミリの微差も生み出し続けられない会社がイノベーションを実現できるはずなどありません。私は、イノベーションは微差の積み重ねによってしか生まれないと考えています。たとえばコストを50%下げるという目標を立てても、一気に下げることは不可能に近い。でも、まずは1%でも下げるところからスタートし、それができたらまた1%下げましょうとやっていくと、現場がいろんなことを考えるようになる。そうすると次は5%下げることを考えるかもしれない。それも実現したら、今度は10%下げることにチャレンジ……と成功体験を繰り返していくなかでイノベーションが生まれてくるのです。
登山と同じで一気にゴールにはたどり着けません。「微差」にこだわりながら、少しずつ前進し続けることが肝要です。
──ともすれば経営サイドは早く結果がほしいとあせるものだから、途中の過程をなるべく早く通過したいと思ってしまいがちですが、それではいけませんね。
遠藤 ええ、現場力にマジックはないのです。「よりよくする能力」「新しいものを作り出す能力」を持ち続けられるかどうかが、「平凡な現場」が「非凡な現場」に変われるかどうかの分かれ目のひとつになります。
経営者は「夢」を語るべき
──最後の第9章(「経営者の役割」)のなかに「現場は経営者の『映し鏡』である」との一文が出てきますが、それがたいへん印象的でした。経営者にしてみれば「うちの現場ももう少し自発的にやってくれればな……」という思いがあるかもしれませんが、経営者自身もそのためのアクションを何も起こさずに、そこで止まってしまっている。そのこと自体に問題があるのでしょうね。
遠藤 現場で何か問題が生じたら、それは現場スタッフの責任ではなく、自分の責任だと思わなければなりません。たとえば品質問題を起こした現場であれば、それは経営者の品質に対する配慮が足りなかったからなのです。よい現場にできるかどうかは、結局は経営者しだいなんです。経営者と現場は、まさに「表裏一体の関係」にあります。現場を変えるには、まずは経営者自身が変わらなければならないのは確かです。
これは結果論かもしれませんが、よい現場には厳しさのなかにも笑顔と明るさがあります。ダメな現場はすぐに分かりますよ。みんなの表情が暗く、重い。そんな現場に誰がしたかといえば、それはやっぱり経営者ですよ。現場には、経営者の人間性がそのまま出てきます。厳しく接することも重要ですが、それだけでは現場に笑顔ひとつ見られなくなる。しかし、経営者にもっと現場を鼓舞するような前向きで明るい言動があれば、笑顔の多い活気に満ちた職場になるんです。現場は、経営者の言動にすごく敏感ですから。
──私からすると、中小企業については、社長と社員が友だちのような意識で、和気あいあいとしているのはいいのですが、多少緊張感に欠けているようなところがある気がします。
遠藤 中小企業の最大の強みは、経営者と現場との距離感の近さにあります。コミュニケーションを取りやすいし、一心同体になりやすい。ただし同一化してしまっては意味がない。経営者は目標を与えることが役割、現場は目標を達成するのが役割なんです。この役割分担をきちんとまっとうすることが大切ですね。
経営者が大きな目標や志をしっかり語ってあげないと、現場を引っ張ることはできません。現場は「夢」をほしがっています。だけど現場が自ら夢を描くことはできない。経営者が夢をきちんと語ってあげなければ、現場は未来へと向かうことができないのです。
──夢を語ることは経営者の義務ですね。
遠藤 最大の仕事と言えるかもしれません。どの会社も、世の中のために何らかの価値を提供したいと考えているはずです。その夢を語っていかなければ、現場に火を付けることはできないでしょう。現場が求めているのはまさしくそこ。みんな「火を付けてくれ」と待ち望んでいるのです。
現場の「誇り」が起爆剤となる
──遠藤先生がそもそも「現場」というものに注目するようになったきっかけは?
遠藤 さまざまな企業の経営コンサルを長年やっていくなかで、よい戦略を作ったり、よい計画を作るものの、実行力が伴わないばかりに「絵に描いた餅」で終わってしまうケースを数多く見てきました。そうしたなかで、実行力の源である現場の力をどう高めていくかが経営にとっていかに大切であるかに気付いたんです。
たとえばトヨタのように実行力がある会社だと、どんな戦略を作ってもやれてしまう。逆に、実行能力が低い会社はできることが限られるため、その中から選択肢を考えざるを得なくなる。つまり、実行力の乏しさが戦略の選択肢をせばめてしまう。やはり企業にとってまず大事なのは、現場力をいかに高めていけるかなんですよ。
──日本企業の現場力は高度成長の時代と比べて弱くなっているのでしょうか。
遠藤 そう思います。「失われた20年」の最大の問題点はそこにあります。外部環境の変化によって国内企業の多くが近視眼的になってしまった結果、「現場をリストラする」「ギリギリの人数で回す」「正社員を非正規社員に変えていく」といったコストダウンを押し進め、現場にさまざまなしわ寄せがいった。加えて、団塊の世代が定年退職を迎えたこともあり、それまで培ってきた技術がきちんと継承できなかった。そうした理由から、現場の能力がしだいに劣化していったのです。
──現場が弱体化した会社もある一方で、優れた現場力を武器に好調な経営を続けている会社もあります。両者を隔てたものは何だったのでしょう。
遠藤 自動車部品メーカーのデンソーは、赤字に転落して経営の危機が叫ばれたとき、コストダウンのために自社の根幹となる部分を子会社として分離したり、内製をやめて外注することを考えたそうです。しかし一度は取締役会で決議されたものの、すぐに思い直して内製化を維持していく方針に戻しました。結局このときの決断の正しさが、いまのデンソーの好調な経営を支えているわけです。この話に限らず、現場を単なるコストセンターと見立てて会社の根幹となる部分を安易に社外に出してしまった会社と、あくまでバリューセンターとして内部にとどめておいた会社とではその後、雲泥の差が出ました。
──そう考えると、子会社をいくつも作り、技術を外部に出してしまった大手電機メーカーS社さんなどは危ないですね。
遠藤 そうですね。現在の不振は、肝心なコアコンピタンス(競争の核となる能力)を切り離していってしまったことが一番の原因です。現場の主役であったナレッジワーカー(*5)が外に出てしまったわけですから。
──いま経営状態の悪い企業は、これから一人でも多くのナレッジワーカーを育てていくしかない?
遠藤 というか、そこしかありません。足元の競争力を高めなければ、企業の再生はあり得ません。
まずは現場で働いている社員の能力を最大限に生かすためには何をすべきかを考える。先ほどの「しか」(多能工化)の話もそうだし、「微差」でいいから1ミリ伸ばす努力をしているか、ということです。微差を自発的に生み出せるナレッジワーカーが現場にたくさん増えれば、企業は必ず力強さを取り戻していきます。
──そのような方向性のもと、各企業が現場力を高めていけば、いずれ日本経済も元気を取り戻すかもしれません。
遠藤 日本企業のなかでも、ものづくりの現場力が劣化する一方で、実は小売業やサービス業については現場力を高めてきました。彼らは製造業をお手本として、現場力の向上に努めてきた。その結果、ナレッジワーカーが大勢いるヤマト運輸のような会社も生まれたし、良品計画のように業務改善を継続的に行っていける小売業の会社も出てきたわけです。
いまは金融の世界にもそうした流れが生まれていて、さかんに現場力が大事だと言いはじめている。それがなぜかというと、画一的に本部が決めた戦略では、もう成長なんかできないと考えるようになったからです。それぞれの地域ごとにお客さまのニーズが違う。営業の最前線から一番遠い本部で考えた戦略なんて、まったく機能しません。そこにようやく気付いたのです。
日本企業が世界に比べてどこに優位性があるかといえば、強い現場を実現するだけのポテンシャルを兼ね備えた「ヒト」の部分だと思います。基本的にまじめだし、勤勉だし、組織に対するロイヤルティーも高い。この強みを生かしつつ、もう一度原点に立ち戻って経営を組み立て直していくことが、業界を問わず今後ますます必要になってくるのではないでしょうか。
──経営者は現場のスタッフに対し、「変わろう」とずっと発信し続けることが求められますね。
遠藤 そのときに現場力という言葉を使うと、現場の人は必ず反応します。現場力という言葉にはものすごい求心力がある。「現場力を示せ!」と発破を掛けると、みんな目の色が変わるんです。
──誇りがあるのでしょうね。
遠藤 そう。「お前たち、現場力があるんだろう?」というと必ず反応する。これは他の国では絶対に見られないことです。
(構成/本誌・吉田茂司)
『現場論』(東洋経済新報社/本体1800円+税)
「平凡な現場」を「非凡な現場」へと転換するための論理と実践について詳しく解説した良書。現場力が進化する過程を3つのプロセスで解き明かす。
- <注釈>
- *1 現場力
- 現場力という組織能力は、次の3つの異なる能力による「重層構造」になっている。①保つ能力②よりよくする能力③新しいものを生み出す能力。これら3つの能力が重なり合い、複合的に形成されているのが現場力である。
- *2 非凡な現場
- 現場の能力格差は大きい。遠藤氏は『現場論』のなかでその能力格差を「平凡以下の現場」→「平凡な現場」→「非凡な現場」と3つに分類。現場から新たな価値が継続的に生み出される卓越した現場力をもつのが「非凡な現場」だ。
- *3 「しか」を「でも」に変える
- 「私しかできない」「彼にしか任せられない」「これしかやらない」など、仕事が属人化し、放置されたままになっているような「しか」が多い現場は生産性が低い。それを「誰でもできる」「新人でもこなせる」といった具合に標準化を進めていくことが、現場を強くしていくためには必要となる。
- *4 微差
- 「改善」によって生まれる差異は、ひとつずつを見れば「微差」でしかない。しかし、競争という視点で見れば、「微差」は決定的な差になり得る。
- *5 ナレッジワーカー
- 「知識」により付加価値を生み出す「知識労働者」のこと。マニュアルワーカー(単純労働者)とは対局の位置にある。「非凡な現場」をつくるということは、ナレッジワーカーの量と質を高め、現場をナレッジワーカーたちで埋め尽くすことにほかならない。