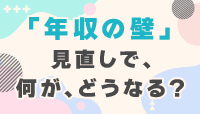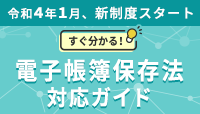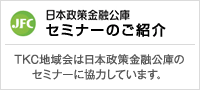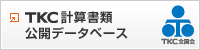『未来投資戦略2018』の重点施策の一つとして「農林水産業のスマート化」が掲げられるなど、農業ではいま、「農家」から「農業経営者」への転換が求められている。法人化や会計への注力、ITやロボットテクノロジーの活用などで成長を遂げた農業経営者を取材した。
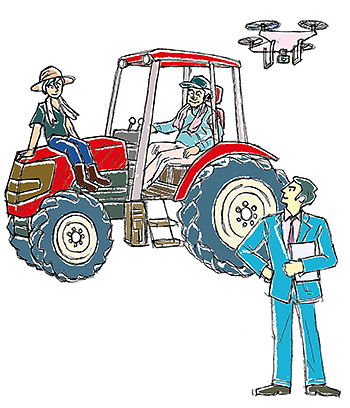
日本の農家の数はものすごい勢いで減っている。農業構造動態調査の結果によると、家族経営体と組織経営体を合わせた2017年の農業経営体の数は、125万8000。これは2010年の167万9000の4分の3の水準である。なぜ減っているのか。端的にいえばもうからないからである。日本の農業は、家族経営の農家が農協(JA)を通じて出荷する「系統出荷」という独特の仕組みを構築してきた。しかしすでに「作物をつくれば売ってくれる」時代はもう終わりを迎えつつある。自分で売り先を探さなくてはいけない時代に入っているのである。
販路を広げたいと考える若い経営者などが、JAを通さず付加価値つけたブランド米や果物を系統外で販売する事例が山ほど出てきている。こうした状況を踏まえ、成長を目指す農業のキーワードとなるのが、法人化だ。実際法人化している農家は、作業場以外のオフィスを整備したり、社員を定期雇用したりしているケースが少なくない。データ上もその優位性は明らかであり、平成28年度の「食料・農業・農村白書」によると、農産物販売金額全体に占める法人経営体の販売金額シェアは27.3%に達している。数でいえば全体のたった数パーセントにすぎないにもかかわらずである。5億円以上の売り上げがある法人は2015年には800を超えており、法人化が収益性の向上と雇用確保につながっていることが分かる。
農業法人5万に引き上げ
政府は2014年に公表した日本再興戦略で、向こう10年間、2023年までに農業法人の数を5万法人に引き上げる目標を掲げた。これを受け農林水産省も、積極的に法人を増やす施策を打ち出している。法人化の一つのメリットは、規模拡大と農地の集約化が容易になることだ。飛び地になっている農地が同一の法人になれば、一つながりのあぜを切り一気に機械で作業でき、生産性の向上が期待できるからである。
では現状はどうか。2017年の農業経営体数125万8000のうち、いまだ家族経営体は122万3000を占め、組織経営体は3万4900にすぎない。組織経営体には法人以外の集落営農なども含まれるので、会社組織のような一般的な法人組織は2万を超える程度である。2009年に農地法が改正され、リース方式による参入が全面自由化となり、一般法人の農業参入が大幅に伸びたのとは対照的に、緩やかな増加にとどまっている。
個人経営を含めた日本の事業者数は約385万者ある。このうち法人数は261万社で全体の68%に達する。一方農業における法人数は農業経営者全体数の2%に満たない。どちらも同じ経営なのに、この比率の差はやはりおかしい。行政もこうした現状に危機感を募らせており、インセンティブを与えるため、法人でなければ活用できない補助金制度などを整備しはじめた。例えば高知県では、オランダなどで盛んに行われている高さ5~6メートルに達する次世代型軒高ハウスの設置に補助金を出してきたが、この補助を受けられる条件の一つに法人化が含まれている。
また経営意欲のある農業者が創意工夫を生かした農業経営を展開できるよう、農業者の経営課題に対し関係機関が適切にアドバイスを行う「農業経営者総合サポート事業」も本年度からスタートした。同事業では、税理士等の専門家などが支援チームとなる「農業経営相談所」で集落営農等が経営相談などを行った場合、法人化(定額40万円)や組織化(定額20万円)における取り組みを支援する。
そもそも法人化による直接のメリットとは何だろうか。まず社会保険および厚生年金加入による福利厚生の充実で、人材確保がしやすくなることが挙げられる。農家が法人化を希望する際、これを最大の理由にする経営者は意外と多い。さらに適時、正確な記帳に基づく決算書や法人登記による証明書で、金融や取引の場などにおける対外信用力が格段にアップする。販路の拡大や輸出への道も大きく切り開かれてくる。
個人事業主として青色申告する場合は、1~12月が決算期と決まってしまうが、法人は自由に決算期を設定できるのもメリットだ。施設園芸の多い高知県ではキュウリの栽培が盛んだが、9月から作付けをはじめ、収穫が終わるのが6月というのが一般的。1月から12月という決算期を強制的にあてはめると、実際の作業の年間サイクルとは異なるので経営の実態をつかむのが非常に難しくなってしまう。これが7月決算であれば前年度の比較も容易になり、とても分かりやすくなる。
事業承継もスムーズに
国は法人化の促進によって農業者の所得を何とか増やしたいと考えているわけだが、それは同時に、農家も経営感覚を養わなければならないことを意味する。そのためには何としても会計を強くしなければならないだろう。農家は3月の確定申告時に「今年の税金はどれくらいか」ということだけに関心を奪われがちだが、日頃から売り上げと経費、それを差し引いた利益を把握しながら経営を行う必要がある。
私が顧問税理士を務めている農業法人でも、社長が会計に力を入れ業績を伸ばしたケースがある。例えば個人農業から法人化して今期で7期目となるI社。ショウガやトマト、キュウリなどを施設園芸で栽培していたが、赤字続きで苦労していた。そこで当事務所の担当者からのアドバイスを元にTKCの『継続MASシステム』を活用して予算と実績を常に見返すようになった。すると3年半で黒字になり毎期1000万円を超えるキャッシュフローが出るまでになったのである。後手に回っていた実態の把握がよりタイムリーに行え、予算達成のための打ち手を早めに講じることができるようになった。
法人化としっかりした会計の整備で業績が上向けば、事業承継もスムーズに進む。一昨年法人化したY社は、自ら販売ルートを開拓して堅調な業績を維持している会社だが、同社が法人化した理由の一つが事業承継だった。
労働基準法などが適用されない個人農家では、土日祝日関係なく仕事場に出るのが一般的。これを嫌って親族が跡継ぎを拒否するケースが多いが、Y社の社長は法人化によって社員を採用し、後継者が計画的に休日をとれる環境を作り出したのである。法人化をきっかけに社員や幹部人材を採用した結果、息子が事業承継を決意、代替わりを果たし今では息子が経営者として辣腕(らつわん)をふるっている。規模拡大と雇用、事業承継すべてが順調にいったケースだが、これができたのもきちんと利益が出ていたからこそ。もちろんしっかり利益を出すためには、会計にもとづいたPDCAサイクルを回す自立型経営がなされていなければならない。
PDCAサイクルとは、経営計画を立てる(プラン)、計画に基づき実行する(ドゥー)、計画と実績の検証を行う(チェック)、計画・実績差の対策を行う(アクション)の循環を指す。農家が複数年にわたる経営計画をつくるケースとしては、5年後の目標とその達成のための取り組みを「農業経営改善計画」として作成し市町村へ申請し、認定を受けると補助金や税制で優遇を受けられる「認定農業者制度」が知られているが、同制度は計画が着実に実行されているかどうかモニタリングできないという難点がある。つまりPDCAサイクルでとりわけ重要なのは、予算と実績を毎月チェックする「C」の部分である。
経営にはヒト(組織)、モノ、カネ、情報、それに会計が必要だ。しかしヒトとモノはそろっていても会計が遅れているという農家がまだ多い。農業も経営である以上、会計の力が極めて重要なのである。
(インタビュー・構成/本誌・植松啓介)