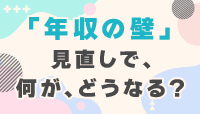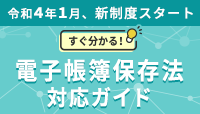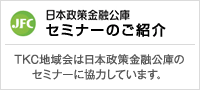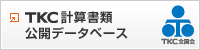店舗を持たず自社のECサイトだけで商品を販売するD2C(ダイレクト・トゥー・コンシュマー)ビジネスが急成長を遂げている。有識者へのインタビューやケーススタディーを通して、D2Cビジネスの全容をひも解く。
- プロフィール
- いばた・たかし●立正大学経営学部卒業後、数社を経てベルリッツ・ジャパン株式会社、インターファクトリー株式会社でウェブマーケティングを担当。2015年にフリーランスとして独立して以降、主にインターネット・マーケーティングのコンサルティングや講演活動に従事している。

ダイレクト・トゥー・コンシュマー(D2C)とは、自社ECサイトだけで商品を販売するビジネスモデルのことで、2015年ごろに米国のコスメティックブランドがこの方式を採用したところ、人気が爆発し話題になりました。日本では、主にアパレルや食品業界のスタートアップ企業で広く採用されています。
ただし、D2Cビジネスの考え方そのものは、インターネットを通じてモノを売るようになった2000年代前半にはすでに確立されており、古くからある考え方がテクノロジーの進歩によって洗練された結果、D2Cという言葉とともに広く知れ渡るようになったと言えます。
D2Cでは、基本的に店舗や代理店を通しませんが、最近では衣服の採寸や食品の試食など、ECサイトではできないことを補完するために店舗を構えるケースも見られます。
誰もがECサイトを持つ時代
日本でD2Cを採用する企業が増えている要因として、次の三つが考えられます。一つはECモールに出店するのと同じように、自社ECサイトの構築が容易になったことです。
インターネットを通じて商品を販売する場合、これまではアマゾンや楽天、ヤフーショッピング、ゾゾタウンなどの大手ECモールに出店することが一般的でした。
しかし、多くのユーザーが利用するECモールでは、商品が人の目に留まりやすく、短期的には売り上げを伸ばすことにつながりますが、お店の名前を覚えてもらうこと、すなわちブランディングには向いていません。
例えばECモールで書籍を買ったとき、「ECモールに出店している個別の書店から買っている」と自覚することは少なく、どうしても売り手の存在が陰に隠れがちです。
業種によっては同業他社が出店していることも多く、価格競争に陥り、商品力やブランドイメージが損なわれる可能性も考えられます。さらに、ECモールでの売上高の一部は手数料としてプラットフォーマーに支払うことになるので、コスト負担も生じてしまいます。
低価格の商品やブランディングなどで差別化しにくい商品(コモディティー商品)は、ECモールでの販売に向いている半面、商品力やブランド力を前面に押し出したい商品は自社ECサイトを構築し、ECモールだけでは伝えきれない商品の特長やブランドコンセプトといった付加価値の高い情報を積極的に発信した方が、売り上げの拡大に結びつきやすいと言えます。
最近ではテクノロジーの進歩やノウハウの蓄積により、自社ECサイトを立ち上げることが容易になりました。商品力やブランド力で勝負したい企業にとっては、ECモールに出店するよりも自社ECサイトを設けてユーザーに直接販売する方が、相対的に得られるメリットは大きいのです。
主体的に情報発信する
二つ目の要因は、従来のウェブマーケティングの手法として活用されてきた「SEO対策(※1)」や「リスティング広告(※2)」の掲載が、昔に比べて効果を発揮しなくなってきていることです。
かつて、SEO対策は外部リンクを貼るだけで一定の効果を挙げることができ、ITの知識が乏しくてもSEO業者に調整を委託すれば、簡単に検索結果の上位に表示することができました。しかし、SEO対策が乱発され、検索結果の信頼性を担保できなくなったことをうけ、2011年にグーグルが検索エンジンのアルゴリズムを改定。SEO対策を容易に行えなくなりました。
リスティング広告も多くの企業が採用していましたが、最近は広告枠に対して出稿企業が大幅に増加し、広告価格の高騰を招いています。現在は出稿するために多額のコストがかかってしまうので、リスティング広告を積極活用することも賢明な手段とは言えなくなってきています。
ウェブマーケティングの本質は、より多くのユーザーに商品情報へのアクセスを促し、購買行動へと転化させることにあるため、情報技術が発達した昨今においては、SEO対策やリスティング広告といった従来の手法を使うよりも売り手が主体となり、自社ECサイトを通じて情報発信する方が、商品の販売にも効果的であると言えます。
そして、これを補強するのがソーシャルメディアを活用することであり、それがD2Cが広く採用されるようになった三つ目の要因でもあります。
今や個人だけではなく、企業もラインやツイッター、インスタグラムといったソーシャルメディアのアカウントを開設し、情報発信に努めています。特に、自社ECサイトでしか商品を目にする機会を持たないD2Cにおいては、ソーシャルメディアの積極的な活用がことさら重要となってくるでしょう。
会社によってはラインで公式アカウントを作成し、クーポンやお買い得情報を発信したり、ツイッターやインスタグラムで商品の販売情報をつぶやいたりするなど、活用方法は多岐にわたります。
重要なのは、企業側からユーザーに対して積極的に情報発信し、自社ECサイトへのアクセスを促すことです。ソーシャルメディアは、D2Cビジネスを展開する上での相乗効果が期待できる半面、誤った情報の発信やユーザーの不信感を招く投稿は、商品はもちろん企業に対する信頼を失う要因にもなりますので、十分に注意を払ったうえで活用することをお勧めします。
※1 検索結果の上位に特定のウェブサイトがくるように調整することで「検索エンジン最適化」ともいう。
※2 ユーザーが検索した言葉に関係性のある広告を検索エンジンに表示することで「検索連動型広告」ともいう。
商品力・ブランド力を磨く
D2Cビジネスを軌道に乗せるには、商品・ブランドのファンやリピーターの存在が必要不可欠です。熱心なファンを獲得するためには、顧客目線に立ってサービスを展開し、「次もこの店で買い物をしたい」と思わせなければなりません。
以前とあるオンラインショップでスニーカーを購入しましたが、届いた箱を開けると商品とともに「お買い上げいただきありがとうございます」と直筆のメッセージカードが入っていました。その後、再び同じショップで別の靴を買ったときも、「前回お買い上げいただいた靴の履き心地はいかがでしたか」と書かれたメッセージカードが同梱(どうこん)されており、この取り組みに好感をもった私はこの店のファンになり、靴は毎回ここで購入しています。
このように、配送一つとってみても、商品・ブランドに好感をもってもらえるような仕掛けを行うことで、巡り巡ってファンやリピーターの獲得につながるのです。
D2Cビジネスでは企業規模を問わず、たとえ中小企業でも大企業以上の露出拡大に成功している事例が複数あります。これらの会社に共通しているのは商品力・ブランド力が高いうえに、商品そのものはもちろん、カスタマージャーニー(顧客が商品を認知してから購入するまでの行動・感情・思考のプロセス)の分析に余念がないことです。
D2Cビジネスを軌道に乗せている企業は、顧客がどのような商品を求めていて、どういった場合に必要とされるのかを分析し、これを商品の企画から生産、販売といった一連の商流に反映することを徹底しています。
D2Cという言葉を耳にすると、どうしても自社ECサイトの構築を先走ってしまい、どうすれば売れるのかといった商品分析を怠りがちです。実際に、力を入れてECサイトを構築したものの、商品企画や開発を疎かにした結果、販売実績が振るわずECサイトは閉鎖された話をよく耳にします。
D2Cを採用するには、商品力・ブランド力が大きく問われます。D2Cという言葉のトレンド感にまどわされず、質の高い商品を作り、市場や顧客からの反応を見て、適宜改良や改善に着手するといった不断の努力が求められるのです。
今やトレンドが生まれてはすぐに消えていく変化の激しい時代を迎えており、すべてを完璧に準備してから実行に移すのでは間に合いません。重要なのは「走りながら考える」ことで、商品の企画、販売、アフターケアなど一つ一つの要素を迅速に取り組むためにそれぞれに精通した人材を育成・確保する必要があります。
ある意味、D2CはECビジネスの中でも難易度が高い業態と言えますが、大企業と比べて機動性が高く、ウェブマーケティングを行いやすい体制にある中小・ベンチャー企業にも勝機のあるビジネスモデルでもあります。
(インタビュー・構成/本誌・中井修平)