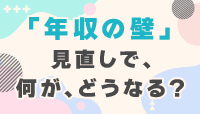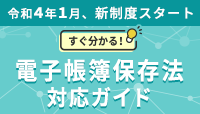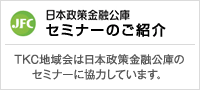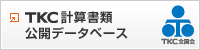長引くコロナ禍も3年目を迎え、産業・社会構造の転換が急ピッチで進められている。そうしたなか2022年度税制改正大綱が明らかになった。新税制は中小企業にどのような影響を及ぼすのか。今仲清税理士に聞いた。
- プロフィール
- いまなか・きよし●1951年生まれ。84年税理士事務所開業。88年経営サポートシステムズ設立、代表取締役に就任。2013年税理士法人今仲清事務所に移行。約280社の中小企業の税務監査、経営計画の策定、経営助言を行う。また、不動産有効活用、相続対策の実践活動を指揮しつつ、講演は年間約80回にのぼる。資産運用の総合対策計画策定のサポートも多数手がける。
──2022年度税制改正大綱の全体的な印象は?
今仲 昨年に引き続いて、あまり大きな変化はなかった印象です。推測するに、菅内閣から岸田内閣への引き継ぎなどで、税制の検討にあまり時間を割けなかったのではないでしょうか。
賃上げ促進税制に注目
──なかでも、一番の注目は?

今仲 清 氏
今仲 雇用者給与等支給額増加税額控除制度、いわゆる賃上げ促進税制の改正です。この制度については、昨年度に、それまでの「継続雇用者給与等支給額」だけが対象だったものを、「雇用者給与等支給額」が対前年増加率1.5%以上の要件を満たせば適用(控除率15%)されるように改正されました。つまり、ベースアップだけではなく従業員を増やして支給総額が増えた場合も対象になるわけで、22年もこの要件が継続されます。さらに、控除率が、21年度までは最大25%だったものが、最大40%へと大幅に引き上げられます。図表1(『戦略経営者』2022年2月号P25)を見てください。対前年増加率が2.5%以上だと、控除率を15%上乗せして30%に。教育訓練費を前年比10%以上増やせば、さらに控除率が10%上乗せされます。つまり、15+15+10で最大40%の控除率が可能となります。
──賃上げには原資が必要です。
今仲 中小法人で黒字申告しているのは40%弱。もちろん、これらの企業には約1,600万人という莫大な従業員が働いており、それなりの効果は期待できます。しかし一方で、残りの60%強の赤字法人はどうすればいいんだということにもなりますよね。赤字法人の賃上げは実質的に難しく、そうなると今回の税制改革の効果も限定的にならざるを得ません。というわけで、21年度の補正予算で赤字中小企業向け賃上げ支援(補助金)が実施されます。「ものづくり・商業・サービス補助金」と「持続化補助金」という2つの制度の建付けのなかで、一定の賃上げを行えば、補助金がもらえるというものです。要するに、利益の出ている法人は税制で、赤字の法人は補助金でメリットを享受して、賃上げを実施し、日本経済を活性化させようという狙いです。
機が熟しつつある5G投資
──法人税でほかに注目すべきものは?
今仲 いくつかありますが、5G投資減税は意外に使えるかもしれません。仕組みは昨年と同じですが、中身が若干変わります。図表2(『戦略経営者』2022年2月号P25)をご覧ください。23、24年と控除率が漸減していくということと、適用基準や対象施設においても一定の見直しがなされる見込みです。この制度は、地域や企業が主体となって特定の敷地内で自営の5Gネットワークを構築する「ローカル5G」の投資に対して30%の特別償却と15%の税額控除のいずれかを選択することができるというもの。5Gは4Gの10倍の高速大容量通信が可能で、遅延も4Gの10分の1以下。加えて4Gの40倍の同時接続もできる。たとえば自動農場管理や建築・土木現場などでの効率性を高める建機遠隔操作、あるいは小売業における商品管理・電子決済での飛躍的高度化などでの活用が有力視されています。
──制度自体は昨年創設されたものですね。
今仲 昨年は、大手事業者のインフラ整備が道半ばで、中小事業者の出番はありませんでしたが、ようやく環境が整ってきました。つまり、大手通信事業者による5Gシステムの販売活動が活性化してくる時期に入ってきたのです。さらに、コロナ禍によってデジタルトランスフォーメーション(DX)が喧伝されていることもあり、22年度あたりから、5Gの活用ニーズが出てくるのではないでしょうか。
──ほかには?
今仲 少額の減価償却資産および一括償却資産の損金算入制度の見直しには、注意をしておくべきかもしれません。これは、20万円未満の減価償却資産は3年で均等償却、また10万円未満の減価償却資産を全額損金算入できるという制度ですが、今回の見直しで、対象から除外する項目が設けられました。たとえば建設用の足場などがそうです。建設用の足場は1本数万円の鉄の棒を組み立てて足場にします。1本が10万円もすることはありません。そのため、何百万円、何千万円、何億円と購入して一挙に損金で落とし、実際に使うところにリース契約で貸すと効果的な節税ができるというわけです。このように節税対策としてこの制度を利用する事業者が出てきたので、対象となる資産から貸付の用に供した資産を除外するという規制を設けたのです(『戦略経営者』2022年2月号P26図表3)。
──どのような資産が節税に利用されているのでしょうか。
今仲 建設用足場のほかにはドローンやLED照明などが考えられます。要するにリース賃貸料と賃貸期間終了後の資産の売却益を合わせた額が、資産の取得価額と同程度になるスキームです。この制度改正によって、結構な数の中小企業が影響を受けます。というのは、グループ経営のなかで自社が購入したものを関連会社にリースして事業を回している中小企業もあり、賃貸業を本業としているところ以外は全部アウトになりますから。節税の意思はなくとも、結果として影響を受けてしまうわけです。
──オープンイノベーション促進税制も改正されました。
今仲 スタートアップ企業に中小企業が投資すると、有価証券になり損金で落とせません。しかし、ベンチャーは成功するか失敗するか分からずリスクが大きい。そのため、中小企業が、経済産業大臣が承認したベンチャーに、新しい技術やノウハウを開発するために1,000万円以上投資した時点で、金額の25%を損金として落とせるというのがオープンイノベーション促進税制です。中小企業はなかなかベンチャーと組んで研究開発を行うという機会がありませんからお金を出しやすくしようという趣旨で設けられたものです。
この制度の適用期限は今年の3月末まででしたが、それを2年間延長し、さらに、最低5年間は株を所持し続けなければならない決まりだったものを、所有期間を3年間に短縮するという改正が行われました。また、出資するベンチャー企業は設立10年未満の会社に限定されていましたが、15年未満の会社にまで拡大されます。
この制度は、すでに100件を超える利用実績があり、たとえば、高精度な血圧測定技術を持つ中小企業が、心電図の解析技術を持つスタートアップ企業に投資し、血圧データと心電図の統合解析による心疾患リスクを予測するアルゴリズムを共同で開発し、心疾患の発想予防の実現を目指している事例。あるいは、医薬品開発にかかわる技術・設備や顧客データを持つ中小企業が、がん治療に有効なウイルスに係る技術を持つスタートアップに出資して、がん治療薬の開発を目指しているといった事例があります。
最近は、大学の研究室がベンチャー企業を立ち上げる際、周辺の中小企業を巻き込んで研究開発を進めるケースも増えており、この制度によって、研究開発型の企業にはチャンスが生まれるかもしれません。活用を検討してみる価値はあると思います。
インボイス制度への対応
──金融・証券税制では?
今仲 エンジェル税制には留意が必要かもしれません。投資家がベンチャー企業に個人として投資をする際に、海のものとも山のものとも分からない企業が上場などで成功する可能性は低いので、なかなか投資家が現れないのが現状です。エンジェル税制は、そうした投資を促進するために投資した金額を所得控除してくれる制度です。たとえば100万円を投資したら、そこから2,000円引いた99万8,000円に40%をかけた金額、つまり約40万円が所得税額から控除されます。これは投資先が設立5年未満の企業。それと、投資した金額を株式譲渡益と相殺する制度もあり、これは投資先が設立10年未満の企業となります。つまり、所得控除か株式譲渡益と相殺するかの2種類あり、これらが3年間延長されます。
──消費税の分野で留意点は?
今仲 適格請求書等保存制度(インボイス制度)の改正案は見ておくべきです。ご承知の通り、インボイス制度は、2023年10月1日からスタートするわけですが、課税事業者にならないとインボイスを発行できません。ということは、課税売上高1,000万円以下の免税事業者は課税事業者になるかどうかの選択をしなければならない。現行制度では、23年10月1日を含む事業年度の間は、途中からでも課税事業者を選択できますが、原則は、その事業年度の前の年に届け出をださないといけません。しかし、そうすると、免税事業者がそれを意識していなかった場合、困ったことが起きる可能性があります。23年10月1日が過ぎてしまい、自社が取引から外されそうになった際、急いで課税事業者になりたいというケースも出てくるでしょう。このような会社が、次の事業年度からしか課税事業者になれないリスクを排除するために、29年9月30日までの日が属する課税期間であればいつでも転換できるように改正されます(『戦略経営者』2022年2月号P27図表4)。つまり、インボイス制度がスタートしたときに起こるだろう混乱に、事前に対応しておこうということです。
──免税事業者は気を付けたいですね。
今仲 課税事業者も気を付けなければなりません。現在、課税事業者は、免税事業者と取引をしても仕入税額控除ができますが、23年10月1日からは、当初3年間は80%、次の3年間は50%を控除できる経過規定がありますが、原則仕入税額控除はできなくなります。なので、取引をするときに免税事業者に対して、「おたくの会社が課税事業者にならなければ取引しない」あるいは「当社が損する消費税分を値引きしてくれ」などと言いたくなるでしょう。しかし、これは下請法違反となる恐れがあります。国は、そのことを広報していこうと、いま準備をしているところだと聞いています。課税事業者は、免税事業者と取引をするときに、決してそうした類の交渉をしてはいけません。
──違法となるのは、ほかにどのようなケースが考えられますか。
今仲 取引完了後、インボイス発行事業者でなかったことが判明したため、消費税相当額の一部または全部を支払わないことにしたり、あるいは、下請け事業者が求めに応じて課税事業者になったのにもかかわらず、その後の価格交渉に応じず、一方的に単価を据え置いたりといったケースは「買いたたき」に該当するので違法だと考えられます。
若年層への資産移転政策
──相続・贈与税の分野ではいかがでしょう。
今仲 住宅取得資金等にかかわる贈与税の非課税措置が見直されます(『戦略経営者』2022年2月号P27図表5)。いままでは、最大1,500万円を、こどもや孫、ひ孫などに贈与しても非課税でした。この制度の建付けは2年間延長されますが、同時に、限度額については、耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する住宅では1,000万円、それ以外の住宅は500万円となります。つまり、限度額を引き下げた上で延長されたことになります。それから、対象となる住宅については、中古住宅の築年数要件がなくなって、1982年1月1日以降の家屋、つまり新耐震基準に適合している住宅であればOKとなります。さらに、2022年4月1日からは民法で「成人」は18歳以上となるので、それに合わせて、受贈者の最低年齢が18歳に引き下げられます。
それから、相続・贈与税の分野では非上場株式にかかわる相続税・贈与税の納税猶予の特例制度にも一部改正があります(『戦略経営者』2022年2月号P27図表6)。コロナ禍などの状況を鑑みて、23年の3月31日までに特例承継計画を提出しなければならかったものが、1年間延長されます。ただし、「特例」の適用の期限は27年12月31日までの贈与となっていて、この延長はありません。まだまだ特例承継計画の提出件数が少ない状況のなかで、提出件数を引き上げ、中小企業の事業承継を促進するための施策です。
──なぜ、提出件数が少ないのでしょうか。
今仲 切実感が足りないのだと思います。われわれが承継をお手伝いするなかで、80歳を過ぎていて後継者がいるにも関わらず、譲ることを決めてない人もおられます。私の肌感覚では、70以上の高齢になっても承継を決めていない経営者は4割くらいいるように思います。70超えたら、いつ何があってもおかしくありません。万が一のことがあった場合には手遅れになります。手を付けるのは早ければ早い方がいいのですが、少なくとも60歳になったら、自分に万一のことがあっても、後継者問題で混乱に陥る、取引に支障が生じることにならないように万全な体制をとっておくべきです。事業承継を進めるために必ず特例承継計画を提出しなければならないということではないにしても、そのきっかけとして承継計画を作成して現実にどんな手を打たなければならないのかを整理することは有効な事業承継対策のひとつだと思います。
──若年層への資産移転の遅れという問題にもつながりますね。
今仲 昨年来、世間をにぎわせている相続税と贈与税の一体化の議論にもかかわってきます。2021年の秋くらいから、マスコミやネットなどで「贈与税がなくなるのではないか」と話題になりました。そのもとになったのは、2021年の与党税制改正大綱でした。要は、1年を区切りとして贈与した財産に課税する暦年課税がなくなって、すべて相続時精算課税、つまり、相続の時には過去に贈与した財産もすべて加算して相続税を計算するようになるのでないかと。そうなれば結果として、小分けしながら贈与したとしても相続税対策にはなりませんから、それがセンセーショナルな伝わり方をしたわけです。だけど、そんなに簡単にこの問題に結論が出る話ではないということは認識しておく必要があります。大きな影響を与えるような制度改正となる可能性は低いという気はします。
住宅ローン減税の控除率下げ
──不動産にかかわる税金についてはいかがでしょう。
今仲 住宅ローン控除の改正が大きなトピックです。改正点はいくつかありますが、一番大きいのは、やはり控除率の引き下げです。現行の控除率は年末の借入金残高に対して1%です。が、これが実際に金融機関で借りる住宅ローンの金利(0.6~0.7%)を上回っていることで、逆ザヤになっているという会計検査院からの指摘を受けて、控除率が0.7%と市中金利の平均値レベルに引き下げられます。さらに、控除期間についても、昨年、引き上げられた消費税率2%分を返しますよという意味で13年に延長されましたが、今回、控除率を引き下げることに対する見返りとしてやはり3年間、控除期間が延長されます(『戦略経営者』2022年2月号P28図表7)。ただし延長の対象になるのは新築あるいは不動産業者が買い取り大幅に改修して再販した中古住宅であり、そのほかの住宅は10年のままです。
所得要件については、現行では3,000万円以下までとなっていますが、これが2,000万円以下に引き下げられます(22年1月1日以降の居住)。勘違いしてほしくないのは、最初に控除を受ける年ではなく、1年ごとの所得で判定されるということ。入口で所得が2,000万円をこえて控除を受けられなくても、2年目に1,900万円だったらOKです。また逆に、最初は控除を受けられても、年収がアップすれば途中から受けられなくなることもあります。
対象住宅の要件には、「ZEH(ゼッチ)住宅基準」というものが新たに導入されました。ZEH基準とは、「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略で、従来の「省エネ基準」をより強化した基準のこと。「認定住宅」の評価基準にも省エネ基準とともにこのZEH基準が採用されるようになり、ZEH基準を満たす省エネ住宅は、借入限度額が大きくなります。
──固定資産税はいかがでしょう。
今仲 固定資産税は3年に1回、評価の見直しがあり、21年がその見直しの年でした。したがって、評価額が21年に変わりましたが、コロナ禍で地価が大幅に下がった上に企業の業績悪化もあり、固定資産税の負担を軽減するために、21年分については20年とまったく同じ税額で据え置きました。22年も、コロナ禍が終息していないということで、通常、地価の上昇により税額が増加する場合、21年の課税標準額に22年の評価額の5%を加算した額が固定資産税となりますが、この加算率が22年度に限って2.5%へ引き下げられます。これは、19年から21年までの3年間、商業地を中心に土地の評価額が結構上がっているので、そこへの配慮としての措置です。
「宥恕」は「今まで通り」ではない
──納税環境整備の分野では?
今仲 帳簿の提出がない場合の過少申告加算税等の加重措置は重要です。経営者のなかには帳簿をつけずに申告している人もいます。そういう会社に対する加算税を、通常よりも10%引き上げますよと。それから、財産債務調書の見直しにも留意すべきでしょう。いままでは所得が2,000万円を超えていて、かつ総資産が3億円以上あるか、あるいは有価証券が1億円以上ある人だけに、財産債務調書の提出が義務付けられていました。しかし、今回、所得ゼロでも総資産が10億円以上あれば、提出しなければならなくなります。具体的には上場企業の株式だけしか持っていない人などが、これに該当します。上場株式の配当は申告義務がないので所得はゼロのままなので、それでも財産債務調書を出さなくてもいいというのはおかしいという話です。
──電子帳簿保存法改正による電子取引データの保存も話題です。
今仲 電子データで来た請求書、領収書等は、紙ではなく電子データで保存しなければならなくなります。しかも、ルールにのっとって保存し、いつでも検索できるようにすることが義務付けられます(『戦略経営者』2022年2月号P29図表8)。しかし、昨年末に国税庁から2年間は「宥恕(ゆうじょ)する」という言葉が飛び出しました。これを、今まで通り紙で保存してもよいととる向きもあるようですが、そんなことはありません。法律そのものは変わっていないので、原則電子保存です。しかし、それを行うにはソフト開発やシステムの購入が必要で、そんなお金も人材もないという会社に対して23年12月31日までは大目に見ましょうと。だから、電子データで保管するのは原則で、それを整然と並べて検索できるようにするために時間が必要なら、「少し待ちますよ」というだけのことです。経営者の方々は、これを取り違えることなく早期に電子データ保存体制の構築に取り組んでください。
(インタビュー・構成/本誌・高根文隆)