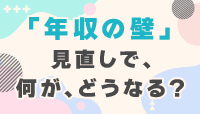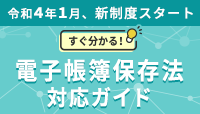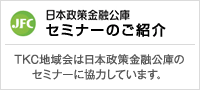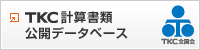TKC全国会は6月1日、令和4年版「TKC経営指標(BAST)」の提供をウェブ方式で開始しました。令和4年版BASTは、昨年1年間(令和3年1~12月)にTKC財務システムを利用して決算を迎えた年商100億円以下の中小企業24万8,962社、1,178業種の経営成績と財務状態を分析したもので、これは全法人数の9%超に当たります。
コロナ融資で手許資金増加

山本清尊 氏
令和4年版BASTのポイントはいくつかありますが、1人当たり売上高が前年比1.9%減少しているにも関わらず黒字企業割合が前年比1.9%上昇していることが最大の特徴といえるでしょう。
まず、グラフ1(『戦略経営者』2022年8月号P65)をご覧ください。過去10年の黒字企業割合の推移です。2度にわたる消費税の引き上げやマイナス金利の導入などの出来事がありましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大までは、どの業種もほぼ右肩上がりでした。それが令和2年には、ほぼ全業種にわたって黒字企業割合が減少しました。これを見ても、コロナ禍が産業界に及ぼした影響の大きさが分かります。
全産業の経営分析表を見ると、1人当たり売上高(年)は前年から56万円減少して1,585万円となっています。これは、前年からコロナ禍の影響が続いていると考えれば自然といえるのかもしれません。ところが、同年の黒字企業割合は、建設業を除いて上昇。ほぼコロナ以前の水準にまで戻しています。なぜなのでしょうか。
もちろん、新事業への進出や事業再構築、あるいは役員報酬を見直すなどといった経営努力によって黒字を達成した企業もあるでしょう。しかし、全体を俯瞰(ふかん)してみれば、本業による営業利益が回復したのではなく、コロナ関連の支援金や助成金収入があったことが影響していると考えられます。たとえば、私の顧問先では、積み立ててあった倒産防止共済を解約し、何とか黒字化したという企業もありました。
また、令和4年版BASTに収録されている全産業の要約貸借対照表を見ると、前年に比べ長期借入金が769万円、現預金が723万円増加しており、先行きの不安定感から手元資金を厚くしたい中小企業が、新型コロナ特別融資を受けたケースが多いことを裏付けるデータとなっています。
宿泊業・飲食サービス業は深刻
黒字企業割合の回復が、利益体質への転換を意味するのではない以上、今後、コロナ関連融資の返済時期が到来すれば、資金繰りに苦しむ企業が出てくる可能性もあります。また、グラフ1(『戦略経営者』2022年8月号P65)を見てもらえば分かる通り、宿泊業・飲食サービス業については、コロナ関連の支援金や助成金では追いついておらず、令和2年に比べると黒字企業割合はやや持ち直しているものの、コロナ前の数字にはほど遠い状態です。もともと、宿泊業・飲食サービス業は、黒字企業割合の低い業界ではありましたが、ここ2年の数字の悪さは深刻です。とくに装置産業である宿泊業では、施設維持費や減価償却費が毎年固定費として出ていく上に、人の移動が回復し顧客が訪れない限り策の打ちようがありません。その点、飲食業の場合は、テイクアウトやデリバリーなどの打ち手で、ある程度売り上げ減をカバーすることができるので、業績を取り戻しつつある企業も増えているようです。
宿泊業・飲食サービス業の状況が極めて厳しいことを裏付けるデータを2つご紹介しましょう。
グラフ2(『戦略経営者』2022年8月号P65)をご覧ください。労働分配率の過去10年間の推移です。労働分配率とは売上高から変動費(原価)を引いた限界利益(粗利益)に対する人件費の割合のこと。この指標が高すぎると、利益を出すことが難しくなります。このグラフを見ると、コロナ禍以降、どの業種も労働分配率が上昇していますが、なかでも宿泊業・飲食サービス業の上昇度合いが際立っています。さらに、グラフ3(『戦略経営者』2022年8月号P65)の売上高経常利益率も同様で、宿泊業・飲食サービス業はコロナ禍以降の2年間、唯一マイナスに沈み込んでいます。つまり、経常利益を出すことが難しい状況だということです。
ただ、今年の4月以降、移動制限の緩和によって人の流れも活性化し、ゴールデンウイークなどは各地でにぎわいが戻ってきました。深刻な状況が続いている宿泊業・飲食サービス業においても反転攻勢の傾向が出てきているようです。そうした先行きの光が少し見えてきたなかで、今度は物価の上昇という難題が持ち上がってきています。仕入れ値と売価をうまくコントロールしないと、利益が出ない状況は、すべての業種にわたって共通の現象であり、中小企業にとってはかなりの重荷となっています。今後、材料費や光熱費の値上がりで、消費者や取引先に値上げが必要であることをきちんと打ち出し、価格改定を実行していく経営者の決断が求められます。
優良企業の新定義とは
さて、BASTの優良企業の定義がこのほど変更されました。旧定義と新定義の比較は、図表をご覧ください。旧定義では、「総資本経常利益率」「自己資本比率」など5指標の上澄みの部分を優良企業としていました。しかし、これでは「結果的に優良企業だった」という指標に過ぎず、経営者が目標とするには分かりにくいという欠点がありました。また、この五つの指標は、業種ごとの構造的な特徴によって達成しやすいものとそうでないものがあり、フェアでないという一面もありました。
そこで、新定義においては、プロセスやコンプライアンスの面を加味しながら、経営者が現実的な目標として明確にとらえることができるようになりました。
一つひとつ見ていきましょう。
「書面添付の実践」と「中小会計要領への準拠」では、経営のベースである会計において、きちんとした手順を踏んで信頼性のある決算書を作成できているかを評価します。ここが新定義の「要」となります。
次に「限界利益額の2期連続増加」です。限界利益は付加価値額なので、ここが増えれば日本のGDPが増えるということになり、つまり、TKC会計人が新定義での優良企業を増やす努力をすることで、日本経済が良くなるという好循環が生まれます。
さらに「自己資本比率30%以上」ですが、自己資本比率が高ければ高いほど財務面の安全性が高くなるので、当然、優良企業の指標となります。ちなみに、旧定義においても自己資本比率「上位85%」というのが指標となっていましたが、これだと結果論になってしまうので明確な目標とはなり得ません。
最後の「税引き前当期純利益がプラス」というのは説明するまでもないでしょう。利益の創出は企業の最大の目的です。
これら5つの新定義によって抽出される新たな「優良企業」では、TKCの自計化システムの利用割合が高く、また、翌月巡回監査の実施回数も多くなる傾向が見られます。ということは、経営者とTKC会計人がコミュニケーションをとりながら「TKC方式の会計」を実践していくなかで、自然と優良企業が増えていくということになります。
収録企業が順調に増え続けているBASTは、全法人数の1割近くをカバーする他に例を見ない統計資料です。外部からの評価も高く利用金融機関は6月2日現在で354機関で約7,500のBAST利用IDが使用されており、また、2022年版中小企業白書において、BASTのデータが分析内容に採用されました。国の統計データよりも早く、スピーディーに足もとの産業動向を知ることができ、日本産業分類に応じた業種別、あるいは地域別、売り上げ規模別の分析もしっかりとできていることが評価されつつあるのだと思います。
もちろん企業経営者にとっても、最新の「同業他社」の業績を垣間見ることができる唯一無二のデータです。ぜひ、BASTのデータを参考にして「他社にできるのだからわが社もできる」という意欲につなげていただければと思います。
(インタビュー・構成/本誌・高根文隆)