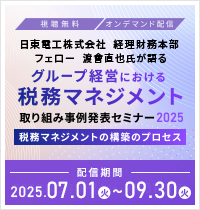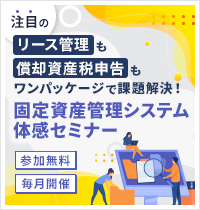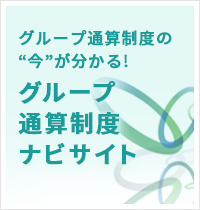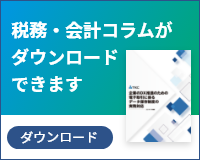更新日 2013.05.13
 TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
税理士 畑中 孝介
「社会保障と税の一体改革」の一環として消費税の増税法案が成立しました。消費税増税に際してはさまざまな経過措置を理解することが必要になります。このコラムでは経過措置を中心に、95%ルールへの影響、そして増税で一層高まる税務リスク・税務コンプライアンスの取り組みなどとの関連について解説していきます。
Ⅰ 消費税95%ルール改正への実務対応
平成24年度税制改正前では、売上のほとんど(95%以上)が課税売上げの場合、仕入税額控除は全額認められていました(いわゆる「95%ルール」)。ただし、この95%ルールを適用した場合には、本来、仕入税額控除が適用されない部分まで仕入税額控除が可能となり、本来の税額に比べ納付税額等が減少する「益税」が発生することになっていました。このため、平成24年度税制改正では課税売上高が5億円超の事業者については95%ルールの適用が除外されました。
95%ルールの適用が除外された場合には、「一括比例配分方式」「個別対応方式」のいずれかを選択して税額計算を行うこととなりますが、「個別対応方式」を選択する場合には、課税仕入れの各取引について消費税の用途区分を「課税対応・非課税対応・共通対応」の3つに細分化して把握する必要があり、システム対応を含め実務上の影響が非常に大きいといわれています。
Ⅱ 「一括比例配分方式」「個別対応方式」の有利・不利判定
一般的な事業会社の場合、「非課税売上げにのみ要する課税仕入れ」はほとんどなく「課税売上げにのみ要する課税仕入れ」の割合が高くなる傾向がありますので、「個別対応方式」のほうが有利になるケースが多いと思われます。
「個別対応方式」の選択が有利であっても、「消費税の用途区分を細分化できない」、「システム対応が困難である」等の理由で「一括比例配分方式」を選択せざるを得ないケースはあるかと思います。また、「一括比例配分方式」を選択した場合は、2年間以上継続することとされており、その間は「個別対応方式」の選択ができないこととされていますので注意が必要です。
一般的なケースでは課税売上高10億円の会社であれば、「一括比例配分方式」と「個別対応方式」の税負担差額は年間30~50万円程度の差額になると考えられます。さらに、消費税率の引上げにより、「個別対応方式」を選択できないデメリットは現行より2倍に拡大すると見込まれます。
このデメリットは、消費税がある限り未来永劫続くこととなりますので、税率引上げ後の影響額も踏まえた対応方針の決定が必要となります。
(詳細はTKC出版「Q&A改正消費税の実務対策」Q5を参照)
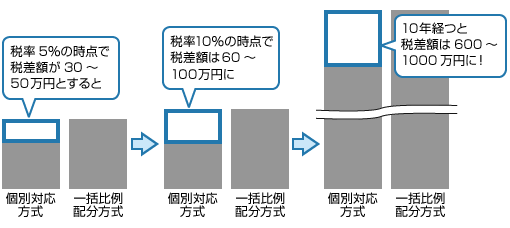
Ⅲ 「課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ」の考え方
非課税売上が1円でもあれば、直ちに管理部門等のすべての経費が「課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ」に区分されるというわけではありません。
まず「課税売上げにのみ要するもの」と「非課税売上げにのみ要するもの」のいずれに該当するかを考え、いずれにも該当しないものだけが「共通して要する課税仕入れ」に区分されることになります。
たとえば、本社の中に営業部門と経理部門がある企業(販売商品はすべて課税対象であるとする)を例にとって、区分方法の一例を見てみましょう。
1.電話代
- 電話番号が細分化されていない請求が来た
- ・・・
- すべてを「課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ」とする。
- 営業部門の電話番号が別になっている
- ・・・
- 営業部門の電話代を「課税売上げにのみ要するもの」とし、その他の番号の分を「課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ」として仕訳を細分化する。
2.広告代
- 製品カタログ・製品広告
- ・・・
- 「課税売上げにのみ要するもの」とする。
- 会社案内・名刺広告
- ・・・
- 「課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ」とする
というように細分化することは認められると思われます。
一般的には製品カタログ・広告などの費用のほうが多額になると考えられます。細分化できない場合には「課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ」となり、仕入控除税額が減ることになります。使用目的や部門等による区分を用いて課税仕入れ等の内容を細分化し、「課税売上げにのみ要するもの」をできるだけ多く抽出することが重要なポイントです。
Ⅳ 部門別管理の徹底が、個別対応方式選択にも有効
上述の事例にもある通り、消費税の個別対応方式を選択する際には、支出内容等を明確にすることと、どの部門に帰属する支出なのかを明確にすることが消費税額の適正化に当たって有効です。またその明確化や検証に当たっては、会計システムで部門等をきちんと分け「部門別の消費税額集計表」等を利用し課税区分が適正であるかを検証することが必要になります。そのことが会社の部門別業績管理体制の強化にもつながると思われます。
つまり、部門別の損益管理を徹底し、それを消費税の課税区分の管理にも使うというような一石二鳥の考え方ができると言えるでしょう。
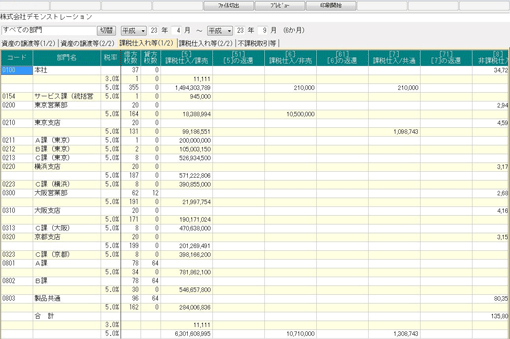
この連載の記事
-
2013.09.09
第14回 税務はグループ全体の視点で取り組もう!
-
2013.08.26
第13回 消費税にもグループ概念導入!? 新設法人の免税点制度の改正
-
2013.08.05
第12回 駆込み需要の取り込みと反動減への対応策
-
2013.07.22
第11回 特別措置法への対応② 総額表示義務の緩和
-
2013.07.08
第10回 特別措置法への対応① 値下げセール等の禁止
-
2013.06.24
第9回 仕入税額控除否認事例も!帳簿の記載要件は満たされていますか?
-
2013.06.10
第8回 控除対象外となった消費税額等の処理について
-
2013.05.27
第7回 緊急掲載:決算申告でミス多発!交際費等の別表加算も必要となる控除対象外消費税額等
-
2013.05.13
第6回 消費税額に差が出る?!消費税95%ルール改正への対応と部門別管理
-
2013.04.15
第5回 軽減税率とシステム対応
-
2013.04.01
第4回 経過措置③ 長期割賦販売・リース契約・資産の貸付・サービス提供など
-
2013.03.18
第3回 経過措置② 売上返品・貸倒
-
2013.03.04
第2回 経過措置について① 請負契約
-
2013.02.18
第1回 消費税法改正の概要と趣旨
テーマ
プロフィール

税理士 畑中 孝介(はたなか たかゆき)
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会 幹事
TKC企業グループ税務システム普及部会会員
TKC企業グループ税務システム小委員会委員
TKC全国会中央研修所租税法小委員会委員
- 略歴
-
ビジネス・ブレイン税理士事務所所長、株式会社ビジネス・ブレイン代表取締役CEO
大手・上場企業の連結納税コンサルティング業務や組織再編アドバイザー業務を行う。上場企業から中小企業・ベンチャー企業・ファンドまで幅広い企業の税務会計顧問業務に従事。TKC企業グループ税務システムの専門委員、中堅・大企業支援研究会幹事等に就任。 - 著書等
-
- 『消費税インボイス制度の実務対応』(TKC出版)
- 『令和6年度 すぐわかるよくわかる 税制改正のポイント』(TKC出版)
- 『企業グループの税務戦略-グループ法人税制・連結納税制度の戦略的活用-』(TKC出版)
- 『CFOのためのサブスクリプション・ビジネスの実務対応』(中央経済社)
- 「旬刊・経理情報」「税務弘報」などにも執筆
- システム・コンサルティング事例
- ホームページURL
- ビジネス・ブレイン税理士事務所
免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。