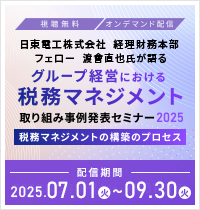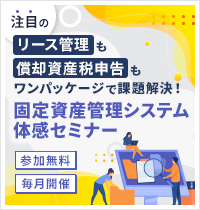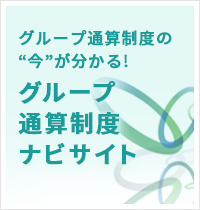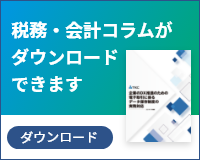更新日 2025.07.07

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
税理士・公認会計士 髙倉 裕幸
内部統制は、会社が事業活動を健全かつ効率的に運営するために必要な仕組みを指します。内部統制を整備することで、社内の不正行為やミスの防止、業務の透明性を高めるなど、重要な役割を果たします。
近年発生している経営者や従業員による粉飾決算や法令違反なども内部統制が適切に整備されていれば未然に防げていた可能性があります。
そこで、内部統制の基本や具体的な事例を紹介するとともに、全社的・決算業務の内部統制の整備、IT統制のポイントを解説します。
当コラムのポイント
- 内部統制の基本と具体的な事例を紹介
- 全社的・決算業務の内部統制の整備、IT統制のポイント
- IPO準備企業や中小企業に期待される内部統制
- 目次
-
前回の記事 : 第3回 会社法と金融商品取引法で求められる内部統制の違いについて
内部統制報告制度における全社的な内部統制と、決算・財務報告にかかる内部統制について解説していきます。
1.概要
内部統制報告制度において、経営者は「全社的な内部統制の評価」と「決算・財務報告にかかる内部統制の評価」を行わなければなりません。
全社的な内部統制とは、企業グループ全体の内部統制が有効に機能するための仕組みや体制であり、企業グループ全体に関わる内部統制の土台となるため、個別業務プロセスの内部統制を支える上位概念に位置付けられます。
全社的な内部統制は、企業グループの信頼性や透明性を支える基盤であり、個別の業務統制がどれほど整っていたとしても、全社的な内部統制が不十分であれば企業としての統制システムは機能しないことになります。そのため全社的な内部統制は、内部統制の中でも最も重要なものとして位置づけられます。
次に、決算・財務報告にかかる内部統制とは、企業が会計帳簿をもとに貸借対照表・損益計算書等の決算書類を作成・報告するための一連のプロセスであり、財務報告の信頼性を確保するために企業グループ全体の体制として整備する必要があります。
内部統制の手続は、主に以下に分類されます。
- ①全社的な内部統制
- ②決算・財務報告にかかる内部統制
- ③個別の業務プロセスにかかる内部統制
- ④IT統制(IT全般統制、IT業務処理統制)
このうち②決算・財務報告にかかる内部統制は、主に経理部門を対象とした統制であり、日常的な会計仕訳の統制のほか、会計方針の決定や会計上の見積り(経営者の判断)、経営方針等経営者の考え方を含み、全社的な内部統制と概念的に近いものとなります。また、企業グループ全体で共通した管理が行われることが多いため、全社的な内部統制に準じた評価が行われます。
※③個別の業務プロセスにかかる内部統制では、例えば売上の勘定科目については「販売プロセス」が対象となり、営業部門、商品管理部門、生産管理部門など、業務プロセスの内容に応じて対象となる部門は多岐にわたります。
内部統制報告制度における内部統制の評価・報告の流れでは、まず①全社的な内部統制の評価を行い、次に②決算・財務報告にかかる内部統制の評価を行います。①と②の評価の結果、そのリスクに応じて重要な事業拠点(*1)を選定し、③評価対象とする「個別の業務プロセス」を識別する、という流れになります。(*1)事業拠点には、親会社、子会社、支社、支店の他、事業部等も含まれます。
2.全社的な内部統制について
内部統制の手続のなかでも、最も重要なものが全社的な内部統制となります。
社内規定やルールが整備されているか、行動規範が明示されているか、内部通報制度は機能しているか、各種教育・研修制度が整えられているか等、企業グループ全体で整備・運用評価を行う必要があります。原則として全ての事業拠点が評価範囲の対象となりますが、重要性の乏しい連結子会社等は、僅少なものとして評価の対象から外すといった取扱いも考慮されています。
全社的な内部統制の評価手順は、主にチェックリストを作成し、運用していく方法が一般的となります。
内部統制の目的が達成されるためには、内部統制の6つの基本的要素が全て適切に整備・運用されることが必要となります。内部統制の実施基準には、全社的な内部統制について、基本的要素ごとに42の評価項目が例示されています。(参照)
全社的な内部統制は、企業のおかれた環境や事業の特性などにより様々であり、企業ごとに適した内部統制を整備・運用することが求められるため、必ずしも例示によらない場合があること、42の評価項目による場合でも、適宜、加除修正することとされています。
6つの基本的要素ごとに評価項目を列記したチェックリストを作成し、評価項目に回答することで、企業グループの統制の状況を文書化していきます。
例えば、「統制活動:全社的な職務規程や、個々の業務手順を適切に作成しているか。」という問いかけに対して、職務ごとの責任、権限、業務範囲が明確化された職務権限規程が作成されていることが必要となります。さらに、従業員の行動が、職務権限規程に基づき適切に行動されていること、それが一時点ではなく一年間を通じて有効に運用されていることが必要となります。
3.決算・財務報告にかかる内部統制について
決算・財務報告プロセスは、財務報告の信頼性を確保するために、企業グループ全体の体制として整備する必要があります。ただし企業グループの財務諸表への影響を勘案し、重要性の大きい個別の業務プロセスは、全社的な観点で評価するのではなく個別の業務プロセスとして評価する必要があります。
主として経理部門が担当する決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものは、全社的な内部統制に準じて、全ての事業拠点について全社的な観点で評価をします。全社的な観点で評価することが適切と考えられる決算・財務報告プロセスは、以下のような手続が含まれます。
- ①総勘定元帳から財務諸表を作成する手続
- ②連結修正、報告書の結合及び組替など連結財務諸表作成のための仕訳とその内容を記録する手続
- ③財務諸表に関連する開示事項を記載するための手続
個別に評価が必要となる決算・財務報告プロセスには、例えば会計上の見積り(貸倒引当金の見積り、投資有価証券の評価、固定資産の減損評価等)や税金計算等が含まれると想定されます。
4.おわりに
全社的な内部統制は、企業グループ全体に共通する組織運営のための基本的な仕組みや枠組であり、企業グループの信頼性や透明性を支えるための土台となる統制です。
内部統制報告制度が必須ではない中小企業等においても、全社的な内部統制の概念を取り入れ、最低限のルール・監視体制を構築することにより、重大な事故を未然に防止することができます。また、経営者の価値観等の浸透、組織の健全性の確保、不正や誤謬の防止、取引先や金融機関からの信用力の向上などを見込むことができます。
【参照】
財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)より 令和5年4月7日 企業会計審議会
財務報告に係る全社的な内部統制に関する評価項目の例(注)
統制環境
- 経営者は、信頼性のある財務報告を重視し、財務報告に係る内部統制の役割を含め、財務報告の基本方針を明確に示しているか。
- 適切な経営理念や倫理規程に基づき、社内の制度が設計運用され、原則を逸脱した行動が発見された場合には、適切に是正が行われるようになっているか。
- 経営者は、適切な会計処理の原則を選択し、会計上の見積り等を決定する際の客観的な実施過程を保持しているか。
- 取締役会及び監査役等は、財務報告とその内部統制に関し経営者を適切に監督監視する責任を理解し、実行しているか。
- 監査役等は内部監査人及び監査人と適切な連携を図っているか。
- 経営者は、問題があっても指摘しにくい等の組織構造や慣行があると認められる事実が存在する場合に、適切な改善を図っているか。
- 経営者は、企業内の個々の職能(生産、販売、情報、会計等)及び活動単位に対して、適切な役割分担を定めているか。
- 経営者は、信頼性のある財務報告の作成を支えるのに必要な能力を識別し、所要の能力を有する人材を確保配置しているか。
- 信頼性のある財務報告の作成に必要とされる能力の内容は、定期的に見直され、常に適切なものとなっているか。
- 責任の割当てと権限の委任が全ての従業員に対して明確になされているか。
- 従業員等に対する権限と責任の委任は、無制限ではなく、適切な範囲に限定されているか。
- 経営者は、従業員等に職務の遂行に必要となる手段や訓練等を提供し、従業員等の能力を引き出すことを支援しているか。
- 従業員等の勤務評価は、公平で適切なものとなっているか。
リスクの評価と対応
- 信頼性のある財務報告の作成のため、適切な階層の経営者、管理者を関与させる有効なリスク評価の仕組みが存在しているか。
- リスクを識別する作業において、企業の内外の諸要因及び当該要因が信頼性のある財務報告の作成に及ぼす影響が適切に考慮されているか。
- 経営者は、組織の変更やITの開発など、信頼性のある財務報告の作成に重要な影響を及ぼす可能性のある変化が発生する都度、リスクを再評価する仕組みを設定し、適切な対応を図っているか。
- 経営者は、不正に関するリスクを検討する際に、単に不正に関する表面的な事実だけでなく、不正を犯させるに至る動機、原因、背景等を踏まえ、適切にリスクを評価し、対応しているか。
統制活動
- 信頼性のある財務報告の作成に対するリスクに対処して、これを十分に軽減する統制活動を確保するための方針と手続を定めているか。
- 経営者は、信頼性のある財務報告の作成に関し、職務の分掌を明確化し、権限や職責を担当者に適切に分担させているか。
- 統制活動に係る責任と説明義務を、リスクが存在する業務単位又は業務プロセスの管理者に適切に帰属させているか。
- 全社的な職務規程や、個々の業務手順を適切に作成しているか。
- 統制活動は業務全体にわたって誠実に実施されているか。
- 統制活動を実施することにより検出された誤謬等は適切に調査され、必要な対応が取られているか。
- 統制活動は、その実行状況を踏まえて、その妥当性が定期的に検証され、必要な改善が行われているか。
情報と伝達
- 信頼性のある財務報告の作成に関する経営者の方針や指示が、企業内の全ての者、特に財務報告の作成に関連する者に適切に伝達される体制が整備されているか。
- 会計及び財務に関する情報が、関連する業務プロセスから適切に情報システムに伝達され、適切に利用可能となるような体制が整備されているか。
- 内部統制に関する重要な情報が円滑に経営者及び組織内の適切な管理者に伝達される体制が整備されているか。
- 経営者、取締役会、監査役等及びその他の関係者の間で、情報が適切に伝達共有されているか。
- 内部通報の仕組みなど、通常の報告経路から独立した伝達経路が利用できるように設定されているか。
- 内部統制に関する企業外部からの情報を適切に利用し、経営者、取締役会、監査役等に適切に伝達する仕組みとなっているか。
モニタリング
- 日常的モニタリングが、企業の業務活動に適切に組み込まれているか。
- 経営者は、独立的評価の範囲と頻度を、リスクの重要性、内部統制の重要性及び日常的モニタリングの有効性に応じて適切に調整しているか。
- モニタリングの実施責任者には、業務遂行を行うに足る十分な知識や能力を有する者が指名されているか。
- 経営者は、モニタリングの結果を適時に受領し、適切な検討を行っているか。
- 企業の内外から伝達された内部統制に関する重要な情報は適切に検討され、必要な是正措置が取られているか。
- モニタリングによって得られた内部統制の不備に関する情報は、当該実施過程に係る上位の管理者並びに当該実施過程及び関連する内部統制を管理し是正措置を実施すべき地位にある者に適切に報告されているか。
- 内部統制に係る開示すべき重要な不備等に関する情報は、経営者、取締役会、監査役等に適切に伝達されているか。
ITへの対応
- 経営者は、ITに関する適切な戦略、計画等を定めているか。
- 経営者は、内部統制を整備する際に、IT環境を適切に理解し、これを踏まえた方針を明確に示しているか。
- 経営者は、信頼性のある財務報告の作成という目的の達成に対するリスクを低減するため、手作業及びITを用いた統制の利用領域について、適切に判断しているか。
- ITを用いて統制活動を整備する際には、ITを利用することにより生じる新たなリスクが考慮されているか。
- 経営者は、ITに係る全般統制及びITに係る業務処理統制についての方針及び手続を適切に定めているか。
(注) 全社的な内部統制に係る評価項目の例を示したものであり、全社的な内部統制の形態は、企業の置かれた環境や特性等によって異なると考えられることから、必ずしもこの例によらない場合があること及びこの例による場合でも、適宜、加除修正がありうることに留意する。
この連載の記事
-
2025.07.07
第4回 内部統制報告制度における全社的な内部統制と決算・財務報告に係る内部統制について
-
2025.02.03
第3回 会社法と金融商品取引法で求められる内部統制の違いについて
-
2025.01.20
第2回 内部統制の事例について
-
2025.01.14
第1回 内部統制の基本的な考え方
プロフィール

税理士・公認会計士 髙倉 裕幸(たかくら ひろゆき)
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
- 略歴
- 1998年に株式会社富士通研究所に入社しJPEGを中心とした画像圧縮技術を専門として研究開発に従事。その後、2008年に公認会計士として有限責任監査法人トーマツに入社し、テクノロジー、メディア、製造業等を中心とした上場会社の監査業務に従事、その間、前職の知識を活かしてIT監査を含むシステム統制を中心とした内部統制の改善提案等を行ってきた。現在は、税理士法人NewRの代表として税理士業務を行いながら、上場子会社のPMIを中心に決算支援や内部統制の構築支援、税務顧問など幅広く業務を行っている。
- ホームページURL
- 税理士法人NewR
免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。