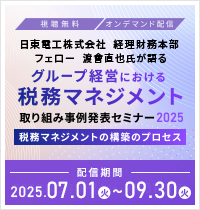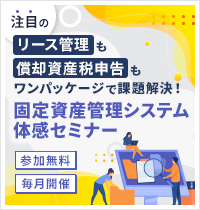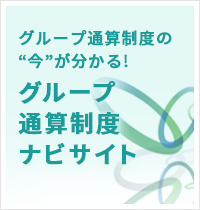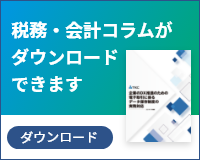更新日 2025.10.20

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
日本・米国公認会計士・税理士 大樂 弘幸
のれんの償却・非償却を巡る国際的議論と、M&A促進へ国内基準見直しの動き及び国際的な開示強化の動きについて解説する。
当コラムのポイント
- 日本は「のれん」の価値が逓減するとの考え方から償却モデルを堅持している。一方、それに対する国内において新たな動きが見られる。
- IASBは圧倒的多数で非償却モデルの維持を決定した。一方で、現状の懸念点へ対応するために新たな開示要求の議論を開始している。
- 会計論争は「償却又は非償却」の議論から開示の透明性へと軸足を移動させている。減損テストの仮定やM&A後の実績の説明責任が企業に求められる可能性がある。
- 目次
-
1.はじめに:グローバルM&Aの巨大化と会計の考え方の対立
「のれん」の会計処理は、日本の企業会計基準委員会(ASBJ)をはじめ、国際的な会計ルールを決める主要な機関の間で、長年にわたり意見が対立してきたテーマです。のれんとは、企業が他の会社を買収(M&A)した際に、支払った金額が、買収した会社の持つ純資産の価値を上回った場合に計上される差額を指します。それは、ブランド力や将来の相乗効果といった、目に見えないけれど価値を生み出す「超過収益力」を表します。
こののれんの取扱いが重要になった背景には、M&A活動の世界的規模での拡大があります。ある分析によると、2023年に発表された買収取引の合計額は3.2兆米ドルに達しており、巨額の買収プレミアムとしてのれんが計上される事例が当たり前になっています。このため、のれんの扱い方は、企業の財務体質、利益の質、そして投資家をどう守るかという点に直結する、非常に重要な問題となっています。
会計基準設定主体が直面する根本的な問題は、のれんの「価値の寿命」に関する考え方の違いです。この違いが、のれんを「決まったルールで少しずつ費用にする(償却)」べきだという立場と、「価値が下がったことが確認された時だけ費用にする(非償却・減損)」べきだという立場の間で、対立を生むことになります。
2.のれん償却の現状:日本が守り続ける「慎重な会計」の考え方と国内変革の動き
日本基準は、国際的な主要基準(IFRS、US GAAP)が非償却モデルを採用する中、一貫してのれんの償却モデルを守り続けてきました。日本基準では、のれんを原則として20年以内の期間にわたって定額法により、規則正しく費用として計上することが求められています。
日本基準の考え方は、古くから「慎重に考える姿勢(保守主義)」と「儲けと費用をきちんと対応させる原則」を重視しています。ASBJが償却モデルを維持する主要な論拠もここにあります。のれんは、将来の超過収益力を期待して支払われた対価であり、この儲けの力を享受できる期間にわたり、規則的に費用として割り振る(償却する)ことで、収益と費用を対応させるのが原則に忠実だとされます。
この考え方では、超過して儲ける力は永遠に続くものではなく、時間の経過とともに必ず弱まっていく性質のものと見なされます。したがって、規則的な費用計上が株主への利益配分を抑制することで会社の財産を守るという、資本維持の視点とも密接に結びついています。また、規則正しい償却は、減損テストのように経営者の主観的な判断に依存することを避け、会計情報の「客観性」と「予測のしやすさ」を高めるというメリットがあると、日本は主張してきました。
一方で、日本国内では、この伝統的な償却モデルが、経済の活性化を阻害しているのではないかという新たな問題意識が提起されています。特に、大企業が革新的な技術を持つスタートアップ企業を買収(M&A)する際、その買収プレミアムとして計上されるのれんの償却費が、毎期の営業利益を圧迫する結果となり、M&Aの足かせになっているとの指摘があります 。企業側からすると、会計上の利益が下がることで、株価や評価に悪影響が出ることを懸念し、M&Aに二の足を踏んでしまうという実情があります。
そのため、経済同友会をはじめとする民間団体は、M&Aの阻害要因を解消するために、のれんの会計処理の見直しが必要だと主張しています。これは、会計基準が、M&Aを促進し、日本経済を持続的な成長軌道に乗せるための政策的手段の一つとして位置づけられ始めていることを示しています。
(1) 日本政府と民間団体による具体的な提案:実務的な妥協点の模索
この国内的な要請の高まりを受け、日本の金融庁もその政策の方針に反映させる動きを見せています。金融庁は「2024事務年度金融行政方針」の中で、「スタートアップへの成長資金の供給の促進」や「金融・資本市場の機能向上」を重要課題として掲げ、直接的に「のれん」に言及していないものの、この流れの中で財務報告のあり方についても検討を示唆しています。
具体的な解決策として、民間団体からはのれんの償却だけでなく非償却も認める「選択制」の導入や、償却費を「営業費用」ではなく「営業外費用」または「特別損失」として計上し、本業の儲け(営業利益)を圧迫しないようにする案が提案されています。これは、国際的な潮流(非償却)と国内の慣行(償却)との間で、両者の利点を部分的に取り入れようとする「実務的な妥協点」の模索といえます。
(2) 国際基準への直近の主張と今後の国内議論の展望
国際的な議論が非償却モデルの維持に傾く中、日本の財務会計基準機構(FASF)の下にある企業会計基準委員会(ASBJ)は、2024年7月12日のコメント・レターにおいて、国際基準設定機関であるIASBに対し、「のれんの償却の再導入が提案されなかったことを残念に思う」という表現を用いて、従来からの日本の立場を表明しています。
一方、こののれんの会計処理を巡る日本基準における議論は、今後、財務会計基準機構(FASF)の諮問会議などを経て、企業会計基準委員会(ASBJ)が本格的な検討の可否を判断する見通しです。
この連載の記事
-
2025.11.04
第3回(最終回) のれん会計の今後の動向と課題
-
2025.10.27
第2回 非償却モデルの根拠:IFRSと米国基準の考え方
-
2025.10.20
第1回 論争の原点:なぜ日本は「償却」を求めるのか、そして国内の変革の兆し
テーマ
プロフィール

日本・米国公認会計士・税理士 大樂 弘幸(だいらく ひろゆき)
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
- 略歴
- 監査法人及びFASで18年以上の経験、及び金融庁企業開示課で2年間の開示行政を経験した。企業開示課ではASBJの会議やIASBの国際会議に参加するなど日本基準及び国際会計基準の基準設定に精通する。現在は独立して会計事務所を設立し、監査業務、IPO支援、税務業務、上場企業の社外監査役業務を行う。
- ホームページURL
- 大樂公認会計士・税理士事務所
免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。