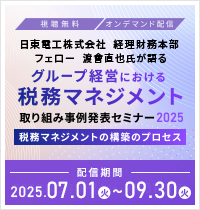更新日 2013.01.21
 TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
税理士 藤井 規生
制度創設から10年が経過し、繰越欠損金の持ち込み制限の緩和や復興特別税の創設等、連結納税制度の適用を検討するためのポイントも変遷しています。
そのため、このコラムでは、連結納税制度の適用を検討するにあたり必要となる制度の基礎的な理解や制度創設時とは変わった点について、わかりやすく解説します。
平成24年9月から10回にわたり連載してきました「連結納税の基礎」コラム。今回でいよいよ最終回となります。最終回では、前回の「連結納税適用の検討から連結申告(初年度)までの主なイベント」で登場した「連結納税下での税効果会計」について解説します。連結納税の適用が、個別財務諸表における税効果会計にどのような影響を与えるか確認しましょう。
1.単体申告と連結納税での税効果会計における相違
税効果会計に関する基本的な考え方に変わりはありませんが、単体申告と連結納税では法人税・住民税・事業税の計算方法が異なるため、繰延税金資産等の計算方法でも以下の相違があります。
- 繰越欠損金に係る税効果については、法人税、住民税及び事業税の別に計算する必要があること。
- 繰延税金資産の回収可能性は、法人税については連結納税グループ全体の将来課税所得の見積額で判断し、住民税と事業税については単体の将来課税所得の見積額で判断する必要があること。
-
連結納税特有の一時差異があること。
- 連結納税開始又は加入時の連結子法人の時価評価に係る一時差異
- 帳簿価額修正に係る一時差異
| ※ | 税効果会計に関する会計基準等について、企業会計審議会から公表された「税効果会計に係る会計基準」及び日本公認会計士協会から公表された実務指針等があります。さらに、同制度を適用した場合の実務上の取扱いを明らかにする必要が生じたため、企業会計基準委員会(ASBJ)から実務対応報告が公表されており、過去に数回の改訂がなされています。 |
|---|
2.連結納税制度における実効税率
連結納税制度においては、繰越欠損金の取扱いが税金の種類ごとに異なるため、繰越欠損金に係る繰延税金資産は、以下の税率を適用して計算することになります。
| 税目 | 繰越欠損金 | 適用税率 |
|---|---|---|
| 法人税 | 連結欠損金個別帰属額 (特定連結欠損金個別帰属額を含む) |
法人税率/(1+事業税率) |
| 住民税 | 連結欠損金個別帰属額 (特定連結欠損金個別帰属額を含む) |
法人税率×住民税率/(1+事業税率) |
| 住民税 | 控除対象個別帰属調整額 | 住民税率/(1+事業税率) |
| 住民税 | 控除対象個別帰属税額 | 住民税率/(1+事業税率) |
| 事業税 | 欠損金額または個別欠損金額 | 事業税率/(1+事業税率) |
注)事業税率は所得割のみであり、かつ、地方法人特別税分を含む
<財務諸表上の一時差異及び繰越欠損金に適用する実効税率の計算例>
(外形標準課税法人:東京都の場合)
| 繰越欠損金に適用する 実効税率 |
H23年度改正前 | H23年度改正後 | ||
|---|---|---|---|---|
| 復興増税期間中 | 復興増税期間後 | |||
| ① | 法人税部分 | 27.893% | 26.080% | 23.710% |
| ② | 住民税部分 | 5.774% | 4.908% | 4.908% |
| ③ | 控除対象個別帰属調整額 控除対象個別帰属税額 |
19.247% | 19.247% | 19.247% |
| ④ | 事業税部分 | 7.022% | 7.022% | 7.022% |
| 財務諸表上の一時差異に 適用する実効税率 ①+②+④ |
40.689% | 38.010% | 35.640% | |
<繰越欠損金に係る繰延税金資産の計算例>
連結欠損金個別帰属額、控除対象個別帰属調整額(住民税の繰越欠損金)、及び事業税の繰越欠損金がある連結法人について繰延税金資産を計算すると以下のようになります。例をわかりやすくするため、繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性はあるものとし、税率は上述の「H23年度改正後 復興増税期間後」とします。
- ・連結欠損金個別帰属額
- 10,000千円
- ・控除対象個別帰属調整額
- 3,000千円
- ・事業税の繰越欠損金
- 20,000千円
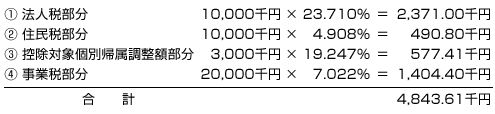
3.連結納税制度における繰延税金資産の回収可能性
回収可能性の判断に関する留意すべき事項の例として、以下の3点が実務対応報告第7号に掲げられています。
- 法人税、住民税及び事業税の別に区分して行うこと
- 法人税に係る繰延税金資産の回収可能性(連結法人税の個別帰属額について、将来の支出又は収入を減少又は増加させる効果を有するかどうか)の判断は、個別所得見積額だけでなく、当該連結納税会社の属する連結納税主体の他の連結納税会社の個別所得金額見積額も考慮すること
- 法人税の連結欠損金個別帰属額に係る繰延税金資産の回収可能性の判断については、連結納税の計算に従って、以下のとおりに行うこと
- (イ)
- 連結納税主体の連結欠損金に特定連結欠損金が含まれていない場合は、連結所得見積額を考慮する。
- (ロ)
- 連結納税主体の連結欠損金に特定連結欠損金が含まれている場合は、連結所得見積額及び各連結納税会社の個別所得見積額の両方を考慮する
- 財務諸表上の一時差異に係る繰延税金資産等の金額については、各連結法人の財務諸表上の一時差異として認識される金額が、連結納税を適用した場合であっても、法人税、住民税及び事業税において基本的に共通であるため、税金の種類ごとに区分して計算する必要はないとされています。ただし、回収可能性の判断については、税金の種類ごとに行う必要があるとされていますから注意が必要です。
- 連結納税制度では、法人税について回収可能性の判断をする上で、各連結法人の個別所得見積額がない場合でも、連結納税グループ全体の連結所得見積額があれば回収可能性があることになります。逆に、各連結法人の個別所得見積額がある場合でも、連結納税グループ全体の連結所得見積額がなければ回収可能性はないことになりますから、各連結法人と連結納税グループ全体の所得見積額の両方を考慮する必要がでてきます。
- 連結納税制度における繰越欠損金の取扱いは、税金の種類ごと及び、繰越欠損金の種類ごとに異なるため複雑な計算を要します。
<繰延税金資産の回収可能性判断の例(財務諸表上の一時差異について)>
X0年度(当期)において発生した将来減算一時差異(2,000千円)について、回収可能性の判断を行います。例をわかりやすくするため、X1年度のみの所得見積額で回収可能性の判断を行い、税率は上述の「H23年度改正後 復興増税期間後」とします。
(1) 単体納税の場合(S社単体)
X1年度の所得見積額(一時差異解消前)は△10,000千円であり、法人税額が発生する見込みがないことから、将来減算一時差異(2,000千円)の回収可能性はない。
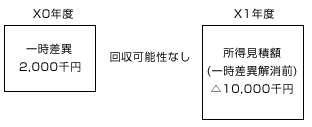
(2) 連結納税の場合(P社とS社の2社連結)
P社(連結親法人)のX1年度の個別所得見積額(一時差異解消後)は15,000千円であり、S社の個別所得見積額(一時差異解消前)△10,000千円と、一時差異の解消額△2,000円の合計△12,000千円と相殺が可能である。S社の連結法人税個別帰属額は△3,060千円(△12,000千円×25.5%)となり、将来減算一時差異の解消額についても、連結親法人から連結法人税個別帰属額として受け取ることができる。したがって、法人税においては繰延税金資産の回収可能性があることになる。
ただし、住民税と事業税においては単体納税と同様に各社の個別所得見積額で回収可能性を判断することになるため、X1年度の地方税の算定基礎となる所得金額、法人税額ともに、S社単体ではマイナスであるため、住民税及び事業税ともに回収可能額はない。
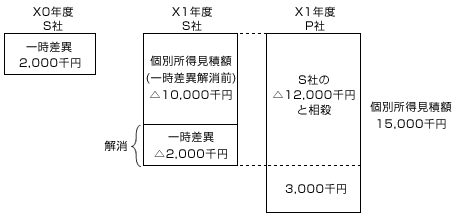
- ①法人税の回収可能額
- 2,000千円 × 23.710% = 474.2千円 → 回収可能性あり
- ②住民税の回収可能額
- 2,000千円 × 4.908% = 98.16千円 → 回収可能性なし
- ③事業税の回収可能額
- 2,000千円 × 7.022% = 140.44千円 → 回収可能性なし
以上のように、連結納税制度における税効果会計は、単体申告と基本的な考え方に変わりはないといえども、その取扱いには大きな違いがあり非常に複雑になっています。
前回の「連結納税適用の検討から連結申告(初年度)までの主なイベント」で述べた、「単体申告最終事業年度において『連結納税制度に基づいて回収可能性を判断』」とは、「単体申告最終事業年度から、将来課税所得を連結納税ベースで見積り、税金の種類ごとに回収可能性を判断する」ということです。「この課題を確実にクリアできる業務システムを選定しておきましょう」と述べた理由は、この複雑さにあります。
<最後に>
連結納税制度を「わかりやすく解説する」をモットーに、「連結納税の基礎」コラムを連載してまいりました。読者の方々が、このコラムを通して連結納税のエッセンスを吸収され、連結納税制度のメリットを享受される一助になれば幸いです。最後まで読んでいただきありがとうございました。
この連載の記事
-
2013.01.21
連結納税制度を適用する場合の税効果会計
-
2012.12.25
連結納税適用の検討から連結申告(初年度)までの主なイベント
-
2012.12.10
個別帰属額等の算定理由と連結納税下の事業税・住民税の取扱い
-
2012.11.26
連結法人税額、連結法人税の個別帰属額の計算
-
2012.11.12
連結所得の計算Ⅱ ③全体での連結調整から連結所得まで
-
2012.10.29
連結所得の計算Ⅰ ①単体調整から②単体での連結調整まで
-
2012.10.15
申告書の種類と提出時期・電子申告のメリット
-
2012.10.01
連結納税制度適用の注意点(時価評価と繰越欠損金)
-
2012.09.18
連結納税の適用による6つのメリット
-
2012.09.03
連結納税の積極的な活用に向けて制度を理解しましょう!
テーマ
プロフィール

税理士 藤井 規生(ふじい のりお)
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会 幹事
TKC企業グループ税務システム普及部会 部会長
TKC企業グループ税務システム小委員会委員
- ホームページURL
- 税理士法人創経
免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。