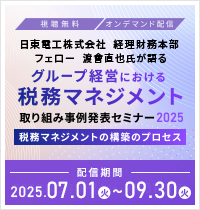更新日 2020.07.20

株式会社TKC 顧問
税理士 朝長 英樹
法人税法22条2項の「無償」の取引に関する定めについては、時価と実際の取引価額との差額の全額を常に益金の額に算入する旨を定めたものであるという解釈をしているものが見受けられます。しかし、このような解釈は、誤っていると考えられます。
本コラムでは、22条2項は、無償又は低額の取引に関し、時価と実際の取引価額との差額の全額を常に益金算入することとしたものではない、ということを確認します。
2.昭和38年の「贈与をした場合の益金算入」に関する条文案の内容が22条2項に引き継がれたと捉えてよいのか否かの検討
このコラムの読者の方々の中には、第1回の1で確認した昭和38年の「贈与をした場合の益金算入」に関する条文の案は採用されなかったことから、その案を22条2項の解釈に用いることには疑問がある、と考える方々もおられるのではないでしょうか。
確かに、そのように考えることにも、十分な理由があると考えます。
しかし、昭和38年の「贈与をした場合の益金算入」に関する条文の案が採用されなかったのは何故なのかということを考えてみると、答は1つしかないと考えられます。その答とは、時価と実際の取引価額との差額は、常に「贈与」となるとは限らず、「賞与」、「配当」、「交際費」等となることもあるため、「贈与」となる場合の益金算入の定めを法律の条文として設けるのであれば、その差額が「賞与」、「配当」、「交際費」等となる場合の益金算入の条文も設けることとせざるを得ないわけですが、現実には、それは非常に困難であったため、その差額が「贈与」となる場合の益金算入のみの条文を設けることとはされなかった、ということです。
第1回の1において引用したとおり、吉牟田勲先生は、昭和38年の「贈与をした場合の益金算入」に関する条文の案について、「これが、法人税法第22条2項の無償による資産の譲渡又は役務の提供として益金の額の列挙へ変わったのである。」と説明しておられるわけですが、この説明は、昭和38年の「贈与をした場合の益金算入」に関する条文の案における無償及び低い価格の取引の取扱いの規定の仕方が22条2項の「列挙」の形式に変ったということを言うものであり、その説明の含意は、その案の取扱いの内容が同項に引き継がれているということを言うものと解することができます。
また、22条2項を含む法人税法の立法作業を主導しておられた武田昌輔先生も、同項によって「受贈益」を益金算入することについて、「法人税法では、受贈益は明確に益金の額に算入することになる。ただ、低い価額で譲り受けた場合においては、その差額に贈与と認められる金額があれば、この規定によって収益の額に算入されることになる。」(「課税所得の基本規定の軌跡 ―法人税法第22条はこうして生まれた― ⑩」、MSG会社税務研究94-1、26頁、平成6年)というように、「その差額に贈与と認められる金額があれば」、22条2項によって「収益の額に算入されることになる」と説明しておられます。このような武田昌輔先生の説明は、昭和38年の「贈与をした場合の益金算入」に関する条文の案の2号の定めと同じことを言うものです。
また、22条2項の「無償」の取引に関する定めと連動して作られた37条8項(低額の取引における寄附金の額)(昭和40年の創設時には、6項)においても、対価の額が時価よりも低いときには、その差額の全額を寄附金の額とするのではなく、その差額の内の「実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額」のみを寄附金の額とするものとされています。このような37条8項の定めも、低い価格の取引について「著しく」という限定がない点を除き、昭和38年の「贈与をした場合の益金算入」に関する条文の案の2号の定めと整合するものです。
また、この37条8項に関しては、昭和40年に大蔵省主税局の職員が執筆した『改正税法のすべて』において、寄附金の額の意義を定めた37条7項(昭和40年の創設時には、5項)とともに、「これらの規定の趣旨は、税法における益金の額の考え方と一体的に考えてみると理解しやすいと思います(法22参照)。」(133頁)と説明されています。つまり、「無償」の取引においても「収益の額」を益金の額に算入するということを定めた22条2項の趣旨は、「贈与又は無償の供与」において贈与又は供与の時における時価を「寄附金の額」とするということを定めた37条7項と低い対価の額による譲渡又は供与においてその対価の額と時価との差額の内の「実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額」のみを「寄附金の額」とするということを定めた同条8項の考え方と「一体的」に考えて理解するべきものである、ということです。
そして、昭和40年の『改正税法のすべて』においては、上記の説明に続けて、37条7項と8項の取扱いについて、「なお、この贈与または低廉譲渡について寄付金とみなす取扱いは、従来通達によって定められていたものです(基本通達77)。」(133頁)とも説明されていますが、この括弧書きの中の「基本通達77」は、第1回の1において引用したとおりです。
このような事情にあることからも、昭和38年の「贈与をした場合の益金算入」に関する条文の案に示されていた取扱いは、低い価格の取引について「著しく」という限定がある点を除き、22条2項の「無償」の取引に関する定めの取扱いに引き継がれていると判断してよいものと考えられます。
もっとも、昭和40年に法人税基本通達77を廃止したことに関しては、当時、国税庁の職員が「贈与または低廉取得の場合に時価との差額を寄付金とする従来の取扱いは、法律に規定されたので削除された(法37⑤)。」(桜井巳津男「法人税整理通達の逐条解説」税理第8巻第13号、91頁、昭和40年)と説明しており、また、東京国税局の職員が「法人が有する資産を著しく低い価額で譲渡した場合には、その譲渡価額とその時におけるその資産の価額との差額に相当する金額を相手方に贈与したと認められるときは、その差額に相当する金額は相手方に対する寄付金として取り扱われる(法三七⑥)。」(海野明「交際費および寄附金の取扱い」税経通信第20巻第12号、84頁、昭和40年)と説明していることからすると、本来は、37条8項に関しても、法人税基本通達77と同様に、「著しく低い価額」という限定があると解釈するのが適当なのかもしれません。
また、37条8項の「実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる」というのはどのような場合をいうのかということに関しては、昭和40年に、国税庁の職員が過去の判決の文言の一部を強調して引用する方法で「『贈与したと認められるとき』とは、譲渡資産の時価と譲渡価格との差額について、任意且つ無償で提供され、相手方もその差額について、何らの犠牲を伴わずに、受益していると認められるときであつて、これに反し、合理的な理由による場合は贈与したものと認められないと解すべきである。」(渡辺昭寿「寄付金の取扱いと問題点」税務弘報Vol.13,No.12、35頁、昭和40年)という解説をしていますので、同項の創設時には、この文言のように解釈することが予定されていたと解して良いものと考えられます。
3.1の確認と2の検討の結果を踏まえた結論
第1回の1で確認した昭和38年の「贈与をした場合の益金算入」に関する条文の案に示されていた取扱いが22条2項の「無償」の取引に関する定めの取扱いに引き継がれているということになると、当然のことながら、同項は、無償又は低い価額による取引について、時価と実際の取引価額との差額の全額を常に益金算入するとしたものではなく、その差額の内に相手方に対して実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額があるときに、その金額のみを益金算入するとしたものと解釈するべきである、ということになります。
22条2項の「無償」の取引に関する定めをこのように解釈することにより、その定めを37条8項の定めと「一体的」に理解することが可能となります。
22条2項の「無償」の取引に関する定めは、確かに、その文言だけを読むと、「無償」の取引には全て「収益の額」が存在しており、それが常に「益金の額に算入すべき金額」になると解釈することになる、と考えてしまいかねないわけですが、その立法過程において行われていたこと、企画立案者の説明、制定時の解説、37条8項の定めとの整合性などを勘案した上で判断すると、上記のような解釈に行き着くこととなります。
本コラムの読者の方々の中には、時価と実際の取引価額との差額が「受贈益」となる場合については上記のとおりであるとしても、その差額が「賞与」、「配当」、「交際費」等となる場合についてはどうなのか、という疑問を持たれる方もおられるものと思われますが、その疑問に対しては、22条2項の「無償」の取引に関して、その全てに「収益の額」が存在してそれが常に「益金の額に算入すべき金額」となるわけではなく、その「無償」の取引の相手方において利益を認識するべき金額だけ「収益の額」を認識してそれを「益金の額に算入すべき金額とするという、同項の構造に関する理解は、時価と実際の取引価額との差額が「受贈益」となる場合にのみ特有のものと解すべき理由がないことから、その差額が「賞与」、「配当」、「交際費」等となる場合についても、同様となる、と答えることになると考えられます。つまり、「無償」の取引の相手方において、「賞与」、「配当」、「交際費」等を受けたと認められる金額があるときに、その金額のみを「収益の額」として益金算入する、ということです。
このように理解すれば、22条2項の「無償」の取引に関する定めについては、取引の双方の者の処理を整合的に解釈することができることとなります。
最後に
最近、22条2項は時価と実際の取引価額との差額の全額を常に益金の額に算入する旨を定めたものであるという解釈をしているものを目にする機会があり、流石に、それは違うということを述べておいた方が良い、と考えたため、その点に焦点を絞って本コラムを執筆してみたわけですが、筆を進めるうちに、制定法の条文の解釈は、安易に過去の判決や「見解」に依拠して行うのではなく、その条文の創設・改正の趣旨や創設・改正の過程を正確に確認した上で行うべきである、と改めて感じた次第です。
これまでも、22条2項の「無償」の取引に関する定めについては、非常に多くの論考や判決が存在するわけですが、これらの中には、解釈論を語っているのか立法論を語っているのかということがよく分からないもの、過去の判決に示された解釈を安易に受け容れただけのもの、「説」とされるものを観念的に論ずるだけとなっているものなどが少なくないように見受けられます。
条文を解釈するに当たり、本来は、条文の創設・改正の趣旨や創設・改正の過程などまで正確に確認することが必要であるにもかかわらず、そのようなことを行わずに判断を下した判決や「説」とされるものに示されている「解釈」について、それを無批判に受け容れ、安易に上塗りを繰り返すことで、その条文の解釈をその創設・改正の時に予定されていたものとは似ても似つかないものにしてしまうなどということは、絶対に避けなければなりません。そのような「解釈」が当たり前のようにまかり通るなどという事態にまで至ってしまうと、解釈を元に戻すことさえできなくなってしまいます。
この連載の記事
テーマ
プロフィール

免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。