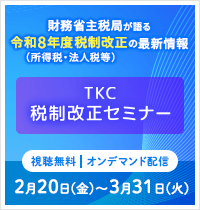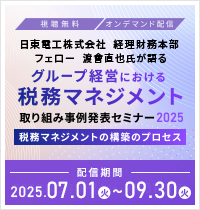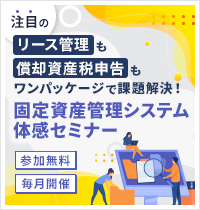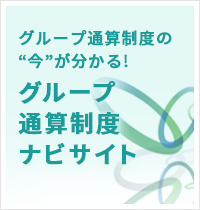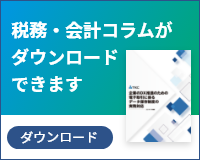更新日 2025.09.01

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC全国会 海外展開支援研究会 研修部会委員
税理士 中垣 光博
国境をまたぐ取引の取扱いとして、消費税には、内外判定、輸出免税等、輸入消費税、電気通信利用役務の提供に対する課税といった制度があります。これらの海外取引に関係する消費税法の制度について解説いたします。
当コラムのポイント
- 取引が「国内において」行われたかどうかの判定
- 輸出免税等と輸入消費税
- 電気通信利用役務の提供に対する課税
- 目次
-
前回の記事 : 第1回 海外取引に係る消費税の概要と内外判定
1.輸出免税
(1) 輸出免税の目的
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税が課税されます。輸出販売は、取引時の資産の所在場所が国内であることから、内外判定では消費税が課税される国内取引となります。しかし、国際的な慣行では、消費税は商品などが消費される国において課することとし、国外に輸出される商品などには消費税の負担が生じないよう国境税調整を行うこととされています(仕向地主義)。そこで、商品などが国外で消費される輸出取引においては、国内での消費税を免除する国境税調整としての輸出免税が規定されています。
(2) 輸出免税等の適用範囲の例示
消費税法7条には、「事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、輸出取引等に該当するものについては、消費税を免除する」と規定されています。輸出免税は、有形資産などの目に見える取引に加え、目に見えない取引(無形固定資産や役務提供)にも幅広く適用されます。以下に輸出免税等の適用となる取引を例示します。
- ①本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
- 輸出免税が適用されるのは、税関に輸出申告をして輸出許可書の交付を受けた輸出者本人のみとなります。
- ②無形固定資産の譲渡、貸付けで非居住者に対するもの
- 税関を通らない取引であるため、非居住者に対して行う取引であることが輸出免税の要件となっています。内外判定で国内取引であることが大前提です。
- ③非居住者に対する役務の提供
- ②と同様、非居住者に対して行う取引であることが要件ですが、まず内外判定で国内取引であることが大前提です。例外として、国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供は、一定の場合を除き輸出免税の対象とはされません。
また、非居住者が国内において直接便益を享受する役務の提供(飲食、宿泊、交通など)については、輸出免税の対象とはなりません。
(3) 輸出証明
輸出免税は、本来課税される取引の消費税を免除する制度です。また、輸出取引に要する仕入れに係る消費税額は控除できます。そこで、不正防止のため「輸出証明」が厳しく求められます。輸出証明書類は、輸出を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間保存する必要があります。
2.輸入消費税の課税
(1) 輸入取引の課税の対象
消費税法4条には「保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税を課する。」と規定されています。国内取引では「取引」という行為が課税対象となるのに対して、輸入消費税は「保税地域から引き取られる外国貨物」という国内に持ち込まれた貨物そのものが課税の対象となっています。保税地域とは「輸出入通関手続きが済むまで、貨物を一時的に保管する場所」です。
通関手続きと並行して、輸入消費税の申告納税が行われます。これは、内外判定では課税対象とならない国外取引である輸入取引については、国境税調整として国内取引とは別建ての課税を行い、国内に存在する課税済みの資産と同じ状態に置くことを目的としています。このように、輸入消費税は税関を通る「貨物」を課税対象としているため、目に見えない取引(無形固定資産や役務提供)には適用されないという課題があります。
(2) 輸入取引の課税標準
輸入消費税の課税標準は、CIF価格(輸入貨物の代金+運送料+保険料)に関税と消費税以外の個別消費税等を加えたものとなります。
また、「対価を得て」行う取引に限定される国内取引とは異なり、国外において無償で譲り受けた貨物の輸入であっても、その貨物の評価額を決定し、そこに運送料と保険料を加えたCIF価格から課税標準が算出され、引き取りの際には輸入消費税を納税することとなります。
この連載の記事
-
2025.09.22
第3回(最終回) 電気通信利用役務の提供の課税と事例研究
-
2025.09.01
第2回 輸出免税等と輸入消費税の課税
-
2025.09.01
第1回 海外取引に係る消費税の概要と内外判定
プロフィール

税理士 中垣 光博(なかがき みつひろ)
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC全国会 海外展開支援研究会 研修部会委員
- 略歴
- 大学卒業後、コンパッソ税理士法人に入所し、運送業、小売業、建設業、製造業、飲食業等の税務申告業務に従事。その後、さくら綜合事務所において証券化業務、組織再編業務、事業承継コンサルティング業務に従事。
2007年11月、税理士法人TGNあすなを設立、独立して現在に至る。 - 主要著書
-
- 『SPC&匿名組合の法律・会計税務と評価』(清文社)(共著)
- 『外国税額控除制度を乱用する取引にかかる同制度の適用の可否』
- 『特定目的会社等における21年度改正のポイント』(税務弘報)
- 『三菱UFJ銀行海外展開支援サイト』記事執筆
- ホームページURL
- 税理士法人TGNあすな
免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。