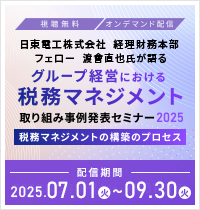更新日 2021.04.05

株式会社TKC 顧問
税理士 朝長 英樹
法人税法における収益の計上時期に関する解釈を述べるものにおいては、棚卸資産の販売収益の計上時期について争われた平成5年11月25日の最高裁判所の判決の解釈が多く引用されています。
本コラムでは、平成5年最高裁判決の一審判決と二審判決を含めて3つの判決のそれぞれの収益の計上時期に関する解釈を確認し、平成5年最高裁判決における収益の計上時期に関する解釈が正しいとは言い難いものであることを具体的に示します。さらに、平成30年度税制改正によって新たに制定された収益の計上時期に関する定めである法人税法22条の2第1項及び第2項の検証も行い、同改正以後における棚卸資産の販売収益の計上時期の解釈の課題について考察します。
4.法人税法22条4項の解釈
昭和42年に創設された法人税法22条4項(平成30年度税制改正前)の条文を確認しておくと、次のとおりです。
4 第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。
法人税法22条4項の文言を読めば直ぐに分かるとおり、同項は、同条2項の「収益の額」の「計算」に関して、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うということを定めるものとなっており、「収益の額」の計上時期に関して一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うということを定めたものではありません。法人税法22条4項の文言を読みさえすれば、同項に「収益の額」の計上時期に言及した文言が全く存在しないことは、誰でも分かるはずです。
「収益の額」の計上時期と計算とが別の事柄であることは、改めて言うまでもありません(注8)。
(注8) 平成30年度税制改正によって制定された法人税法22条の2においても、1項から3項までにおいて、収益の額の計上時期を定め、それらの規定とは別に、4項と5項において、収益の額がどのような金額となるのかということを定める、ということになっています。
何故、法人税法22条4項で、収益の額について、計算のみを定め、計上時期を定めなかったのでしょうか。
法人税法22条4項で収益の額について計算のみを定めて計上時期を定めなかったことには、明確な理由があります。
その理由は何かというと、それは、収益の額の計上時期に関しては、昭和40年の法人税法22条2項の創設時に、「「帰属主義」とも言い得るもの」とするということで、既に、答を出している、ということです。
換言すれば、法人税法22条2項は、昭和42年に同条4項を創設する直前には、収益の額の内容とともに計上時期に関して既に答を出しているが、しかし、収益の額の計算に関しては、答を出していない、という状態となっていた、ということです。
このような状態となっていたが故に、昭和42年に、法人税法22条2項の収益の額に関して、同条4項に収益の額の計算の定めを設けることが可能となったわけです。
昭和42年には、同年の税制改正で創設された法人税法22条4項について、従前の取扱いを変更するものではないという解説がなされていますが、昭和40年に収益の額の内容と計上時期について答を出し、昭和42年に収益の額の計算に答を出した、ということになっていなければ、そのような解説がなされることはありません。
実際に、そのようなことになっているということは、法人税法22条4項の立法過程を確認すれば、より一層、明確になります。
法人税法22条4項の立法過程においては、収益の額等の計算に関する規定を設けることに止まらず、益金の額等の帰属時期を定める規定として、第5項に「第1項の当該事業年度の益金の額及び当該事業年度の損金の額の帰属の時期は、法人が継続して適用する適正な会計慣行によるものとする。」(昭和41年12月22日大蔵省主税局税制第1課「所得計算の基本規定を設けることについて」の中の条文案の「第2案」)という条文を設けることについても検討されていますが、既に同条2項で「「当該事業年度の収益の額とする。」という表現をとつていること」等から、そのような規定は、設けないこととされています。
要するに、法人税法22条4項の文言からだけでなく、同項の立法過程を確認してみても、同項が収益の計上時期を定めていないことは、明確であるわけです。
ところで、収益の計上時期に関する論考には、収益の額の計算に関する定めを設ければ、自ずと、その計上時期に関する定めを設けていることともなる、と解釈しているものが見受けられますが、そのような解釈は、明らかに誤っています。
法人税法22条2項の収益の額に関しては、その内容、計上時期と計算の3つが常に問題となるという関係となりますが、それらは、計算について定めを設ければ内容と計上時期も自動的に決まってくるなどという関係とはならないことが明らかです。
つまり、法人税法22条4項で収益の額について、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って計算すると定めれば、自ずと収益の額の計上時期も決まってくる、という短絡的な解釈は、明らかに誤っている、ということです。
5.法人税基本通達の棚卸資産の販売収益の計上時期に関する定めの解釈
『昭和40年 改正税法のすべて』において、「今後の検討」に委ねることとされた収益の計上時期の「基準」は、棚卸資産の販売による収益の額に関しては、昭和44年に制定された旧法人税基本通達2-1-1(たな卸資産の販売による収益の帰属の時期)において、次のとおり、昭和40年の法人税法22条2項の創設前から引き継がれてきた引渡基準とされました。
(たな卸資産の販売による収益の帰属の時期)
2-1-1 たな卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあつた日の属する事業年度の益金の額に算入する。
この棚卸資産の販売による収益の計上時期の基準である引渡基準は、『昭和40年 改正税法のすべて』において説明されていたとおり、「帰属主義」とも言い得る「主義」の下での「基準」と捉えられるものです。
この引渡基準について、「実現主義」に基づくものと言い得るのかというと、『昭和40年 改正税法のすべて』において説明されていたとおり、法人税法22条2項の「帰属主義」とも言い得る「主義」は企業会計における「実現主義」と「一致するという保証がない」ため、「実現主義」に基づくものとは言い得ず、また、仮に「実現主義」を税法に固有の概念であると整理したとしても、『昭和40年 改正税法のすべて』において説明されていたとおり、「実現という用語を用いることは避け〔る〕」こととされたわけですから、「実現主義」に基づくものとは言い得ない、ということになります。
改めて言うまでもありませんが、この引渡基準は、引渡しという事実があった日に収益を計上させるというものであり、旧法人税基本通達249の本文にあった「売買契約の効力発生の日」のように、契約の効力発生という法的な判断ができるようになった日に収益を計上させるというものではありませんので、「権利確定主義」に基づく基準とは言い得ません。「引渡しによって権利が確定する」というような説明をして、引渡基準は「権利確定主義」であると主張するものも、一部、見受けられますが、仮に、そのような説明が正しいとすれば、旧法人税基本通達249において、「但し」という例外を示す用語を用いて引渡基準を定めるなどということをするはずがなく、そのような説明は、詭弁と言わざるを得ません。
なお、固定資産の譲渡による収益の額の計上時期に関しては、昭和44年当時、旧法人税基本通達2-1-3(固定資産の譲渡による収益の帰属の時期)において、「引渡しがあつた日」に収益計上を行うことを原則としつつ、「ただし」という特例を示す文言を用いて、「契約の効力発生の日以後引渡しの日までの間における一定の日」(昭和55年の改正によって「契約の効力発生の日」に改正した上で、通達番号を2-1-14に変更。)に収益が生じたものとすることを認めることとされていましたので、特例として「権利確定主義」によることが認められていた、と捉えることができます。
6.平成5年最高裁判決における収益の計上時期の解釈の内容の検証
(1) 法人税法22条4項の解釈誤り
― 法人税法22条4項は、収益の額の計算について定めたものであって、収益の額の計上時期について定めたものではないことが明確であるため、収益の額の計上時期の根拠規定とはならない ―
平成5年最高裁判決においては、第1回の3において確認したとおり、「当該事業年度の収益の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算すべきものとされている(同条4項)。したがって、ある収益をどの事業年度に計上すべきかは、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うべき」というように、法人税法22条2項の収益の額の計上時期について、同条4項に定めが設けられているという前提に立って、その解釈を述べています。
しかし、上記4において述べたとおり、法人税法22条4項は、収益の額の計算について定めたものであって、収益の額の計上時期について定めたものではないことが明確です。
このため、平成5年最高裁判決において、法人税法22条4項を引用した上で、「したがって」という、同じことを言い換える場合の接続詞を用い、「ある収益をどの事業年度に計上すべきかは、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うべき」と判示した部分は、明らかな誤りということになります。
要するに、平成5年最高裁判決の「ある収益をどの事業年度に計上すべきかは、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うべき」と判示した部分は、法人税法22条2項及び4項について、誤った解釈を示していることが明確であるため、早急に判例変更をする必要がある、ということです。
(2) 法人税法22条2項の解釈誤り
― 法人税法22条2項の収益の額の計上時期に関する「主義」は、「「帰属主義」とも言い得るもの」とされており、「実現主義」や「権利確定主義」とはされていないことが明確である ―
平成5年最高裁判決においては、第1回の3において確認したとおり、「これ〔引用者注:一般に公正妥当と認められる会計処理の基準〕によれば、収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する年度の益金に計上すべきものと考えられる。」という解釈を示しています。
しかし、第2回の3において述べたとおり、法人税法22条2項の収益の額の計上時期に関する「主義」がどのようなものとされているのかというと、「「帰属主義」とも言い得るもの」とされており、「実現主義」や「権利確定主義」とはされていません。
平成5年最高裁判決においては、第2回の3において述べたことを覆すに足るような ことは、全く何も示されていませんので、上記の「これによれば、収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する年度の益金に計上すべきものと考えられる。」という「考え」は、根拠のない誤った「考え」ということにならざるを得ません。
このため、平成5年最高裁判決の「これによれば、収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する年度の益金に計上すべきものと考えられる。」という部分についても、早急に判例変更をすることが必要である、ということになります。
〔参考〕法人税法22条2項においては、「資産の販売」、「資産の譲渡」、「役務の提供」と「資産の譲受け」が取引の例示として挙げられていますが、収益の額を生じさせるのは、これらの取引だけではなく、「その他の取引」についても、収益の額を生じさせるものとされています。
そして、この「その他の取引」の中には、補助金収入や拾得金に係る収益などのように、引渡しや完了を伴うことなく収益の額を計上しなければならないというものも存在しており、それらの中には、権利が確定した時に収益を計上するべきであるとした方が適当であるというものも、現に存在しています。
このため、収益の計上時期に関して、「権利確定主義」を完全に排除するべきということにはならないと考えられます。
(3) 固定資産と棚卸資産の収益の計上時期の相違の認識誤り
― 棚卸資産の販売収益の計上時期については、「基準」が引渡基準であることに全く疑義がないため、「実現主義」や「権利確定主義」というような「主義」を持ち出す意義は全くない ―
平成5年最高裁判決の事件は、棚卸資産の販売収益の計上時期について争われた 事件であって、固定資産の譲渡収益の計上時期について争われた事件ではありません。
そして、棚卸資産の販売収益の計上時期に関しては、第2回の2から上記5までにおいて述べたとおり、法人税法22条2項の立法過程を確認すると、一貫して引渡基準を採ることとされていたことを確認することができますので、棚卸資産の販売収益の計上時期に関しては、わざわざ「実現主義」や「権利確定主義」というようなものを持ち出す意義は、全くありません。
要するに、平成5年最高裁判決において、第1回の3において確認した解釈を示した裁判官は、固定資産の譲渡収益の計上時期については引渡基準を原則としつつも約定基準によることも認められることがある一方、棚卸資産の販売収益の計上時期については引渡基準のみによることとなる、という相違があることを認識していないとともに、棚卸資産の販売収益の計上時期については、「基準」が引渡基準であることに全く疑義がないため、「主義」を持ち出す意義がないということを全く理解していない、ということです。
そのような基本的な事項に関する認識不足や理解不足のまま示された棚卸資産の販売収益の計上時期の解釈が正しいはずがありません。
(4) 法人税法22条2項及び4項の立法過程の確認漏れ
― 法人税法22条2項及び4項の立法過程を確認すれば、棚卸資産の販売収益に関しては、「権利確定主義」も「実現主義」も採っていない、ということが明確に分かる ―
法人税法22条2項と4項は、それらの文言を読むだけで、「権利確定主義」も「実現主義」も採っていないことが分かるわけですが、第2回の3及び上記4において述べたとおり、これらの規定の立法過程を確認すれば、なお一層、棚卸資産の販売収益に関しては、「権利確定主義」も「実現主義」も採っていない、ということが明確に分かります。
第2回の3及び上記4において述べたことは、いずれも法人税法22条2項と4項の立法過程において、実際に確認される事実であって、論者の見解等によって変わるようなものではありません。
つまり、平成5年最高裁判決において法人税法22条2項と4項の解釈を述べた裁判官には、これらの規定の立法過程における事実に関する確認漏れがある、ということです。
当然のことながら、法人税法22条2項と4項の立法過程における事実に反する解釈は、早急に改められなければなりません。
(5) 「実現主義」と「権利確定主義」の内容に関する理解不足
― 「実現があった時」と「収入すべき権利が確定したとき」は、「すなわち」という接続詞で結ぶことができるものではない ―
平成5年最高裁判決においては、第1回の3において確認したとおり、「収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する年度の益金に計上すべきものと考えられる。」と述べています。
しかし、収益の額を「その実現があった時」に益金に計上すべきであるとするもの(「実現主義」をいうものと解されます。)と「その収入すべき権利が確定したとき」に益金に計上すべきであるとするもの(「権利確定主義」をいうものと解されます。)とは、前に述べたことと同じ内容のことを別の言葉で述べるときに用いる「すなわち」という接続詞によって説明することができる内容のものでないことが明確です。
平成5年最高裁判決が出されて以後、その解釈について、多くの研究者や実務家が論考を書き、多くの判決が引用をしているにもかかわらず、筆者は、「その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したとき」という文言が誤っているという指摘を行ったものを見た記憶がありません。
しかし、裁判所が示した解釈であってもその適否は検討する必要があるという問 題意識を僅かなりとも持ってさえいれば、「その実現があった時」と「その収入すべき権利が確定したとき」とが同じ時となるとは限らないということは、容易に分かるはずです。
このように、平成5年最高裁判決の「収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定したときの属する年度の益金に計上すべきものと考えられる。」という解釈については、「実現主義」と「権利確定主義」の内容に関する理解が不足しているものであることが明らかです。
平成5年最高裁判決の上記の文言は、収益の計上時期について、「実現主義」によって判断することも、「権利確定主義」によって判断することも、また、引渡基準によって判断することもできると解される状態となっており、例えて言えば、 買い手よし売り手よし世間よしという「三方よし」の精神をもって法律の条文の解釈を示したかの如き観を呈するものと言ってよいでしょう。
確かに、一般論として言えば、全員が満足するものが良いに越したことはありませんし、裁判においても、裁判官が紛争解決の手段として、互譲による和解を勧告するということが行われています。
しかし、法令の条文の解釈には、「和解」などというものは、ありません。
このため、棚卸資産の販売収益の計上時期の判断をするものが「実現主義」、「権利確定主義」、引渡基準のいずれとも読み取れる平成5年最高裁判決の上記の文言の解釈は、適切ではないことが明らかである、ということになります。
(6) 本来は「棚卸資産の販売による収益の額はその引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入することとされている」と言うだけで済む
棚卸資産の販売収益の計上時期に関しては、第2回の3から上記5までにおいて述べた とおり、法人税法22条2項の立法過程においても一貫して引渡基準によることとされてきており、法人税基本通達における解釈も引渡基準によることとされています。
このため、棚卸資産の販売収益の計上時期に関しては、平成5年最高裁判決の第1回の3において確認した解釈にあるように、収益の額を「その実現があった時」に益金に計上すべきであるとか、「その収入すべき権利が確定したとき」に益金に計上すべきであるとかという必要は全くなく、単に「棚卸資産の販売による収益の額はその引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入することとされている」と言うだけで済むということになります。
換言すれば、単に「棚卸資産の販売による収益の額はその引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入することとされている」と言うだけで済むものについて、「その実現があった時」に益金に計上すべきであるとか、「その収入すべき権利が確定したとき」に益金に計上すべきであるとかと平成5年最高裁判決が述べたことで、棚卸資産の販売収益の計上時期に関する解釈がおかしくなってしまっている、ということです。
繰り返しになりますが、このような平成5年最高裁判決の誤った解釈は、早急に変更されるべきです。
この連載の記事
-
2021.04.19
第5回(最終回) 法人税法22条の2第1項及び第2項の検証
-
2021.04.12
第4回 法人税法22条の2第1項及び第2項の検証
-
2021.04.05
第3回 平成5年最高裁判決の解釈の検証(その2)
-
2021.03.29
第2回 平成5年最高裁判決の解釈の検証(その1)
-
2021.03.22
第1回 昭和61年神戸地裁判決・平成3年大阪高裁判決・平成5年最高裁判決の解釈の確認
テーマ
プロフィール

免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。