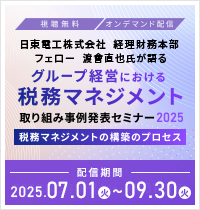更新日 2021.03.29

株式会社TKC 顧問
税理士 朝長 英樹
法人税法における収益の計上時期に関する解釈を述べるものにおいては、棚卸資産の販売収益の計上時期について争われた平成5年11月25日の最高裁判所の判決の解釈が多く引用されています。
本コラムでは、平成5年最高裁判決の一審判決と二審判決を含めて3つの判決のそれぞれの収益の計上時期に関する解釈を確認し、平成5年最高裁判決における収益の計上時期に関する解釈が正しいとは言い難いものであることを具体的に示します。さらに、平成30年度税制改正によって新たに制定された収益の計上時期に関する定めである法人税法22条の2第1項及び第2項の検証も行い、同改正以後における棚卸資産の販売収益の計上時期の解釈の課題について考察します。
1.昭和47年9月27日の東京地方裁判所の判決と昭和50年12月26日の鹿児島地方裁判所の判決の解釈の確認
法人税法22条が昭和40年に制定された直後に、同条2項が適用されて課税を受け、それが争いとなり、裁判において同項の収益の計上時期に関する解釈が示されたというものとしては、昭和47年9月27日の東京地方裁判所の判決(昭和48年10月30日に東京高等裁判所で控訴棄却により納税者の敗訴が確定)と昭和50年12月26日の鹿児島地方裁判所の判決(昭和59年10月25日に最高裁第一小法廷で上告棄却により納税者の敗訴が確定)があります。
これらの判決の解釈は、平成5年最高裁判決の解釈と基本的には同旨と捉えることができるものとなっています。
昭和47年9月27日の東京地方裁判所の判決においては、次のような解釈が示されています。
「右益金の額は、別段の定めがあるものを除き、資本等取引以外の取引にかかる当該事業年度の収益の額である旨定めている(同法22条1、2項)。そして、右の当該事業年度の収益の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるべきものとされている(同条4項)。したがって、法人の所得の算定にあたり、当該収益がどの事業年度におけるものであるかを決定するについても、公正妥当な会計処理の基準に従うべきものと解するのが相当である。ところで、近代企業にあっては、複雑な取引形態の下に多数の債権債務が同時に併存する実情にあるため、会計処理上、いわゆる現金主義によってはとうてい正確な損益を把握することができないから、これによることは適当でなく、いわゆる権利確定主義ないし権利発生主義によるのが公正妥当な会計処理の基準に従う所以であるというべきである。」(注1)
(注1) この判決に関しても、「公正妥当な会計処理の基準」に従えば「権利確定主義」や「権利発生主義」を採るということになるのか、また、そもそも「権利発生主義」というものが存在するのかなどという疑問があります。
また、昭和50年12月26日の鹿児島地方裁判所の判決においては、次のような解釈が示されています。
「資産の売買に関する収益の帰属すべき事業年度については、法人税法およびその関係法令上、直接には規定がないが、法人税法第22条第4項は損益の計算について一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うべき旨規定しているところ、企業利益計算上の会計慣行の準則である企業会計原則(経済安定本部企業会計制度調査会昭和24年7月、中間報告)は、損益の計算については原則としていわゆる発生主義によるべきとしつつも(同一A)、商品等の売上高についてはいわゆる実現主義の原則に従うべき旨規定している(同三B)こと、同条第3項第2号は損金の計算について、いわゆる権利確定主義を採用すべき旨規定していること、および法人税法の要請する課税の公平、明瞭、確実、普遍等の諸原則を勘案すると、原則として売買契約の効力の発生する日の属する事業年度の益金に算入すべきである(いわゆる権利発生主義)が、商品、製品等の販売にあたっては、引渡あるいは検収完了等、所得を生ずべき権利の所得実現の可能性が確実になったものと客観的に認められるに至った時期を含む事業年度の益金に算入すべきである(いわゆる権利確定主義)とするのが相当である(法人税法基本通達第249号参照)。」(注2)
(注2) この判決に関しても、① 法人税法22条3項2号(損金の額となる販管費)は、「いわゆる権利確定主義を採用すべき旨」を規定しているのではなく、債務の確定をもって費用を損金とする旨を規定しているということ、②「原則として売買契約の効力の発生する日の属する事業年度の益金に算入すべきである」とするものは、「権利発生主義」ではなく、「権利確定主義」とされるのが通例であるということ、そして、③「商品、製品等の販売にあたっては、引渡あるいは検収完了等、所得を生ずべき権利の所得実現の可能性が確実になったものと客観的に認められるに至った時期を含む事業年度の益金に算入すべきである」とするものは、「権利確定主義」ではなく、単に「引渡基準」と呼ばれるのが通例であるということ、この3点を指摘しておきます。
何故、昭和47年9月27日の東京地方裁判所の判決や昭和50年12月26日の鹿児島地方裁判所の判決が収益の計上時期に関して「権利確定主義」によるべきであるという解釈を示したのかというと、昭和50年12月26日の鹿児島地方裁判所の判決に「(法人税法基本通達第249号参照)」とあるように、法人税法22条2項が昭和40年に創設され、同条4項が昭和42年に創設された後、昭和44年に法人税基本通達が抜本改正されるまでの間、次の旧法人税基本通達249(売買損益の帰属の時期)がそのまま存置されていたためです。
- 「(売買損益の帰属の時期)
- 249 資産の売買による損益は、所有権移転登記の有無及び代金支払の済否を問わず売買契約の効力発生の日の属する事業年度の益金又は損金に算入する。但し、商品、製品等の販売については、商品、製品等の引渡の時を含む事業年度の益金又は損金に算入することができる。」
昭和40年には、法人税法22条2項が制定されていますので、同年から旧法人税基本通達249が廃止される昭和44年までの間、旧法人税基本通達249は、そもそも何れの条文の解釈を示しているのかということが明確ではなく、また、昭和44年の法人税基本通達の抜本改正において、旧法人税基本通達249と同じ内容の通達が制定されたわけでもありませんので、その解釈が適切であるのか否かということも明確ではありませんでした。
そして、旧法人税基本通達249における収益の計上時期に関する解釈の内容に着目すると、その解釈は、法人税法22条2項及び4項の規定の創設時に予定されていた解釈によってこれらの規定を解釈したものではなく、これらの規定の創設前の解釈によってこれらの規定を解釈したというものとなっていますので、これらの規定の解釈としては、妥当ではない、ということになります。
このような状態の下で、法人税法22条2項及び4項と旧法人税基本通達249とを適用する事件について、昭和47年9月27日の東京地方裁判所の判決や昭和50年12月26日の鹿児島地方裁判所の判決の解釈が示され、それらが同法22条2項の収益の計上時期に関する解釈とされて、平成5年最高裁判決においても、同旨の解釈が示される、ということになっているわけです。
このように、平成5年最高裁判決に示された収益の計上時期の解釈のルーツを探っていくと、法律のレベルでは、昭和40年と42年に新たに法人税法22条2項と4項の規定が制定されたにもかかわらず、通達レベルでは、昭和44年までこれらの規定の制定前の規定の解釈を示した旧法人税基本通達249がそのまま存置されており、昭和40年から44年までの4年間にわたって法律と通達が不整合であったという事実に行き着くこととなります。
2.旧法人税基本通達249の解釈
旧法人税基本通達249に示されていた解釈がどのように捉えられるものであったのかということに関しては、昭和39年1月20日付けの政府税制調査会の税法整備小委員会の「所得税法及び法人税法の整備に関する答申」の中で、次のように説明されています。
- 「4 所得の発生時期
- (3)法人税法基本通達「249」は、本文における権利確定主義のただし書として、商品、製品等の販売については引渡基準を認めている。」(16頁)
この説明から分かるとおり、「権利確定主義」とされているのは、旧法人税基本通達249の「本文」の「所有権移転登記の有無及び代金支払の済否を問わず売買契約の効力発生の日の属する事業年度の益金又は損金に算入する。」という部分であって、「但し、商品、製品等の販売については、商品、製品等の引渡の時を含む事業年度の益金又は損金に算入することができる。」という但し書きの部分は、「権利確定主義」を採ったものではなく、「引渡基準」を採ったものとされています。旧法人税基本通達249の但し書きの部分を「権利確定主義」と捉えているということであったとすればこのような説明とならないということは、改めて言うまでもないことです。
旧法人税基本通達249において用いられている「但し」という接続詞は、その前にあるものを否定する場合に用いられるものであって、仮に、「引渡基準」が「権利確定主義」に含まれるものと捉えられているということであれば、「但し」ではなく、「この場合において」等の文言を用いて「商品、製品等の販売」の収益の計上時期について「引渡の時を含む事業年度の益金又は損金に算入することができる。」等と定めることとしなければなりません。
要するに、旧法人税基本通達249に関しては、「資産」の売買による収益の計上時期について、原則として「権利確定主義」を採るとしながら、「商品、製品等」という棚卸資産の販売収益の計上時期については、「権利確定主義」は採らずに「引渡基準」を採るとしたものと捉えられていた、ということです。
上記1で確認した昭和47年9月27日の東京地方裁判所の判決の事件は「雑収入」の計上時期に関して争われたものですが、上記1で確認した昭和50年12月26日の鹿児島地方裁判所の判決の事件は、「PC矢板」等の製品(棚卸資産)の売上の計上時期に関して争われたものです。
このため、昭和50年12月26日の鹿児島地方裁判所の判決に関しては、「(法人税法基本通達第249号参照)」というように、旧法人税基本通達249を参照するように指示して判示した「商品、製品等の販売にあたっては、引渡あるいは検収完了等、所得を生ずべき権利の所得実現の可能性が確実になったものと客観的に認められるに至った時期を含む事業年度の益金に算入すべきである(いわゆる権利確定主義)とするのが相当である」という解釈は、旧法人税基本通達249(「法人税法基本通達第249号」の「法」と「号」は、不要です。)の但し書きの部分を「権利確定主義」と捉えているため、誤りであった、ということになります。
3.法人税法22条2項の収益の計上時期に関する部分の解釈
昭和40年に法人税法22条を創設した際に、同条2項に関しては、『昭和40年 改正税法のすべて』において、次のように、収益の額の内容と計上時期に関する説明が行われています。
「それから、「収益の額」という場合の収益の内容ですが、商品の販売の場合には売上高、役務の提供の場合には収入を意味するように利益とは異なりグロスの概念です。この収益という用語は会計上広く使われており、財務諸表規則その他の法令においても使用されているところですが、法人税法上は収入金額に近い意味において使われているものと考えられます。ただ、収入金額では評価益等が含まれないことになるので収益という言葉が用いられたのですが、資産の贈与により生ずる収益等が含まれている点で、企業会計上の用語としての収益とその範囲が若干異なることになります。
また、この項の規定は、益金の額の内容を規定するものであると同時に、いわゆる期間損益に関する事項を規定したものであります。この点は「当該事業年度の収益の額」というこの「の」によって表現されているのであって、「当該事業年度に帰属する収益の額」と解されます。
この点については、「当該事業年度において実現した収益の額」とするべきかどうかについて検討の行われたところでありますが、この実現という用語は主として企業会計の用語であって、この実現という用語の確定した内容というものも必ずしも統一的に解されているかどうかについて疑問があるのみならず、現在の税務慣行上の収益計上時期についての取り扱いがこの実現の内容にほぼ近いものと考えられるとしてもこれが一致するという保証がないため、実現という用語を用いることは避けられることとなったものです。なお、この収益の額をどのような基準によって当該事業年度に帰属させるべきか、あるいは如何なる表現によって具体的にその帰属関係を明らかにするかについては、なお今後の検討にゆだねられている事項と考えられます。」(103頁)
この説明から分かるとおり、収益の計上時期に関しては、「帰属」を示す「の」という用語を用いて「「帰属主義」とも言い得るもの」とすることとした、とされています。
(注3) 昭和40年当時に立法に携られた方々が執筆された『昭和40年 改正税法のすべて』などの解説書においては、法人税法22条2項の収益の計上時期に関し、「権利確定主義」や「実現主義」などのように、「・・・主義」という言い方をしたものは、見当たりません。
「主義」とは、「基本的な考え方」と言うべきものであり、それに対して、「基準」とは、「具体的な判断の拠り所」と言うべきものであって、「主義」と「基準」との関係は、「・・・主義」に基づき「・・・基準」がある、という関係となります。
この「主義」と「基準」の相違と関係を正しく理解していないために何を言おうとしているのかということが良く分からない判決文や解説が数多く見受けられます。
そして、この「「帰属主義」とも言い得るもの」は、企業会計における「実現主義」とは異なるため、法人税法22条2項において「実現」という用語を用いることは避けることとされたわけです(注4、5、6)。
(注4) 法人税法22条2項は、昭和39年11月18日の案までは、「権利確定主義」を採ることとして「当該事業年度において収入する権利が確定したもの」を計上すべきものとされていましたが、その後、昭和40年1月6日の案までは、「実現主義」を採ることとして「当該事業年度において実現した収益の額」を計上すべきものとされており、その後、「実現主義」は採らないこととして、「当該事業年度の収益の額」というように、「の」という文言を用いて、「帰属する」ものを計上することとすることで決着しています。
(注5) 大蔵省・国税庁の出身者の一部の方々の会であった「七夕会」で平成3年に作成された『税務同時代外史』においては、昭和40年の法人税法の制定に主導的に携わられた武田昌輔先生が次のように書かれています。
「実現の用語を用いることに対する反対の理由としては、実現という用語は、第一は、法令用語としては存しないので、この内容が法令上明らかでないこと、第二は、企業会計上の用語としては用いられているので、この用語を用いると、その解釈は企業会計が主導的役割を持つことになるという危惧があることなどであった。」(16・17頁)
要するに、企業会計に「主導的役割」を持たせることとしないために「実現主義」とはしなかった、ということであり、この記述は、法人税法の立法に携る者が法人税法と企業会計との関係をどのように考えているのかということを窺い知ることができるものとなっていますので、大変、興味深い、と感ずる方々も、多いのではないでしょうか。
筆者も、法人税法22条2項の立法に携わられた方々が本音を「外史」ではなく「正史」で書いておいてもらえれば、同項の収益の額の計上時期が「権利確定主義」によるものであるとか「実現主義」によるものであるなどという誤った解釈は出てこなかったはずであると感じています。
(注6) 『昭和40年 改正税法のすべて』の上記の引用部分の最後のなお書きである「この収益の額をどのような基準によって当該事業年度に帰属させるべきか、あるいは如何なる表現によって具体的にその帰属関係を明らかにするかについては、なお今後の検討にゆだねられている事項と考えられます。」という部分に関しては、法人税法における収益の計上時期について「権利確定主義」によるのか「実現主義」によるのかというような「主義」を今後の検討に委ねたものと解している向きがあります。
しかし、この部分は、その文言の中にあるとおり、「基準」や「如何なる表現によって具体的にその帰属関係を明らかにするか」ということを今後の検討に委ねたものであって、「主義」を今後の検討に委ねたものではありません。
この「基準」や「具体的」な「帰属関係」は、昭和44年に、法人税基本通達において、引渡基準等として明らかにされることとなります。
収益の額をどのような「基準」によって当該事業年度に帰属させるべきかということ等に関しては、法律の条文に記載するべきことではなく、法律の条文の解釈で対応するべきことと整理されていますので、上記の引用部分の最後のなお書きにおいて、「今後の検討」に委ねることとしたとされていますが、法人税法22条2項の立法過程において大蔵省主税局の法人税法の改正の担当部署が作成した資料(昭和39年11月18日に大蔵省主税局税制第1課が作成した「収益計上の時期」等)や同項の企画立案及び条文案の作成を行った大蔵省主税局の職員の昭和40年当時の解説を確認してみると、「商品」や「製品」の販売収益の計上時期に関しては、一貫して引渡基準を採ることとされていたことが分かります。そして、後に第3回の5において確認するとおり、その解釈がそのまま昭和44年に制定された旧法人税基本通達2-1-1(たな卸資産の販売による収益の帰属の時期)に引き継がれています(注7)。
(注7) 「権利確定主義」は、「権利」が「確定した時」に収益の額を計上するべきであるとする「主義」ですから、契約の効力が発生したと法的に判断できるようになった日に収益を計上させるという「基準」(「契約効力発生基準」と呼ぶべきでしょう。)と最も整合性があり、「実現主義」は、商品等の販売又は役務の給付によって実現した売上高を計上するべきであるとする「主義」ですから、商品等の引渡しを行ったという事実があった日に収益を計上させるという「基準」である引渡基準と整合性があると言ってよいでしょう。
上記の「「帰属主義」とも言い得るもの」は、「帰属する」という用語が法令用語として用いられる場合の意味から推測すると商品等の移転の効果が発生した時に収益を計上させるという「主義」と解することができるものであり、法人税法11条(実質所得者課税の原則)において用いられている「収益の法律上帰属する」という文言から「法律上」という用語を取った「収益の帰属する」という文言で収益の額の計上時期を判断する「主義」と言ってもよいものです。
このため、その「基準」がどのようなものとなるのかということになると、法律上、商品等の移転の効果が発生するのか否かということは別にして、事実上、商品等の移転の効果が発生すると考えてよい引渡しの時を判断の拠り所とするものと最も整合性があると捉えてよいはずですから、引渡基準となると判断してよいと考えられます。
なお、『昭和40年 改正税法のすべて』においては、収益の額の計算をどのように行うのかということに関して、何も言及されていない、ということを確認しておきます。
この連載の記事
-
2021.04.19
第5回(最終回) 法人税法22条の2第1項及び第2項の検証
-
2021.04.12
第4回 法人税法22条の2第1項及び第2項の検証
-
2021.04.05
第3回 平成5年最高裁判決の解釈の検証(その2)
-
2021.03.29
第2回 平成5年最高裁判決の解釈の検証(その1)
-
2021.03.22
第1回 昭和61年神戸地裁判決・平成3年大阪高裁判決・平成5年最高裁判決の解釈の確認
テーマ
プロフィール

免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。