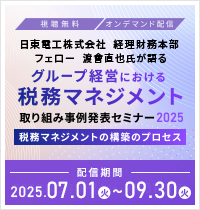更新日 2021.07.26

株式会社TKC 顧問
税理士 朝長 英樹
令和3年度税制改正により、株式交付の取扱いに関する税制措置が設けられました。
株式交付の法制度は、かなり柔軟な制度となっており、また、株式交付の税制も、緩やかなものとなっています。このため、株式交付は、今後、多くの場面で使われるようになる可能性が高いと考えられます。しかし、株式交付の税制には、株式交付が「現物出資の一種」であるのか否かという疑問があったり、法人税法132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)が適用されるのか否かという疑問があります。
本コラムにおいては、株式交付の法制と税制の概要を確認するとともに、このような疑問について見解を述べることとします。
1.株式交付税制の趣旨目的
株式交付税制は、他の組織再編成税制とは異なり、理論の法である法人税法ではなく、政策の法である租税特別措置法に定められており、その趣旨目的は、第1回の2で確認したとおり、「株式対価M&Aを促進するため」と説明されています。
このため、租税特別措置法66条の2の2に定められている株式交付税制の趣旨目的を「株式対価M&Aを促進するため」と捉えるべきことに何ら疑問はありません。
しかし、租税特別措置法66条の2の2の趣旨目的をこのように捉えるだけで済むのかという点には、やや疑問なしとしません。
「株式対価M&Aを促進するため」に株式交付税制が創設されたということであれば、株式交付税制は、迷うことなく、政策の法である租税特別措置法に定められることとなりますが、株式交付税制に関しては、株式という個別の資産を譲渡するものであり(注4)、しかも、株式交付子会社となる法人の株主のうちの株式譲渡に応ずる者のみを対象とするものであるため、法人税法に定めることができなかったとも聞くところです。
(注4)組織再編成税制は、平成13年度税制改正によって創設された当時は、資産を単独で移転する組織再編成は単なる資産の譲渡に過ぎないことから、そのようなものを適格組織再編成とすることは予定されておらず、「事業」や「業務」などと言い得るものを移転する組織再編成を適格組織再編成とすることが予定されていました。
しかし、その後、平成22年度税制改正において、残余財産の分配が「適格現物分配」とされたり、「事業を移転しない適格分割」等に関する取扱いが定められたりしていますので、同改正以後は、組織再編成税制が「事業」や「業務」などが移転するものだけに移転資産の譲渡損益の計上の繰延べ等を認めて従前の課税関係を引き継がせるという趣旨目的のものであるのか否かということについて、改めて整理しなければならない状況となっています。
仮に、このような理由で株式交付税制が法人税法ではなく租税特別措置法に定められたということであったとしたら、株式交付税制の趣旨目的を「株式対価M&Aを促進するため」とだけ捉えることが正しいのかという疑問が湧いてこざるを得ません。
税法の条文の改正や創設を行った場合には、その趣旨目的が何かということは、まず初めに説明しなければならない非常に重要なことです。条文の解釈は、その条文の趣旨目的を踏まえて解釈しなければなりませんし、その条文の趣旨目的がどのようなものであるのかということによって租税回避となるのか否かという判断が変わることともなります。
租税特別措置法66条の2の2に関しても、その趣旨目的が何かということは非常に重要であるわけですが、6月末の時点では、未だ、同条の文言の解釈や租税回避の判断などに用いることができる程、明確になっているとは言えないと考えられます。
今後、租税特別措置法66条の2の2の趣旨目的が何であったのかということについて、詳しく説明が行われることを期待したいと思います。
また、租税特別措置法66条の2の2自体の趣旨目的ということではありませんが、20%以下という制限があるとはいえ、金銭等の交付をするものにまで株式の譲渡損益の計上の繰延べを認めることとした趣旨目的は何かということについても、明確な説明が求められます。
他の組織再編成においては、わずかでも金銭等の交付をすれば、資産の譲渡損益の計上の繰延べは認めないこととされていますので、株式交付においてのみ、何故、金銭等の交付をするものについて株式の譲渡損益の計上を繰り延べるのか、また、何故、20%以下としたのかということを明確に説明する必要があります。株式交付子会社の株主は、株式の譲渡損益の計上が繰り延べられれば、既存の株式が株式交付親会社の株式に置き換わるだけであり、その取引は、当然、等価交換となっているはずですから、金銭等を交付されれば株式交付親会社の株式の価値がその金銭等の額に相当する金額だけ下がるだけであって、論理的に考えると、金銭等を交付されることが「株式対価M&Aを促進するため」ということにはならないはずです。また、株式の譲渡損益の計上を繰り延べるということであれば、株式交付子会社の株式に含み益があったとしても納税が必要となることはありませんので、株主において納税資金が必要となることを考慮したために金銭等の交付をするものについても譲渡損益の計上を繰り延べることとしたということも、論理的に考えて、あり得ないはずです。
このように、これまで公表されているものを手掛かりにして、何故、20%以下の金銭等の交付をするものについてまで株式の譲渡損益の計上を繰り延べるのかということを考えてみても、答えが分かりません。
何故、今回、20%以下の金銭等の交付をするものについて譲渡損益の計上を繰り延べるという制度を創ったのかということについて、誰もが納得できる論理的な説明が早急になされることを期待したいと思います。
2.株式交付の取扱いの原則
株式交付税制における株式交付子会社の株主の株式の譲渡損益の取扱いは、合併税制等の組織再編成税制における株主の株式の譲渡損益の取扱いとは異なり、法人税法ではなく、租税特別措置法に定められていますので、原則は法人税法に定められて特例が租税特別措置法に定められているということになります。
租税特別措置法66条の2の2に定められている特例は、第1回の2において確認したとおりですが、株式交付の取扱いの原則は、どのようなものとなっているのでしょうか。
租税特別措置法66条の2の2第1項においては、「法人税法第61条の2第1項の規定の適用については、…とする。」と定められていますので、法人税法61条の2第1項の取扱いが株式交付の取扱いの原則となっていることは、明確です。
第1回の1で述べたとおり、会社法においては、株式交付は、株式の「譲渡」と位置付けられており、法人税法においても、株式交付を株式の「譲渡」ではないとすべき特段の事情は存在しないと考えられますので、法人税法61条の2が株式交付の取扱いの原則を定める規定となっているということには、何の疑問もないと考えられます。
しかし、株式の「譲渡」に適用される法人税法の条文は、同法61条の2だけではありませんので、株式交付が株式の「譲渡」(注5)に含まれるとしても、株式交付がどのような内容の「譲渡」に該当するのかということは、明確にしておく必要があります。
(注5)法人税法における「譲渡」は、被合併法人の株主が保有する株式が合併によって消滅すること、現物出資法人が資産を出資することなどまで含むものであり、その範囲は、非常に広くなっています。
この点に関して、株式交付は「現物出資の一種である」という説明がなされているとも聞くところです。
株式交付が通常の株式の譲渡であっても株式の現物出資であっても、法人税法61条の2が適用されることに変わりはありませんが、法人税法の他の条文は、株式交付が通常の株式の譲渡であるのかあるいは株式の現物出資であるのかということによって、適用の有無や取扱いが変わってきます。例えば、法人税法132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)の適用があるのか否かの判断が変わるなど、実務にも大きな影響を与えることとなるわけです。
このため、株式交付が通常の株式の譲渡であるのかあるいは株式の現物出資であるのかということは、非常に重要となってきます。
租税特別措置法66条の2の2第1項においては、「他の法人を会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付子会社とする株式交付により」、「株式交付親会社(同号〔引用者注:会社法774条の3第1項1号〕に規定する株式交付親会社をいう。…)」とされていますので、租税特別措置法66条の2の2第1項が適用される株式交付は、会社法において株式交付とされたものに限られます。法人税法においては、合併等の組織再編成は、特に会社法等の条文を引用して定めることとはされていませんので、会社法等において合併等となるものであっても、法人税法においては合併等とはならないと判断したり、会社法等において合併等とならないものであっても、法人税法においては合併等となると判断したりすることがあるわけです。しかし、租税特別措置法上の株式交付は、法人税法上の合併等とは異なり、会社法上の株式交付と同じであって、会社法上で株式交付とならないものは租税特別措置法上も株式交付とならず、会社法上で株式交付となるものは租税特別措置法上も株式交付となる、ということになります。
そうすると、会社法において、株式交付が「現物出資」とされているのか否かということが問題となるわけですが、既に述べたとおり、会社法においては、株式交付は「現物出資」とはされていません。株式交付には「現物出資のような規制はない」という説明をしているものが見受けられますが、株式交付に「現物出資のような規制」があるのか否かという以前に、そもそも、株式交付には、現物出資について定めた会社法207条(金銭以外の財産の出資)等は適用されませんので、会社法においては、株式交付と現物出資が別のものであることは明らかであって、株式交付が「現物出資の一種」であるなどということは、あり得ません。
株式交付が「現物出資の一種」であると言い得る可能性があるとすれば、それは、租税特別措置法66条の2の2とは別に、法人税法において「株式交付」が会社法の規定を引用せずに用いられている場面ということになります。
そのような場面で、個別事案ごとに株式交付が現物出資であると事実認定をするのではなく、法人税の解釈において一般的に株式交付を現物出資とするということであれば、法人税法においては、株式交付を現物出資と捉える理由があるということを明確に説明しなければなりません。
仮に、法人税の解釈において、株式交付を現物出資とする理由があると主張するとすれば、その理由として挙げることとなるのは、「給付」と「交付」という用語が現物出資にも株式交付にも用いられているということになると考えられます。会社法においては、現物出資について、同法34条(出資の履行)1項において「その出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない」とされていたり、同法207条(金銭以外の財産の出資)8項において「現物出資財産を給付する」とされていたりするとともに、株式交付についても、同法774条の7(株式交付子会社の株式の譲渡し)2項において「株式交付子会社の株式を株式交付親会社に給付しなければならない」とされているという状態にあり、また、「株式を交付する」という文言も、各所で用いられています。このように、株式交付と現物出資は、株式の「給付」を行い、株式の「交付」を受けるという点では、共通性があります。
このため、法人税法の解釈において、株式の「給付」と株式の「交付」が行われるものは現物出資であると言い得るのであれば、株式交付は「現物出資の一種」と言い得るということになります。
しかし、「給付」とは「債権の目的たる債務者の行為(作為又は不作為)をいう。給付の内容は、金銭その他の物の交付である場合もあれば、療養の給付のように、役務の提供である場合もある。」(法令用語辞典(学陽書房))とされており、「交付」とは「物を他人に渡すこと、すなわち物の所持を他人に移転することをいう。」(同前)とされており、法人税法においても、現物出資に限って「給付」や「交付」という用語が用いられると解釈されているわけではありません。
このような事情にあることからすると、会社法では株式交付は「現物出資の一種」ではないが法人税法では株式交付は「現物出資の一種」であると主張することも、明らかに困難ということになります(注6)。
(注6)租税特別措置法66条の2の2第1項においては、第1回の2のⅴ、ⅶ及びⅷに記載したとおり、株式交付割合等を計算する場合には、株主に交付した金銭等の額から「剰余金の配当等として交付された金額」を除くこととされていますが、この「剰余金の配当等として交付された金額」がある場合には、法人税法においても、それを「剰余金の配当等」として取り扱うことになるものと考えられます。
しかし、第1回の2のⅱとⅲに記載したとおり、いわゆる8割要件の割合を計算する場合には、株主に交付した金銭等の額から「剰余金の配当等として交付された金額」を除くこととはされていません。
これは、8割要件について、税制の観点から「剰余金の配当等」があると認定して当事者が合意した株式の交付の割合を再計算して判定をするのではなく、その合意した株式の交付の割合に基づいて判定をすることとしたものではないかと推測されます。
しかし、租税特別措置法66条の2の2の条文のみからは、そのように規定した確たる理由が分かりませんので、同条の企画立案者はその理由を明確に説明する必要があると考えられます。
そうすると、必然的に、株式交付に適用される法人税法の規定は、「現物出資」に関する規定ではなく、現物出資に該当しない「譲渡」に関する規定であるという結論となります(注7)。
(注7)株式交付よりも分社型分割の方がその内容等から判断すると現物出資に近いと考えられるため、仮に、法人税法において株式交付が「現物出資の一種」ということになるとすれば、分社型分割も「現物出資の一種」ということになって、分社型分割にも現物出資の規定が適用されるということになるかもしれません。
株式交付が「現物出資の一種」であるのか否かということは、法人税法における「株式交付」と「現物出資」という用語の解釈の問題ですから、最終的には司法判断によって決着がつけられることとなります。
この連載の記事
-
2021.08.02
第3回(最終回) 株式交付税制の検証-適用される法人税法の規定-
-
2021.07.26
第2回 株式交付税制の検証-趣旨目的と取扱いの原則-
-
2021.07.19
第1回 株式交付制度と株式交付税制の概要の確認
テーマ
プロフィール

免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。