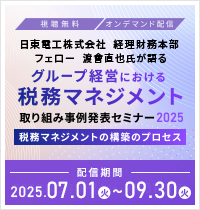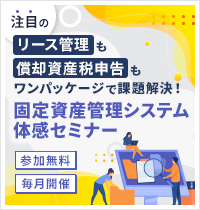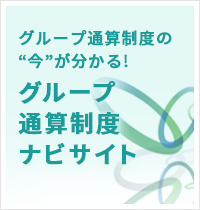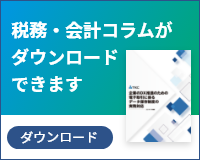更新日 2025.07.14

株式会社TKC 顧問
税理士 朝長 英樹
ポイントの利用が大きく広がり、ポイントを貯めたり活用したりする“ポイ活”も話題になっている中で、最近、ポイントの所得税や法人税の取扱いについて質問を受けることも増えてきました。
そこで、本コラム欄で既に説明したポイントの消費税の取扱いに加え、今回、ポイントの所得税及び法人税の取扱いについて説明します。
当コラムのポイント
- 消費者は、ポイントを使用した場合、それが自社ポイントと共通ポイントのいずれであっても、全く同様に、「値引き」を受けた場合と同じ「経済的利益」を得る
- ポイントを使用した個人及び法人は、それが自社ポイントと共通ポイントのいずれであっても、「事実」に基づき、所得税法及び法人税法上も、「値引き」を受けたとされる
- レシートや領収書がポイントの使用によって「値引き」が行われたことを適切に表示していない場合には、「値引き」が行われなかったという本末転倒の処理をするのではなく、レシートや領収書の表示を適切に訂正することを考えるべきである
- 目次
-
1.ポイントの所得税の取扱い
1においては、個人がポイントを取得して使用した場合のその個人の所得税の取扱いを中心に説明を行います。
この説明は、国税庁がタックスアンサーで公表している「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」(以下「No.1907」といいます。)の内容を確認して行うこととします。
1においては、所得税の取扱いを説明することになりますので、説明を分かり易くするために、取引の相手方のお店も個人商店であるものとします。
(1) 国税庁のタックスアンサー
No.1907の「問」と「答」は、次のとおりです。
問
私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。
その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得または使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。
答
原則として、確定申告をする必要はありません。
(説明)
1 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
2 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
(注) ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
No.1907のタイトルには「個人」という用語を用いていますが、この「個人」について、「答」では「消費者」としていますので、以下の説明においても、「消費者」という用語を用いることとします。
また、消費者とお店との間では、商品の取引だけでなく、役務の取引も行われることがありますが、ポイントを用いた取引の取扱いが変わるわけではありませんので、以下、消費者とお店との間では、役務の取引に言及する場合を除き、商品の取引が行われるものとして説明を行います。
(2) 国税庁のタックスアンサーから確認できること
① 消費者が「値引き」をしてもらって得た「経済的利益」は、課税対象となる「経済的利益」とはならない
No.1907の「答」の「(説明)」の「1」を見てみると、そこでは、通常の商取引における「値引き」をしてもらって消費者が得た経済的利益について、「原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています」(注1)と書かれています。
(注1) No.1907の「答」とその「(説明)」の「1」においては、それぞれ1カ所で「原則として」という文言が用いられていますが、「原則として」という文言を用いているのは、「答」の「(説明)」の「2」の「(注)」で述べられているように、一時所得として課税対象となることがあるためであると考えられます。
この「答」の「(説明)」の「1」に書かれていることに関しては、「値引き」に「経済的利益」がないとされているのではなく、「値引き」には「経済的利益」があるものの、その「経済的利益」は「課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています」とされていることに留意する必要があります。
所得税法においては、「得をした」というだけで常に課税されるということにはなっていません。
商品を購入して「値引き」をしてもらった消費者は、「値引き」をしてもらったことで得た「経済的利益」に課税されることはありません。
「値引き」をしてもらったことによる「経済的利益」が課税対象とならないのは、「値引き」が取引価格の調整であって支払金額を少なくするものでしかないからです。
この「値引き」が取引価格の調整であるというのは、「値引き」をした者においても、同様であり、「値引き」をした者においては、「値引き」は受取金額を少なくするものでしかありません。
このように、「値引き」をしてもらった消費者と「値引き」をした者において、「値引き」を取引価格の調整と捉えるのは、通常の商取引において「値引き」が取引価格を調整するものとなっているという「事実」があるためです。
② 消費者が「値引き」をしてもらって得た「経済的利益」がレシートや領収書の書かれ方の違いによって課税対象となる「経済的利益」であるのか否かの判断が変わることはない
No.1907の「答」の「(説明)」の「1」には、レシートや領収書に言及したところは、全くありません。
これは、消費者が商品を購入し、「値引き」をしてもらい、「値引き」後の代金を支払ってその代金が記載されているレシートや領収書を受け取ったという場合に、そのレシートや領収書に、「値引き」の記載があるのか否か、「値引き」の記載があるときにその記載がどのような記載となっているのかなどにより、「値引き」が行われなかったことになるということが無いからです。
つまり、消費者が「値引き」をしてもらって得た「経済的利益」がレシートや領収書の書かれ方の違いによって課税対象となる「経済的利益」であるのか否かの判断が変わることはないということです。
③ 消費者はポイントを使用することで「経済的利益」を得るという「事実」があることを踏まえて、課税関係を判断する必要がある
「答」の「(説明)」の「2」をより正確に補って書いてみると、次のようになります(下線を付したところが補足箇所です。)。
2 (一般的に)(注2) 企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを取得した消費者がそのポイントを商品の購入の決済代金の支払いに使用した場合には、そのポイントを使用した消費者にとっては、その商品の購入において、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用によって消費者が得た経済的利益については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
(注2) 「答」の「(説明)」の「2」は、「一般的に」という文言から始まっていますが、冒頭にこの文言を用いた理由は、明らかにされておらず、「一般的」と言い得ないものがあった場合に異なる判断がされることがあることを担保する趣旨の一種の保険のように見受けられます。
この記述から、消費者がポイントを商品の購入代金の支払いに使用した場合には、その消費者がポイントを使用することで「経済的利益」を得るという事実が判断の前提になっていることが明確に分かります。
このように、ポイントを使用した消費者が「経済的利益」を得ることは、上記①で確認した「値引き」と同様に、「事実」であって、税法の定め方等によって変わるものではありません。
このため、所得税法、法人税法、消費税法などにおいて、消費者がポイントを使用した場合の取扱いを判断する場合、その判断の前提となる「事実」として、その消費者がポイントを使用することで「経済的利益」を得ているということを常に考慮しておくことが必要となります。
④ 消費者がポイントを使用することで得た「経済的利益」は、消費者が「値引き」を受けたことで得た「経済的利益」と同様のものであるため、課税対象となる「経済的利益」に該当しない
「答」の「(説明)」の「2」は、その全体が「一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、・・・と考えられますので、・・・課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています」となっています。
このため、消費者がポイントを使用することで得た「経済的利益」は、消費者が「値引き」を受けたことで得た「経済的利益」と同様のものであって、課税対象となる「経済的利益」に該当せず、確定申告は不要ということになります。
「答」の「(説明)」の「2」においては、消費者がポイントを使用した取引について、「通常の商取引における値引きと同様の行為が行われた」としていますので、No.1907は、消費者がポイントを使用した取引において、「値引き」が行われた取引と同様に、取引価格を下げる調整が行われて、商品の取引価格がポイントの使用後の金額に下がったという「事実」があると捉えていることになります。
⑤ ポイントの「取得または使用」の意味
「答」の「(説明)」の「2」においては、「ポイントの取得または使用」について、「課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています」とされています。
これは、消費者がポイントを使用することは、消費者が「値引き」をしてもらうことであると事実認定をすることができるため、所得税における「値引き」の取扱いどおりに、課税対象となる「経済的利益」はないものとして取り扱うということです。
ただし、この記述に関しては、「取得または使用」をどのように解するのかという問題があります。この問題は、No.1907のタイトルにある「取得又は使用した」をどのように解するのかという問題でもあります。
タックスアンサーの「答」も、法令の条文の解釈に基づくものでなければなりませんので、基本的には、そこで用いられている用語も、法令用語を念頭に置いたものとなっているはずです。法令用語における「又は」は、通常、or という意味で用いられますが、andという意味で用いられることもあります。このため、「取得または使用」は、「取得」or「使用」と解釈されるのが通例ですが、「取得」and「使用」と解釈すべき場合もあります。
これを踏まえて「答」の中の「取得または使用」を見てみると、「答」の中には、ポイントを取得する取引に関して「値引き」が行われたとする記述がありませんので、この「取得または使用」は、「取得」or「使用」と通例どおりに解するのではなく、「取得」and「使用」と解するべきであると考えられます。
しかし、そうすると、何故、「及び」という用語を用いて「取得及び使用」としなかったのかという疑問が湧いてくることになります。
もちろん、それには理由があると考えられます。
その理由は何かというと、後に⑦で述べるように、一部、ポイントがどのようにして取得されたかにかかわらず、ポイントの使用の場面だけを見て課税関係を決めているところがあるためであると考えられます。
このように、「答」がポイントの「取得」という場面とポイントの「使用」という場面の関係をどのように捉えているのかということは、「答」に書かれていることを正確に理解する上で重要となるものであり、後に(3) ②等において述べること(ポイントの取得から使用までの全体の「事実」を一連のものと捉えて課税関係を判断しているということ)とも繋がる非常に大事なことです。
もっとも、筆者は、ポイントにはキャッシュバックがあり得るという点からも、「取得又は使用した」ではなく、「取得し又は使用した」(注3)という文言とするのが適切であると考えています。
(注3) No.1907では「取得又は使用した」と表題で用いていますが、法令においては、「取得」と「使用」を動詞として見出しで用いているものはなく、これらが動詞として用いられるのは全て条文の文言中となっており、全て「、」を間に入れて「取得し、又は使用する」となっています。
なお、「答」の「(説明)」の「2」の「取得または使用」は、本来は、表題と同じく「又は」を用いて「取得又は使用」とするべきであるということも、蛇足ながら付言しておきます。
キャッシュバックをしたポイントについては、その後の取引において、ポイントを使用することがないため、キャッシュバックをその後の取引における「値引き」と捉えることはできません。
ポイントのキャッシュバックは、ポイントを取得した取引の「対価の返還」と捉えるしかなく、それが実態であり、事実でもあると考えられます。
一部には、「値引き」と「対価の返還」を同視した説明も見受けられますが、キャッシュバックの例に目を向けると、「値引き」と「対価の返還」の違うところが明確に確認できるはずです。
⑥ ポイントの使用で一時所得が発生するとされることがある
「答」の「(説明)」の「2」の「(注)」においては、「ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイント」については、「値引き」と同様の行為が行われたものとは考えられないとして、「そのポイントを使用した場合」に、「その使用したポイント相当額」が一時所得となるとされています。
これは、消費者がポイントを使用して得た「経済的利益」が「臨時・偶発的」に得た「経済的利益」であって「通常の商取引」において得た「経済的利益」ではないと判断しているためです。
このような判断と消費者がポイントを使用して得た経済的利益を一時所得とする取扱いは、所得税法34条(一時所得)1項に規定する「一時の所得」という一時所得の定義に合致するものであり、適切であると評価されるものと考えられます。
しかし、一時所得には、50万円の特別控除がありますので、一時所得があるとされた場合でも、実際に一時所得として課税されるケースは、あまりないかもしれません。
ただ、実務において、消費者が使用したポイントが商品を購入したり役務の提供を受けたりするなどの通常の商取引によって取得したものであるのか、あるいは、ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したものであるのかということを正しく判別することができるのかという点は、気になるところです。
もっとも、このようにして臨時・偶発的に取得したポイントを使用したものについて、そのポイント使用額相当額を「値引き」としたとしても、それによって減少する税額は、次の⑦で確認する二つの取扱いによって変動する税額よりもかなり少額に止まるはずです。
⑦ 「参考」の本文と注記には、「答」に書かれていることと異なる二つの取扱いが書かれている
No.1907の「参考」には、次のように記述されています。
参考
ポイントの使用に関する課税関係は上記のとおりですが、ポイントを使用して医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合など、所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合には、
1 ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法
2 ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法
のいずれかの方法により、所得金額および所得控除額を計算してください。
(注) 証券会社等においてポイントを使用して株式等を購入した場合、一般的には、その株式等の取得価額(取得費等)はポイント使用前の支払金額(ポイント使用相当額を含めた支払金額)を基に計算するとともに、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。
No.1907に書かれていることを「問」「答」「参考」という順番で読まれた方は、「参考」に書かれていることが「答」に書かれていることと整合しないと感じられるものと思われます。
所得控除に関して所得金額と所得控除額を「1」と「2」のいずれかの方法によって計算してよいという、「参考」に書かれている取扱いは、「答」に書かれていることからすると、本来は、そのような取扱いとはならず、消費者が使用したポイントが商品の購入によって取得したものであった場合には「1」の方法によらなければならず、消費者が使用したポイントがポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したものであった場合には「2」の方法によらなければならないというものとなるはずです。
そして、「参考」の「(注)」に書かれていることも、「答」に書かれていることからすると、本来は、このような取扱いとはならないはずです。
このような事情にあることからすると、「参考」として本文と注記に書かれている二つの取扱いは、消費者に配慮した個別の場面の取扱いと捉える必要があると考えられます。
⑧ 消費者がポイントを使用して得た「経済的利益」がレシートや領収書の書かれ方の違いによって「値引き」を受けたことで得た「経済的利益」であるのか否かの判断が変わることはない
No.1907の「答」の「(説明)」の「1」と同様に、同「2」及びその「(注)」のいずれにも、レシートや領収書に言及したところは、全くありません。
そして、ポイントを使用した取引の所得控除について、二つの方法の選択を認めるとしている「参考」にも、レシートや領収書に言及したところは、全くありません。
これは、消費者が商品を購入し、ポイントを使用して支払代金を少なくし、その代金を支払ってその代金が記載されているレシートや領収書を受け取ったという場合に、そのレシートや領収書に、「値引き」の記載があるのか否か、「値引き」の記載があるときにその記載がどのような記載となっているのかなどにより、「値引き」が行われなかったことになるということが無いからです。
つまり、消費者がポイントを使用して得た「経済的利益」がレシートや領収書の書かれ方の違いによって「値引き」を受けたことで得た「経済的利益」であるのか否かの判断が変わることはないということです。
消費者がポイントを使用して商品を購入した場合に、消費者が使用ポイント相当額の「値引き」を受けているということは、「事実」に他なりませんので、「答」の「(説明)」の「2」及びその「(注)」並びに「参考」のいずれにも、レシートや領収書に言及したところが無いのは、当然のことです。
この連載の記事
テーマ
プロフィール

免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。