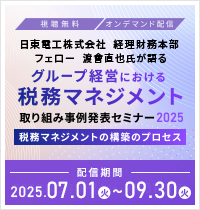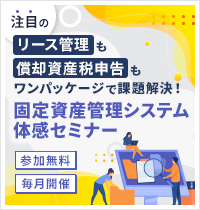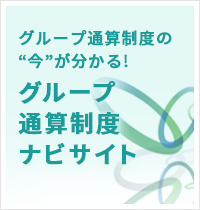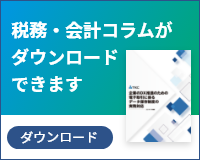更新日 2025.07.14

株式会社TKC 顧問
税理士 朝長 英樹
ポイントの利用が大きく広がり、ポイントを貯めたり活用したりする“ポイ活”も話題になっている中で、最近、ポイントの所得税や法人税の取扱いについて質問を受けることも増えてきました。
そこで、本コラム欄で既に説明したポイントの消費税の取扱いに加え、今回、ポイントの所得税及び法人税の取扱いについて説明します。
当コラムのポイント
- 消費者は、ポイントを使用した場合、それが自社ポイントと共通ポイントのいずれであっても、全く同様に、「値引き」を受けた場合と同じ「経済的利益」を得る
- ポイントを使用した個人及び法人は、それが自社ポイントと共通ポイントのいずれであっても、「事実」に基づき、所得税法及び法人税法上も、「値引き」を受けたとされる
- レシートや領収書がポイントの使用によって「値引き」が行われたことを適切に表示していない場合には、「値引き」が行われなかったという本末転倒の処理をするのではなく、レシートや領収書の表示を適切に訂正することを考えるべきである
- 目次
-
1.ポイントの所得税の取扱い
(3) 国税庁のタックスアンサーの理解を深めて分かること
① 国税庁のタックスアンサーに示されているように、ポイントを使用することが「値引き」をしてもらうことと同じであることは、商品券を使用した取引とポイントを使用した取引を対比してみると、より一層、明確に分かる
上記(2)においては、国税庁のタックスアンサーであるNo.1907において、消費者がポイントを使用することで得た「経済的利益」が消費者が「値引き」で得た「経済的利益」と同じものであるとされていることを確認しましたが、これは、ポイントに係る所得税の取扱いを考えるうえで、最も重要なことですから、ここで改めて確認をしておきます。
例えば、消費者が同じ金額に換算される商品券とポイントを持っていたとして、その消費者が商品券を使用して商品を購入したとすれば、現金の支払い額は、商品券の額面金額を超える部分の金額のみとなり、ポイントを使用して商品を購入したときの現金の支払い額と同額となりますが、その消費者は、商品券を取得する際に、商品券の額面金額に相当する対価を支払って取得しています。
このため、商品券は現金に替わる支払手段として用いられるもの(注4)でしかなく、その消費者は、商品券を使用して商品を購入しても、何ら「経済的利益」は得ていません。
(注4) 例えば、楽天キャッシュは、現金をチャージして利用することができますので、商品券と同じように支払手段として用いられるものということになりますが、楽天ポイントは、現金をチャージして利用することはできません。
本コラムで「ポイント」と言っているものは、楽天キャッシュのように支払手段となっているものではなく、楽天ポイントのように支払手段とはなっていないものですから、両者を混同しないように注意してください。
これに対し、その消費者は、ポイントについては、商品券と異なり、その取得の際に対価を支払って取得しているわけではありませんので、その消費者は、ポイントを使用して行った商品の購入において、その使用したポイント相当額の現金を支払わなくて済んだ分だけ、「経済的利益」を得ています。
この「経済的利益」がどのようなものであるかということを考えてみると、それは、現金で商品を購入した場合に、その商品の価格について、一部を支払わなくてもよいとされたことで得られた「経済的利益」であって、「値引き」をしてもらったことで得られた「経済的利益」と何ら異なるものではありません。
このように、ポイントを使用した取引と商品券を使用した取引を対比してみると、商品券を使用した取引においては消費者が何ら「経済的利益」を得ることがない一方、ポイントを使用した取引においては消費者が「値引き」をしてもらった場合と同様の「経済的利益」を得ることとなることから、ポイントを使用することが「値引き」をしてもらうことと同じであることがより一層明確に分かってきます。
現に、消費者が商品券を使用して商品を購入する場面と消費者がポイントを使用して商品を購入する場面を想定し、消費者が商品券を使用することとポイントを使用することについてどのように考えているのかということを推測してみると、前者においては、商品券は現金に代わるものであるため「現金を支払わなくて済む」と考えており、後者においては、ポイント相当額の現金を支払うことがありませんので「ポイントを使えば安くなる」と考えているものと思われます。
これは、消費者がポイントを使用することが「値引き」をしてもらうことに他ならないことを意味するものです(注5)。
(注5) 本コラムは、ポイント制度を定義することを目的とするものではありませんが、ポイント制度は、消費者に「値引き」と同じ効果をもたらすものであって、制度として「値引き」の機能を果たしているものですから、敢えて言うならば、「ポイント制度は「値引き」を制度化したものである」と言ってもよいと思われます。
ただし、注意を要するのは、ポイントを使用することが「値引き」をしてもらうことになるとはいっても、それは、「値引き」を勘定科目として計上しなければならないということを意味するわけではないということです。
現金値引きにおいて「値引き」という勘定科目を計上しないことからも明らかなように、ポイントを使用して「値引き」をしてもらっても、「値引き」という勘定科目を計上することはありません。ポイントの使用に関して「値引き」を仕訳で示すことがあっても、それは、説明の便宜のためにそうしているわけであって、実際の処理において、勘定科目として「値引き」を計上しなければならないということではありません。
② ポイントの取得から使用までの全体の「事実」を一連のものとして捉えて課税関係を判断する必要がある
「答」の「(説明)」の「2」においては、消費者がポイントを使用する取引において「値引き」と同様の行為が行われたものと考えられるとされていますが、これは、消費者がポイントを取得する取引から消費者がポイントを使用する取引までの全体の「事実」を一連のものとして捉えてそれを「通常の商取引」と見て下した判断ということになります。
そして、「答」の「(説明)」の「2」の「(注)」においては、消費者がポイントを使用する取引において一時所得が発生するとされており、結論こそ、「答」の「(説明)」の「2」とは違っていますが、消費者がポイントを取得する取引だけを捉えて事実認定を行ったり、消費者がポイントを使用する取引だけを捉えて事実認定を行ったりしているわけではなく、消費者がポイントを取得する取引から消費者がポイントを使用する取引までの全体の事実関係を一連のものとして捉えて判断を下していることに、何ら変わりはありません(注6)。
(注6) 「答」の「(説明)」の「2」の結論と「答」の「(説明)」の「2」の「(注)」の結論が違うのは、消費者がポイントを取得する取引から消費者がポイントを使用する取引までの全体の「事実」を一連のものとして捉えると、前者においては、「通常の商取引」が行われたと見られるのに対し、後者においては、消費者がポイントを取得する際に商品を購入する等の取引が行われていないため、「通常の商取引」が行われたとは見られず、「臨時・偶発的」なことが起こったとしか見られないからです。
③ ポイントを取得した時ではなくポイントを使用した時に「値引き」となる
消費者が商品を購入してポイントを取得することが「値引き」をしてもらったということにならないのかという疑問が湧いてきてもおかしくありませんので、No.1907では触れられていませんが、消費者がポイントを取得する取引についても、ここで確認しておきましょう。
消費者は、商品の購入を行ってポイントを付与されることになりますが、この付与されたポイント自体は、上記①でも述べたとおり、対価を支払って取得しているわけではありません。
この商品を購入するという取引の経済実態はどのようなものかということを考えてみると、消費者は取得したポイントの時価に相当する金額の「経済的利益」を得ていると考えることもできないわけではありませんが、消費者が実際にポイント相当額の現金を得るのは、ポイントの使用時であり、ポイントは使用されずに失効するものが少なからずあって「経済的利益」を得ることに不確実性もありますので、ポイントを取得した時に「経済的利益」を得た、つまり、「値引き」をしてもらったと取り扱うことには、無理があると考えられます。
このような事情にあるため、「答」の「(説明)」の「2」においては、消費者がポイントを取得した時ではなく、消費者がポイントを使用した時に、「値引き」と同様の行為が行われたと考えられると記述しているわけです。
④ ポイントの使用で雑所得や事業所得が発生するとされることもあり得る
「答」の「(説明)」の「2」に書かれていることから推測すると、消費者がポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして付与されたポイントではなく、消費者がアンケートに答えるなどの役務提供の対価として付与されたポイントを商品の購入に使用した場合には、消費者がポイントを取得する取引から消費者がポイントを使用する取引までの全体の「事実」を一連のものとして捉えると、消費者がポイントを取得する取引において消費者は役務提供をしているわけですから、ポイントを商品の購入に使用して得られた「経済的利益」は、一時所得ではなく雑所得となると考えられます。
もっとも、雑所得は、20万円未満であったということであれば、申告をする必要がありませんので、消費者がポイントを使用して「経済的利益」を得たとしても、確定申告が必要となるというケースは、それほど多くはないものと思われます。
ただし、最近は、SNSで投稿をすることで得られるポイントやアフィリエイト報酬型のポイント、さらには事業用仕入れにポイントを使用するというものなども見受けられるようになってきましたので、いずれは、ポイントを商品の購入に使用して得られた「経済的利益」が雑所得として課税されるというケースが出てくる可能性が高いと考えられます。
そして、実際にどれほどあるかは別にして、消費者がポイントを貯めることを事業と言い得る状態で行っていたという場合には、雑所得の場合と同じ理由で、消費者がポイントを商品の購入に使用した時に、消費者がポイントを使用して得た「経済的利益」を事業所得として確定申告をすることが必要となるものと考えられます。
⑤ 「参考」の本文と注記に書かれている二つの取扱いは、いずれも実務を重視した個別の場面の取扱いと捉えるべきものである
上記(2)⑦において、No.1907には、「参考」の本文に所得控除の取扱いとして二つの方法を選択できると書かれていることを確認しましたが、このように、二つの取扱いを選択できることは、納税者と税理士にとっては、歓迎するべきことです。
このように、この「参考」の「1」と「2」のいずれの方法でも良いという取扱いとすれば、選択肢が広がることになり、確実に、誤りも少なくなります。
しかしながら、この取扱いには、疑義なしとしないところもあります。
上記(2)⑦において、確認した「参考」の「2」の方法による取扱いには、仮に、消費者が使用したポイントがポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したものであったとしても、なお疑問があります。
この「2」の方法による取扱いは、消費者がポイントを使用して得られる「経済的利益」が薬品購入費用の決済代金を減少させる「経済的利益」であるにもかかわらず、その「経済的利益」を「一時所得の総収入金額」(所得税法34条2項では「一時所得に係る総収入金額」という文言となっています。)に変えるものです。このように、「費用」の金額や「資産」の取得価格を減少させる「経済的利益」について、それを「収入」に変えて課税をするということであれば、その理由を明確に説明する必要があると考えられますが、そのような説明は行われていません。
また、この「参考」の所得控除に関する取扱いについては、「答」で行っていたようなポイントの取得と使用を一連のものとして見るということをせず、「答」で行っていたような理由を述べるということもせず(「答」の二つの取扱いについては、それぞれ「そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので」(「答」の「(説明)」の「2」)と「通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので」(「答」の「(説明)」の「(注)」)というように、理由を述べています。)、ポイントの使用を「値引き」とする取扱いをする場合の所得金額及び所得控除額の計算(この「参考」の「1」の方法による計算)とポイントの使用で一時所得が発生するとする取扱いをする場合の所得金額及び所得控除額の計算(この「参考」の「2」の方法による計算)のいずれでもよいという、理論的に説明が困難な取扱いを示しています。
この所得控除に関する取扱いは、本来の正しい取扱いではなく、実務を重視した割切りの取扱いであって、その取扱いが割切りの取扱いであるが故に、「答」には書き得ず、「参考」として書くこととなっているものと考えられます。
加えて、この「参考」の「(注)」に書かれている株式等の購入にポイントを使用した場合に株式等の取得価額をポイント使用前の金額とするとともにポイント使用相当額の一時所得を発生させるという取扱いについても、「答」に書かれていることからすると、本来は、そのような取扱いとはならず、使用したポイントが商品の購入によって取得したものである場合にはポイントの使用後の支払金額を基に株式等の取得価額を計算しなければならず、使用したポイントがポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したものである場合にはポイントの使用前の支払金額を基に株式等の取得価額を計算するとともにポイント使用相当額の一時所得を発生させなければならないというものとなるはずです。
しかし、この株式等の購入にポイントを使用した場合の取扱いについても、「答」で行っていたようなポイントの取得から使用までの全体の「事実」を一連のものとして捉えるということをせず、「答」で行っていたような理由を述べるということもせずに、あたかも決め打ちであるかのように、ポイントの使用前の支払金額を基に株式等の取得価額を計算するとともにポイント使用相当額の一時所得を発生させるという取扱いのみを示しています。
この株式等の購入にポイントを使用した場合の取扱いについても、本来の正しい取扱いではなく、実務を重視した割切りの取扱いであって、その取扱いが割切りの取扱いであるが故に、「答」には書き得ず、「参考」として書くこととなっているものと考えられます。
要するに、この「参考」の本文と注記に書かれている二つの取扱いは、いずれも実務を重視した個別の場面の取扱いと捉えるべきものであると考えられるわけです。
もっとも、「参考」とは、何かをするときに自分の考えを決める手がかりにすることができるものをいう用語ですから、この「参考」として書かれている二つの取扱いは、その内容からすると、はたして「参考」と言うべきものであるのか、「参考」にすると、かえって自分の考えを決めることができなくなってしまうのではないか、「例外」ないし「特例」ということになるのではないかなど、さまざまに疑問が残るものとなっていると感じます。
また、所得控除の取扱いにおいては、例えば、この「参考」の「1」の方法で計算して申告を行っていたがこの「参考」の「2」の方法で計算する方が有利だと分かったために、「2」の方法で計算を行うように更正の請求を行い得るのかというような疑問が生じてくるはずです。これに関しては、法令に当初申告要件などの定めがあるわけではなく、国税庁自身も次に述べる株式等の購入にポイントを使用した場合の取扱いとは異なって「1」の方法と「2」の方法の二つを挙げたうえでいずれの方法も選択できるという内容の説明をしているわけですから、納税者が有利な方法を選択することは当然のことであって、そのような更正の請求も行い得るということになるものと考えられます。
そして、株式等の購入にポイントを使用した場合の取扱いについても、何故、所得控除に関する取扱いと同様に、いずれの方法でもよいとしなかったのかという疑問が生じてこざるを得ないはずですが、筆者が推測するに、それは、過去に、ポイントの使用前の支払金額を基に株式等の取得価額を計算するとともにポイント使用相当額の一時所得を発生させると回答したものがあって、その回答をNo.1907で変えると実務が混乱することにならざるを得ないことから適当でないと判断されたためであろうと思われます。
⑥ ポイントを使用した取引について、レシートや領収書の書かれ方の違いによって「値引き」となったり「値引き」とならなかったりするなどということは、理論、実態及び所得税法の規定のいずれからしても、有り得ない
そして、No.1907の「答」と「参考」のいずれにもレシートや領収書に言及したところが全くない理由は、消費者がポイントを使用して商品を購入した場合に、消費者が使用ポイント相当額の「値引き」を受けているということが「事実」に他ならないためであるということも、上記(2)②及び⑧において確認したとおりです。
上記(2)②及び⑧において確認したことの再確認ということになりますが、ポイントを使用した取引について、レシートや領収書の書かれ方の違いによって「値引き」となったり「値引き」とならなかったりするなどということは、理論及び実態のいずれからしても、有り得ないことです。
もちろん、所得税法にも、ポイントを使用した取引がレシートや領収書の書かれ方の違いによって「値引き」が行われた取引となったり「値引き」が行われなかった取引となったりすると解釈するべき規定は、存在しません。
このため、当然のことながら、レシートや領収書がポイントの使用によって「値引き」が行われたことを適切に表示していない場合には、「値引き」が行われなかったという本末転倒の処理をするのではなく、レシートや領収書の表示を適切に訂正することを考えるべきであるということになります。
⑦ 給与所得者が企業の経費の立替払い等をして得たポイントを使用して給与所得課税を受けることもあり得る
ポイントの取扱いで多く疑問が生じてくるのは、給与所得者が会社の経費を立替払いして給与所得者にポイントが貯まり、給与所得者が自らの生活費等の支払いのためにそのポイントを使用したという場合に、そのポイントの使用額に相当する金額が給与の支給金額とされることにならないのかということではないでしょうか。
これに関しては、会社が自ら経費を支払えば、会社にポイントが貯まり、その後、会社はそのポイントを使用して次の経費の額を「値引き」によって少なくすることができるところ、給与所得者が会社の経費を立替払いすれば、給与所得者にポイントが貯まり、その後、給与所得者はそのポイントを使用して自らの生活費等の額を「値引き」によって少なくすることができる一方、会社は次に発生する経費の額を少なくすることができなくなります。
このため、給与所得者が会社の経費を立替払いし、給与所得者にポイントが貯まり、その後、給与所得者が自らの生活費等の支払いのためにそのポイントを使用したという場合には、会社が給与所得者に対してポイントの使用額に相当する「経済的利益」を供与したということにならざるを得ません。
会社の経費を支払うカードを給与所得者の生活費等を支払うカードと分けるというようなことをしていたり、給与所得者が会社の経費を立替払いして得たポイントは会社の経費の建て替えにしか使用しないということにしていたりすれば、このような問題は生じませんが、そのような対応をせずに給与所得者が会社の経費を立替払いしているということになると、このような問題が生ずることを避けることはできません。
このような給与所得課税が実際に行われたという例は、未だ聞いたことはありませんが、理論的には、給与所得課税となるということが明確ですから、いずれはどこかで発生することになるように思われます。
⑧ 消費者がお店との間でそのお店の独自ポイントを用いて取引を行っても共通ポイントを用いて取引を行っても、消費者がお店から「値引き」をしてもらうことに全く何の違いもないため、消費者とお店におけるこれらの取引の所得税法上の取扱いは、その「事実」に基づき、いずれも「値引き」が行われたものとされる
No.1907は、ポイントの中のお店の独自ポイント(注7)に関するタックスアンサーとなっていますが、ポイントが共通ポイントであっても、その答は、全く変わりません。
(注7) 特定の企業又は店舗のみで用いることができるポイントは、通常、「自社ポイント」と呼ばれていますが、1においては、消費者が商品を購入するお店も個人としていますので、「会社」を意味する「自社」という用語ではなく「独自」という用語を用いることとし、「独自ポイント」と記載することにします。
これは、お店の独自ポイントと共通ポイントの両方を持っている消費者がお店で買い物をして、そのお店の独自ポイントを使用したという場面と共通ポイントを使用したという場面を思い浮かべて、何か違いがあるのかと考えてみるだけで、誰でも直ぐに分かることです。この消費者がレジでそのお店の独自ポイントを使用しようが共通ポイントを使用しようが、この消費者とお店との間の取引には、全く何の違いもありません(注8)。
(注8) No.1907について、上記(1)において引用した「問」の中にある「同ストアが発行するポイント」を「共通ポイント」に改め、更に、同じく(1)において引用した「問」及び「答」並びに上記(2)⑦において引用した「参考」の中にある「ポイント」を「共通ポイント」に改めても、「問」、「答」及び「参考」の記述内容は、全く変わりません。
勿論、上記(2)及び上記①から⑦までの説明も、同様であって、これらの説明の中にある全ての「ポイント」を「共通ポイント」に改めても、その記述内容が変わるところは、全くありません。
このため、消費者とお店は、お互いの間の取引について、そのお店の独自ポイントが使用された場合と共通ポイントが使用された場合とで、税法上の取扱いを変えることはできません。
同じものに対して異なる課税をすることが許されないことは、当然です。
お店の独自ポイントと共通ポイントの違いは、消費者とお店との間の取引にあるわけではなく、その取引のバックヤードで行われる取引にあります。
お店の独自ポイントは、お店が独自に「値引き」をして集客を図るものであり、共通ポイントはお店が複数で「値引き」をして集客を図るものです。
このため、お店は、消費者がそのお店の独自ポイントを用いて買い物をした場合、そのお店だけで「値引き」の処理を完結させることができますが、消費者が共通ポイントを用いて買い物をした場合には、そのお店が付与したポイントを消費者が他のお店で使用することがあったり、消費者が他のお店で付与されたポイントをそのお店で使用することがあったりしますので、そのお店だけで「値引き」の処理を完結させることはできません。
消費者が共通ポイントを使用して買い物をした場合には、その消費者にそのポイントを付与したお店とその消費者がそのポイントを使用して買い物をした他のお店との間で、「値引き」の金額に相当する金銭の授受を仲介する共通ポイントの「運営会社」が必要となり、そのお店と他のお店は、その運営会社との間で、消費者に付与したポイント相当額の金銭を支払い、消費者が使用したポイント相当額の金銭を受け取る、という取引をすることになります。もう少し詳しく言うと、消費者にポイントを付与したお店は、消費者がそのポイントを使用して「値引き」をしてもらうことになる金額を負担するために、付与したポイント相当額の金銭を運営会社に支払い、その支払いを受けた運営会社は、一旦、その支払いを受けた金銭を預かり、その後、消費者がそのポイントを使用して買い物をしたお店に支払う、ということになります。このため、消費者にポイントを付与したお店には、運営会社に対して支払う経費が発生し、消費者がポイントを使用したお店には、運営会社から受け取る収入(注9)が発生します。これらは、消費者とお店との間の取引のバックヤードで行われる取引ということになります。
(注9) お店は、消費者に商品を売り、その商品の販売価格を「値引き」後の金額に下げる調整をして、その商品の販売価格は「値引き」後の金額となっています。
そして、上記本文の「収入」は、その商品の販売価格を「値引き」後の金額に下げて調整した部分に相当する金額を運営会社から受け取るものです。
このため、上記本文の「収入」は、「売上」とは異なる「収入」又は「収益」とする必要があります。
このように、上記本文の「収入」が「売上」とならないことは、その商品を購入した消費者がその商品の販売価格から使用ポイント相当額を控除した金額しか支払うことがないことからも、自明のことです。
仮に、このお店が受け取る上記本文の「収入」がこの消費者が運営会社に支払ったものであったとすれば、上記本文の「収入」が「売上」の一部ということになり得ますが、上記本文の「収入」は、この消費者にポイントを付与したお店が運営会社に支払ったものであって、この消費者が運営会社に支払ったものではありません。
消費者とお店との間の取引に話を戻すと、消費者とお店との間では、お店が1社で消費者に値引きをすれば「値引き」になって、お店が複数社で消費者に値引きをすれば「値引き」にならないなどということは、あり得ません。消費者は、お店の独自ポイントを使用して商品を購入しても、共通ポイントを使用して商品を購入しても、お店から全く同じ「経済的利益」を得ることになります。
このように、お店の独自ポイントを使用して取引が行われても、共通ポイントを使用して取引が行われても、消費者とお店との間の取引に何ら異なるところはないわけですから、消費者が共通ポイントを使用して取引を行ったとしても、その所得税の取扱いは、上記(2)及び上記①から⑦までに述べたとおりとなります。
つまり、消費者がお店との間でそのお店の独自ポイントを用いて取引を行っても共通ポイントを用いて取引を行っても、消費者がお店から「値引き」をしてもらうことに全く何の違いもなく、それは「事実」として確認できることであるため、消費者とお店におけるこれらの取引の所得税法上の取扱いは、その「事実」に基づき、いずれも「値引き」が行われたものとされる、ということです。
この連載の記事
テーマ
プロフィール

免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。