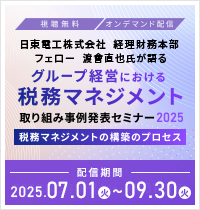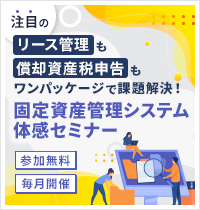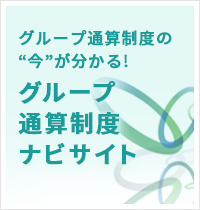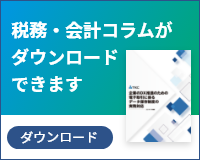更新日 2025.07.14

株式会社TKC 顧問
税理士 朝長 英樹
ポイントの利用が大きく広がり、ポイントを貯めたり活用したりする“ポイ活”も話題になっている中で、最近、ポイントの所得税や法人税の取扱いについて質問を受けることも増えてきました。
そこで、本コラム欄で既に説明したポイントの消費税の取扱いに加え、今回、ポイントの所得税及び法人税の取扱いについて説明します。
当コラムのポイント
- 消費者は、ポイントを使用した場合、それが自社ポイントと共通ポイントのいずれであっても、全く同様に、「値引き」を受けた場合と同じ「経済的利益」を得る
- ポイントを使用した個人及び法人は、それが自社ポイントと共通ポイントのいずれであっても、「事実」に基づき、所得税法及び法人税法上も、「値引き」を受けたとされる
- レシートや領収書がポイントの使用によって「値引き」が行われたことを適切に表示していない場合には、「値引き」が行われなかったという本末転倒の処理をするのではなく、レシートや領収書の表示を適切に訂正することを考えるべきである
- 目次
-
2.ポイントの法人税の取扱い
2においては、法人がポイントを取得して使用した場合のその法人の法人税の取扱いを中心に説明を行います。
この説明は、適宜、前記1における説明を引用しながら行うこととします。
2においては、法人税の取扱いを説明することになりますので、説明を分かり易くするために、法人が取引をする相手方のお店も法人であるものとします。
(1) 法人が「値引き」をしてもらって得た「経済的利益」は、所得の金額を増加させて課税対象となる
前記1(2) ①においては、消費者である個人がお店から「値引き」をしてもらって得た「経済的利益」は所得税の課税対象となる「経済的利益」とはならないということを確認しましたが、法人税においては、消費者である法人がお店から「値引き」をしてもらって得た「経済的利益」は、法人税の課税の対象となります。
何故、消費者である法人がお店から「値引き」をしてもらって得た「経済的利益」が法人税の課税の対象となるのかというと、法人がお店から「値引き」をしてもらうと、法人税法22条(各事業年度の所得の金額の計算の通則)において「損金の額に算入すべき金額」を定める3項の中の1号の「売上原価」等の額又は2号の「費用(・・・)の額」が下がって、それが法人の所得の金額を増加させるからです。
改めて言うまでもないことですが、お店から商品を購入し、そのお店から「値引き」をしてもらった法人は、その商品の仕入価格や費用の額が下がって、所得の金額が増加し、その商品の「値引き」をしたお店は、その商品の売上金額が下がって、所得の金額が減少することになります。
(2) 法人とお店との間のポイントを用いた取引の事実関係は、個人である消費者がお店との間でポイントを用いて取引を行った場合の事実関係と全く同じである
前記1(2) ①及び④でも述べましたが、法人がお店から商品を購入してその決済代金の支払いにポイントを使用した場合には、その商品の取引価格を下げる調整が行われて、その商品の取引価格がポイントの使用後の金額に下がることになります。
このように、法人がポイントを使用して商品を購入すればその商品の取引価格がポイントの使用後の金額に下がるということは、「事実」に他ならず、この「事実」は、法令の取扱いを判断するに当たって前提となるものであって、その法令が所得税法であろうが法人税法であろうが何ら変わるものではありません。
つまり、法人とお店との間のポイントを用いた取引の事実関係は、前記1(2) で確認した事実関係、即ち、個人である消費者がお店との間でポイントを用いて取引を行った場合の事実関係と全く同じであるということです。
(3) 法人がお店との間でそのお店の自社ポイントを用いて取引を行っても共通ポイントを用いて取引を行っても、法人がお店から「値引き」をしてもらうことに全く何の違いもないため、法人とお店におけるこれらの取引の法人税法上の取扱いは、その「事実」に基づき、いずれも「値引き」が行われたものとされる
前記1(3) ⑧においては、消費者がお店との間でそのお店の独自ポイントを用いて取引を行っても共通ポイントを用いて取引を行っても、個人である消費者がお店から「値引き」をしてもらうことに全く何の違いもないため、消費者とお店におけるこれらの取引の所得税法上の取扱いは、その「事実」に基づき、いずれも「値引き」が行われたものとされることを確認しましたが、これは、ポイントを用いる者とお店が法人である場合も、全く変わりません。
つまり、法人がお店との間でそのお店の自社ポイントを用いて取引を行っても共通ポイントを用いて取引を行っても、法人がお店から「値引き」をしてもらうことに全く何の違いもないため、法人とお店におけるこれらの取引の法人税法上の取扱いは、その「事実」に基づき、いずれも「値引き」が行われたものとされるということです。
何故、前記1(3) ⑧で確認したことがポイントを用いる者とお店が法人である場合も全く変わらないのかというと、上記(2) でも述べたとおり、法人がポイントを使用して商品を購入すればその商品の取引価格がポイントの使用後の金額に下がるということは、「事実」であって、法人税法も、所得税法と同じく、「事実」に基づいて取扱いを判断することになるからです。
ところで、上記(1) 及び(2) で述べたとおり、法人がポイントを使用して「値引き」をしてもらって得た「経済的利益」は、所得の金額を増加させて課税対象となるわけですが、その「経済的利益」は、商品の取引から離れて独自に所得の金額を増加させるものではないことに留意する必要があります。
既に述べてきたとおり、ポイントを使用した「値引き」は、商品の取引価格の調整であって、法人がポイントを使用して「値引き」をしてもらって得る「経済的利益」は、その法人が仕入れを計上する時又は費用を計上する時に、商品の取引価格を減少させることで所得の金額を増加させることとなります。
確かに、法人がポイントを持っている状態は、法人が「資産」(注10)を持っている状態と言ってよいものであり、その「資産」は、その後、その法人に「利益」をもたらす可能性が高いわけですが、その「利益」は、法人税法22条2項の「益金の額に算入すべき金額」を増加させて所得の金額となる利益ではなく、同条3項の「損金の額に算入すべき金額」を減少させて所得の金額となる利益です。
(注10) 将来、ポイントを使用して商品を購入することがあれば、その際に使用ポイント相当額の「値引き」をするという、実行されることが確実ではないことに関する約束としての「資産」と言ってもよいように思われます。
このため、法人が持っているポイントの取扱いについて、それを法人税法22条2項の「益金の額に算入すべき金額」の問題と考えてしまうと、観点がずれた話を延々とするようなことになりかねませんので、そのようなことにならないように、十分、注意する必要があります。
了
この連載の記事
テーマ
プロフィール

免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。