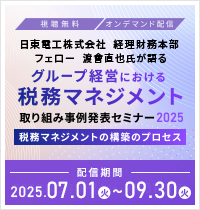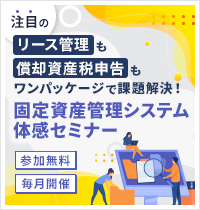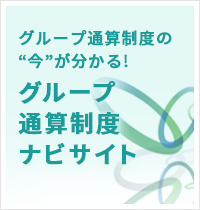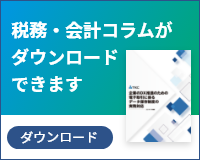更新日 2025.09.16

株式会社TKC
企業情報営業本部 税務システム営業部 税務コンサルティング支援課
2025年2月19日(水)、TKCシステム(ASP1000R、e-TAXグループ通算等)を利用する多くのユーザー企業が課題とする「人材不足」をテーマに、①最新情報を知る、②他社事例を知る、③他社と情報交換する、交流の場としてTKCユーザー会を開催しました。
- 第1部:企業税務の最新動向と人材不足の課題と対策
(講師)PwC税理士法人 - 第2部:パネルディスカッション
(パネリスト)
東レ株式会社 栗原様
鹿島建設株式会社 京極様
長瀬産業株式会社 根岸様
PwC税理士法人 橋本様 - 第3部:参加者によるテーブルディスカッション
さて、今回はユーザー企業事例として、第2部パネルディスカッションで、各社のパネリストが語った「人材不足の課題感や対応策」をご紹介します。なお、以下2点につき予めご了承ください。
- ①記事の中には第1部の講演内容を踏まえた発言、また当日の順番のまま記載しておりますので予めご了承ください。
- ②長瀬産業株式会社 根岸様の講演内容は、当日ご参加された方向けの特別講演となるため、当コラムでは割愛しております。
当コラムのポイント
- 企業税務の最新動向
- 人材不足の課題と対応策の企業事例紹介
- 税務部門の貢献とあるべき税務ガバナンスとは?
- 目次
-
2.東レ株式会社 栗原正明様
(1) 税務室のあり方
うちの税務室は全員で8名です。弊社の場合はほぼ全員で税務コンプライアンス業務や申告と税務調査対応をしていまして、税務戦略を考える仕事、世間でいうタックスプランニングは十分できていないというのが感想です。私が日々の事務は任せて、朝から晩まで税務戦略をどうしようか、と1人で思い悩んでいるため、事務をしながら税務戦略を考えることができるのか、別の組織にした方がいいのかなどをずっと考えています。そのためには、コンプライアンス業務を外注するのが一つの手かもしれませんし、親会社以外のどこかにまとめてしまうというのも一つの手かもしれません。
(2) 税務人材の不足
人手が足りないという意味での人材不足もさることながら、今日お話がありましたIT人材とか、戦略を考えられる人材が不足しているのではないかと感じます。これまで好きこそものの上手なれと言うことで税務好きな人ばかり集めてきたため、少々人材が偏ってしまったと感じています。税務部にも1人から2人くらい税務以外の視点、特にITの視点が必要だと思います。今日AIという話が出ましたけれども、実は4年前に税務室全員で当時流行っていたRPAの研修を受けたのですが、誰一人興味を示さなかったため、それ以降4年間何もしないままになっています。
一方、グループ内を見回すと、経理と兼務している人が非常に多くいます。そういった担当者から、税務は難しい、税務は専門ではない、決算までは何とかできる、税務申告データをTKCのシステムに入力しているけどちゃんとできているのか非常に不安である、といった声をよく聞くようになりました。こういったグループ会社の税務事務こそ外注化が望ましいのではないかということで、先日子会社の税理士さんへ相談に行きました。
(3) グローバル・ミニマム課税
また、今後の体制に影響を与えるテーマとしては、グローバル・ミニマム課税があります。IIR情報申告が制度化されていますが、とりあえず3年間は簡易方式になっています。3年後どうなるかによっては体制を変えていく必要があるかもしれませんが、今は動きづらいというのが正直なところです。QDMTTやUTPRも入ってきて、15%未満の地域はなくなるはずですから、重々しい情報申告を止めていただいて、その工数を考える時間に充てられればもっと良くなるのではないかと考えています。
(4) 税務ガバナンス
税務ガバナンスについてですが、言葉がイメージしづらいので、会社によって違ってよいものだと思っています。ただし、自社が思い描くガバナンスがどういうもので、現状はどうだろうというのを理解する必要があると思います。つい他社と比べると、マイナス面ばかりが目に入って、他社より劣っているのではないかという気がしてしまい、自社にとって適切なガバナンスを見失いがちになることもあると思いますので、各社が目指されている税務ガバナンスはきっと間違っていないと言いたいところです。
(5) これからの税務部長
後任の税務部長について考えたときに、これまでは税務に長けた人が税務部長になるべきという流れでしたが、必ずしもそうではないのではないかと考えています。たしかに税務は職人という時代があり、税務に精通した人を求める傾向にありますけども、税務部も会社の組織です。組織運営や税務が得意な部下を上手くマネジメントできる人、現状と対比しながら戦略立案できる人ということで、事業部長経験者が適していると最近は考えていますが、あまり賛同は得られていません。
(6) 税務室のタコつぼ化回避に向けて
税務のタコつぼ化についてコメントします。2017年に税務室を作り、少ないながらもグループ通算制度を担当する国内グループと、移転価格などを担当する国際グループに分けました。メンバー全員が専門分野を持ったわけですが、専門分野が非常に気に入ってしまったのか、細かく分けると国内と国際の交流がなくなってしまいました。今思えば、当然の流れだったのかなと思います。一人で思い悩んでいても仕方がないので、税務室全員で意見交換をする場を近々持ちたいと考えています。今後どうすべきなのか、またそれ以上に皆が何をできるのかを考えるのが非常に重要な機会だと思っています。
【司会:白土晴久先生(PwC税理士法人)】
ありがとうございます。最後にありました税務責任者の方は、必ずしも税務に長けた方でなくても良いというのは大変興味深いと感じました。ここまでのお話から少し視点を変えて、テクノロジーの観点で今の人材不足に対する対応策について橋下さんからコメントをいただけますでしょうか。
3.PwC税理士法人 橋本純先生
先程AIの活用について、「人材不足」の解決策として、外部専門家の活用などのお話もありましたが、テクノロジーの活用も今後重要になってくると思います。先ほどご紹介した生成AIの活用は、税務部門の業務効率化に大きな可能性を秘めています。申告書の作成や社内問い合わせ対応といったルーティン業務を自動化することで、税務担当者はより高度な分析や戦略的な業務に集中することができます。
また、栗原さんがおっしゃるように、テクノロジーの活用には人材の育成も欠かせません。税務部門のスタッフに対して、最新のテクノロジーに関する研修を実施し、ITスキルの向上を図ることが重要です。ただ、税務部門の方々はテクノロジー活用に興味を示さない可能性もあります。その場合は、テクノロジー活用ができる人材を社内あるいは外部から調達して、短期間でもよいので部内に在籍させ、小さな活用事例を作り、皆で成功体験を共有してもらえると、全体で取り組む姿勢ができるのではないかと思います。これにより、テクノロジーを効果的に活用できると、組織全体のパフォーマンスを向上させることができると考えます。
活用が進むと、人材の在り方や組織の在り方も変えていく必要があるでしょう。ここで結論は出しませんが、その変化は「人材不足」の解消という意味では、プラスになる変化だと思います。
この連載の記事
-
2025.09.16
第1回 イントロダクション
-
2025.09.16
第2回 人材不足の課題と対応策(その1)
-
2025.09.16
第3回 人材不足の課題と対応策(その2)
-
2025.09.16
第4回 参加者からの事前質問への回答(その1)
-
2025.09.16
第5回(最終回) 参加者からの事前質問への回答(その2)
テーマ
プロフィール

株式会社TKC
企業情報営業本部 税務システム営業部 税務コンサルティング支援課
免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。