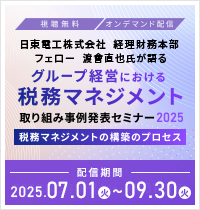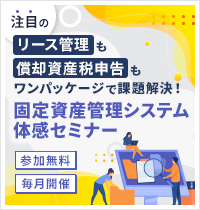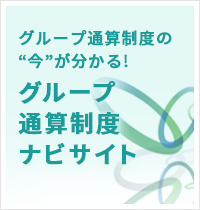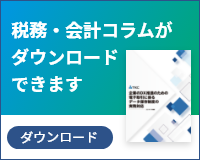更新日 2025.09.16

株式会社TKC
企業情報営業本部 税務システム営業部 税務コンサルティング支援課
2025年2月19日(水)、TKCシステム(ASP1000R、e-TAXグループ通算等)を利用する多くのユーザー企業が課題とする「人材不足」をテーマに、①最新情報を知る、②他社事例を知る、③他社と情報交換する、交流の場としてTKCユーザー会を開催しました。
- 第1部:企業税務の最新動向と人材不足の課題と対策
(講師)PwC税理士法人 - 第2部:パネルディスカッション
(パネリスト)
東レ株式会社 栗原様
鹿島建設株式会社 京極様
長瀬産業株式会社 根岸様
PwC税理士法人 橋本様 - 第3部:参加者によるテーブルディスカッション
さて、今回はユーザー企業事例として、第2部パネルディスカッションで、各社のパネリストが語った「人材不足の課題感や対応策」をご紹介します。なお、以下2点につき予めご了承ください。
- ①記事の中には第1部の講演内容を踏まえた発言、また当日の順番のまま記載しておりますので予めご了承ください。
- ②長瀬産業株式会社 根岸様の講演内容は、当日ご参加された方向けの特別講演となるため、当コラムでは割愛しております。
当コラムのポイント
- 企業税務の最新動向
- 人材不足の課題と対応策の企業事例紹介
- 税務部門の貢献とあるべき税務ガバナンスとは?
- 目次
-
前回の記事 : 第4回 参加者からの事前質問への回答(その1)
2.質問:「あるべき税務ガバナンスはどのように各社で考えていくべきでしょうか?」
それでは、続きまして、あるべき税務ガバナンスはどのように各社で考えていくべきでしょうか。こちらは栗原様、お願いできますでしょうか。
【東レ株式会社 栗原正明様】
税務ガバナンスという言葉自体が難しいところがありますが、私個人の解釈では、税務リスクを把握して評価でき、必要な時に対応がとれている状態を税務ガバナンスが取れていると解釈しています。もう少しわかりやすく言うと、例えば資本的支出と修繕費であれば、多分皆さんは会社の状況を的確に把握されており、対応もされていると思います。ただし、税務調査で否認を0にすることは難しいと思いますが、否認されたらどう対応されるかもよくご存じでしょう。そういう状態をガバナンスがとれている状態だと解釈しております。一方で、先程申し上げたグローバル・ミニマム課税だと、欧米企業は子会社のデータを全部持っている、日本企業はこれから集めるとなると、ちょっと遅れているという雰囲気がありますが、データがあるだけで生かしているかは非常に疑問ですし、仮にデータが今なくても必要に応じて定期的にデータを取り寄せて評価できていれば、税務ガバナンスはできているのではないかなという風に感じています。
最後に一言、先ほどの税務責任者は事業部長経験者が適しているというお話について補足させていただきます。正直言うと勝手な思い込みに過ぎないけれども、税務に長けた人は、税務コンプライアンス業務が比較的好きで、過去の実績をどう守るかというのは非常に得意な反面、不確実な将来部分については必ずしも得意でない方が多いのではないかと思います。事業部の人は、リスクを取りながら必要な対策を講じつつ、日々のビジネスを展開しているため、将来の税金費用をコントロールしたり、削減していったりする仕事に合うのではないかと思っています。多分事業部出身の税務部長は、税務の知識がほとんどないので、税務コンプライアンス業務を得意な人にお任せするわけですが、知らない部下の顔色を見ながら、進捗状況を逐次チェックしながら進めていくので、意外とうまくいくのではないかと思います。私のような30年選手をこれから育成していくのは不適当ではないかなと考えています。
3.質問:「AI活用が進むと、外部専門家の活用とテクノロジーの活用の境目がなくなっていくように思えるのですが、どのように考えればよいでしょうか」
それではもう一つ最後のご質問になります。こちらはテクノロジー関係ということで、AI活用が進むと外部専門家の活用とテクノロジーの活用の境目がなくなってしまうように思えますが、こちらについてはどのように考えれば良いかということで、橋本先生お願いします。
【PwC税理士法人 橋本純先生】
先ほどの話と関連しますが、外部専門家を使うというのも間接的には既にテクノロジーの活用に至っていると思います。我々のような税理士法人もテクノロジーの活用を積極的に進めており、AIの活用事例を紹介させていただきました。人数比でいうと、全従業員の5%ぐらいがテクノロジー人材になっていますし、グローバル全体の投資も含めて、金銭的にも投下して対応しています。そのため、アウトソースとして使っていただく場合は、間接的に我々が投資しているテクノロジーを享受していることにつながると思います。
一方で、専門家とテクノロジーの境目がなくなってきたので、なるべく社内で対応するという方向性もあると思います。ルーティン業務は社内で生成AIやRPAを活用することで業務効率化が図れる領域でもあると思いますし、ある程度の判断を要する領域も、先ほどお見せした通り、AIで代替できます。その一方で、税制改正の解釈や複雑で事例が少ない判断などは、AIではまだ難しい領域ですし、外部専門家の活用は、そのような高度なアドバイザリー限定になってくる可能性もあると思います。
【司会:白土晴久先生(PwC税理士法人)】
我々自身も努力しなければいけないということで、大事なポイントだと思います。まだまだご登壇者の方々からお話をお伺いしたいところですが、この第2部のパネルディスカッションは以上とさせていただきます。それでは、改めまして栗原様、京極様、根岸様、橋本さん、ご登壇どうもありがとうございました。この連載の記事
-
2025.09.16
第1回 イントロダクション
-
2025.09.16
第2回 人材不足の課題と対応策(その1)
-
2025.09.16
第3回 人材不足の課題と対応策(その2)
-
2025.09.16
第4回 参加者からの事前質問への回答(その1)
-
2025.09.16
第5回(最終回) 参加者からの事前質問への回答(その2)
テーマ
プロフィール

株式会社TKC
企業情報営業本部 税務システム営業部 税務コンサルティング支援課
免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。